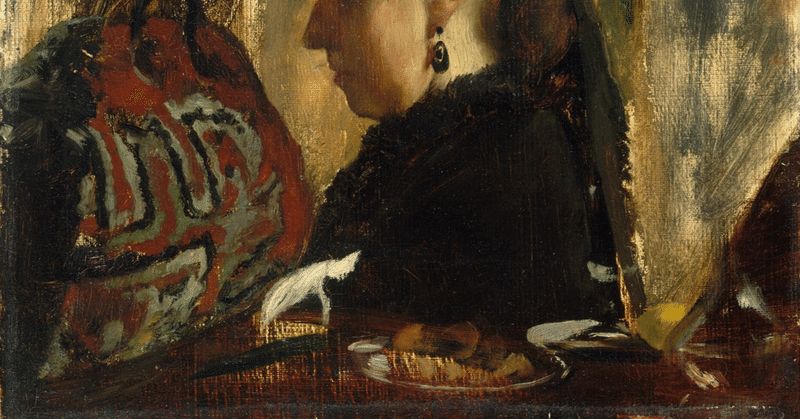
2023年2月に観た映画
2月に観た映画のレビュー。
最後に誰がどうなるみたいなネタバレは書かないつもりだが、多少具体的な作品の内容には触れると思う。
イニシェリン島の精霊

2022年
109分
1923年、アイルランドの小さな孤島イニシェリン島。住民全員が顔見知りのこの島で暮らすパードリックは、長年の友人コルムから絶縁を言い渡されてしまう。理由もわからないまま、妹や風変わりな隣人の力を借りて事態を解決しようとするが、コルムは頑なに彼を拒絶。ついには、これ以上関わろうとするなら自分の指を切り落とすと宣言する。
中年男が中年男からある日突然絶交を言い渡されて戸惑う、という作品がアカデミー賞有力?なんて思ってしまうが、やはりマーティン・マクドナーのスリルある脚本、物語に隠された様々な意味などを大いに楽しむことができる。
個人的に、監督の前作『スリー・ビルボード』は人生ベスト映画のひとつ。
作中でこれまでの二人を回想などで描かないため、実際は二人の仲がこの日までどんな感じだったのかは観客の想像に委ねられる。
コルムが言う、「パードリックはつまらん男だった」という件も、彼の一方的な言い分でしかない。
パードリックがちょっと気の毒な感じも、でもコルムの言い分も分からなくもない感じも、観客はこの決別宣言以降の二人しか見ていないのでジャッジしようがないという点は、今作が上手くできているところ。
絶交にも関わらず自分に話しかけてくるパードリックに対しコルムはある奇策に出るのだが、こういうのは一方的に相手を加害者化する自らの被害者化でかなりタチが悪い気がする。一種の脅迫のようなものだろう。
そして彼はつまらん友人と絶交して芸術活動を極めようとしていたのに、この行動によりもう楽器が弾くことができない。元も子もない状態である。
二人の仲違いは、劇中でも描かれる島の向こう、本土で行われている内戦(そしてもちろん、現実に今起きている戦争)のメタファーともとれる。
隣同士の国ほど仲が悪くなるという世界中で起きている現象にもとれるし、恋愛の話にもとれる、普遍的な破局の物語である。
「島に二つの死体が転がる」という不穏な予言がされ、それはパードリックとコルムのことかと思いきや…という展開は、結局、争いの犠牲となるのは始めた当事者ではなく関係のない市井の者だという戦争の悲惨さを指すのだろう。
もう過去の二人には戻れない。
大きな犠牲も出た。
それでも、分かり合えないからこそまたここから始まる何かもあるんじゃないかと思いたい。
KIDS/キッズ

1995年
92分
ニューヨーク、暑い夏の昼下がり。絡み合う舌と舌。ヴァージンに目がないテリーはいつものように口八丁手八丁で女の子をモノにした。その後、年中ラリってる友達のキャスパーと取るに足らない話をしながら街を歩き、仲間の家でビールを飲んでドラッグをキメてSEXの話、そんな日常。一方、ルビーの家ではジェニーたち女の子5人がSEXの話で盛り上がっている。ジェニーはヴァージンだけ奪ってバックれたテリーにムカついている。そして、経験豊富なルビーの付き添いで受けたHIVの検査結果を聞きに行く。
セックスとドラッグに溺れる、NYストリートで暮らす少年少女たちの日常をドキュメンタリータッチで描いた作品。
このポスターも、オマージュのようなものを時々見かけるので後の影響が大きい作品だということが分かる。
身体だけが大人に近付いていく時期。
その姿がとても生々しく、痛々しい。
若者の運命は、やはり環境に左右されてしまうことが多いのだろう。
出演している俳優はみな素人で、特にテリーとキャスパーを演じる二人は拙いが、それがより無理をして大人ぶっている感じが出ている気もする。
最近だと『デッド・ドント・ダイ』で見たクロエ・セヴィニーも今作でデビュー。既にスクリーンジェニックな存在感。
キャストたちの後日談を調べると悲しくなる作品である。
結構きつかったので再見することはないと思うが、強烈な印象を与える作品だった。
『ウルフ・オブ・ウォールストリート』みたいな大人が酒・セックス・ドラッグをやりたい放題やる映画や、同じく未成年が主役でも『プロジェクトX』くらい突き抜けた映画だと楽しめるし何度でも観たいと思う。
こういう題材はダウナーなものよりアッパーなブラックコメディの方が好みかも。
対峙

2021年
111分
アメリカの高校で、生徒による銃乱射事件が発生。多くの同級生が殺害され、犯人の少年も校内で自ら命を絶った。事件から6年。息子の死を受け入れられずにいるペリー夫妻は、セラピストの勧めで、加害者の両親と会って話をすることに。教会の奥の小さな個室で立会人もなく顔を合わせた4人はぎこちなく挨拶を交わし、対話を始めるが……。
子供同士のトラブル(今作はトラブルというレベルでもないが)について、加害者と被害者の両親がひとつの部屋に集まり話し合いをするワンシチュエーションもの、といえばどうしてもロマン・ポランスキーの『おとなのけんか』を思い出す。
『おとなのけんか』も、最初はお互い「大人の対応」をしようとのことで冷静に事をおさめようとするところどんどん洒落にならない事態になっていく最高に笑える会話劇だったが、今作はかなりシリアス。
題材的に舞台っぽいなと感じたが、やはり映画ならではの画作りが印象的。
四人の親たちが最初はどう座るか、そして話し合いを進めるうちに誰がどう動いていくのか。それをどう映すか。
序盤、話し合いの舞台をセッティングする段階からどことなく緊張感が漂っている。
原題の"MASS"からして、かなり宗教色も濃い映画。
まず被害者と加害者の親同士を対面で、立会人無しの四人きりで会わせること自体がかなりアメリカ的。
日本で公的に同じことは実現可能なのだろうか。
これをさまざまな国で作った場合どのような内容に、そしてどのような決着になるのか知りたくなった。
観ていてずっと息苦しかったが、それでも、深くもがいて苦しみ抜いた人間にだけ見えるものが何かあるのかもしれないと教えてくれる作品だった。
アントマン&ワスプ クアントマニア

2023年
125分
「アベンジャーズ エンドゲーム」では量子世界を使ったタイムスリップの可能性に気づき、アベンジャーズとサノスの最終決戦に向けて重要な役割を果たしたアントマンことスコット・ラング。ある時、実験中の事故によりホープや娘のキャシーらとともに量子世界に引きずり込まれてしまったスコットは、誰も到達したことがなかった想像を超えたその世界で、あのサノスをも超越する、すべてを征服するという謎の男カーンと出会う。
いよいよフェーズ5に突入したマーベル・シネマティック・ユニバース。
サノスの次なる敵、カーンが登場する作品ということだが、思いのほか単体作として楽しめる作品だった。
事前情報では「ドラマ『ロキ』は観ておいた方がいい」(カーンが初めて登場したエピソードがあるから)など言われていたが、個人的にはそこまで必死になる必要はない気がした。
もちろん、観ておくに越したことはないのだが。
量子世界の描写は、同じディズニーだと最近観た『ストレンジ・ワールド』に近いものを感じた。あれのスプラットみたいな、ぷにぷにした可愛いやつもいる。
量子世界に住んでいるキャラクターたちは個性豊かで、画面の隅々までいろんなキャラクターがいるためその世界観を大画面で観る価値がある。
ミシェル・ファイファー、マイケル・ダグラスといった名優が出ているので当然なのかもしれないが、今作はやはりジャネットとピム博士の魅力に惹かれる。
キャシー役として新しく参加したキャスリン・ニュートンも、実は中身は殺人鬼だし強いねんりきを出せるコダックを連れているので無敵。キュートで頼もしい、新たなヤング・アベンジャーズの一員が増えて嬉しい。
すべての世代、老若男女が活躍する作品だという風通しの良さもある。
そしてやはりカーンの存在、演じるジョナサン・メジャースの演技が今作をより面白くしている。
まだ謎に満ちており、そのキャラクターからしてどこまで彼が言うことが本当なのかも分からない。
カーンは大勢いるということで、もしかしたら今後のMCU作品であらゆるカーンが出てくるのかもしれない。その度にさまざまな演じ分けを見られるのも楽しみだ。
「もしかしたら俺は取り返しのつかないことをしてしまったのかもしれない………けどまぁいいや!」のシーンは良かった。
まぁいいやの精神はいつも大切にしたい。
別れる決心

2022年
138分
男性が山頂から転落死する事件が発生。事故ではなく殺人の可能性が高いと考える刑事ヘジュンは、被害者の妻であるミステリアスな女性ソレを疑うが、彼女にはアリバイがあった。取り調べを進めるうちに、いつしかヘジュンはソレにひかれ、ソレもまたヘジュンに特別な感情を抱くように。やがて捜査の糸口が見つかり、事件は解決したかに見えたが……。
パク・チャヌクの最新作は、一言で言えば「不倫ロマンスミステリー」だが、ありとあらゆる映像表現を駆使した、観客も迷宮を彷徨い続けるような夢幻的な物語である。
夫が山で転落死、そして他殺を疑われる妻というプロットは増村保造の傑作『妻は告白する』に似ている。
この作品を映画館で観て衝撃を受け、昔の日本映画にのめり込んだ時期のことを思い出した。
『妻は告白する』の若尾文子も、『別れる決心』のタン・ウェイも、その美しさに劇中の男だけでなく観客もつい惹かれてしまう魅力がある。
タン・ウェイ演じるソレは決して「悪女」のような描き方はされておらず、今作はそういったミステリー、ノワール作品での「悪女」的なキャラクター造形への返答とも言える。
「愛してる」というキーワードが重要となるこの作品。
そして、人間は「愛してる」という直接的な表現を使わなくてもそれを表現することがある。
それを発する相手によっては、日常的な何気ない会話も、仕草すらもあなたを愛しているという信号になり得るのだ(そしてそれが一方通行だった時の虚しさはひとしお)。
今作で表現されるさまざまな愛の表現は、観客のフェティシズムをとことん突き刺してくる。言ってしまえばかなり変態的な作品だ。
機械音声(翻訳機)を使った会話すら、どこか色っぽく見えてしまう不思議。
一か所だけある直接的なセックスシーンの方が、むしろ空っぽで乾いているように見えてしまう。
別れる決心をすることは、二度と忘れない、忘れさせないという決心をすることなのかもしれない。
愛は一種の呪いのようなものである…と書くとなんだかこの作品がドロドロしているように思えるかもしれないが、鑑賞後はドロドロとは程遠い、名状し難い熱い感情が込み上げてくる。
たとえその結果自分が「崩壊」してしまうとしても、見つめていたい人がいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
