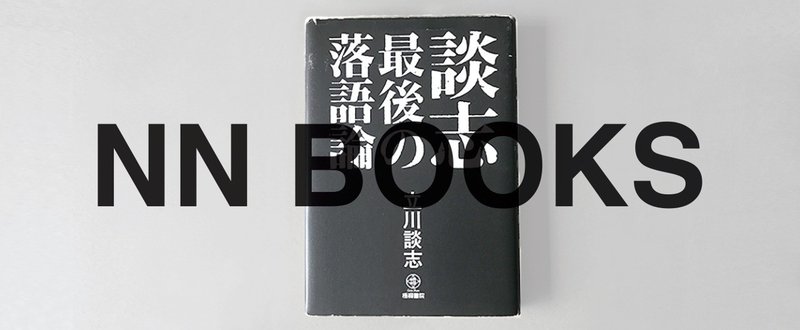
談志最後の落語論
今日ご紹介するのはズバリ落語の本。“談志最後の落語論”です。
“落語はムズカシイ、江戸を舞台にした話なんて21世紀に聞いてもオモシロクない”と、ぼくも思っていました。しかし一度ハマってみるとこれが深くてオモシロイ。
たとえば30点な一日を送っても、大きな成果を残さずに上半期が終わってしまったとしてもあまり凹まなくなりました。それは何故か?この本の著者、立川談志師匠は落語とは“人間の業の肯定”と説きました。
かつて浄土真宗の祖と言われた親鸞和尚は死ぬ間際に“我が人生わかっているけどヤメラレナイ人生だった”と言い残して亡くなったそうですが、まさに人間は分かっちゃいるけどヤメラレナイ、スーダラ節なソンザイ。
21世紀の現代人もそこは全く進化していません。例えば、ダイエットしたくても思わずアイスを食べてしまったり、英語を覚えたくて三日坊主になってしまったり、締め切りギリギリにならないと手が動かなかったり、知ったかぶりをしてしまったり、カッコつけてしまったり。人間はダメでできているなと日々学ばぬ自分にトホホセンサーも常に鳴ってしまいますが、そんな人間を肯定してくれるのが落語なのです。
落語の登場人物に“与太郎”いう人物がいます。
辞書で引くと“バカ”“間抜け”“役立たず”とそれはそれはダメな言葉のオールスターズなんですが、落語の世界では「立派な行い」を笑い「非常識」を肯定するという文化が脈々と生きづいており、談志師匠はこう綴っています。
与太郎は人間の人間社会のその仕組みの無理を知っている。与太郎はバカではない。世間は「生産性がない」ということだけで「バカ」という称号を与える。けど、与太郎はその上をいく。“バカと言われてもいい”と思ってるし“でもあたいは働かないよ”と言っている。「働く(金儲け)なんぞ大したことじゃない。人生に意義なんぞ持つとロクなこたァない」そういうこった。意義を持たないで暮らせりゃ、そんな結構なことはない。けども、人間というのは、意義がないと生きられない厄介な生き物だから、その意義を持つことを“よし”としている。そして世の常識に組み込まれ“よし”とされ、それを「出世」と称している奴なんざァ腹からバカにしている。
まぁ、こんな生き方を地でいったら、大変なことになってしまいますが、落語はそんな気分を代弁してくれます。
そしてもう一つ。落語がカッコイイのは落語には「美談」はないということ。「いいことをすると恥ずかしい」という文化があり、本当の美談は恥ずかしがって表には出てこない。
そう言われてからテレビを見ていると、震災後被災地にわざわざテレビカメラを連れてボランティア活動をするタレントさんがいますが、落語はそういう美談の胡散臭さも見抜くのです。
人生、粋、品、も教えてくれる落語。本書は落語とは何かを現代の言葉で教えてくれます。もし取っ付きにくいと思っているならEテレで放送している“超入門!落語 THE MOVIE”もオススメです。
最後に“やきもち”とは何かを談志師匠の解説で。
やきもち。すなわち「嫉妬」とは何かを教えてやる。己が、努力、行動を起こさずに相手の弱みを挙げつらって自分のレベルまで下げる行為。これを「嫉妬」と言うんです。本来なら相手に並び、抜くための行動、生活をすれば、それで解決するんだ。しかし、人間はなかなかそれができない。嫉妬してるほうがらくだからな。けどな、よく覚えておけ。現実は正解なんだ。時代が悪いの。世の中が悪いの。と言ったところで。状況は何も変わらない。現実は現実だ。その現状を理解し、分析しろ。そこには必ず、なぜそうなったかと言う原因がある。それが認識できたら、あとは行動すればいいんだ。そういう状況判断もできないような奴を俺の基準では馬鹿と言う。©︎立川談志
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
