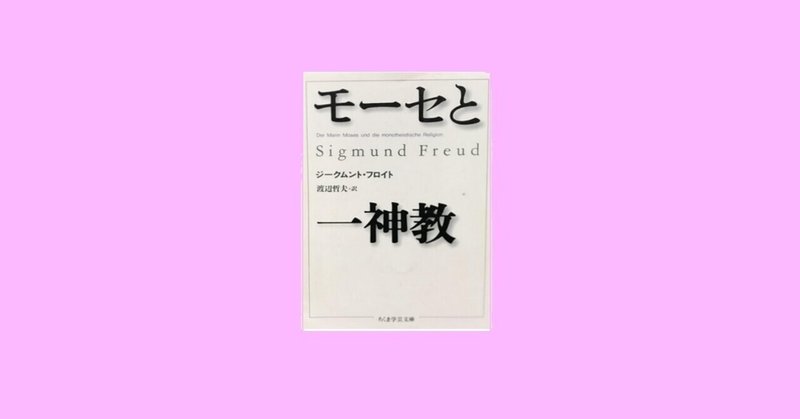
「日本人とユダヤ人」講読
野阿梓
第十一講 モーセ(6)
22
ともあれ、肝心のゼリンの原著論文は私には語学力不足で読めないし、フロイトの引用の内容に不明な点があるし、論文としては参照文献リストがないし、個人的には、これはエセーであって論文ではない。という印象です。生涯にあまたの論文を書いてきた人なら、最期に残すべき論文をこのような雑駁さで書き記すだろうか。疑念はモヤモヤと晴れません。
ただし、その論文について、何か言及している他のサイトや文献があるかも知れない。
そう思いついて――私も一応、元図書館員ですから――、そこで今度はアプローチの方法を変えて、現在、入手可能なフロイトに関する論文で、後代に書かれたものの中に、その引用の出典を明記した文献がないかを、PubMedで検索しました。
PubMedとは、医学・生命科学系のデータベースで、誰のどんな文献が、いつのどの雑誌や媒体に載っているか書誌情報を網羅したものです。
最初は紙媒体のIndex Medicusという月刊誌で、これは創刊が一八七九(明治一二)年で〇四年に電子化に伴い終了するまで、一二〇年間の伝統があります。毎月刊行され、その年の最後に製本された書籍版が送られてきました。あらゆる症例や病名、そして薬物が階層記号化され、私たち図書館員は手作業でそれを牽いていました。戦時中は米軍から戦略物資と見なされ日本への輸出が制約された由です。
私が八〇年代に初めてオンライン検索に携わった頃は、それが電子版のMedlineとして提供されて、学術情報センター(現国立情報学研究所。CiNiiの運営元)のドル箱データベースでしたが(一分間当たりの接続料が二一〇円でした)、今では米医学図書館が無料で公開しています。「医学情報におけるアメリカの最大の貢献」と称されています。
およそ医学・生命科学関連の文献ならグレイリテラチャーと呼ばれる学会で配布されるパンフレットや未刊行媒体の抜き刷りからネットにだけ掲載された文献まで網羅している厖大なデータベースです。ここなら、何かあるかも知れない。
聖書学者ゼリンの論文やその批評は文系ですからデータベースがありませんが(需要と供給の法則から、世界的に、文系のデータベースは概ね貧弱か皆無です)、フロイトの論文は精神分析学の分野なので、PubMedにある可能性に目を付けたのです。
その結果、九四年にロバート・A・ポールという精神医学者が書いた「フロイト、ゼリン、そしてモーセの死(Freud, Sellin and the death of Moses)」という論文を見つけました。ビンゴ!です。「国際精神分析学誌(International Journal of Psychoanalysis)」という専門誌に載ったものでした。
一二頁ほどの論文ですが、英語に堪能でない私には、そのままでは通読できないため、グーグル・ドキュメントでコピーのJPEG画像を取りこみ、テキストでダウンロードした英文を、スペルチェッカーにかけた上、DeepL機械翻訳したものを元に、私訳しました。OCRの精度はグーグルではかなり上がっており、ほとんど修正しないでも良いほど高精度な仕上がりに少し感心しました。いい時代になったものです。
R・A・ポールについては、〇八年のエモリー大学のサイト他によれば、四二年十月一一日コネチカット州ニューヘイブン生まれ(現在七八歳)。六三年にハーバード大の歴史文学の学士号取得。九二年にエモリー大学精神分析研究所臨床研修プログラムを卒業。〇三年現在、米はジョージア州アトランタのエモリー大学大学学部長。九四年当時は同大学精神・行動科学部准教授で精神分析医として勤務。受賞歴に九六年、ハインツ・ハルトマン賞と全米ユダヤ人図書賞が有りましたので後者を調べると、彼の著作「モーセと文明。フロイトの神話に隠された意味(Moses and Civilization: The Meaning Behind Freud's Myth)」(イェール大学出版局)にドロット財団賞が授与されています。これだけでは、彼がユダヤ系かどうかまで判りませんが、そこまで立ち入った調査は、ある意味でPC的に人種差別かも知れない。ジレンマですが個人的には興味がありました。まあ、不明でもいいでしょう。
ともあれ、その論文は、フロイトの末裔たる精神分析家が精神分析の開祖フロイト最後の論考を批判的に論じており、探し当てて本当に好かったと思うくらいに、興味津々な内容でした。
しかし、これを検証するに際しては、注意すべき点が二つあります。
一つ目はエルネスト・ゼリンは聖書学者だった、そしてフロイトは精神分析医だったことです。
二つ目は、他ならぬこの論者R・A・ポール自身も精神分析医だ、ということです。
第一点については、フロイト自身がゼリンの論文に関して、「正しく解釈したかどうかを判断する立場にはありません」と認めている。これはポールにも当て嵌まります。聖書学と精神分析では分野も方法も異なるはずです。そしてフロイトはそれを承知でゼリンの論文からアイディアだけ拝借している(ポールはそう考えています)。
第二点として、彼自身もまたフロイトの又弟子のようなものですから、精神分析学の開祖フロイトへの遠慮の有無を考慮する必要があり(むろん、だからこそ手厳しくなる可能性も否定できません)、そのまま鵜呑みには出来ない。そしてまた、彼も聖書学には門外漢なのです。さらに言えば(言うまでもないかも知れませんが)、私自身、どちらの学問分野に関しても全くの素人です。しかしここは手持ちのカードで勝負するしかありません。
著者ポールの疑念は、まずフロイトがゼリンの論文を見つけて、そこからヒントを得ているにも関わらず、その時点からゼリンの論と距離をおこうとしている点にありました。なぜゼリンの論を「発展」させないのか。この件に関しては、フロイトは、一見、傲岸不遜とも取れる発言をしています。
「われわれはゼリンから(その考えを)借用する。……しかしこの考え以外に関しては研究者に依存せず、独自に「わが道を行く」ことにする」と。
いかにフロイトが精神分析学の泰斗であれ、これはないでしょう。分野こそ違え、同じ研究者なのですから、互いに敬意と礼節は払うべきです。だが、彼は学者として最低限の節度を守っていない。それにはそれなりの理由があるはずだ、とポールは推論します。
従って、ポールは、まず全体をスケッチし、そしてゼリンの論文からフロイトが何を借用したのか、そこからゼリンの仮設を検証する、と言います。妥当な線でしょう。
ポールの観点では、ゼリンの論の中核はホセア書ではなく民数記第二十五章(以下、民数記25と略)の解読にあります。
そこに、おそらくモーセ殺害の秘密が隠されている。そしてモーセが「殉教」したと解読できれば、次にゼリンはイザヤ書第五十三章の「苦難の僕」へと移ることが出来る。これは旧約の預言書ですが、ユダヤ教とキリスト教がともに「救世主」到来の予言であると解釈されていますから、この場合、モーセが「苦難の僕」と見なされ、「殉教」した(が故に)後世になり戻ってくる(=復活する/再臨する)可能性が生まれるだろう。そういう論旨です。
23
しかしゼリンは、まず、補助線としてホセア書(アンカー聖書版)を精査し、「バアル・ペオル(Baal Peor)」を探し当てます。
「彼らはバアル・ペオルのところに来た。彼らは恥に身を捧げた」(第九章第十節)
バアル・ペオルこそ、何か恐ろしいことが起きた地点である、と彼は確信します。バアル・ペオルは地名であり、モアブの地、死海の北東部に位置し、シッテムとも近い場所にある山です。ベト・ペオル(ペオルの家)とも呼ばれ、バアルは元は「主」「所有者」の意味ですから、ペオル山に住むバアル神を崇めていた人々の聖地です。
ここで、私たちは、先に民数記25のシッテムで起きた涜神行為と、血なまぐさい事件を思い出します。モーセの率いる民がモアブの女たちと淫行し、ペオルのバアルを慕ったので、ヤハウェが民を憤った。そしてアロンの孫のピネハスがシメオン族の男とミデアンの族長の娘と番っている現場に乗りこみ、二人を串刺しにした挿話です。
しかし、民(の大半)がバアル信仰に走ったなら、それは創世記で、モーセがシナイ山に入って十戒を授けられている間に、アロンの指導の下に作らせた黄金の仔牛を民が崇めていた事例と等しなみに、一神教と背反する偶像崇拝の重大な涜神行為であり、実際、この二つのケースは対で語られることが多い。
にも関わらず、そして怒れる神ヤハウェは先にモーセに対して、「民の首領をことごとく捕え、日のあるうちにその人々を主の前で処刑しなさい」と命じ、モーセも「あなたがたはおのおの、配下の者どもでペオルのバアルにつきしたがったものを殺しなさい」と民に命じている。だのに、その命令が実行に及ぶ前に、たった一人の英雄が不品行に耽った一組の男女を殺害したことでヤハウェはピネハスを称え、彼に免じて疫病を止めています。罪と罰とその調停の重さが、どう見ても釣り合っていないのです。
もっともこの疫病でユダヤ人は二万四千人が死んだ、とあります。ヤハウェはイスラエル人すべてを全滅させる気でいた、と言いますから、ピネハスが淫行の二人を串刺しにしていなかったら、どれほどの被害があったやら、とも思わせる書き方ですが、別な確度から見ると、非常にうさんくさい。何らかの隠蔽工作の跡が窺えるのです。
その次の第二十六章では、民の人数を算える場面が続くのですが、この時点で(女子供を除いて)六〇万一七三〇人とあります。新共同訳では「壮年男子だけで」とあります。家族も含めた総人数はどこに書いてありませんが、単純に家長と長男だけの数として彼らの妻子を想定すると、おそらく一〇〇万の単位でしょう。最低でも三倍か四倍のはずです。六〇万は、やはり数秘術を応用した誇張した数値と考えるのが妥当だと思われます。そんな人数で、エドムの国境をスリ抜け、モアブやアンモンの地を通っていたら、それだけで一悶着ありそうです。
余談ですが、この中にルベン族の支族の一人として「ダタン(Dathan)」の名があります。これが、ベンダサンの名の由来になっています(BenDathan はダタンの子の意)。ダタンとその仲間はモーセとアロンに逆らった「コラの反乱」の際、神罰で大地に口が開いて呑みこまれたそうです。とにかく、なんだってこのタイミングで国勢調査をしているのか、全く判りませんが。民数記は英語では「Book of Numbers」だから、元々、統計に関する章なのかも知れませんが、読み手の関心をそらすことには成功しているでしょう。
リチャード・E・フリードマンは「旧約聖書を推理する―本当は誰が書いたか」(原著一九八七年刊、海青社 八九年刊)で、「この章はJE資料とP資料に分かれている」と主張していますが、それだけでは説明が付かない点が多すぎます。なぜ、ユダヤ人の一人の男がミデアンの娘と(見た感じ)白昼堂々と睦み合っていたのか。そもそも彼らは当時、モアブの地に宿営していたのですから、ミデアンからは遠い(間にエドムの土地がある)。モアブとミデアンの人々がユダヤ人に対して連携して何かを策んでいたのか。また何故ピネハスは英雄たりえたのか。彼の行為がどうして祭司の先祖となるのか。
と、疑問は尽きないのですが、ゼリンは、ここで、全く新しい観点から、エレガントな解法を示して見せるのです。
「モーセ自身以外に誰がミデアン人の妻を娶ったのか? モーセがその民の罪のために自分を殺すようにヤハウェに懇願したのは、彼以外に誰がいたのか? そして、他の誰の死によって、記述されていたような恐ろしい疫病が全国民から取り除かれることができただろうか」と。
すなわちシメオン族のジムリもミデアンの女コズビも、全て「偽名」で虚構だと言うのです。
モーセはミデアンの地に寄留していた間に、養父エテロの承認の下、その娘チッポラと結婚しています。というよりチッポラの娘婿となることでエテロの養子になった、というべきでしょうか。しかし、神の召命があってエジプトに戻った時のモーセは一人でした。シナイ山にエテロが訪れた時、彼は娘チッポラやその子らを連れてきてもいます。しかるに、チッポラたちがどうなったのかは不明のまま、シナイ半島を彷徨っている際に「モーセはクシの女をめとっていた」(民数記第十二章第一節)ことで、姉兄のミリアムとアロンから非難されています。ところがミデアンの部族神のはずのヤハウェは、逆にモーセを擁護し、ミリアムを重い皮膚病(ツァーラト)に罹らせ罰する、という挿話があります。
モーセが「重婚」の罪を犯したなら、それは彼を批判するミリアムとアロンの方が正論だと思うのですが、古来、ユダヤ社会では、アブラハムからソロモンにいたるまで一夫多妻制が普通でしたから、どこまでがユダヤ社会での「正論」かは判りません。ソロモンはファラオの娘をはじめ多くの政略結婚をしており、それがために(その側室の)偶像礼拝を認めて、神の怒りをかっていますから、少なくとも族長の一夫多妻制はともあれ、その結果は「正論」とは認められないでしょうが、偉大な男なら数多くの妻を持つことは神も認めていたのかも知れない。新約時代では、さすがに一夫多妻制は認められていないので、これは伝説時代の「偉大な男たち」の物語の属性と考える方がよいか、と思われます。そして、この時すでにヤハウェはもうミデアンの部族神では有りないのです。
いずれにせよ、モーセは重婚を厭わなかった。それは神も認めていた。しかし民の中には(というより民を代表して実の兄と姉が)モーセの重婚を非難する声もあった。そこが重要です。
クシ(クシテ)は、ノアの三人の息子、セム、ハム、ヤペテのうち、ハムの息子であり、一般名詞では古代エチオピアを指す言葉ですので、どうして突然、ここにエチオピアの女が登場するのかも不思議なのですが、これは18項で先述したように、ヨセフスのユダヤ古代誌には、エジプト時代のモーセが将軍としてエチオピアに遠征した、という説話が記されています。しかし、おそらく無関係でしょう。ユダヤと無関係な他国民なら誰でもよかったのです。
あっさり言ってしまえば、モーセは指導者/原父という立場を利用して、一般の民には許していない重婚により淫行に耽った。モーセ五書に描かれた民の堕落は他ならぬモーセが犯した罪であった。だから、民の代表としてアロンとミリアムはそれを叱った。いや、叱っただけではなく、おそらく、民は(アロンとミリアムの媒介なしにでも)大勢で襲って、この理不尽な淫行に耽る暴戻なる原父を殺害したのでしょう。それがバアル・ペオル、またはシッティムで犯された「血の罪」だった。というのが真相だとゼリンは言います。
24
ここでポールが奇妙だと言うのは、ジムリという偽名で原父モーセが、重婚の妻との性交中に、彼の大甥ピネハスに殺害された、とゼリンが唱える、極めて「フロイト的」な挿話が、当のフロイトには何ら感度がなく、見過ごされていることです。なにより、ここでのゼリンの考察は驚くほどフロイトのエディプス・コンプレックスなどの考察に似ている。エディプス的な行為、男根、去勢、サディスティックな復讐といった舞台装置がそろったなら、それは「トーテムとタブー」でフロイトが描いた、原始的な圧伏されていた下層民の血の復讐として、フロイトは、むしろ喜び勇んでその箇所を取り上げたでしょう。それなのに、なぜか、この挿話は不当なまでに無視されている。
しかも、この生世話的な場面は結構、ユダヤ人にも卑俗なる関心があったらしく、ミドラーシュ(聖書解釈学)には、無数の枝葉が付されています。いわくピネハスが幕舎に入った時、天使が顕れて、二人の姦夫姦婦が離れないよう動けなくした。ピネハスの槍は二人の性器を貫いた。その時槍は伸びて天使がピネハスの膂力を強めたので二人を串刺しにしたまま、彼はそれを持ち上げた。などなど。英雄譚には付きものの枝葉と言ってしまえばそれまでですが、内容があまりにもセンシュアルすぎます。
後代の解説書では、もっと露骨に情景を描いています。たとえば……その邪悪な男(=ジムリ)は一日のうちに百二十四回も媾合し、ピネハスは彼の力が弱まるのを待っていた。六十回目までに男が腐った卵のようになり、女は水で満たされる溝のようになった。女の子宮は一キュビト(四五センチ)に開いていた。等々。
精神分析家のポールは、これ以上の説明がいるだろうか、と言います。彼は「フロイト主義者」がこのような資料をどのように利用するかは誰にでも判る。と主張します(ここで「誰でも」と言われているのは「「国際精神分析学誌」の読者なら誰でも、の意味でしょう)。それなのに、当然、こうした周辺資料はフロイトも知っていたはずであるにも関わらず、なぜか、彼は反応しない。もし、ここで殺されたのが民数記にあるように、一介のユダヤ人族長の「ジムリ」だったら、おそらくフロイトは大喜びで「分析」したでしょう。だが、しない。それどころか、
「ゼリンは東ヨルダンにあるシティムの地をモーセへの凶行がなされた舞台と見なしている。しかしこのような地域の特定がわれわれの思索にとって受け容れられない」
――とまで言って、フロイトは、ゼリンの論を採択しないのです。著者ポールは、
「フロイトがゼリンを使ったことに関する謎は、なぜゼリンに説得されたのかではなく、むしろなぜゼリンを使わなかったのかである、という命題を擁護できる立場になりました」
――と評しています。確かに、そう言われても仕方がない。ここまで来ると、最初の謎であった、フロイト文献に学術論文なら必須の真っ当な引用文献一覧がなかった意味が判ってきます。彼はそれを、自分がゼリンの本から「引用」した箇所を書けなかった。なぜなら、引用したくとも、出来なかったからです。しかし、だとすると、一体フロイトは何をしたいのか。ゼリンに触発されながら、ゼリンの考えを採らないで一体なにを言いたいのか。
ゼリンの論を上げながら、モーセが荒野に彷徨わせた民に殺された、という点しか、フロイトはゼリンの論から獲ていません。しかも、先に引用した箇所の全文では、実は、
「エジプト人モーセがユダヤ人によって打ち殺され、モーセによって伝えられた宗教が捨て去られた、という考えをわれわれはゼリンから借用する」
――とフロイトは言っているのです。
エジプト人モーセ? ここでポールはフロイトの「虚勢」を指摘します。なぜなら、
「ゼリンは、モーセがエジプト人であるとは信じていませんでした。それどころか、ゼリンは、ドイツ(プロテスタント)聖書学者の先輩や同僚たちとは正確に異なり、イェルシャルミが指摘するように、彼はモーセが聖書に書かれている通りの実在の歴史上の人物であり、ファラオの家で養子として育てられたイスラエル人であり、イスラエル人一神教の創始者であると信じていた」からです。
つまり、フロイトは、モーセが民に殺された、という以外の考えを超えて、ゼリンから何も借りてはいないのです。しかしながら、さすがにポールも現役の精神分析家であり、そこは抜け目がありません。彼は、
「しかし、いわゆる「エジプト人のモーセ」についてのフロイトの「スリップ(言い間違い)」は、ゼリンのテキストとフロイト自身の奇妙な関係を解釈するための手がかりとなります」と、鋭い観察を見せるのです。心理の揺れ動きを読み取る分析家ならではの、着目でしょう。その創始者であるフロイトにしても、ついうっかりと「言い間違い」をする可能性は、確かにある。
特に言及しておくと、ここで言う「言い間違い(英語=Slip)」とはフロイト的には深い意味のあるタームです。そもそもフロイトが唱えた学術用語であり、「フロイト的言い間違い(Freudian slip)」とは、他にも「書き間違い」「ど忘れ」といったものを総称して「錯誤行為/失錯(parapraxis)」と呼ばれます。要するに、人は心の底で欲望し期待していることがあり、それが自己の倫理的規範に抵触するとき、思いもしない間違いを言ったり書いたり忘れたりするものだ、ということです。これは本当に心の底=無意識で起きる働らきですから、意識の表面には上がってきません。心理学者、精神分析家だけが、鋭く深い洞察によってのみ、それに気づくのです。
しかし、「言い間違い」をしたのなら、その人が、その時、何かしらの葛藤をかかえていることを意味している。それが精神分析家なら判ります。つまり、この時、フロイト自身が、そういう「言い間違い」をした=葛藤していた、と分析家ポールが言えば、それは確かなことであり、この時、フロイトが内心、葛藤していたことも自明なのです。
フロイトは、明らかにそう書くつもりはなかったのに、つい「(ゼリンの言う)エジプト人モーセ」と書いてしまった。ゼリンはそんなこと露さら思ってもいないし、書いてもいないはずなのに、フロイトは、自分が意識下で、自分がそう思いたいから、つい潜在的願望として「言い間違い」をしてしまった、というわけです。
25
さらに、フロイトの時代には、多くの聖書学者は、旧約の時代に歴史を見出し、そこに書かれたことが何か実際に起こったことのように構築するのに腐心していたことをフロイトは見抜いていました。つまりフロイトは自らの歴史の再構築が、同時代の聖書学者たちの「ロマンス」と等しなみだと知っていたのです。ところが、ゼリンは違う。いかに専門分野外の学問であっても、フロイトはそれくらいは理解していた。
そこでポールは確信するのです。
「ゼリンが彼ら(他の聖書学者)と異なっていたのは、一神教という考え方が、野蛮な火山神を崇拝していた初期のミデアン人やレビ人の祭司であるモーセに関する伝説の中に時代錯誤的に読み込まれたものではなく、すでに倫理的な一神教であった本物のモーセが存在していた、という信念でした。……(だとすれば)この点でのフロイトの独創性は、モーセの一神教がどこから来たのか、また、それが失われたように見えても、実際には何世紀もの間保存されていたのかという問題をどのように解決したかにあります」
このあたりは、精神分析学の創始者であるフロイトの論を、ほぼ六十年後に、その弟子の末裔である精神分析家ポールがいかに読み解いていくか、というドラマティックな解釈と再解釈、隠蔽と暴露のせめぎ合いです。ポールは、フロイトがこの論の草稿に使った「歴史小説(英語:Historical Romance)」の語を、再び日の下に引きずり出します。それはフロイトの「家族小説(英語:Family Romance)」というファンタジー分析の再話です。
ユダヤ民族がその何度となく(もうこれ以上立ち直れないほどに)打ちのめされ続けた悲惨な「歴史」に対して、「これは俺たちの本当の歴史じゃない。俺たちは本当は神に選ばれた聖なる民なのだ。この惨めでどん底の歴史から抜け出させてくれるために、いつかきっと救世主が顕れ、俺たちを救ってくれるはずだ」という幼児的な幻想を抱いていることは、実は、誰も憶えていない、思い出せないほど太古の昔に、自分たち自身が恐るべき凶行を、血の罪を犯したのではないか、という深層/真相を暴くことです。いや、そこまで決めつけるのは勇み足でしょうか。しかし――、
「フロイトの考え方によれば、モーセがエジプト人であったならば、彼はファラオのイクナトンが創設した一神教の信奉者であった可能性がある。師(イクナトン)の死と混乱を生き抜いたフロイトのモーセは、伝統的なアメン司祭たちによる復活した信仰の迫害に耐えましたが、師の教えを後世に残す方法を思いつきました。彼は、エジプト社会のはずれから賦役労働者と牧畜民の一団を弟子として選び、アマルナ革命が無残に崩壊した後の内戦の期間中に、エジプトからシナイ砂漠のオアシスであるカデシュに彼らを導くことに成功しました」
「そこで彼は、イクナトンの新宗教の中心的な特徴であった正義の概念「マアト(Maat)」から派生した厳格な法規範を彼らに課しました。しかし寄せ集め労働者たちは、モーセが課した「律法」の厳しさに耐えられず、反発心を募らせ、ついにモーセを暗殺しました」
これが、ポールによるフロイトの論の分析でした。
しかし、いつわりのモーセの物語は、まだ終わりではありません。なにしろそこは遮るものとてない荒野の真ん中で、彼らは地図も目的さえない烏合の衆でした。一時の激情にかられてモーセを殺害はしたはいいが、彼らは指導者モーセがいなければ何も出来ない存在だった。羅針盤すらないのです。しかしながら、モーセは単独でこの偉業を成し遂げようとしたわけではない。レビ人と呼ばれる彼の親衛隊は残っていました。
葦の海をわたってから一直線にシナイ山まで辿ったのは、おそらく彼らレビ人が、エジプトの古道――かつて銅鉱とトルコ石の採掘場だったルートを知っていたからでしょう。王族の親衛隊を務めるには、そういう知識も、いざと言う時のために必要だったのでしょう。彼らは、この古道を南下すれば追っ手を撒けると思ったはずです。だからこそ大迂回路をめぐってシナイ山に来た。そこでモーセが十戒を授かった、という説話は、この古道を通るためのアリバイ工作のようなものだったと思われます。
そして、アロンらレビ人と烏合の民との利害は一致します。頼る者がほかにない彼らは、一時の亢奮からさめると、荒野の中で立ちすくんだでしょう。もうエジプトには帰れない。新しいファラオは、脱走した彼らを捕らえて、再び賦役に付けるでしょうか。否、政府高官のモーセを殺した今、おそらくまだ内戦状態のあの国に帰るのは自殺行為だろう。それくらいの知恵はまわったはずです。だとすれば――もう、このレビ人たちに付いていくしかない。
一方――、
当然ながら、親衛隊=レビ人の長であるアロンは、目の前で暴民が激昂するのを抑えきれず、主人モーセが殺害されるのを座視するしかなかったことで大きく動揺したはずです。しかし、そこは軍事国家エジプトでだてに高官の親衛隊長を務めていたわけではないアロンは、すぐさま次の手を考えたでしょう。もはや主たるモーセの計画は半ば頓挫してしまった。だがモーセの仕えた王イクナトンと、そしてモーセ自身の夢と野望は未然のまま、残っている。かくなる上は、どうにか自分たちが、この温和しくさせた暴民ハビル人を引き連れて、主人モーセとその王イクナトンの見果てぬ夢と計画とを完遂するしかない。
レビ人たちにしても、むざむざと自分たちの最高指揮官であるエジプト王宮の高官モーセを目の前で殺されてしまい、面目を失なって混乱したかも知れませんが、すぐにその主席補佐官たるアロンは、状況を把握し、上記の判断にいたったことでしょう。当時はヤハウェ神の祭司であるより主人に忠誠を誓う戦士の側面をもつ彼らなら、そう考えたはずです。見晴るかす一望の荒野と峨々たる山岳よりほか何もないシナイ半島と異なり、すぐ隣りのアラビア半島は群雄割拠の激戦区です。レビ人たちの彼らはそれをよく知っていました。無法者のハビル人がモーセを殺したのがカデシュだとして、北方にはエドム王の領土があり、迂回してミデアンの地に出たとしても、(もしカデシュでなされた、という十二人の斥候=密偵の挿話が真実だとすると)乳と蜜の流れる沃野カナンには、モアブ、アンモン、ペリシテ人ら猛者が折りあらば互いに侵攻しようと盤踞している。カナンの地にはエリコなど城塞都市群があって攻めるに堅く、いくらモーセの初志を貫こうと、親衛隊規模のレビ人が民を叱咤激励したところで、四十年前まで奴隷だった流浪の民が一夜にして戦闘団になるものではない。では、彼らは一体どうしたのか?
26
ここまでは、私にも、ポールの思考は追えるし、理解もできるのですが、この後が違ってきます。
「その後、この難民の一団は「レビ人」に率いられ、カデシュ周辺で火山の神「ヤハウェ」を崇拝するミデアン人の族長と同盟を結んだ。エジプトの「レビ人」とこの新しいミデアン人の族長との間で妥協が成立し、レビ人からは割礼や豚肉を食べることの禁止などのエジプトの習慣を維持しつつ、ミデアン側からはヤハウェという部族神をイクナトンの(アトン神という)一神教で崇拝されている神と同一であると認識されることになった。
一方、ミデアン人の族長は「モーセ」という敬称を名乗り、この名を冠してカナン征服を計画したが、ヨルダン川を渡る前に死んでしまった」
――とポールは言います。ちょっと驚くべき論の展開です。ひょっとしたら、開祖のフロイトよりも想像力に長けているのかも知れない。当時の歴史状況と、フロイトの唱えたロジックを重ね合わせて、さらに奇怪な「歴史小説」を精神分析家ポールは描き出します。
すなわちモーセは二人いたことになる。一人はエジプトの貴族で一神教の信者、もう一人はミデアン人の将です。エジプト貴族の方はカデシュの手前であえなく殺害され、誰もその遺骸を葬り去った場所すら知らない。否、誰ひとり記憶したくないから忘れたのでしょう。他方、ミデアンの部族長は、ポールの書き方だと、きっと二代目の「モーセ」なのでしょうが、彼は、レビ人が唱えたであろう道徳律「マアト」も一神教も厳格な倫理観などにも全く興味がなく、なんとかミデアンの地でエジプト流の軍事訓練を受けて、多少は進歩した「イスラエル人」としてカナンを征服することに成功します。
エリコ攻略に見るヨシュアの軍事行動は、おそらく、それまでのカナン=パレスチナの地には無かったような、斬新で奇抜な「近代的」な戦略と戦術――軍事大国エジプトで一千年にわたって培われてきた思考と実戦の産物だったのでしょう。エリコ攻略は、ヨシュアが派遣した斥候(スパイ)が、城内の遊女を籠絡して、いわば内部からの外患誘致の作戦によって成ったものです。
ところで面白いことに、記録される最古のスパイは、時代は少し違いますが、ラムセス二世がヒッタイトと戦った、その名も「カデシュの戦い」の時に記されています。このカデシュはバアル・ペオル近くのそれではなく、オロンテス河畔にあった古代シリアの都市を指します。
当時、捕らえたヒッタイト軍のスパイの自白により、敵陣がアレッポにあると知ったラムセスは、神速の行軍でカデシュ陥落を謀りますが、実はこの情報は虚報で、カデシュの丘の向こうにはヒッタイト軍の戦車隊が潜ませてあったのです。捕らえた密偵の情報は偽わりでした。否、最初からエジプト軍を攪乱する目的で、偽情報をもたらすために、その密偵はわざと捕らえられた可能性すらある。
そこでラムセス王は苦境に陥いるのですが、遅れて到着した支援部隊のお陰でなんとかヒッタイト軍を打ち払います。出エジプトがいつの時代だったか、それは問題ではありません。要するに、ヒッタイトと戦役を構えたエジプトにも、それだけの知謀の蓄積はあっただろう、ということです。密偵を放ち、その密偵にすら偽わりの情報を与え、敵の裏の裏をかく戦術があった。古代の情報戦です。
そしてエジプト王朝に仕えた王家の親衛隊たるレビ人にも、一千年の戦争によって発達した、その知略が背後にある。大国同士の正規軍が戦う戦役です。パレスチナの荒野での小規模な小競り合いとは訳が違う。たぶん、そのせいで、新生モーセ改めヨシュアに率いられたミデアン=ハビル連合軍は破竹の勢いで、アッという間にカナン侵攻を果たせたのでしょう。
ポールは詳しくは書いていませんが、ここで、第二のモーセがヨルダンを渡河する前に死んで、その後をユシュアが継いだかどうかは、あまり問題になりません。ミデアンの戦士が、自らをモーセと名乗るのを止めて、ヨシュアと名乗ることにしたのかも知れませんし、そもそもが元はホセアだったヨシュアの出自は曖昧なのですから、どっちでも構わない。だが、いずれにせよ彼にはエジプト王朝の暗い理知であるレビ人の叡智が常に側近くあった。そして新たなヨシュアにはミデアン人として戦ってきた実戦経験があった。それこそが重要なのです。
群雄割拠するカナンの地をアッという間に撃破し進軍した、ヨシュア麾下の異質な強兵は、初めてシナイ半島で遭遇したアマレク人と闘った時のヨシュアとは明らかに違う。その間に流れた四十年の歳月を考慮しても、両者は違っている。戦略戦術は「知識」として有るだけでは役に立たない。必ず実戦が、それも軍団単位でのそれが必要となる。ミデアンの戦士とエジプト軍の知略が合わさってこそ、それが成ったのでしょう。この聖なる野合によって、カナンの地のパワーバランスが崩れ去り、ミデアンの戦士に率いられるモーセ親衛隊レビ人とハビル人部隊は、カナンを席巻できたのです。
しかしミデアン人たちと合流し野合して出来た「ハビル人」の末裔らは、カナンに入植してから何世紀もの間、モーセ殺害も、イクナトンの革命も、また忘れ去られたままでした。フロイトの言う「潜伏期」です。
ところが、それから数百年後、ユダヤが南北に分裂し、巨大帝国が襲いかかる民族的危機が訪れます。その時――、
「預言者の時代になって、イスラエル王国の興隆と衰退を経て、エジプト人モーセの高尚な教えが、それまでの休眠状態から途方もない力をもって復活したのである」とポールは説きます。
こうした歴史の再構築によって、フロイトは、彼独自の類推の方法で、ユダヤ・キリスト教文明の宗教史に、一人の個人における強迫神経症の歴史の経過についての精神分析的理解を適用することができる。人は幼少期に(それが現実であれ幻想であれ)エディプス的な性と暴力の場面をくぐっている。エディプス・コンプレックスが解消された後、「潜伏期」には、記憶/空想が抑圧され、反応形成、隔離、および行うことと元に戻すことの古典的な強迫性な防衛機制が構築される。
思春期には、性的衝動が急増すると、防衛機制は、強迫、儀式、禁止、および思考と行動の他の制限として抑圧されたものが戻ることを可能にするために多少の小径を与える。これらの「症状」は、同時に無意識のエディプス幻想/記憶を繰り返し、追い払おうとする妥協の形成である。
このようにポールは分析、解明していきます。
フロイトが分析したであろうモーセの民の場合、彼らは、集団として「エディプス的暴力(=モーセの殺害)」という行為の記憶を民族全体の意識下に抑圧していた。
ところが、民族滅亡の危機の時代になると、それは、預言者や後のラビが最初に唱えたエレミヤ書、厳しい禁止事項、法治主義的な道徳的要求に代表される文化的な超自我の構築の基礎となって戻ってきた。
一人の人間心理の分析された古層にも似て、一民族の古層はそれなりに狂暴なエディプス的暴力に満ちていたのである。それは幼くして想像または体験された樹の切り株のように、成長してもなお傷痕として残り、ふだんは抑圧しているから平静を保っていられるのだが、危機的状況となると、とたんに回帰して個人を、そして民族をも脅かす深層に流れる目に見えないエネルギーなのだ……。
27
このように分析してきたポールは、立ち止まって、(ワイルドのサロメめいた)自問自答します。然れど、しかし――、
「もし、ゼリンが銀の大皿の上に、彼の夢の性と暴力の再構築されたエディプス的な行為を手渡したとしたら、なぜフロイトは、かたくなに、否、殺人はシッティムでは起こりえなかったと主張する代わりに、ゼリンが提唱したその贈り物を受け入れなかったのだろうか?」
「その答えは、フロイトの歴史的なナラティヴ(物語)の解説を見れば明らかでしょう。
ゼリンがエジプト人でもミデアン人でもなく、普通の古いモーセであったのに対し、フロイトの物語では、これら二つの全く異なるモーセが必要になります。
前者のエジプト人は、洗練された厳しい倫理観を持つ一神教の信者であり、後者は基本的に軍事指導者でした。律法を授ける一神教のエジプト人の殺害だけが、フロイトが試みた強迫神経症との類推と一致するでしょう。ユダヤ人や後のキリスト教の神が抑圧された者の回帰として理解されるならば、抑圧された者が神の無意識のモデルとなったことが適切でなければならない。
このような(一軍事指導者である)人物の殺害は、砂漠のどこかで無差別にベドウィンの指導者が暴力的に死んだ場合と同様に、抑圧されたトラウマのように歴史の中で作用することはなかったでしょう」
そしてポールは、ふたたびシッテムに帰ってきます。カデシュではない。
それは、バアル・ペオル(ベト・ペオル)に隣接する、ヘブル人が四十年に及ぶ荒野の旅の最後の宿営地であり、また、ヨシュアがカナン侵攻の最初の作戦であるエリコの攻撃を開始した場所です。しかし、そこにいるのは、ヨシュアを名乗る軍事指導者です。モーセではなく、またエジプト人、あるいはハビル人でさえ、ない。
だからこそ――、
「シッティムで死んだ「モーセ」は、フロイトのシナリオでは、エジプトの律法学者ではなく、ミデアン人の戦争指導者に対応していなければならない。エジプト人の「モーセ」は、フロイトの「二人のモーセ」理論が機能するためには、シナイの荒れ地での滞在中に、もっと早くに殺されていなければならない。
したがって、もしフロイトが、モーセの死の現場をシッティムとしたゼリンの説を受け入れるとすれば、殺されたモーセはエジプトの宗教指導者であって、砂漠の戦士ではないというフロイト自身のテーゼが否定されることになるでしょう。
ユダヤ・キリスト教文明の歴史と強迫神経症のケースとの間の類似性を維持するために、フロイトはこのようにして、ゼリンの解釈スキーム全体を拒否することを余儀なくされ、ゼリンの再構築された歴史の中に暗示されている典型的なエディプスの原始的なシーンのイメージと一緒に拒否されるのです」
ポールは、このように推論した後、ゼリンの論文を前に、フロイトがどう思案したかを追いつつ、いくつかのシナリオを分けて、フロイトがどのような選択肢を考えたであろうか、と思いをめぐらせています。たとえばフロイトは、ゼリンの論文から、「民数記25の象徴的なイメージをソースとして使用して、ユダヤ・キリスト教の伝統の中で、モーセの殉教という仮説のエディプス的な意味を探求する」ことも可能でした。あるいはゼリンと無関係に、全く異なるシナリオもあった。それは、「イクナトンの一神教とモーセオリジナルの一神教とが何世紀にもわたって遅延状態で存在していたことで、預言者たちの時代に圧倒的な説得力をもって再び現れることができるという利点がある。これはモーセ殺害と強迫神経症の中心にあるオリジナルなトラウマとの類推に依存して」います。
最終的にフロイトは、ゼリンの中核とは異なる周縁的なアイディアだけ「借用」して、独自の理論を打ち樹てるのですが、ここでポールは、当時のフロイトが置かれていた状況を勘案して、再び、ちがった思考に進みます。すなわち、それ自体蠱惑的であるゼリンのアイディアを犠牲にしてまでも、フロイトがその独自路線を進んだ最大の思いが何だったのか、という問いです。ポールは、それを、フロイトがモーセその人と自分を同一視していた可能性について言及するのです。
ちょっと見には、いかな二十世紀最大の知の巨人とはいえ、フロイト自身が、ユダヤ教を創始したモーセと自分を等しなみに見なすのは倨傲に思えますが、それが落想された決定的な時と場所は、安全な亡命の地ロンドンではなく、一番最初にフロイトがこの論文を創案した三五年のウィーンなのです。
迫り来る病魔と自らの遠くない死、同様に迫り来るナチスの昏い影。そうした危機的強迫が、当時のフロイトにはありました。さらにいえば、ユダヤ人特有の厳格な「父」としてのフロイト自身の性格から、育てた弟子たちが次々の離反していた現実があります。自身の死、ナチスの勝利、そして自分の信奉者の離反によって、自身が打ち樹てた精神分析の学理そのものが、消滅してしまう可能性をも、彼は、老君一人寂寞として視つめていた。
これは、単に一学問が消え去るよりも、フロイト最大の関心事として、西洋文明の自己理解が(彼の理論によって)可能になるか、それとも消滅するか、という気宇壮大な問題になります。個人を超えた葛藤があったわけです。そこでポールは、
「潜伏期の間に元の記憶が失われたように見えて、抑圧から戻ってきて、ずっと後になって自分自身を取り戻すという強迫神経症とのアナロジーは、彼自身のような偉大な真理もまた同じような運命をたどるのではないかという願いと希望を満たしていたのではないか」と想像するのです。
創始者の迫害と死(殺害)、それの抑圧。長い潜伏期を経て復活する(学問の)復活――、こうした強迫神経症のアナロジーは、ついに、フロイトが自分自身をモーセと同化することによって、彼に一つの希望を与えることになる。つまり、今、自分がモーセのように死ぬことで、自分の創始した学としての精神分析の原理は、あたかもモーセが創始したユダヤ教のように、長い潜伏期間をへだてて、将来において、輝ける復活を遂げるかも知れない。
そのようにポールはフロイトの思考をトレースします。ここで、通常の神経では至るはずのない逆転が起きます。
「「イクナトン」とは、「有名な謎を解いた」若きエディプスの勝利者であるフロイトのことである。一方、「モーセ」は疲れ果て、諦念をいだきつつ、敵対する世界での不確かな運命を、亡命によって、かつての栄光の時代の遺物として貴重な教義を、手放した頑固な老人であった」と。
それゆえ、「フロイトが、おそらく不合理な希望を育んだかもしれないと思うのも不思議ではない。彼の教えは、抑圧された初期の記憶のように、消えてしまったように見えるかもしれないが、勝利のために再び立ち上がることができるだろう」
すなわち、この理論から行けば、今、フロイトが老いて朽ち果てても、その理論は長い潜伏期間を距てて、いつか世界に再臨する(かも知れない)。あたかも荒野で、その墓の在り処すら誰にも知られずに死んだモーセのように、亡命先で一人孤独に死んだフロイトの思想は、やがていつの日にか、世界を救済する預言の書として「復活」するかも知れない、と。
そして、ポールはいかにもユダヤ人フロイトに沿った思考の果てに、次のように論考を結んでいます。
「それは、イザヤ書「苦難の僕」の読解の中で、ゼリンがモーセに対して企てた運命に似ていなくもない」と。
一人の精神分析家が、その創始者の最期の論考と真正面から立ち向かい、歴史の闇に葬り去られた陰惨なる出来事を暴き、それとフロイトが対象となるモーセと自分自身を同一視するまでの思考を追っていく姿は、その元のフロイトの論考がいかに荒唐無稽に思えるか、といったことを離れて、同じ原理による論理と論理が葛藤し、ついにそれを解いてゆく過程は、あたかもエディプスがスフィンクスの謎を解き明かしたように、いっそ神話的ですらある。それは一種、感動的で崇高な魂の闘いにすら見えます。
同時にまた、精神分析という学派の原理が、人間の魂の奥底を剔抉する手法であることを思う時、私は、自分が八十年代に愛読していた柄谷行人の次のような言葉を思い出さずにはいられませんでした。
「たとえば、フロイトの精神分析の方法についてはだれでも読みかじっている。が、精神分析によってひとりの患者の全容を知るのにはまず五年はかかると覚悟しなければならない。われわれは症例報告だけを読むから、それがやすやすとなされたかのように錯覚しがちだが、フロイトが生涯で治療しえた患者の数は非常に少ない。厳密にはゼロである。彼はその過程でたえず理論を検証し修正しつづけたのであって、できあがった精神分析的方法を文学に適用するといった怠惰な作家の作業とは根本的に異なるのである。
のみならず、精神分析とは、それ自体「読む」ことであり、むしろ精神分析こそ文学批評に属しているというべきである。さらにまた、フロイトのテクストを「読む」ことはけっして容易ではない。フロイトのテクストのなかに、反フロイディズムをさえ読むこと、それが「読む」ことなのだ。「フロイト的方法」などといったものを斥けなければ、フロイトの「方法」を読むことはできないのである」(「反文学論」冬樹社 七九年刊/講談社学術文庫 九一年刊より、四七頁)
PREV | NEXT
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

