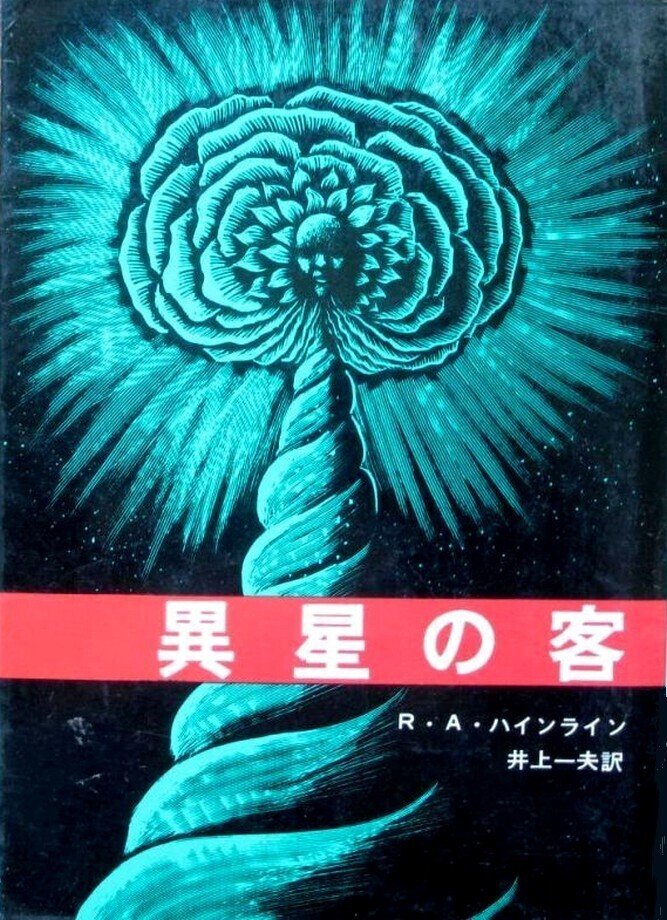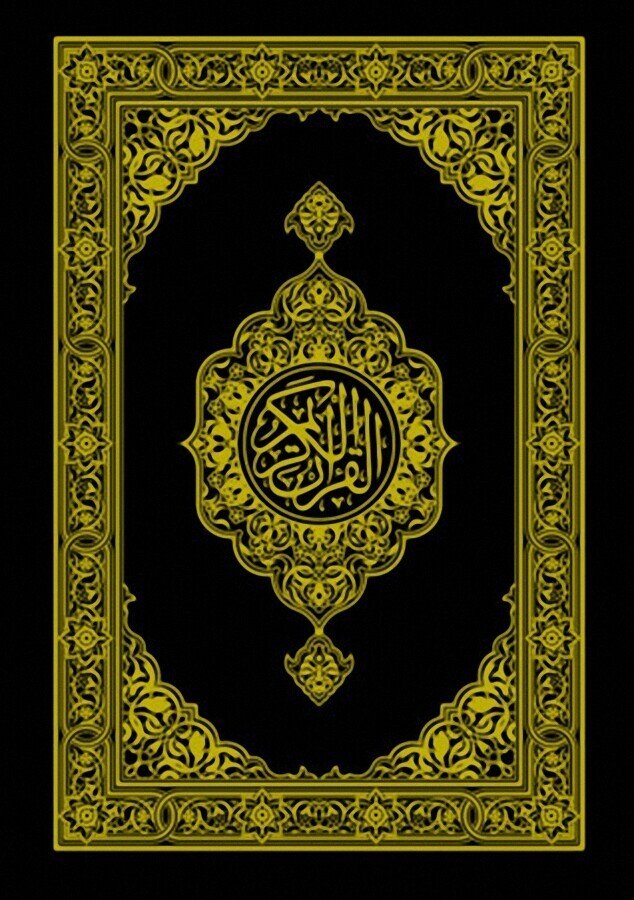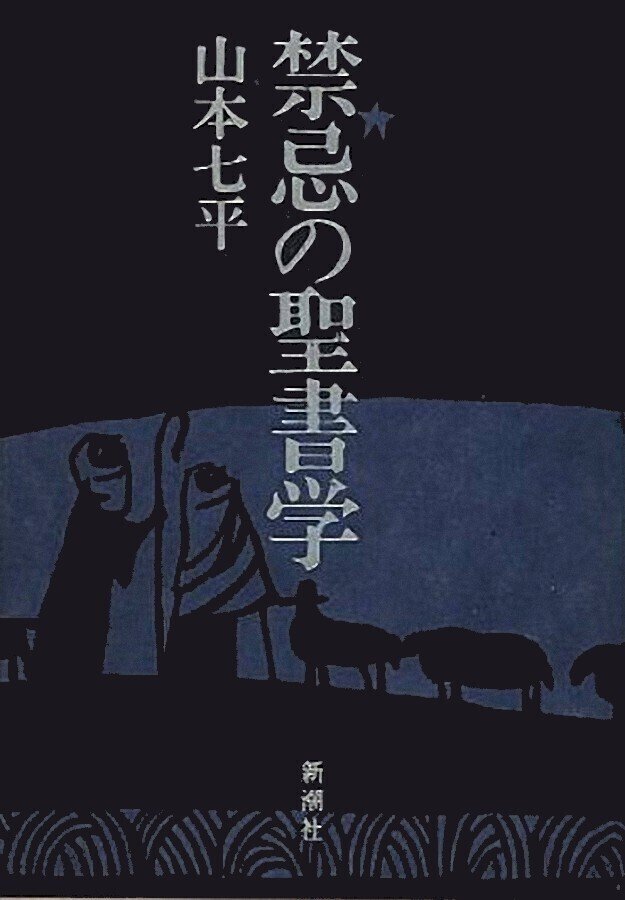「日本人とユダヤ人」講読
野阿梓
第五講 ギデオン(1)
1
日本でも、ビジネスホテルなどに泊まると、部屋に聖書が置いてあるのをよく見かけます。
あれは、奥付には「日本国際ギデオン協会」とあり、無償でホテルなどに配布している聖書です。そこで通称「ギデオン聖書」と呼ばれています。七〇年当時、現物をまだ見たことがなかった私が、これを知っていたのは、ダシール・ハメット「血の収穫」の中に言及されていたからです。まあ、それは別にいいでしょう。さすがに引用はしません。
クリスチャンではない無信徒に無料で聖書を配るのが協会の使命だと聞きます。協会(「教会」ではない)によると、「自由に持ち帰って良い」そうです。太っ腹ではありますが、あまり日常的に聖書に親しみのない日本人は、まずホテルでいかにヒマであっても読まないだろうし、また持ち帰る人も稀だろう、とは思います。
文庫版には――、
「この行事は三千年以上昔のギデオンの時代から、二十世紀まで連綿とつづいている。聖書のギデオンの記事と、一九三六年にパレスチナを旅行したキッテルの記述とが、余りに似ているのにだれでも一驚する」(六〇頁)
――とあります。
が、残念ながら、大半の読者はギデオンもキッテルも知らないでしょう。七〇年時点で、前者は知っていた私も、後者は初耳でしたし、今回、調べて初めて知ったようなものです。
この場合のギデオンは、協会の名の由来となった古代ユダヤ人のギデオンで、先に述べた士師(さばきつかさ)の一人です。旧約聖書、士師記の第六章から八章にかけて活躍の記述があります。どちらかと言うと、ギデオンはペリシテ人その他との戦いよりは、ユダヤ人自身のバール神への偶像礼拝を撤廃することに傾注したように見えるのですが、第八章の末尾によると、彼の死後、「イスラエルの人々はまたバアルを慕って、これと姦淫を行い、バアル・ベリテを自分たちの神とした」とあるので、なんだか、それまで描かれたギデオンの獅子奮迅の活躍も虚しい気がします。
年代でみると、大体、紀元前一四〇〇年から一一〇〇年にかけての三百年間ほどが、士師記の時代だと言われています。旧約聖書以外に、これを示す文献が他にないため、確かではありません。ギデオンの他で、日本人に名前が知られている士師は、たぶん、サムソンだけでしょう。ペリシテ人の策略によって、デリラなる美女に騙され、怪力の源泉である髪の毛に刃を入れられ、力を失ない、両眼を抉られて虜囚になるも、神に祈って力を回復し、獄舎から引き出されて見世物にされている時、つながれた鎖もろとも建物を破壊し、自らの生命と引き替えに多くのペリシテ人を(建物の下敷きにして)打ち殺した話は有名で、何度か映画にもなっています。また絵画の主題にも取り上げられ、レンブラントの絵に「目をえぐられるサムソン」があります。
士師は男性だけではなく、女性の士師もいて、デボラは女預言者でしたが、召命により士師となり、同じくバラクを士師として呼び、ともに戦います(士師記第四章から五章)。ただ、私が見るに、ここで活躍しているのは士師ではないヤエルという女性で、預言どおりカナン人の将軍シセラをいつわって天幕で休ませている間にこめかみに釘を打って殺害し、民を救います。
また、旧約外典で、しかも士師とは呼ばれていませんが、ユディトも戦う女性として有名です。ただユディト書の記述には誤記が多く、アッシリア王のネブカドネザル軍にベトリアの町が包囲された際、若くして寡婦となった美貌の女性ユディトが、包囲軍の将軍ホロフェルネスに投降した振りをして欺き、四日目の夜にその首を落としました。しかし残念ながらネブカドネザルは新バビロニアの王であり、ベトリアという地名も所在が不明です。が、聖画の題材としてはボッティチェリからクリムトにいたるまで数多くの画家が描いています。
一応、士師は聖人なので、人名にも使われており、有名なのは、バラク(・オバマ)、デボラ(・カー)など。またユディトは英語だとジュディスで、SF批評家ジュディス・メリルが知られています。あと、創作ですが、英国ミステリに「ギデオン警視」シリーズがあります。
もう一人のキッテル、というのは、二十世紀初頭のドイツ人プロテスタント新約聖書学者のことです。ゲーアハルト・キッテル(Gerhard Kittel)。一八八八年生まれ、一九四八没。反ユダヤ主義で、ナチスを肯定し、戦後、公職追放になった由。ウィキペディアの英語版に項目が立っていますが、日本語版は今のところ見当たりません。グーグル翻訳でザッと見たところでは、キッテルのパレスチナ旅行記といった書物は不明でした。また、日本の国会図書館および米国議会図書館も検索しましたが、紀行記の書名はありません。彼の名を冠した「新約聖書神学辞典」は七四年に日本語訳が出版されていますが、旅行のような雑記は、有ったとしても未訳のようです。
こういう、ごく当たり前のように、七〇年当時はもちろん、今の知識人でも容易には判らないような知識(聖書学者でもない限り、キッテルを知っている人はいないでしょうし、検索しても出てこないパレスチナ紀行の本を読んだ人はさらに少ないと思われます)を放り込んでくるのがベンダサンの油断のならないところで、それはいいのですが、まあ、記述からして、両者は似ているんだろうな、としか思うしかありません。
士師記の該当箇所を引用すると――、
「イスラエルの人々はまた主の前に悪をおこなったので、主は彼らを七年の間ミデアンびとの手にわたされた」
「イスラエルびとが種をまいた時には、いつもミデアンびと、アマレクびとおよび東方の民が上ってきて陣を取り、地の産物を荒らしてガザの附近にまで及び、イスラエルのうちに命をつなぐべき物を残さず、羊も牛もろばも残さなかった。彼らが家畜と天幕を携えて、いなごのように多く上ってきたからである(後略)」
こういうところでは、聖書は勧善懲悪(ヤハウェに民が忠実なら平和だが、不実だとたちまち神の怒りが下る)なので、イスラエルの民衆が神に背いたり、バール神などの偶像礼拝をすると、必ず天罰覿面に罰せられます。モーセの十戒からユダヤ国家が亡びるまでの歴史は、実に、ユダヤ人たちが、少しでも隙あらば異神や偶像を崇めようとするのを、預言者や士師たちが、なんとか食い止める、そのくり返しのようです。
なお、ここでイスラエル人に仇なす敵対民族として登場する、ミデアン人は、聖書学的には、全イスラエルの祖アブラハムの子ではあるが、最初の子イサクの子(孫)であるヤコブとは系統が異なります(旧約ではヤコブの子らだけが聖別され、十二支族の祖を名乗っています)。
ユダヤ教では、アブラハムの正妻サラの子であるイサクだけが正統で、それ以外の妾ハガルの子や後妻ハガルの子ら、イサクの異母兄弟たちはアラブ人の祖になったと考えられており、なんとも遠大な民族差別の大元です。神に愛されしイサクの子ヤコブを、兄弟たちは虐待し奴隷として売ったりしているので、無理もないとはいえ、ヤコブと双子の兄エサウなどは、後に和解しているのですが。
エサウは、エドム人の祖とされ、イエス生誕の際の嬰児殺害で有名なヘロデ大王は、その父の系譜からエドム(=イドマヤ)系とされています。地名としては、アカバ湾から死海にかけての土地でした。民族的には現在のエジプト人だと言われます。またアマレク人もエサウの子孫であり、本来は同じ民族のはずでなのですが、すでにモーセ五書の段階で敵と見なされています。
2
ここで、ちょっと寄り道ですが、「聖書」について、少し言及しておきます。
一般的にいって、日本人にとって、キリスト教(およびユダヤ教、イスラム教)の聖典である聖書は、馴染みが薄いものだと思います。聖書は、ユダヤ教の聖典である旧約と、キリスト教の典拠でもある新約からなります。前者はユダヤ人の歴史、律法、預言、詩編、黙示録などからなり、後者はイエスの言行録である福音書、使徒の言行録、初期キリスト教会から布告された書簡、そして黙示録から成ります。量的には、新約は旧約の三〇%程度です。
新約だけならともかく、旧約新約を全巻読破した人はめったにいないでしょう。「レクティオ・ディヴィナ(Lectio Divina)」という言葉があり、最近の教皇であるヨハネ・パウロ二世から始まった聖書を読む運動で、中世の修道士が「読む(Lectio)、黙想する(Meditatio)、祈る(Oratio)、観想する(Contemplatio )」という諸段階で聖書を学んでいたメソッドを広く教徒にも普及させようと推奨したものです。しかし、今ごろになって言うくらいですから、元々カトリック教徒は聖書を読まない(読ませなかった)伝統があります。教皇の一人や二人が勧めたくらいでは今でも読まないでしょう。日曜日のミサに出席して聖句が読まれる。それを熟考すれば立派なカトリック教徒であり、なんら信仰に恥じることはありません。
プロテスタントは、そうしたバチカン教会を否定して「聖書のみに拠る」という立場ですので、カトリックに較べれば読むでしょうが、たいてい新約聖書と、それに照応した旧約の箇所だけです。だから、クリスチャンでも、旧約・新約の両方全部を読破した、という熱心な人はなかなか稀だと思います。
しかしながら、これは教徒の熱心さの不足というわけではなく、目の前にありながら、それでも読まれないのは、それなりに読まれないだけの理由があります。まず表面だけを読んでも、なんだかサッパリ意味が判らないからです。註解聖書、という本が別にあり、あるいは中央公論社から以前「世界の名著」の中で抜粋ですが聖書が収録されていて、それの注釈を読んでいけば、かろうじて理解できる。といった難点があるのです。だから市販されている聖書をいくら念入りに読んでも、その真の意味はなかなか掴めません。注釈なしで聖書を読むのは、注釈なしでダンテ「地獄篇」を読むのと同じくらい苦行です。
一例を挙げると、ロトの物語があります。
硫黄と火で焼かれた悪徳の町ソドムとゴモラに住んでいた義人で、アブラハムの甥にあたります。神はソドムとゴモラを焼こうとするのですが、アブラハムは甥のために助命嘆願します。そこで義の人が十人いたら滅ぼさない、との約束を取りつけるのですが残念ながらロト一家以外、悪徳の都ですから町は焼かれました。天使が二人、訪れて確認します。その際、ロトは天使を迎え入れ、ソドムの町の住民は天使が見目良い人に見えたので、差し出すようにロトに強要します。ロトは自分の未通の娘を代わりに差し出すので勘弁してくれ、というのですが町の住民は言うことをきかない。天使が目くらましをかけて去らせるが、この一件からソドムは滅ぼすべしとの神命が下ります。そこで天使らはロトに逃れよ、と言うのですが、ロトの妻は「振り向けてはいけない」という命令に背き、後ろを見たことで「塩の柱」と変じます。この話は有名なのでクリスチャンでなくてもご存じの方も多いでしょう。その後、ロトとその娘たちは山に逃れ、安全圏に達し、生命を救われます。しかし隣りの町まで逃げて、さらに逃れて荒地に出た一家は洞窟に身を潜めます。そこで、ロトの娘たちは子孫を絶やさぬよう、父であるロトと交わり、子をなすのです(創世記第十九章)。

これがどう言う意味を持つのか、長いこと謎だったのですが、以前、宗教画によって聖書を読み解く、という本(タイトルは失念しました)を読んでいて、やっと判りました。ロトの子孫は、モアブ人とアンモン人ですが、ともに後代にはユダヤ人の敵です。申命記には、
「『モアブを敵視してはならない。またそれと争ってはならない。彼らの地は、領地としてあなたに与えない。ロトの子孫にアルを与えて、領地とさせたからである』」(第二章第九節)
――とあります。昔は、アブラハムの甥の子孫だ、ということで敵対関係にはなかったようですが、その後、相争う間柄となりました。そして、だからこそ、このロトと娘の挿話が、この箇所に挿入されたのだ、というのです。近親姦の禁忌を犯した者=戒律を破った者たちの子孫だから、モアブとアンモンの人間たちは敵だ、という思想です。わざわざ近親姦の挿話を入れることで、祖先の悪行が子孫に及んでいる、とのネガティヴキャンペーンと把えることも出来ますが、かなり陰険な書き方でしょう。
SFなのに、後年、ヒッピーの聖典と見なされた妙な本に「異星の客」というハインラインというSF作家の作品がありますが、そこで老学者が年若い人にロトの説話を語り、ロトが天使を迎えた後、ソドムの住民が押しよせた際に取った行動を、きわめてアメリカ的に「女衒も同然の行為だ」とか評すところがあります。ハインラインは非常に波乱に富んだ人生を送っており、青年時代はリベラル派だと思われていたのですが、後年、保守主義に転じたようにも見えます。ただ人種差別主義者ではなく、これは代表作「宇宙の戦士」の主人公が最後にフィリピン人青年だと明かされることで証明されます(使う言葉がタガログ語だとある)。性的にも自由恋愛主義で、「異星の客」に見られるヒッピーの聖典化といった契機を内在してもいますが、他方、頑ななまでに個人主義的でもある。
全体に、よく判らない人なのですが、しかし聖書は読んだだろう、と思われます。学識は豊富な人でした。とはいえ、ロトの説話に対して、あれほどの主観的な意見を述べる(登場人物の内で一番の賢者にそう述べさせている)ところを見ると、聖書の背景にあるオリエント文化ならびに古代ユダヤ教に関する知識の欠如は明らかでしょう。
ロトが町の人間から客を守ろうとするのは、二つ、意味があります。まず第一に、沙漠の民は、いったん幕舎の内に旅人を招き入れたら、自らが危険に曝されても、それを守らねばならない、という古代からの好遇(ディヤーファ)の慣習があります(※1)。
第二に、ロトが、天使らを神の御使いだと認識したら、妻子はもとより何を犠牲にしてもそれを守らなければならかったはずだ、という古代ユダヤ教の神学的認識があります。これらについての無知は明らかでしょう。そして最後に、ロトの説話が、後年のモアブ人とアンモン人との敵対関係を予型するものだ、という聖書学的な知識もなかった。
ハインラインと言えば、SF黄金時代の、A・C・クラーク、アシモフとならぶビッグ3です。要するに、そのハインラインにして、すなわち、その時代を代表する非常に聡明かつ未来を見透していたSF作家にして、ついに典型的な一アメリカ市民である以上ではなかったことになります。むろん、ハインラインは聖書をくり返し読んだでしょう。だがしかし、ただ表面を読むだけでは、聖書を読解したことにはならない、ということが、上記のことで判ると思います。
それほど、聖書とは、眼光紙背に徹したくらいでは、たやすくは、くみ取れない策みや秘密がある書なのです。
※1)これはベドウィンの慣習とされる「客人好遇(ディヤーファ=diyafa)」の掟ですが、「見ず知らずの客でも三日間は、その間、何不自由なく、もてなさねばならない」と言われています。その起源については、折口信夫の民俗学で言う「まれびと(まろうど)信仰」に基づく異人=神の認識との説もありますが、ベドウィンの他にも、ゲルマン民族やケルト民族にも見られる世界的なものです。
しかし仏大革命への干渉をプロイセンやスペインが行なった際、仏軍の反撃に遭って旗色が悪くなったプロイセンは一七九五年、バーゼル和約を結んで講和します。この時、プロイセンの哲学者カントは、この和約が一時的な条約ではなく、将来も有効な恒久平和となすために、「永遠平和のために」という書を刊行しています。その中で彼は「世界市民の法=権利は、普遍的な友好をもたらす諸条件に制限されなければならない」として「客人好遇」に制限を示しました。カントはあくまでも、「好遇」は美徳や慣習ではなく、世界市民の「法と権利」の問題として捉えており、それは「客人の権利」ではなく「訪問の権利」だと規定しています。これは二十世紀になってユダヤ系フランス人哲学者ジャック・デリダによって批判されるのですが、少なくとも、ハインラインは、沙漠の民の「ディヤーファ」の慣習を知らなかったことになります。聖書について、自己の投影であろう作中人物の「賢者」が読者対象とひとしい年若い登場人物へ語るには、あまりにも聖書について、知らなさすぎる。そう言わざるを得ません。
3
ただ、明治生まれで、特に新約聖書を熱心に読んだ日本人はいました。特に文学者に多い。聖書が、海外文学に最大の影響を与えた書だと判っていた人たちは、欧州の文芸を理解するためにも、また、なによりも、そうした文芸を生み出した根源たるクリスチャニティを理解するためにも、聖書を読む必要にかられたのでしょう。
ことに戦前に出た、文語訳の聖書は格調が高く、愛読者が多かったせいもあります。代表的な例では、芥川龍之介や太宰治が有名です。最近だと、吉本隆明でしょうか。おそらく彼らは暗誦するほど聖書を読んだのではないか、と思われます。前者の「西方の人」や後者の「駆け込み訴え」、また隆明の「マチウ書試論」などは、よっぽど新約を読み込んでいないと書けないものです(隆明の作品は、さらに既成の聖書翻訳を斥けて、わざわざフランス語の聖書を独自に訳すことによって、聖書の翻訳の系譜の断絶を図っています)。
しかし、そういう人たちは、いずれも、その多くが信仰にはいたっていません。むろん、日本人のクリスチャン作家もいます。面白いことに、明治時代には留学などの海外体験のない文学者ほど聖書や賛美歌の影響が強く、若年にてクリスチャンになり、その後、棄教する傾向があり、典型例は、一八八八年(明治三一年)に刊行された「新撰讃美歌」をそっくりパクった「若菜集」で詩人としてデビューした島崎藤村でしょう。彼は一六歳で受洗し、二十歳で女子ミッション校の教師となりますが、教え子との恋愛と教師の責務の板挟みの葛藤からキリスト教を棄教し、職を辞しています。その後も、いろいろあるのですが、他にも島崎のほぼ同世代人だった国木田独歩は、二十歳で日本基督教会の指導者である植村正久から受洗し、クリスチャンになっています。しかし三六歳で早逝した彼は、「信仰は心理的遊戯なり」と言っており、最終的には日本的な自然主義へと回帰します。
対して、ともに若くして海外留学の経験をもつ森鴎外にせよ夏目漱石にせよ、ドイツや英国といった国々で宗教的世界と出会い、クリスチャンと日常的に接し、また当然、聖書も読んでいるはずですが、安直に信仰には入らず、むしろ距離を置いています。鴎外は「(自分は)多くの師には逢つたが、一人の主には逢はなかつたのである」(「妄想」(一九一一年))と書いていますし、漱石は英訳本のニーチェ「ツァラトゥストラはかく語りき」の余白に「言葉の真の意味に於ける[贖罪]はありえない。我々がやったことはもう取返しがつかないのだ。……だから[贖罪]は我々自身によってではなく、キリストという名前の愚かな間抜けによってなされた」との烈しい言葉を書き込みしています。
このように三者は、共通の聖書がそこにあるのに、どれも対照的です。というよりも、日本に限った話ではありませんが、キリスト者か非キリスト者かは、絶対的に相容れないように見えます。ただ、欧米では新教、旧教の違いはあれども、およそ周囲全員がクリスチャンです。だが、日本はそうではない。特に、明治時代は、(キリシタンを別にすれば)日本人が初めて公的にキリスト教に出会った時期ですから、身近にキリスト者がいたなら、求めればすぐに受洗できた。だが、同時に、それは彼らにとって、その日本的アイデンティティを揺るがしかねない精神的重圧ともなった。それは彼らが一般の人間ではなく、表現者だったことから、即座に作品へと反映されます。あるいは、書くことへの障害となる。藤村や独歩の「棄教」はその揺らぎを物語っているように思います。
両者の間には、超えがたい溝が、暗くて深い川のように横たわっているのです。クリスチャンにしてみれば、たとえ聖書を全巻読破しなくても、信仰の道があれば、それで良いのですが、彼らにとって、いかに聖書を暗唱するほど読んだ人でも、そこに信仰がなければ、まったく意味がないからです。
私は、ミッション高校時代、「聖書」の時間、という単元があり、そこでの副読書に信仰者(クリスチャン)が信仰なき聖書の読解を忌み嫌うように書いているのを見て、あまり愉快ではありませんでした。自分自身が、おそらく信仰は持たないだろう、ということもありましたが、日本人クリスチャンの言説は、かなり排他的で、太宰や芥川を低く見る、というか、残念な人たちだ、というか、要するに差別的だったのです。まあ、宗教とは本来そういうものですが、ギリギリ、信仰の手前までいって、そこから信仰への道へと一歩踏み出せなかった人々への、温かい見守り、といった視線が、なんら感じられませんでした。ただ「聖書」の時間に教えられた知見は、そうした差別的なもの以外は、多感な時期の私に多くの影響を与えてくれました。後述する予定ですが、バルト、ブーバー、レヴィナスやデリダらの学説に、(そうとは知らずに)最初に触れたのは、まさにその「聖書」の時間だったので、今では、感謝しています。
聖書は、今述べたように、あまたの海外文学の重要な出典でもあり、信仰とは離れたところから、クリスチャンではない、多くの人たちにとっても、読み方さえ判れば、それなりに興味深い書なのですが、七〇年当時、私が読んだ、日本人クリスチャンの本からの、そうした冷たい眼差しを感じている間は、日本での広がりは望みべくもないように思えました。これは今でも、私の中で、変わっていません。これはクリスチャンの人たちの責任ではなく、おそらくキリスト教会の問題でしょう。信者に、非信徒への寛容の精神を教育していない。そこに問題があると思われます。最近のバチカンのエキュメニカル主義は、今イチ信用できないのですが、そういう面では評価に値すると思っています。しかし、プロテスタント系の宗派は、依然として頑なですから、そういう無信心な人への冷々たる内面は隠すべくもない。残念なことです。そうしたことが結局、キリスト教文化を日本人から遠ざけているのですが、それを理解しようとしていない。というのが、私なりの見解です。短見にすぎないのであれば、歓んで撤回いたしますが、たぶん、その通りではないか、と思われます。私は他の宗教の信徒も知っていますが、一部のカルト教団などを除けば、クリスチャン、特にプロテスタント系のキリスト教徒が一番、そういう意味では排他的に感じます。
ただし、そうした若い時からキリスト教に接していた私が、しだいに自分の考えを固めていき、それなりの思惟の能力を持ち、自分なりの思考をするようになって、そして以下に記すようなことを想考する段になってからは、どうも、キリスト教の非寛容性は、それがユダヤ教という一神教から枝分かれしたせいではないか、と思うようになりました。ユダヤ教も相当に頑迷な宗教だからです。しかも、同じ一神教でもイスラム教とは、ずいぶん違います。確かにムハンマドは「片手にコーラン、片手に剣」をもってイスラム圏を拡大しましたが、それは相手に剣を突きつけて、コーランの民(ムスリム)への改宗を迫ったわけではありません。
イスラム帝国に征服された民は、人頭税(ジズヤ)を支払うことで、改宗を避けることが出来たのです。聖戦と称して十字軍を組織し、エルサレム内の「異教徒」を殺戮したキリスト教騎士団とは大きな違いがあります。
まさか、それほどではありませんが、キリスト教徒とユダヤ教徒、それにおそらくそこから派生して誕れたであろうマルクス=レーニン主義の共産党系の党派の人々の非寛容性は、独特な共通点があって、どうも彼らは同根の何かではないか、と私は考えています。やたら内部で異端審問をやりたがるとか、いろいろ類似の論点は有るのですが、民族宗教か世界宗教か、それとも国際的思想集団か、といった差異を超えて、この三つには、どこか似通ったものを感じないではいられない。しかも、それはイスラム教を証左として、唯一神の宗教だから、という理由だけではない特徴なのです。
まあ、これは余談ですので、この辺で措きます。
4
ともあれ、「日本人とユダヤ人の」の講読は、私にとって、単に興味本位のテーマではなく、そして青春時代に影響を受けた、というに留まらず、強く深い縁を感じる本である、ということが言いたいわけであります。
だから、以下は、念のための言及です。すでに知っている人や、聖書にまるで関心がない方は、読み飛ばしても構いません。
まず、言っておくと、聖書は、キリスト教だけの聖典ではありません。
エルサレムがキリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒、三つの宗教の信徒にとって「聖地」であるように、聖書もまた、この三つの宗教の「聖典」です。彼らは、同じ「啓典(けいてん)の民」と呼ばれています。ただし、異なるのはキリスト教とイスラム教が「世界宗教」であるのに対し、ユダヤ教はユダヤ人のみの民族宗教であることでしょうか。ユダヤ教からキリスト教が派生し、さらにイスラム教が最後に世に出ました。神の呼び名はすこし違っても(ヤハウェだったり、アッラーだったり)、いずれも等しく、「啓典の民」の宗教が「一神教」であることに変わりありません。宗教や民族的対立はあっても、彼らはひとしなみに、同じ一つの神を崇めているのです。
先述したように、聖書には、旧約聖書と新約聖書があり(「訳」ではなく契約の「約」です)、厳密には、旧約(の一部)だけが三つの宗教に共通した聖典です。新約はキリスト教だけのもの、と考えていいでしょう。ユダヤ人にとっては、ナザレのイエスは優れたラビ(ユダヤ教の教師)であっても預言者でも何でもないので、当然です。むしろ、ユダヤ人を迫害してきたキリスト教の開祖ですから、その文献に価値を見いださないのは自然かと思われます。他方、イスラム教では、ノアもモーセもイエスも等しく先行する預言者(=ナビー)と認められ、それなりの敬意を払われていますが、開祖たるムハンマドだけは「最後の預言者」として別格の扱いです。またイスラムにとって正式な経典はクルアーン(コーラン)が最優先ですが、モーセ五書などは、啓典のひとつとして扱われています。あと、クルアーンはアラビア語で書かれたものだけが正式なイスラムの啓典なので、他言語に翻訳されたものはクルアーンとは認めていないことも、重要な点でしょう。キリスト教が布教するに当たって、およそ二千七百カ国語に翻訳されたことを思えば、最大の違いだと思われます。ムスリムになるためには、クルアーンを原語で詠唱することが必須条件なのです。世界宗教において、この言語的閉鎖性は非常に特殊ですが、むしろ、その閉鎖性によって、強い世界的連帯と「広がり」を持ったのかも知れません。民族宗教であるユダヤ教が、同様の閉鎖性によって「閉じて」いるのに対して、対照的な姿です。
旧新約の「約」とは「契約(=英語のTestament)」の意味で、神(ヤハウェ)と民との契約のことです。ヘブライ語の旧約聖書は、新約聖書が編まれた後で編纂されており、レトロニム(後付け語)と言ってもいいでしょう。奇妙なことですが、事実です。新約の中で、最初の福音書が書かれたのは、大体、紀元六〇年代から八〇年代だと言われています。「新しい契約」と呼んだのは、初期キリスト教の教父テルトリアヌスらで、紀元二世紀頃です。ユダヤ教では、ユダヤが最終的に滅んだ紀元七〇年のユダヤ戦争以後、国家として滅びたユダヤ人が、自分たちのアイデンティティ確立のためでしょうが、紀元一世紀末のヤムニア会議で正典の確認がなされています(※2)。
※2)ヤムニア会議での正典、という箇所は、後の講読で触れますので、ここは暫定的に留保づけしておいて下さい。
ただし、「正典(Canon:カノン)」ではないのですが、一番よく引用される旧約は、紀元前三世紀から前一世紀にかけて、アレクサンドリアにて成された「七十人訳聖書(セプトゥアギンタ=LXX)」と呼ばれる旧約聖書があります。これは、その頃すでにヘブライ語が話せなくなっていたユダヤ人のためにファラオが命じてヘブライ語およびアラム語からギリシャ語に翻訳した、とされる、ほぼ旧約聖書の内容です。ユダヤ十二氏族から各々六人ずつ、合計七二人のラビを出させ、七二日間で完成させた、という伝説がありますが、実際の完成には、紀元前二五〇年から紀元前一世紀くらいまでかかったとされています。当時のオリエント社会では、エジプトでさえ、その上層部(ファラオ)はギリシャ人に支配されていましたから、アレクサンドリアのユダヤ人は一様にギリシャ語を話していたのです。それゆえの翻訳作業でした。
私が昔に詩誌「ユリイカ」で読んだ、E・M・フォースターのアレクサンドリアに関するエセーでは、七十人の博士たちが召集され翻訳にあたり、あまりの精神統一により誤訳でさえ、一致した。といった逸話が美文調で語られていました。ほとんど伝説的な訳業ですが、成立の過程は諸説あって、よく判っていません。フォースターの美文に飾られたことどもも、多くは伝承でしょう。一説に、ユダヤ十二支族から各々六名ずつラビたちが集められた(よって正確には七十二人となる)、とも言われていますが、紀元前八世紀には北イスラエル王国は滅亡していますから(いわゆる「失なわれた十支族」)、これも伝説の域を出ない説だと思われます。ただ、フォースターの現地取材に基づく文章では、今はもう崩れ去ってないファロス灯台の下に、七十人の学者たちが住まわせられていたであろう遺構が残っていたらしく、そういう描写を、私は拙作「兇天使」に借りたことがあります。
七十人訳聖書は、成立過程その他はともかく、古代オリエント世界では、かなり流通した書で、ほとんどの旧約の引用は、このギリシャ語からなされています。文庫版一七二頁に、
「(七十人訳聖書について言及した後)いずれにせよ、イエスの時代には、ユダヤ人はヘブル語ができなかった。おかしいと思われるかもしれないが、これは事実で、彼らはアラム語とギリシア語を使っていたのである。従って旧約聖書の引用は多くはこのセプトゥアギンタによってなされた」
――とあるとおりです。
5
また、新約聖書も基本的にギリシャ語で書かれています。
ただし、山本七平氏によると、新約のギリシャ語は、民衆の使う「コイネー(通俗ギリシャ語)」であって、著作家が使う「アチケー(アッチカ擬古典文)」ではなかった、ということです。当時の「教養人にとっては、読むに耐えるギリシャ語ではなかったんだろう」、とまで言っています。
「イエスの弟子たちに、アチケーで著作しろと言ったって無理だよ。パウロだってそれはできない」(「禁忌の聖書学」新潮社 九二年刊より)
とはいえ、コイネーは、アレクサンダー大王の征服によって起きたヘレニズム文化において、その版図内で話された「公用語」としてのギリシャ語で、公式なものであり、たどれば近代ギリシャ語を介して現代ギリシャ語の基礎となった言語です。ギリシャ語の(翻字で)「Koine」とは、「共通の」という意味で、古代ギリシャ語のアッティカ方言およびイオニア方言を基盤として成立した言葉と言われています。
対する著作家の使ったというアチケーとは、アッティカがアテネやその周辺を意味する用語なので、その「アッティカ方言」を指します。これはヘレニズム文化爛熟期の紀元二世紀頃、アッティカの作家特有の洗練された文体を規範とする文学的志向の産物だそうです。当然、教養ある(というか、正規の学問を修めた)エリートの人々しか草しえない文章だったのでしょう。日本で言えば、江戸時代における商人などが読む読み本の文章と武士が読み書きする文語体との違い、あるいはそれ以上の開きがあったもの、と考えられます。
付言しますと、ローマ帝国時代のローマを中心とする帝国の西半分では、ラテン語が「公用語」でした。そして残りの主に地中海沿岸を中心とする帝国の東半分では、このコイネーが「共通語」になっていました。すでにLXXがあって、旧約聖書の引用の大半はそれに依ってなされているのですから、当時のユダヤ人で識字能力のある人間はコイネーを読み、語り、書き綴ったと考えるのが自然でしょう。バビロン捕囚以来、民族離散(ディアスポラ)を経験しているユダヤ人の多くは祖国を失ない、母国語であるヘブライ語を奪われた彷徨える民族として共通語のギリシャ語(コイネー)を使うのが当たり前になっていましたから尚さらです。ただし、イエスを含め、イスラエル土着の多くのユダヤ人は日常会話はアラム語であったとされています(※注)。またイエスに識字能力があったかどうかは判っていません。
※注)ただし、イエス時代に、ヘブライ語が完全に廃れた訳ではなく、口語でヘブライ語を話す人もいた、という記録があります。他ならぬ新約の使徒行伝に、パウロがエルサレムのユダヤ人に批難されて群衆が集まって私刑にかけられそうになるのを、駆けつけた千卒長が保護し、尋問すると、パウロは自分の口で民衆に弁明したい、と言い、千卒長がこれを許してパウロが弁明する場面です。
「千卒長が許してくれたので、パウロは階段の上に立ち、民衆にむかって手を振った。すると、一同がすっかり静粛になったので、パウロはヘブル語で話し出した。
「兄弟たち、父たちよ、いま申し上げるわたしの弁明を聞いていただきたい」。
パウロが、ヘブル語でこう語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった」(第二十一章第四十節から第二十二章第二節)
パウロはヘブライ語(ヘブル語)とギリシャ語が話せた、ということがこれで判ります。同時に、それを聴いている聴衆も彼の話すヘブライ語を理解している。つまり当時、ヘブライ語がまだ疎通していたことも判ります。ここはエルサレムの神殿の中という特殊な場ですから、集っているのもユダヤ人の中でも聖都に在住している教養のある人たちが多かったのかも知れませんが、しかし、パウロが最初に弁明していた相手は、「アジアからやってきたユダヤ人」とありますので、当時、ヘブライ語がどういう地位にあったのか、よく判らないのですが、とにかく話して判る人びとの層が一定規模あったことは確かでしょう。
パウロはキリキヤのタルソ生まれで、その一帯は小アジア(アナトリア)と呼ばれ、北を黒海、西をエーゲ海、南を地中海にはさまれ、東にアルメニア、メソポタミア、シリア地方につながる地域を指します。現在のトルコ共和国のアナトリア半島です。昔から要衝の地であり、アレクサンダー大王がペルシャ帝国を破った後、とりわけ大王の死後から所有者が転々として、最終的にローマ帝国の属州となりますが、その際に無血開城した功績で、その地に生まれた者はローマ市民権を持つ、ということになります。
上述の千卒長は出身が判りませんが、ここで、パウロに「自分はこの市民権を多額の金で買い取った」と話しており、パウロが「わたしは生まれながらの(ローマ)市民」だと応えると、畏れをいだく場面があります。ローマ市民には、特権として拷問や鞭打ちをしてはならない、という規則があり、金で市民権を買った千卒長としては、縛って鞭で打つように命じた(実行はしなかった)経緯から、畏れるだけの理由があるわけです。ローマ市民の身分には、パウロが誇るだけのものがありました。
ところで、第五講「ギデオン」の項目でも触れましたが、イエス時代のユダヤ人は、すでにその多くがヘブライ語を話せなくなっており、アラム語とギリシャ語を話していた、とありましたが、他の言語はともかく、アラム語とは、一般の日本人には耳慣れない言葉です。しかもヘブライ語ではない言語をなぜ、ユダヤ人たちは使っていたのか。説明が必要でしょう。
6
クリスチャンで在野の聖書学研究家の市川喜一氏によれば(※)、
「当時のパレスチナの住民はアラム語を日常語として用いており、イエスご自身もペトロをはじめ弟子たちもアラム語を使っていたのですから、当時の歴史的状況を理解する上でアラム語をめぐる状況を知ることが重要となります。それでアラム語についてごく概略のことを、ここでまとめておきます。
アラム語は、ヘブライ語、フェニキア語などを含む北西セム語系の言語の一つです。この言語を用いていた遊牧民であるアラム人が、前二〇〇〇年頃にメソポタミアやシリアに侵入して定住し、多くの都市国家を形成します。アッシリアが興り、これらの都市国家が滅びた後も、アラム語は通商や交易のための国際語として残ります。アッシリア帝国の移住政策により、アラム語はエジプトからメソポタミア南部までの広い地域に広がり、その地域の国際語となります。この時期(ほぼ前七世紀の終わり頃まで)のアラム語は「古アラム語」と呼ばれています。
その後カルディア人が建てた新バビロニア帝国の外交語となり、さらにペルシャ帝国の治下では近東だけでなく、南は上エジプト、西は小アジア、東はインド亜大陸までを含む広い地域の共通語となります。ほぼ前二〇〇年ごろまでの帝国の公用語として使われていたこの時期のアラム語は「帝国アラム語」と呼ばれています。旧約聖書の後期の文書であるエズラ記の公文書の部分(第四章第八節から第六章第一八節、第七章第一二節から第二六節)は、この時期の帝国アラム語で書かれています。
ヘレニズム時代およびローマ帝国時代になると、この地域での行政の公用語はギリシア語になります。また、この時期のヘレニズム都市ではギリシア語が用いられるようになりますが、周辺の土地ではアラム語が使い続けられるという言語状況が見られるようになります。各地方のアラム語はそれぞれ独自に発展していきますが、書き言葉のアラム語は比較的統一を保ち、各地域間の交流手段として用い続けられます。この時期、すなわち二五〇年頃までの時期のアラム語は「中期アラム語」と呼ばれます。ダニエル書のアラム語部分(第二章第四節から第七章第二八節)、死海文書の一部、タルグム(ヘブライ語聖書のアラム語による解説的翻訳)などは、この時期のアラム語で書かれています。
その後イスラームの拡大にともなって、七〇〇年頃には、日常語でも文章語でも、近東ではアラビア語がアラム語に取って代わるようになります。しかし、アラム語を用いる地域も残り、現在でも少数ながらアラム語を用いている地域とか部族があります。アラム語の歴史は、後期アラム語を経て、現代アラム語に至ります。現在でもアンティオキアのキリスト教会は、イエスと弟子たちが用いたアラム語を使っている教会として、その古さを誇っています。
イスラエルの民の言語はもともとヘブライ語でしたが、捕囚以後はパレスチナでもペルシャ帝国の共通語であるアラム語が徐々に日常語として使われるようになっていました。ヘレニズム期になると、パレスチナでも大都市では一部の階層でギリシア語も使われるようになりますが、周囲の農村部住民および庶民階級の都市住民はアラム語を使っていました。イエスの時代では、パレスチナのユダヤ人の日常語はアラム語であったと言える状況でした。
イスラエルの民の言語はもともとヘブライ語でしたから、父祖アブラハム以来の歴史とその中での宗教体験はヘブライ語で書かれ、律法や預言書などの聖文書はすべてヘブライ語で書かれることになります。神殿での祭儀も会堂(シナゴグ)での礼拝もすべてヘブライ語の聖書に基づいて執り行われます。イスラエルの民の日常語がヘブライ語であるかぎり問題はないのですが、捕囚期以後民の日常語がアラム語に移行するに従って、宗教活動に問題が出て来ます。
ヘブライ語とアラム語はもともと同じ北西セム語系の言語であって、きわめてよく似ています。文字も同じ文字を用いています。しかし、時代が下ると共に、アラム語を用いる民衆はだんだんとヘブライ語聖書を理解することができなくなります。神殿での祭儀はヘブライ語の式文で執り行われても深刻な問題はありませんが、会堂における聖書朗読やその解説は、会衆の理解のためにアラム語で行われるようになり、そのためにヘブライ語聖書がアラム語に翻訳され、解説もアラム語で行われるようになります。
アラム語に翻訳された聖書は「タルグム」と呼ばれますが、これは単なる日常語への置き換えではなく、ヘブライ語聖書の意味を解説する注解書の役割も兼ねています。タルグムはヘブライ語聖書のアラム語への解説的翻訳と言うことができます。会堂で朗読される聖書はヘブライ語聖書でなければなりませんが、解説し勧めをする者はタルグムを用いることになります。子供たちは「書物の家」(会堂付属の学校)でまずタルグムを学び、それを通して聖書のヘブライ語を学習することになります」
※注)市川喜一氏が個人出版した天旅出版社の著作集が氏の以下のサイトで披見できます。
http://www.tenryo.net/old/index_CD.htm
前後の厖大な文書も、この論考を記すために、大いに参考にさせて頂きました。記して感謝いたします。
ただ一言、付け加えておきますと、ユダヤ教の会堂に「シュナゴゲー(シナゴグ)」とルビが振られていますが、(面倒なので、私も以下はそれに倣うつもりですけれど)本当は、これはギリシャ語「synagoge(集会所)」からの転移で、ヘブライ語では「Beth Keneseth(ベト・クネセト)」が正しい呼称です。新約が誕生した時点で、参照したLXXにそうあったため、イエス時代の会堂に全て、その単語が宛てられたのでしょう。さらに言えば、「教会」は英語では普通「church」ですが、聖書ではギリシャ語起源の「ecclesia」の語を用いていることが多いのは、おそらくユダヤ教のシナゴグと区別するためだと思われます。西ローマ帝国が滅びた後のロマンス語(くだけたラテン語)を使う多くの国(仏、西、葡、蘭語など)で、これを語源とする用語が「教会」として日常的に使用されるのも、おそらくユダヤ教との断絶を図ったからだと考えられます。
以上の引用で、イエス時代のアラム語とは何か、りんかくは理解されたことと思います。
とはいえ、いかにアラム語が言語系的には、ヘブライ語と同じセム系言語であったとしても、一体、いつ頃からユダヤ人がヘブライ語を話せなくなったのかは判りません。推察するに、バビロン捕囚により、祖国喪失した時期に、土着の人々が母国語よりも、周囲で使われるペルシャ帝国の共通語であるアラム語に飲みこまれたのだと思われます。南のユダ王国が滅亡してバビロン捕囚があったのが、紀元前五八六年ですからイエスより六世紀も昔の話です。その間、ユダヤは何度も復興しては滅ぼされ、星霜を重ねています。気が遠くなるような時間と、惨苦に満ちた時期をくり返している。なにがあっても不思議はありません。イエスの生きた時代は、特にアレキサンダー大王の征旅によってオリエント世界全域がヘレニズム文化に掩われた時代でもあり、そこでのローマ帝国の版図の東半分が、共通語がギリシャ語だったのは肯けます。しかし、アラム語は、少し意外な気がする人が多いのではないでしょうか。
上述したように、それを話し解す人たちが実際にいたわけですが、実際には、エルサレムを中心として、なおヘブライ語を話すパウロのような人がいて、同時に、ギリシャ語は中東地域の共通語として流通している。新約では、よく混同して記していますが、パウロが話したヘブライ語とは、純粋な典礼用のヘブライ語で、アラム語をそう言い換えたものではありません。さらにイエスの生まれたユダヤ国内でも地方ではアラム語が話されている。そして、イエスの弟子だった人が書いた福音書はギリシャ語で書かれている。他方、パウロのようにヘブライ語とギリシャ語のバイリンガルもいる。多言語文化と言えるでしょう。
しかし、パレスチナにおける、言語の変遷の詳細については、今となっては判りかねます。
裕福な階級に生まれ、しかもローマ市民権を持っていた教養人のパウロはヘブライ語とギリシャ語を解し、ひるがえって貧しいガリラヤ地方のナザレ村の大工職人だったイエスはアラム語を主に使っていた、という違いでしょうか。イエスは幼い頃から会堂(シナゴグ)などで祭司による聖書の朗読に接したでしょうが、おそらく文盲だったのではないか、と私は思います。新約のどこにも彼が文字を読み書きした、という光景を描いた証言はないのです。イエスは天才的な記憶力で聴いただけのことは憶え、吸収していたので、聖書の文言を自在に引用できたとしたのかも知れません。しかし大工というより細工師だったので、それなりの図面とかは読めたかも知れませんが、もとよりユダヤの中でも最も貧しく「罪人の都」と呼ばれたガリラヤ地方のナザレ村に生まれ育った彼が、会堂に付属する「書物の家」で、初等教育さえ受けた可能性は低いように思えます。むろん、イエスが無学だったとしても、その偉大さを少しも毀損するものではないことは、言うまでもありません。
PREV | NEXT
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?