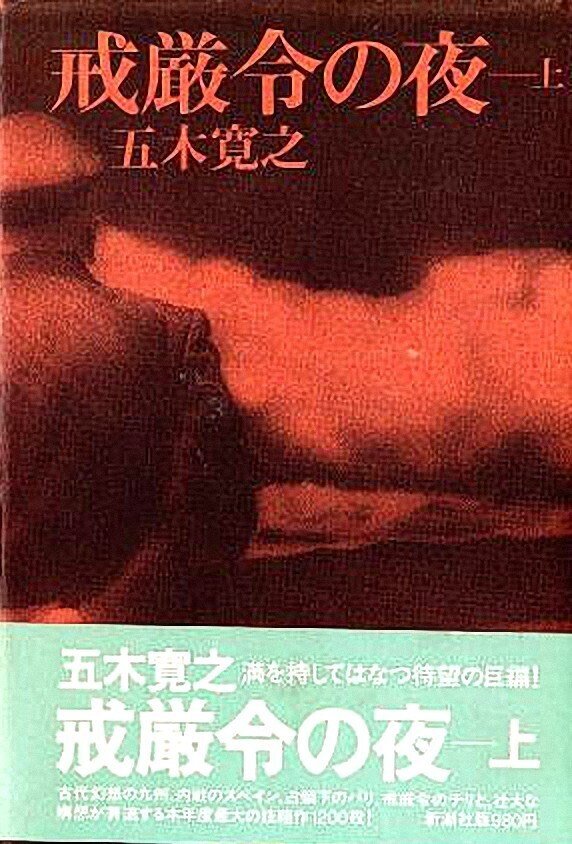「日本人とユダヤ人」講読
野阿梓
第十二講 ロープシン(5)
18
さて、以上、粗く略述したように、今現在の「世界」は、そういう状態です。
六七年に五木寛之が描いた黙示録的な世界は、今は様変わりしています。もっと悪くなっている、と言ってもいいでしょう。「蒼ざめた馬を見よ」では、少なくとも人は殺されていません。この謀略で重要な役割を果たしたオリガという女性が自殺したと言われていますが、おそらく故殺ではなく自殺だろう、と思われます。彼女は謀略の全貌ではないが、自分の役割は判っていたからです。そして、なによりも、この物語で主人公は自分の役割について、無邪気なほど、なにも疑っていません。
主人公は、ある種の正義感と、青春時代に「噛まれた」一人の作家への思い入れから、なるべくして巻きこまれて、国際的謀略の中に身を置きますが、今だったら、おそらく無事に返されるとは思えません。この主人公は、国際的謀略の一翼を担いながら、そして、その秘密を知らされた上で、なお日常的な世界(結婚を考えている、とあります)へと帰っていきます。六七年には、悪夢のような国際的謀略に巻きこまれた人間が、つまり、ひとたび蒼ざめた馬を見た人間が、そのまま平穏裡に一般社会へと回帰してゆくことが逆に「リアル」だったかも知れませんが、二十一世紀の今、同じような事件を描いた作家がいれば、必ず、確実に、オリガは密殺されて、死体も出てこない、そして主人公もまた仕組まれた事故死で終わらせたことでしょう。それが現在の「リアル」だからです。
しかし、六七年の水準で、五木寛之が可能な限り、作家的想像力の達しうるかぎり、「蒼ざめた馬」の疾駆する「黙示録」的情景を描いたのは、確かです。それは誰にも否定できない。主人公が殺されもせずに、一般社会へと回帰していったのも、ある意味では、黙示文学の要素としての第二項、たとえ世界が破滅したとしても、そこには一条の救済の光が差している、という原則にのっとったものであることは理解されると思います。
ただ出口のない、絶望的な世界を素描するだけが作家の仕事ではありません。作品は、ことにエンタメとして書かれた作品は、カタルシスがないといけない。ロシアに対して、アンビバレントな感情を持ちつつ、ロシア文学を専攻し、世界的視野からその亀裂を視つめ、エンタメで身を立てると宣言した五木寛之は、それら諸原則に従って、それを美事に全うしたのです。
物語の出だしは「その部屋にいるのは、三人だけだった」で始まり、その序章は、主人公がたちまち急落の瀬に引きずりこまれるかのように謀略の世界に巻きこまれて、それを承諾したとたん、「そのとき急に陽が翳って、部屋の中がふっと暗くなった」。そして、主人公は「自分の一言が今、世界中のジャーナリズムを捲きこむ巨大なキャンペーンの撃鉄を起こしたのだという事に、気づいていなかった」と終わります。
個々に見ると、気恥ずかしくなるほどの通俗的なクリシェ(決まり文句)なのですが、しかしブラッシュアップされた言葉で、さらにそれを臆面もなく重ねることによって、そうした気恥ずかしさを打ち消して、五木は効果を上げています。
出だしの唐突さは「掴み」です。このように特定な場所に秘密めかした空気を醸成したり、時には、何の説明もなく、会話から始めることで、読者を、出し抜けに起きる事件の始まりに引きこむための、いわば古典的な常套手段です。方法はいくつかありますが、作家は、それをいかに効果的に使うか、選択を迫られます。掴みが巧くいけば、その後の三人の会話の中身が途轍もなく有りえないような陰謀であっても、読者を説得できる。そうした積み重ねによって、序章の末尾の、ある意味では気恥ずかしくなるようなクリシェでさえ、たたみ込むことで、誰も笑う人はいない。そうした深刻な真剣さが伝わってくる。そのように作者が創意工夫しているからです。
デビュー作の後書きで書いたように、彼は、意図的に「エンターテインメントの要素であるカタルシスやメロドラマチックな構成、物語性やステロタイプの文体などを、「目的としではなく」手段として採用する事」に、ここでは見事に成功しています。
しかしながら、かつてのファンとしては、非常に残念なのですが、先述した生島治郎との対談(「生島治郎の誘導訊問」七四年刊)において、当時、休筆中(七二年から七四年まで充電期間)だった五木寛之氏は、盟友でもある生島氏と、小説について、いろいろな理想と現実を語るわけなのですが、そしてそれは滅法面白い対談だったのですが、しかし――、
いざ、休筆が終わった時に、五木氏は「休筆中に今わたしはこういうものが書きたい」と言っていた、まさにその通りのものを書き始めたのです。書きたいと言っていた全てのものをブチ込んできたように思いました。ところが、氏の再開後の最初の仕事として、おそらく氏が満を持して書いたであろう「戒厳令の夜」(新潮社 七六年刊)というその大部の作品を私は読んで、もう本当に失望しないわけにはいきませんでした。なんというか、あらゆることが理念だけ先走って空回りし、読んでいてそれが躓きとなり、ちっとも面白くないのです。
この物語は、七三年九月一一日にチリで実際に起きた、世界で初めて自由選挙によって選出されたアジェンデ政権という、一つの社会主義国家を、米の軍産コンプレックスと秘密機関の協力を得た、チリ軍部のクーデタが倒すに至る謀略事件をめぐる、一種の「伝奇小説」です。
この事件はニクソン政権下の米CIAが絡んでいると思われる、現実に起きた出来事であり、私は、その後、七八年に書かれた米国作家トマス・ハウザーの原作を得てコスタ・ガブラス監督の映画「ミッシング」(八二年)がクーデタの実態を(八二年の現在から過去への視点で)描いたのを観ています。
往年のコメディアン俳優ジャック・レモンが地味だが重厚な演技で保守主義の父親役を演じ、クーデタの中で行方不明となった左翼の息子を義娘シシー・スペイセクと一緒に探すという直線的なストーリーで、現実的であり、非常に判りやすい作品でした。彼はリベラルな思想の息子に反感を持っていて、その妻でもある若いシシーにも反撥しながらも息子の捜索をつづけるうちに、しだいに自分の祖国アメリカが、けして自由の国ではないことに気づかされていきます。保守的な父親が、やがて反米に近い感情をいだくようになる過程が、とてもリアリスティックな作品でした。
この事件に関しては、他にも十を超える小説や映画が作られており、南米では「九・一一」と言えば、同時多発テロよりも、この事件を指します。クーデタにより独裁政権となったピノチェット将軍のチリ政府は度重なる弾圧、暗殺、拉致などで悪評を高め、レーガン政権時にワシントンDCで起きたアジェンデ政権時の外相の暗殺が遠因となり、米はチリから手を引き、ついにピノチェット政権は八九年に民政移管を余儀なくされます。
「戒厳令の夜」は、最初、サスペンスフルな現代小説、あるいは国際的謀略をめぐるスパイ小説かと思って読み始めると、いつの間にか伝奇小説となって読者は少々、唖然とさせられるのですが、それは別にいいのです。問題は、その企図が、ほぼ全編にわたって破綻したことです。しかも、にも関わらず、作者の志は高いのです。これじゃあ本末転倒だと思うしかない。全体の構成も破綻していましたし、なによりも、行間から作者の意図が見え透いてしまっている。眼高手低といったら、小説の手練れである氏には失礼かも知れませんが、結果は、そうとしか言いようがない出来映えでした。作者の意図が、作者自身の目線の高さにあるならば、小説は、最低でも同じ高さになければならない。だのに、おそろしく作品の質が低いのです。せいぜい子供の背丈くらいしか、ない。これじゃあ、どうしようもない。長い休筆から目醒めた作家の傑作になるはずの作品が、これか。と私たちは失望しました。
これは七五年に、休筆からの復帰第一作といった鳴り物入りで雑誌に長期連載され、その後、七六年に上下二巻のハードカヴァで刊行され、さらに映画化もされるのですが――これは作者には責任がないかも知れないにせよ、その映画(東宝 八〇年)が一番ひどかった。もう目も当てられない出来でした。TVドラマならまだ許せるが、ゼニを払って観に来る客に応える出来ではなかった。真面目な話、樋口可南子が本作でデビューした(ついでながらバスト五四だか五八の微乳のヌードを魅せた)、という映画史的事実がなければ、記録にもとどめる価値のない作品だったのです。最終的には脚本を手がけた竹中労と佐々木守、それに監督の山下耕作の責任でしょうが、小説が、まず水準以下だったのに加え、脚本と演出の不味さが致命的で、出来上がった映画は箸にも棒にもかからない駄作だったことで、あの五木寛之でさえ、こうなるのか、とダメ押しをした格好でした。
細かいことを言い出したらキリがないのですが、最後に、もうクーデタが起きているチリの首都サンチャゴに徒歩で向かう、主人公と樋口可南子が(竹中英太郎描く)絵を持って、これをチリ人民に渡すのが自分たちの使命だ、とか訳の判らぬことを言って、そのまま二人の行方は判らない、とかクレジットが出ていたように記憶しますが、その時点でクーデタの勃発している都市に反体制派の日本人二人が入って、身柄拘束されないわけはないので、一体、この脚本家どもは何を考えているのだろう。と思ったことではあります。
クーデタ当時、アジェンデ派の人々が巨大なスタジアムに集められ、有名なフォルクローレ歌手ヴィクトル・ハラは、場内で拷問や処刑が始まった時、反戦歌を歌い、ために腕を切断され(あるいは折られたとも)、ロシアンルーレットの拳銃で頭を射抜かれた、などと聴きます。ほとんど生き残った人間がいない場でのことなので、どこまで本当か判りませんが、そうした現地の惨状は当然、予測されるのに、一体この二人の日本人は何のために首都に向かっているのか、ひどく虚しく感じたことを憶えています。ちなみに、この時の男性主人公役の伊藤孝雄は、かつて「さらばモスクワ愚連隊」(東宝 六八年)で大使館員を演った人だそうですが、何一つ印象に残っていません。
どうしてこんなことになったのか、私も当時、いろいろと考えたのですが、やはり、どこかで何かを見失なってしまったのだろう、としか言いようがありません。その後、「水中花」(七九年)や「風の王国」「ヤヌスの首」(八五年)などを見ましたが、そこにはあの颯爽たる時代の寵児は影も形もありませんでした。なんというか、冷えた鋳型で造られた鋳造物のようで、読むのがつらくなり、以後、私は、氏の作品をあまり記憶していません。
19
似たようなことは、他の作家さんでも感じたことがあります。船戸与一という人がいました。
デビューは、「非合法員」(講談社 七九年刊)という、けったいな作品でしたが、数年後「山猫の夏」(講談社 八四年刊)、これが好かった。ブラジルを舞台にした無法者たちの冒険譚なのですが、とにかく凄い作品で、これは現物を読んでほしい、としか言いようがない傑作でした。なんといっても作者が世界の現実を直視している。その姿勢と眼差しの確かさが際だっていました。
この人は、最初、豊浦志朗名義で「叛アメリカ史」(ブロンズ社 七七年刊)というドキュメンタリーを書いたのですが、フィクションに転じて「山猫の夏」という傑作長編小説を書きながらも、外浦吾朗の別名義で、さいとうたかを「ゴルゴ13」の脚本(原作)も手がけ、八二年には平野仁「メロス」の原作も手がけています。なにか義理でもあったのかも知れませんが、ふつう、小説が売れたら、もうマンガ原作には戻らないのが当たり前の世界ですから、何を考えていたのか、よく判りませんでした(と言っても、私たちが、外浦吾朗が船戸与一の別名だと知ったのは、かなり後になってからのことで、一一年に船戸名義で外浦時代のゴルゴ13原作を小説化して刊行したのです)。
そして、またもや、なのですが、その後も、順調に冒険小説を書きつづけていった船戸氏は、しかし、途中で急に失速します。「蝦夷地別件」(新潮社 九五年)あたりまでは、なんとか持ちこたえたのですが、「かくも短き眠り」(毎日新聞社 九六年)で、とうとう破綻しました。これは八九年にチャウシェスクが失脚して革命が起きた数年後のルーマニアを舞台にした話なのですが、なんというか、冷戦構造の崩壊後の世界に作者がもう付いていけなくなっている。重層的な敵を見すえていた、「山猫の夏」の作者の姿はなく、誰が敵か味方か判らない世界の実体を、作家がきちんと捉えきれていない。要するに、作者の思想と方法が破綻している。それも無様にそれを晒している。見ていられないほどの惨状でした。世界の現実を見すえて、それを作品に反映させている物書きが、いったん現実の世界を見失ったら、どうなるのか、ということを、まざまざと見る思いがしました。その後、「流沙の塔」などでも、その失速を回復することが出来ず、私はとうとう、読むのを止めました。
冷戦構造が崩壊した後の世界を、なぜ作家が描けなくなるか、という問題は、他の多くの要因もありますので一言では言いにくいのですが、要するに、その作家の資質と関係していて、普遍的な問題ではないと思われます。言い換えれば、その作家が背景としている思想の問題ではない。この場合、船戸氏だけの固有の問題として捉えるべきでしょう。氏は、敵味方がハッキリしている場合は良いのです。しかし、ポスト冷戦構造の世界では、誰が敵で誰が味方なのか、判然としない。そこで物語も失速を余儀なくされるのではないか、などと思われます。
冷戦構造が終わる直前に、政治経済学者フランシス・フクヤマは、論文「歴史の終わり?」をタカ派の雑誌「ナショナル・インタレスト」(八九年夏号)に投稿し、彼は、
「ソ連・東欧ブロックの崩壊で共産主義が敗北し、その最終局面を迎えようとしている。今後も局地的な戦いはあるだろうが、全体主義や共産主義のようなイデオロギーに基づいたグローバルな闘争はもうないだろう。歴史は自由主義の勝利をもって終わったのだ」
――と説き、世界的な衝撃を与えました。彼は当時、レーガン政権の米国務省の政策スタッフでした。当時はネオコン(=リベラル右派の新保守主義)と見られていましたが、イラク戦争の〇三年から、そうした立場から今は距離をおいています。しかし「世界の終わり」を刊行した当時、彼は間違いなくネオコンであり、そのイデオローグだったのです。ネオコンの特色は、(その語義矛盾が示すように)最初から右派だったのではなく、かつてリベラル左派か、あるいはトロツキストを含む極左であった人間が、転向して一転、右派になる歴史と思想のねじれ現象にあります。単純なタカ派と一線を画すのはこの点でもあり、よけい厄介で危険です。
子ブッシュ政権時、周囲にいたタカ派は、伝統的右派は当然として、ユダヤ系ネオコン、それにキリスト教右派でした。いずれも第一講のヘルツェルを論じた際に、なぜアメリカがパレスチナでのイスラエルの暴戻を見過ごすのか、という設問の際に論じた対象です。ネオコンを支持するのは、主に共和党内のユダヤロビーが急先鋒ですが、同様にキリスト教右派も大きく関与しています。共和党は中東の民主化を掲げましたが、それは一見、中東で唯一の民主国家たるイスラエルを利しています。しかし現実には、イスラエルの行っていることは米国と同じ覇権主義なのです。パレスチナ人民はファシズム国家の圧制下にあるも同然です。悲しむべき現実ですが、中東のような、まだ部族が国権を握っている国々で、口先だけ民主主義を唱えても意味がなく、現実を見ようとしない共和党員は、結果的に米=以の帝国主義に加担している、としか言えません。
「歴史の終焉」という理念は、フクヤマと同じように、第二次大戦後のフランス政府内の経済産業省で働らいて、欧州経済共同体(EEC=現在のEUの前身)の形成に寄与した、ロシア生まれの哲学者コジェーヴが、「ナポレオン戦争によって歴史は終わった」と述べたことに淵源します。
コジェーヴもまた若い頃には左派でした。革命後のロシアから亡命した彼は、三十年代にソルボンヌ大学でヘーゲルの「精神現象学」の講義をしており、ジャック・ラカンやメルロ=ポンティからジョルジュ・バタイユやアンドレ・ブルトンらが受講していたと言います。スターリンの死を知った時、彼は「父を失ったようだ」と語った由です。そうした過去を持ちながら、大戦が終わると、「歴史の終焉」を言い出します。
皮肉なことに彼らはその個人史から「歴史が終わった」という言説までが、くり返しの歴史となっているのです。
フクシマは、その後、国務省を退いてから、軍産コンプレックスに近いシンクタンク、ランド研究所で研究を続け、それまでに書いた論文を「歴史の終わり」(三笠書房 九二年刊)という書物にまとめ、またもやセンセーショナルな評判を取ります。
しかし、この本に対して、世界中のリベラル左派からの反撥は強く、たとえば日本では浅田彰氏などが猛然と反感を剥きだしにして、フクヤマ本人を含む世界各国の現代思想家(SF作家J・G・バラードを含む)との対談から、その言説の一面性を否定し、「「歴史の終わり」と世紀末の世界」(小学館 九四年刊)にまとめました。
浅田氏の言いたいことは、一言でいえば、冷戦が終わったりソ連が崩壊したくらいで歴史が終わるものか、というものです。代表的な対象は、たとえば解体した旧ユーゴスラヴィアで起きていること(民族浄化その他)であり、それは二十世紀の時代錯誤な民族主義の再びの台頭にも見えるが、実は来たるべき二十一世紀を先取りした、冷戦構造後の戦争のプロトタイプかも知れないのだ。といった論調で、ポストコロニアリズムの視点から、フクシマの楽観主義を否定しました。同時に、彼はフクシマがコジェーヴの反復であることを指摘して、「歴史が終わったのだから哲学も終わった。後は経済的な利害調整くらいだ」と言って、フランス政権に入りこみ、現在のEUに繋がるEECの設立に動いたコジェーヴの処世を批判しています。つまりそれはネオコン時代のフクシマへの批判にもなっているのです。
フクシマは、ブッシュが九・一一の後、周囲の強硬派に推されてイラク戦争を始めると、ネオコンから距離をおきました。コジェーヴよりはマシだったとは言えるでしょうが、同時に、その自己矛盾的なビヘイビアに対する厳しい批判も浴びています。あれから四半世紀後の現在、浅田氏の見透した世界のパースペクティヴは確かであったことが証明されたかに見えます。
しかしながら、浅田氏は思想家であり、作家ではありません。彼に見えているものが、全ての人に自明なはずもないし、対談を除くと単独著作もなく、影響力は大きくない。側聞するところによると、ごく身近な友人にだけFAXで自分の論考を送信しているそうですが、メールの時代にFAXというのも、ちょっとどうかと思われます。
それまでの既成の価値観で来ていた人たちは、ポスト冷戦構造の時代に、そこでいきなり足をすくわれ、よろめいてしまうのは避けられません。そして前方は霧がかかったように不透明で何も見えない。現在も未来も曖昧な、歴史のトワイライトゾーンです。その狭間に落ちこんでしまったら、ある種の作家は、もうどうにもならない情態に陥ってしまう。特に、敵味方が画然としていた時期に力量を発揮した作家ほど、その失速は大きい。しかも船戸氏は、そういう黄昏の世界を先んじて描いてきたはずなのです。敵味方がハッキリしない第三世界で、なおも、自分一個を信じて、まわり中がどう考えようと己の信念をつらぬく。そうした主人公を描いていたはずでした。それなのに、いざ、世界そのものが、敵も味方も白夜のような明暗のはっきりしない世界になった途端に破綻するのでは、一体いままでの作品はどうなったんだ、と問わざるをえない。まあ、この作家さんに関しては、もう故人ですので、ここではこれ以上、論じません。
20
五木寛之氏に戻ると、六七年時点での氏が、非常に大局的に世界を視つめる視座がしっかりしていたことは確かです。バックグラウンドとしての現代思想もキチンと把握していた(私がパリで知り合った友人が言っていたように、氏は構造主義を理解し、作品に取り入れていました)。だのに、何故、それが休筆をはさんだとはいえ、たった十年足らずで、作家がそれほど頽落することが有りうるのだろうか。不思議でなりませんでした。私も、(後追いとはいえ)デビュー作から愛読していただけに、「戒厳令の夜」を読んだ時のショックは大きかったのです。当時、連載された雑誌で読んでいたので、毎月毎月、物語がどんどん、ダメになっていくのを見るのが辛かったのを記憶しています。一体、なぜなのか。私は問い続けたものです。
一つの補助線として、これは少しばかり、セルフコンシテッドなのですが、笠井潔氏の論考があります。これは当初、書評として書かれたものから拙作についての箇所だけ抜粋した形で解説として「バベルの薫り」文庫版に付せられました。最初の書評では、あろうことか大江健三郎氏の「治療塔」と並べて批評対象となり、おそらく、本命はそちらを論究する目的だったと思われますが、それはこの際、措きます。笠井氏は、半村良氏の「産霊山秘録」(七三年)をもって「日本に固有な伝奇SFのスタイルが確立」された、として次のように続けます。
「半村良の発明になる伝奇SFは、SFというジャンルの枠を超えて、一九八〇年代には日本のエンターテインメント界を猛烈な勢いで席巻した」として、八〇年代の伝奇SF作品として、栗本薫「魔界水滸伝」、藤川桂介「宇宙皇子」、荒俣宏「帝都物語」、さらにコミックとして永井豪「手天童子」を挙げ、八〇年代のエンタメ界をスケッチします。続けて、
「八〇年代に圧倒的な成功をおさめた伝奇SFは、都の権力(天皇制)に闘争を挑む「逆賊」ヒーローという二項対立的な図式を、ほとんどの作品で執拗なまでに反復している。それはまた、縄文と弥生、山人と農耕民の二項対立にも通じるだろう。しかし、八〇年代の伝奇SFに奇妙な捩じれが存在したことを、無視することはできない。その偉大な先行者は、むろん「産霊山秘録」の半村良だろうが、同時に「日ノ影村の一族」から「風の王国」にいたる、五木寛之の影響もまた濃厚である。
少し注意して、半村と五木の伝奇小説を比較してみよう。すると、ほとんど同型的な図式を使用しているように見えて、じつは両者が決定的に相違しているという事実が判明する。五木作品の場合には、縄文と弥生、山人と農耕民、「逆賊」と天皇制という二項対立が、それぞれの作品の深部において物語を駆動している。だが半村良の「産霊山秘録」では、さほどに事態は単純ではない。この作品でヒの一族(ヒは「日」にも「卑」にも通じる)は、天皇家に征服された日本列島の原住民だが、同時に古代から中世まで、天皇家を守護する秘密組織(勅忍)として存続していたという具合に設定されている。
征服と被征服、支配と被支配の構図は半村良の場合、戦後左翼イデオロギーに影響された五木寛之のように、必ずしも単純な二項対立を構成するものではない。両者は対立しながらも複雑に絡みあい、ほとんど一体化し、ようするに奇妙な補完関係にある。被征服民の子孫が征服王朝に反逆するためには、おのれの肉まで喰い込んでいる倫理や規範を、血の涙を流しながら抉りだし、あえて自己否定しなければならないのだ。
「産霊山秘録」のヒーロー飛稚が勅忍のアイデンティティを放棄し、天皇制批判の立場に到達するには、戦国時代から敗戦直後へのタイムスリップが求められる。五百年という時間的な断層は、飛稚による回心の困難性を象徴するものだろう。以上のように物語を駆動する二項対立という点では、一九八〇年代に盛大な流行をみた伝奇SFは通説に反して、半村良よりも五木寛之の影響下に成立したものといえる。
八〇年代の伝奇SFは、九〇年代の前半になると川又千秋や荒巻義雄による戦争シミュレーション小説に、エンターテインメント界の主役の座を奪われてしまう。一九八九年の昭和天皇の死が、五木的な二項対立の構図を失効させたのかも知れない」
――と解明します。これを一読して、私は長いこと不明だった五木氏の失速の理由が判った気がしました。
21
私自身の作品について付会して説明することを許して頂けるなら、「バベルの薫り」は、まさしく笠井氏の炯眼が示すように半村良氏の「産霊山秘録」へのオマージュでした。半村氏は、小松、星、筒井ら諸氏と同時期の、いわゆる第一世代に属する作家ですが、デビュー以後、しばらく創作活動から離れます(日本SF作家クラブの活動には参加していましたので、全く無縁だったわけではありません)。それが七二年に「石の血脈」という壮大なスケールの幻想小説で復活し、その後、SFマガジンに「産霊山秘録」を連載の形で発表していきます。これがまとまった本として刊行されたのは七三年で、早川書房の日本SFノヴェルズの一冊としてでした。これが日本における伝奇小説の中興の祖となったのは、笠井氏が述べる通りです。
ちなみに伝奇小説とは、大本は中国の唐宋伝奇にさかのぼりますが、これが戦前の日本で隆盛をみたのは、白井喬二「神変呉越草紙」や国枝史郎「蔦葛木曽桟(つたかずらきそのかけはし)」などで優れた功績を示し、同時代の芥川龍之介に「あれだけのものを空想で書いたとしたら、たいしたもの」だと言わしめています。しかし、その後、戦後になって山田風太郎の忍法帖から派生した作品などを除くと、ジャンルとしての隆盛はありませんでした。ところが七〇年前後に興った「異端文学復刻」ムーヴメントに乗って、七六年に「神州纐纈城(しんしゅうこうけつじょう)」などを収めた「国枝史郎伝奇文庫」(講談社)が刊行、復刻されるや、三島由紀夫の高い評価を受けるなど、その素地が整っていきます。そこへ半村氏の「産霊山秘録」が登場して、ジャンルとしての基礎を固めた格好です。
新ジャンルに相応しく、時のSFマガジン編集長の森優によって「伝奇ロマン」の名が冠せられて、SF以外の分野からも、この新興ジャンルに大勢の作家たちが参入し、八〇年代の隆盛を見ました。業界的には、日本SF界に「批評」を導入しようとした初代編集長・福島正実氏が、その試みに頓挫し、責任を取る格好で編集長を辞したことから、二代目の森編集長は新しい方向性をエンタメ志向で模索しており、その一つが半村氏の作品群となった、とも言えます。これに匹敵する影響力を持った強い遺伝子をもつ作品は、その後の架空戦記ブームをもたらした荒巻義雄氏の艦隊シリーズくらいしか思いつきません。おびただしい作家さんが、それぞれの時代に伝奇ロマンと架空戦記に参戦しました。
しかしながら、伝奇ロマンに関するかぎり、その興隆の実体は、笠井氏が分析してみせたように、実際には、五木寛之流の、天皇制に対する「まつろわぬ民」のルサンチマンといった単純な二項対立に回帰してゆく構造が多かったのも確かな事実です。後にSFマガジンに載った矢野徹氏による作家インタビューでは、半村氏は、「この分野では大体十人以上の作家が食える鉱脈だと思い、他の人が書く前に唾を付けておこうと、思いつくかぎりの分野内のメインテーマとなる作品を書いた」(大意)といったことを述べています。
半村氏は三三(昭和八)年生まれで、三二年生まれの五木氏と大した年齢差はないのですが、幼少時に父親を亡くし、旧制中学を出た後、苦労したことが、後の天皇制への批判となっていると思われます(とはいえ、それは単純な左翼的イデオロギーとは無縁の、一般庶民の目線で語られるものであり、作品に反映する時は、飛稚の最後の叫びとして描かれたように、天皇制に対する矛盾した感情をそのまま矛盾として描き、多少なりともアンビバレントな側面があります)。
対して、五木氏は、生まれは本土でしたが、生後まもなく朝鮮半島に渡り、植民地育ちです。前述の生島治郎氏などもそうですが(彼は生まれからして上海でした)、植民地で育つ、ということは非常に奇妙な体験になります。まず、どんな内地の日本人よりも、そこでは純粋培養された理想的な「純正日本人」という規範を植えつけられて、抜きがたい原体験となります。
しかも、それが四五年八月一五日を境に一変して、今までの支配階級だった日本人は周囲の被支配者から、よくて冷遇、悪くすると暴行殺害されても文句は言えない立場に転変するのです。価値観も思想も、一どきに転倒し、幼い日々に癒やしがたい心的外傷を受けます。さらに日本に帰るためには言うにいえない悲惨な引き揚げ体験がつきまといます。
こうした国家と戦争に翻弄された不条理な少年期の体験が、本土の日本人や、その戦争経験とは全く異なることは容易に察しられると思います。要するに、植民地だった海外に生まれた日本人は、生まれながらにして純粋な天皇主義思想の中で育ち、それを疑るようなことはないし、周囲にそれに反対するような成人もいない状況で成長して、その挙げ句、日本の敗戦によって、植民地の住民から怨嗟(ルサンチマン)を浴びて、復讐される。といった悲劇的個人史を持つのです。
笠井氏が、半村氏と五木氏の二つの伝奇ロマンの違いを指摘するのは、おそらく、二人のアドレッサンスの時期と環境にまで遡る必要があると思いますが、今は、それは捨象して、そういう違いがあったことだけ、記すにとどめます。
一言だけ付け加えておけば、私は「バベルの薫り」を半村良氏の「産霊山秘録」へのオマージュとして書いたのですが、そのために、天皇制を比喩的な次元で、国家が一つの「身体性」を表徴する際に、それが司る「免疫系」があるとしたら、そこに内在しつつ対立する存在(いわゆる、まつろわぬ民)を「自己免疫疾患」として把える、という生物学的仮説を借りて、伝奇ロマンを、よりSFに近づける構図を描きました。これは八四年にノーベル生理学・医学賞を受賞したイェルネのイディオタイプネットワーク仮説に基づくものでした。
ただ、まあ、残念なことに半村氏には、拙作がご自分の作品へのオマージュだというメッセージは伝わらなかったようでした。人づてに、氏が拙作に対して、「天皇制を描くなら、被差別民への言及がないとね」といった批判をなされた、と聴きました。しかし、狙ったわけではないのですが、昭和が終焉するまさにその時期に、天皇制に否定的な物語を書きつづけることすら作家としては重圧だった上に、タブーである被差別コミュニティにまで言及するのは、事実上、当時の日本の出版界では不可能事です。これに少しく義憤を感じた私は、やむをえず――あまり見っともよいことではないのですが――自分の作品の出自を語る、というエセーをユリイカ誌(九三年)に書く、という少々、忸怩たることをしたのですが、最終的に氏にそれが伝わったかどうかは判りません(この小論は「ジャパネスクSF試論」として後に巽孝之編「日本SF論争史」に収録されましたし、拙サイトでも公開しています)。
長々と牽強付会なことを書いたような気がしますが、私が言いたかったのは、六七年には時代の最先端で有効だった「異議申立(オブジェクシオン)」が、七〇年代に失効した、というのは、そういうことだったのではないか、と思ったからです。拙作は対象外ですが、「産霊山秘録」と「戒厳令の夜」を較べれば、自ずと、その差異は明白になります。ほぼ数年の差で、ともに雑誌連載されていた作品が、片方は、おそらく二十一世紀の検証と再読に耐えうる論理的堅牢さを有しているのに対し、もう片方が、もはや二十世紀末には失効している、という作品内部の論理的脆弱さを露呈しているのは、故なしではない。一つや二つの個々の作品を恣意的に取り上げて、それがそうだからこうだ、というものでもありません。これは、半村氏と五木氏の作家的資質の根源に根ざす、なんらかの違いに由来する差異によるものだ、というしかないのです。
ただ、六七年の段階で、「蒼ざめた馬を見よ」は間違いなく「黙示文学」たりえていました。
それ以降の日本の現代文学であれ、娯楽小説であれ、黙示文学に迫ろうとした作家も、そしてそれで成功した作品も私は知りません。それゆえ、五木寛之氏の「蒼ざめた馬を見よ」は孤立した栄光をいまだ、まとい続けているのです。
PREV | NEXT
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?