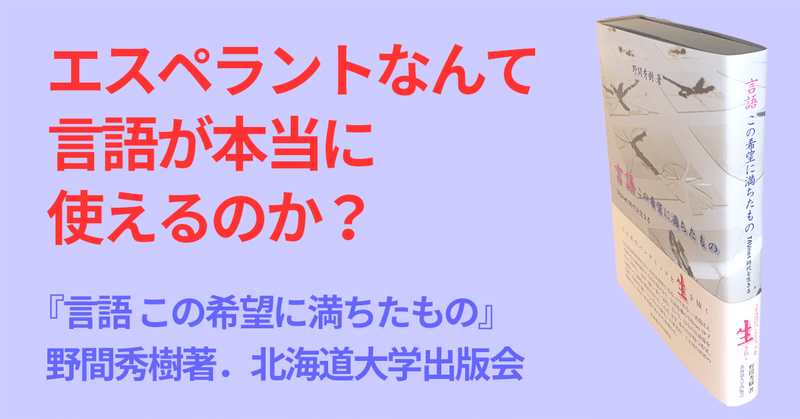
「国際人工語」エスペラントは本当に使えるのか?
国際語とか族際語などと呼ばれるエスペラント.それは実際に使えるのでしょうか?
野間秀樹『言語 この希望に満ちたもの』北海道大学出版会から,3000字ほどを公開します.
エスペラント、理想は解った。しかしそんなものが使えるのか
ソシュールの筆頭の弟子とも言うべき、フランスの言語学者アントワーヌ・メイエ(Antoine Meillet, 1866-1936)は、ヨーロッパの諸言語についてとりわけ歴史的、社会的な視点から述べたメイエ(2017)の末尾に、「人工語の試み」という章を置き、エスペラントについて問答無用と言わんばかりに、高く評価し、次のように述べている:
簡単に学べる人工語を作り上げる可能性と、このような言語が使用できるという事実は、実践によって証明されたのである。理論的な議論はどれも無駄である。エスペラントは機能を果たしたのだ。実際に使われることがないだけである。 ――メイエ(2017: 460)
「実際に使われることがない」という最後の一文は、同書の原著初版一九一八年、第二版一九二八年以降の、エスペラントの数多の実践が書き換えてしまった。
イタリアの記号学者、小説家のウンベルト・エーコ(Umberto Eco, 1932-2016)もエーコ(2011)『完全言語の探求』のやはり末尾に「国際的補助言語」の章を据え、エスペラントを語る中で、その称揚者たちを紹介している。右のメイエはもちろん、ソシュールと並ぶ〈音素〉の発見者とも言うべき、ロシア構造主義言語学の祖、ポーランドの言語学者、ボードアン・ド・クルトネ(Baudouin de Courtenay, 1845-1929)、全七巻の英文法の巨冊で絶大な影響を与えたデンマークの英語学者、オットー・イェスペルセン(Otto Jespersen, 1860-1943)、英国の哲学者、バートランド・ラッセル(Bertrand Russell, 1872-1970)、ドイツ語圏の哲学者、ルドルフ・カルナップ(Rudolf Carnap, 1891-1970)。
さて、言語の実践にあっては、この点が重要なのだが、いくら言語構造が簡素であっても、自然言語が表し得るような、複雑で微妙なことどもを表せないのでは、浅い表面的な疎通にしか役立たない。しかしエスペラントはその点で、既に豊かな実践を経験している。ザメンホフ自身がエスペラントで詩を書いたり、アンデルセンの童話集、シラーの『群盗』(La rabistoj)、ゴーゴリの『検察官』(La revizoro)、シェイクスピアの『ハムレット』(Hamleto)、『旧約聖書』(La Sankta Biblio)の一部などをエスペラントに翻訳していたのを始め、その後、多くの言語で多くの人々によって、詩、小説、戯曲、エッセイ、論考など様々なテクストが翻訳されている。もちろん『源氏物語』(Rakontaro de Genĝi)などもある。
新聞や放送の歴史も長い。エスペラント=エスペラント辞典はもちろん、エスペラント=日本語辞典を始め、多くの二言語辞書が刊行されている。日本エスペラント学会エスペラント日本語辞典編集委員会編(2006)『エスペラント日本語辞典』は、日本語圏で編まれた中辞典規模の二言語辞書の中でも、独仏西韓中語などの二言語辞書にゆうに匹敵する高い水準だと言える。
エスペラントの国際大会や国際合宿なども盛んに行われている。前インターネット段階では、エスペラントに接したくとも、実のところ大きな困難を伴っていた。エスペラントの言語場は、書物や、文通や、同好会のような言語場に限られがちであった。それでも例えば日本と韓国の間のエスペラントでの交流の場は、一九八〇年代以降、なかなか活発に続けられていた。ところがインターネット段階を迎えた今では、こうした困難が劇的に改善されることになった。話者の多い他の自然言語同様、ネット上でいくらでもエスペラントに接することができるようになったのである。つまり学んでも使えない、学んでも出会えない、などということが、少なくともネット上では、なくなった。つまり、私たちの今日の日常の言語場でも、なくなったのである。ちなみにウィキペディア(Wikipedia)の言語別の記事数では、三一九言語のうち、三五位となっている。二〇二一年三月八日。
日本語圏では一九〇六年に日本エスペラント協会が発足しており、経験値も蓄積されている。小説家・二葉亭四迷が『世界語』という題名で最初の学習書を刊行したのを始め、エスペラントに係わった人士は少なくない。柴田巌・後藤斉編、峰芳隆監修(2013)『日本エスペラント運動人名事典』は物故者二九〇〇人を採り上げており、壮観である。国際連盟事務次長も務めた教育者・新渡戸稲造(1862-1933)、社会主義者・堺利彦(1871-1933)、コロケーション研究で知られる『英和活用大辞典』の勝俣銓吉郎(1872-1959)、『国史大系』の編纂などで知られる歴史学者の黒板勝美(1874-1946)、民俗学者・柳田國男(1875-1962)、『広辞苑』の言語学者・新村出(1876-1967)、大正デモクラシーを代表する思想家・吉野作造(1878-1933)、『日本改造法案大綱』(1923)の右翼、国家主義者・北一輝(1883-1937)、アナキスト・大杉栄(1885-1923)、詩人、童話作家の宮沢賢治(1896-1933)、『一般言語学講義』を訳し、ソシュール言語学を日本に導入した言語学者・小林英夫(1903-1978)、文化人類学者・梅棹忠夫(1920-2010)、中国での反戦運動で知られる長谷川テル(1912-1947)などなど、多彩である。柳田國男については後藤斉(2015)も詳しい。
アナキズムの影響を大きく受け,また英仏語の翻訳も多く手がけた中国の小説家・巴金(Bā Jīn, 1904-2005)のことばが、エスペラントのこのかんの姿をよく表している:
エスペラント、それは理想ではない、事実である
エスペラントは弾圧もされた。闘争せねばならぬ言語でもあったのである。闘うエスペラントのありようを知るには、書名からして思わず気合いが入るが、大島義男・宮本正男(1974, 1987)『反体制エスペラント運動史』があり、またウルリッヒ・リンス(1975)、その名も『危険な言語――迫害のなかのエスペラント』がある。後者はエスペラントからの日本語への翻訳書という実践の形でもあって、エスペラントが言語として働くありようを、文字通り手にとって、リアルにわしづかみすることになる。田中克彦(2007)の書名は『エスペラント――異端の言語』、なるほど異端ではある。そしてその異端から、人間にとって言語とはという、本質的な中枢へ迫ろうとしている。ザメンホフの思想はザメンホフ(1997)で読める。また小林司(2005)。
エスペラントもまた、単なる「道具」ではなかった。それは〈言語〉だったからである。言語道具観がいくら喧伝されようとも、言語はいつも人の存在の深いところと共に在る。
『言語 この希望に満ちたもの』北海道大学出版会
https://www.hup.gr.jp/items/65001915
『言語 この希望に満ちたもの』からは次の記事もどうぞ:
見えている世界は,ことばという被膜に覆われている
https://note.com/noma_h/n/nfd846d7c3d57
〈Aとは何か〉という問いはなぜ危ないのか?
https://note.com/noma_h/n/n1ffa030a72be
万葉仮名という上代キラネーム法
https://note.com/noma_h/n/n17cc1fb06fb8
ツイッターで見る『言語 この希望に満ちたもの』
https://note.com/noma_h/n/n7f51fe465a95
「こんな人」ってどんな人? 指示語の機能が崩壊する
https://note.com/noma_h/n/n74c41f78a030
ウイルスの時代だからこそ見据えるべき〈言語〉:
言語こそは私たちの最後の砦
https://note.com/noma_h/n/n3235bc7a381f
選書企画★言語この希望に満ちた本たち
https://note.com/noma_h/n/n36df8ca4e32d
「すき!」などいただければ,たいへん励みになります.
ありがとう存じます!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
