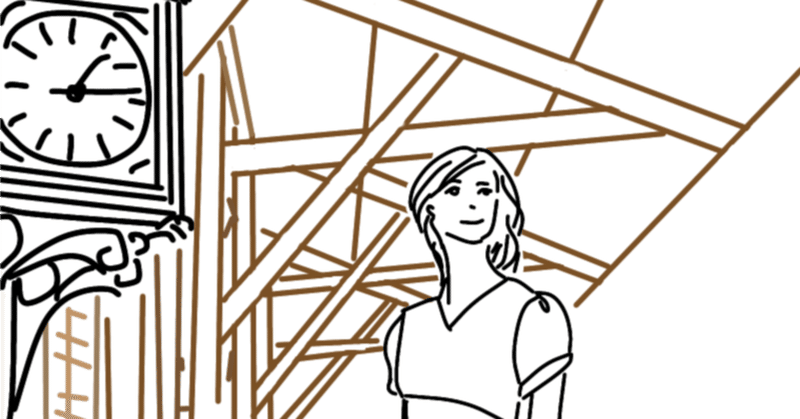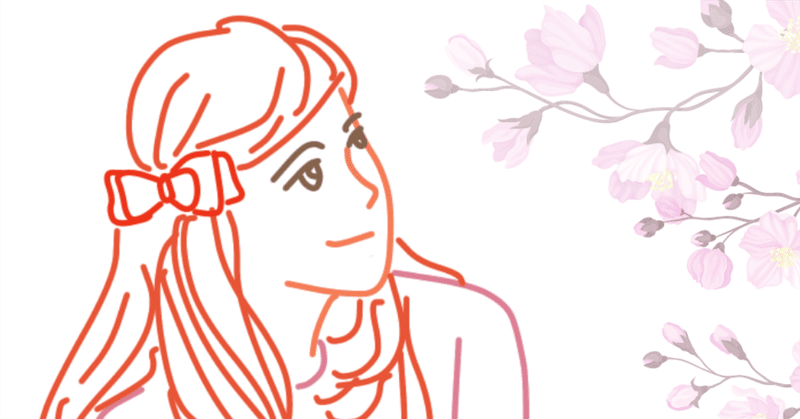タニリョウジの秘密の日記帳です。
月額課金ではなく、買い切りです。なので、一度購入すると、過去アップされたものも、これからアップされる未来のものも、全部読めるのでお得です。
¥390
- 運営しているクリエイター
2022年10月の記事一覧
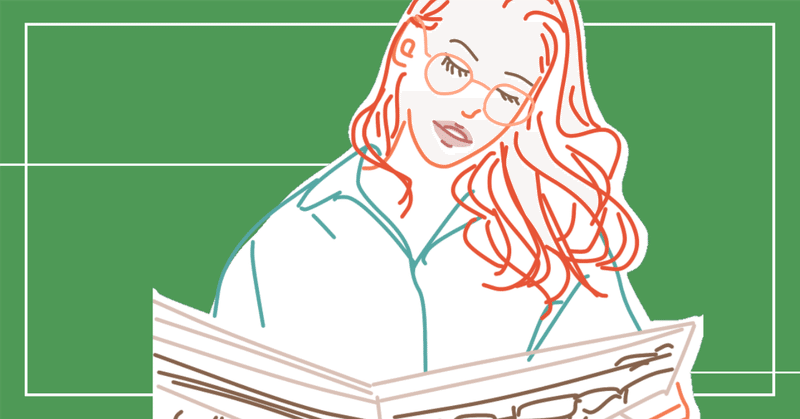
身体が近くにいることで生じる「ついで」の効果〜東畑開人『聞く技術 聞いてもらう技術 』・小川 さやか『チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学』
ここ最近、私はあまり元気がなかったのだけど、ちょっと散歩した先でなにかイベントをやっているのを見かけて、近づいてみたら、そこで古い知人とばったり出会って、「あらータニさんじゃないですか、奇遇ですねー」みたいなところから3分くらい立ち話があった。その時間を経て、なんだか自分の中の元気の無さが薄れていたのが印象的だった。 多分、ここ最近の自分の元気の少なさは、FOMOの一種みたいなものじゃないかと薄々思っていて。しかし冷静に考えれば、その感覚でさえ幻みたいな、まあ要するに想

「縁が君を導くだろう」〜ターリ シャーロット (著), 上原 直子 (翻訳)『事実はなぜ人の意見を変えられないのか-説得力と影響力の科学』白楊社、2019
ターリ シャーロット (著), 上原 直子 (翻訳)『事実はなぜ人の意見を変えられないのか-説得力と影響力の科学』白楊社、2019読みました。面白かったです。 最近でも話題だったワクチンを打つかどうかみたいな話でもそうであったように、ワクチンの有効性にしても害毒にしても、事実は人の意見を変えない。 これはなぜなのか、というお題を切り口に、行動経済学や社会心理学の知見が示されるわけだけど、端的には、人間の頭がそういう風に作られてないからだ。 むしろ、下手にデータを与