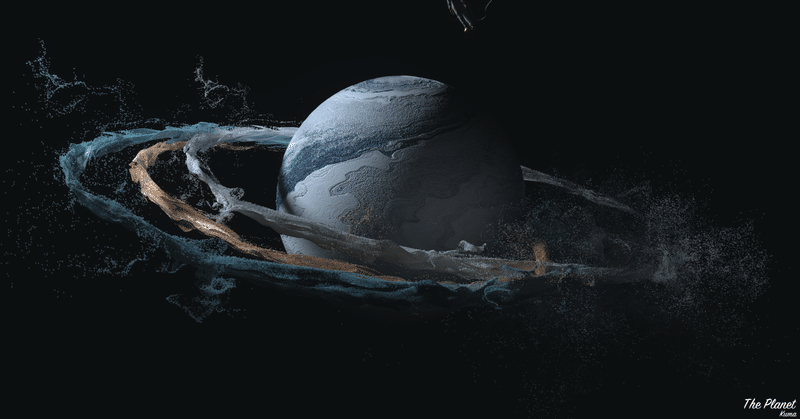
プロジェクト・ヘイル・メアリーを読んで(※ネタバレあり)
今年のお盆は比較的時間があったので、ずっと読みたいと思っていた「プロジェクト・ヘイル・メアリー」を一気に読んだ。
この小説は、「火星の人」でおなじみのアンディ・ウィアーの最新SF小説である。(最新といっても発刊は去年)
SF作家である柞刈湯葉や、Podcastチャンネルのいんよう!でも大絶賛されていたので、映画化される前に読んでおこうと心に決めていた。
元々は実家に帰る交通機関の中で暇つぶしとして読む程度の期待だった。
しかし、内容があまりにも面白いものだから、せっかく久しぶりに実家に帰ったというのに、親ともろくに話さず読書に耽ってしまった。
そんなめちゃくちゃ面白いプロジェクト・ヘイル・メアリーなのだが
内容を少しでも言うとネタバレになってしまう。
柞刈湯葉も言っていたが、
この本は誰かにネタバレされる前に読んだ方がいい!
プロジェクト・ヘイル・メアリーを読んで!!
映画化されることも決まっているので、メディアで取り上げられる際にもネタバレされかねないし、映画の予告編ですら事前情報なしで読んだ時の面白さを損なう可能性がある。
しかし、こんな面白い小説、話さずにはいられないじゃないか!
ということで、この先はネタバレありで感想を書いていくので、ネタバレされたくないと言う方は5秒数えるうちに、いいねだけ押してブラウザバックしてほしい。
(ネタバレから救ってあげたのだからいいねするのは当然だろう?)
5
4
3
2
1
オーケイ。
ネタバレされたくない方は消えてくれただろう。
もし、逆にネタバレを見にきた方がいるかもしれないので一応断っておくが、この記事はプロジェクト・ヘイル・メアリーの内容を事細かに紹介するものではない。
すでにこの小説を読まれた方と感想を分かち合いたい!というモチベーションで、この小説を読んで私が何を感じたか、考えたかという個人的な話を紹介する記事だ。
なので、細かい設定の説明などをするつもりはない。
お前の感想なんか興味ねぇよ!という方はブラウザバックしていただきたい。
…
オーケイ。さらに読者を絞り込んでしまった。
ここまで読んでくれている人がいるかは分からない。たぶん、1人2人くらいは読んでくれているだろう。おそらくだが。
だが問題はない。いつも読んでくれているのはこれくらいの人数なのだから。
なにやらプロジェクト・ヘイル・メアリーと火星の人が混ざったような文体になってしまった。(これがやりたかっただけ)
…茶番はこれくらいにして、感想を話していきたい。
リアリティがすごい!
まず、私が面白いと感じたポイントは、
リアリティだ。
SF小説はあまり読んだことがなかったので、この小説の科学考証のレベルがどの程度なのかは分からないが、文系の私からすると全く何を言っているか分からないレベルで詳細に科学的な設定が詰められている。
次から次へと起こるトラブルや想定外の事態に対して、頑張ればほんとに実現するんじゃないか?と思ってしまうほど具体的な科学的理屈で解決がされていくので、とてもワクワクした。
その辺のミステリー小説より断然現実味がある。
それほどリアリティがあるのだ!
特にアストロファージの持つ性質に関しての設定は見事だと思う。
あらゆる性質がすべて上手く繋がっている。
エネルギーを吸収しても温度が96.45℃なのはエネルギーをニュートリノとして保存しているからで、かなりのエネルギーを保存できる。
そのエネルギーを吸収する性質は、ヘイル・メアリー号の燃料になるのはもちろん、外殻一面にアストロファージの層を作っておくことで放射線から守ることに活きている。
フィクション作品の原則としてよく言われるのが、大きな嘘は1つまでということだ。
この作品の場合、大きな嘘はアストロファージの存在だろうか。
いや、ニュートリノを通さないアストロファージの細胞膜のみが嘘な気がする。この魔法の細胞膜があればそのほかの性質は自然発生的に起こりうるのではないか。(わたしは科学は全くの素人なので本当にそうかは分からないが、それほどリアリティがあるということだ。)
え?宇宙人の存在が最大の嘘だって??
それが嘘かどうかは実際にエリダニに行ってみないと分からないでしょうが!
人間賛歌の小説
とはいえ、宇宙人ロッキーとの関係性がこの作品の最もエモいポイントであるのは疑う余地がない。
最後に主人公が自分が生きて帰ることを諦め、ロッキーを救いに行くシーンはグッとくるものがあった。
作者もここを最も描きたかったのではないか。
この作品では宇宙人は「いいやつ」として描かれている。それも、人間によく似た精神性を持った知的生命体としてだ。
好奇心旺盛で、計算能力も非常に高い。友人や恋人を持ち、友人や星の存続のためなら自己犠牲も厭わない。トラブルに対して諦めずに仮説検証を繰り返して解決を図る。
そんな人間の持つ美徳を宇宙人であるエリディアンも持ち合わせている。
人間の持つ美徳は宇宙人にとっても美徳である。
これは生物の繁栄にとって必要な機能ということだろうか。
では、作者の伝えたかった人間賛歌は、人間とエリディアン共通で持つ美徳である、自己犠牲の精神や諦めない心だろうか。
それもそうだろう。しかしそれでは人間賛歌でもありエリディアン賛歌でもある。
真の人間賛歌はなんだろう。
そこで思った。人間によく似た宇宙人であるエリディアンと人間の最も大きな違いはなんだ?
それこそがこの作者の考える、真の人間賛歌ということではないか?
エリディアンと人間は、見た目や身体機能こそ大きく違えど、精神や文化的なところの違いはあまりないように見える。
しかし、1つ決定的に違うのは、人間の方が科学技術が進んでいるということだ。
エリディアンは視覚を持たないので仕方ないかもしれないが、コンピューターを持たないし相対性理論も放射線の存在すらも知らない。
はるかに人間を上回る寿命、地球にはない高性能な金属素材、単体で電卓並みの計算能力、一度聞いたことを忘れない記憶力、なんでも作り上げる工学能力と、軒並み高スペックなエリディアンだが、科学だけは人間に劣っている。
これこそまさに作者の伝えたかった人間讃歌ではないだろうか!
科学とは、先人から脈々と受け継がれてきた人間の知の積み重ねの結晶であり、最も尊いものだ。
人間はエリディアンと比べて寿命が短いし頭も良くない。しかし、その短い命を燃やして、種の繁栄のために自分のするべきことを見つけて、そこを命を懸けて解き明かそうとする。
そして、その営みは決して1代で途切れることなく、脈々と受け継がれていく。
その知の積み重ねの尊さを訴えているのではないか。
小説のラストで主人公はエリディアンの子供に対して科学の授業を始める。
これはまさに、人間の尊さである知の積み重ねが、エリディアンの文化に継承されようとしているところである。
(エリディアンの社会にも学校のようなものは元々ありそうなので、見当違いかもしれない)
とにかく、科学技術が、人間の知の積み重ねこそが人間讃歌だと作者は伝えているように私は感じた。
SF小説がこんなに面白いなんで、正直知らなかった。
もっとぶっ飛んだ現実味の無い話かと思っていた。
しかし実態は真逆だった。ちょ~現実的である。
なんでも実際に体験してみないと実態は分からないということだ。
総じて、何かに挑戦する勇気をこの小説はくれた。
もっと自分に正直に生きよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

