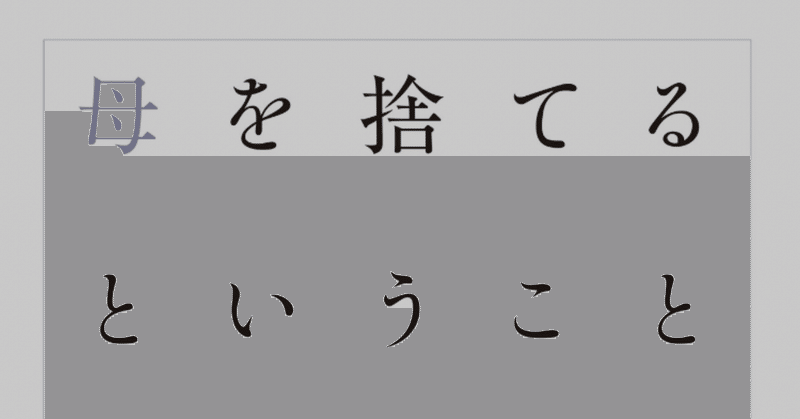
ぼっち在宅介護 「母を捨てるということ」おおたわ史絵(著)を読んで
2021年、テレビにおおたわ先生がでてらして、お母様の話をされていました。
元看護師だったお母様が、心のバランスを崩してお薬の中毒にかかってしまっていたこと、ご家族である開業医のお父様や医学生だったおおたわ先生に暴言や悪態をついたりして、大変な見守り生活を長くされていたことなどを知りました。
私は、どんなジャンルでも、経験者、先輩方の話を聞いたり読んだりすることが好きでして。
その頃、家族の問題と、母の認知症と父の介護生活に悩みを抱え、日々、父と泣きいたので、吸い込まれるように、おおたわ先生の本を読みました。
基本、本はお安くたくさん読みたいので、あちこち古本を探して、最安値で購入し届くのを楽しみにするのですが。
おおたわ先生の本は、すぐにでも読みたくて、当時、Kindle買いして一気に読みました。
内容は、ぜひ読んでいただきたいので、ざっくり気味に。
おおたわ先生とお父様は、お母様を捨ててはいらっしゃいません。
救世主のようなドクターがお二人の前にあらわれて、お母様ではなく、お二人に入院をするよう勧められました。
お二人が入院をし、冷静に物事の判断ができるようになるためです。
お母様との距離を取るという大切な決断をすすめられたんです。
開業医だったお父様、医大生だったおおたわ先生、いろんなご事情を理由に、家をあけることを拒まれていましたが、最終的には家を出られます。
お母様はまだ若く、お世話する方がいらしたので、日常生活にお困りはない環境がそろっていました。
そして、お二人は、お母様と距離をとり、心のバランスを崩している方との接し方を学ばれます。
家に戻られても、それなりに学び直しの日々は続くのですが、、、
それでも、一度、お二人とお母様の間に風が流れて、空気が変わったことで、考え方や暮らしが変わっていかれました。
ま、めっちゃ、ざっくり、軽めにに書いてしまいましたけど…
なかなか深く…実話なのか?ドラマなのか?とどんどん引き込まれていくお話です。
外からは、豊かでエリートな一家の暮らし、でも、さまざまな事情を各家庭は抱えているのだなぁと思いました。
お医者様という立派な方、医療に従事する立派な方々でも、煩悩なのかなんなのか、悩み苦しみ答えがなかなか見つからない現実があるのだなぁと思いました。
そして、この本は、私に、母を捨てる勇気をくれました。
「母を手放そう、一度見捨てよう」
その勇気をくれました。
ウチのことはこんな感じです↓
(分岐する家族のことですので、オブラートに包み過ぎて何を書いてるかわからないと思いますが、本を読んで気持ちの整理がついていったことを書きたいので、書いてみます。)
認知症である母には、私のきょうだいとその家族がパラサイトしていました。
本人らには、その意識があるのかないのかは、グレーです。
高齢者介護の観点から見れば、正解はこう。
家族の問題から考えたら、正解はこう。
子供たちの教育事情を考えたら、正解はこう。
障害を抱えた子供を持つ家庭を助けることを考えたら、正解はこう。
定年間際の大人たちの心のアンバランスを考えたら、正解はこう。
各家庭には各家庭の事情があり、何が正しく、何が必要かなど、見方を変えれば全部正しいし、全部が間違ってることになります。
ウチは高齢者介護の問題だけではなく…
他にも家族人数分の諸問題があり、分岐した家族内で攻略できなかった問題が、母を飲み込んで、父や母の生活に侵食していました。そこに高齢者問題が混ざり合い、認知症が混ざり、混沌とした状態になっていました。
父と母の明日からのただの暮らしすらできない状態になっていたんです。
(長らく気づけなかったんです…私)
で、
金銭的問題
母の認知症という問題
がある中、
母は、父や私を罵倒しながら、一生懸命に自分がしたことを正当化するため、辻褄のあわない正論を繰り出そうとしながら、失敗を続けまして…やがて、父を残して家出をしました。
母が正当化しきらなければ、
付随する者全てが、ややこしい立場になる…という思いと、
母自身が父からの信頼を取り戻したい思いとで、がむしゃらに通らないいい訳をしていたように思います。
いろいろを背負って、母は認知症になりながら、うそをついたり、ぼけたフリをしたり、はたまたホントにぼけて、現実を凌いでいました。
が、当初の父と私は、認知症も裏事情も分からなくて…
とにかく母を正気に戻さなくては!と正面から意見をしたり、
めんどくさくなって放置(スルー)したり(好きにさせたり)
同居しながら、あの手この手で頑張ってみましたが、結果、母を振り向かせることはできず、家を出させてしまうことになりました。
母のためと思って重ねてきた現実が、
「コレかよ…」
父も私も自分たちを責める思いと
母やきょうだいを責める思いと
がこんがらがり…
「とうとう家を出してしまった…」と思いに責められ続けていた時に、この本に出会いました。
「一度、手放そう」そう思いました。
母を出してしまったことをずっとよかったのかどうか悩んでいたんです。
でも、父と私が手を離さなければ、あっちはあっちで手を離さないので、母の心と体はバラバラにちぎれていたと思うのです。
当時は、心の持っていきようが見つからずにいました。
が、この本が、その時の私の気持ちを支えてくれました。
母であっても、捨ててもいいのだと。
思いを一度断ち切ることで、見えてくるものがあるということを。
いろいろなことがガンジがらめになっている時は、最優先すべきことが見えなくなります。
見方を変えたら、
目線の高さを変えたら、
事情がわかれば、
どれも大切だったり、
どれもどうでもいいことだったりで
良かれと思ってやってきた事は、
そもそも良かったのか?
人道に基づいているのか?
人道ってなんだよ!
みたいな絡まったなんかしら
まず、そこから出ないと俯瞰できない。
一番目に繋いでる手を離さなければ…
そもそも絡まった世界からは出られない。
そんな思いにさせてくれました。
後日談的に、
私が落ち着きを取り戻して思ったことは、あの時、本当に母の手を離してよかったなと思っています。
なぜならば、母のもう片方を握りしめている私のきょうだいは、目の前から母親を失わずにすんだからです。
いろいろあって、そのきょうだいは、当時、父から実家への出入りを禁止されていました。
ずっと前から、きょうだいは父と母の世話を焼いたりしながら、孫を見てもらったり、お互い家族を助けあっていたように見えていました。
が、いろいろあって本当にいろいろあって、とうとう父の信用を失ってしまいました。
そこには、母のダメな優しさとか、認知症も混ざっていて、誰の何がダメだったとはいいがたいのですが…
何より、もともと他力本願、
幼少より依存性が高い…
それを、放置し、支援し続けた父母があかんと言えばそうなんです。
父が手を離し、
母までもを無理に取り上げたら…
きょうだいは、永遠に親に会えなくなっでいたかもしれません。
きょうだいの依存性を少しでも解消するには、、、
依存するネタを提供しないということが最優先であり、父はその舵を死に際にきることを決めたんです。きょうだいの本来の成長を止めてはいけないと。
母には、その強い決意が伝わったんではないかと思うのです。(美談にしているかもですが…今ならそう思ってあげられる感じです)
だから、認知症になってでも、私があの子に最後まで寄り添うんだ!と意思をもって、家を出たのかなぁと思ったりしています。
(ちょっと親バカならぬ娘バカですみません。血のもんです)
最後に
おおたわ先生のお母様との距離をとることとは…
それは、お母様の欲しい時に欲しいだけお薬を与えないということ。
与える環境を失くすということでした。
それはつまりは、お父様が開業医を辞めるということになります。
苦しい選択です。
欲しがる→与えない
ではなく
欲しがる→そもそもない (環境をつくる)
これが、どれほど辛く悲しい道か…
いやいや、ウチなんてまだまだだなぁ…と思いました。
とは言え、
欲しがる→与えない
というのは、あかんと思っても、与え続けてきた人たちにとっては難しい問題です。
そもそもない状況にできる場合と、できない場合がありますし。
そもそもの問題がどこにあるかという問題が、頭を回ります。
ウチの場合は…
父に任命された私は、母やきょうだいの妬みの対象になり、有る事無い事を言われました。それはまだいいとしても…
私の母やきょうだいは、主人にもひどいことを言いましたし、やがては親族の家にも乗り込み…コロナ禍に前相談もなくデイサービスに乗り込み、ケアマネージャーさんにも会社さんにも、本当に皆さんにご迷惑をおかけしました。。。
正直、私と父は疲れ切っていて、途方に暮れていました。
母を盾に暴走するきょうだいを止められないし、同伴し続ける母も止められないし。
内容が複雑すぎるけど、家族の問題なんで(またの機会に書けたらかきますが…)
周りも、話を聞くことしかできませんでした。し、それで仕方ないと思っていましたから、、、
本当に、その時、この本が目の前に来てくれて、呼吸することを思い出した気がします。
心のバランスを崩してしまうことは、
それは誰にでもあります。
相談できないことと、隠して頑張り続けるこが当たり前になってしまうことがあります。
恥ずかしいとか
ご迷惑をかけるとか
相談する資格なんかないとか
コンプレックスとか
見栄とか
世間体とか
でもねぇ…
ちょっと困った時に、問題と正面から向き合っていたら違った景色があったかもしれないなぁと思います。
母は、臭いモノには蓋をする人でしたので…(笑)
素直に「助けて」と言えない強がりなところがあって、だから見栄っ張りで。
でも、ちょっとズルくて賢いもんで、問題を表面的に解決できてしまう人でした。
そもそもそこが問題と言えば問題だったかなぁ…と、今は呑気に思います(笑)
今年のはじめに、父と親族と相談して、弁護士の先生のところへ行ってきました。
とてもいい先生との出会いで、私も父も本当にスッキリしました。
実は、先生には、お話を聞いていただいただけなんです。
「うん、法律的に、私に今できることは何もありませんけど、法律的に何の問題もおきてませんよ。あなた方の対応で大丈夫と思いますよ。こんなんですがいいですか?(笑)」
と言われました。
ですが、万事、気持ちがスッキリしたんです。
ここ7年、8年背負っていた重荷が、ガサっと取り除かれ、目の前の視界がクリアになったんです。
あー、早く相談すれば良かった…と、父、主人、親族と話しました。
この話は、またの機会に書きますが。
父は、心のバランスをちょっとずつ取り戻してきたんだと思います。
だから、脅威の復活劇を何度も見れているんだと思います。
今、母はどうしているかはよくわかりません。
ただ、きょうだいの伴侶さんは、きちんとしたお仕事をされている人なので、「変なことはできないだろう」と弁護士の先生はおっしゃっていました。私も父もそう思います。
父も私も、母のことはもう心配はしていません。いや、そう思うことにしました。
ハッキリと「あとをお願いね」と言って出た母なんで。いろんな決意を秘めて、残る人生をかけて、家を出たのですから、そこをうやむやにしては母に失礼です。(あ、母は母の年金の通帳をちゃんともって出ています)
今、
父にできることは、
母より長生きしてやることと思ってるんではないでしょうか。
私にできることは、
父のやりたい方法に付き合うことと、
できれば家族の皆が100%満足する結末はなくとも、、、薄く平たく、ちょっとずつ譲り合って、それぞれの暮らしに負担の少ない着地を見つけることと思っています。
あれ?
読書感想文じゃなくなってしまった…スミマセン。
noteを書く皆さんのように、
うまく母を語れません。
家族を優しく、厳しく、書けません。
だけど、ここまで読んでくださった方がいらしたら、、、ほんまにありがとうございます。
えっと、無理やり着地します。
おおたわ先生の本、救われました。
おおたわ先生の姿勢、大好きです。
2018年から、犯罪者を収容する矯正施設で受刑者への医療活動をされています。
すごいなーって、思います。
良ければ、本📕手に取ってみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
