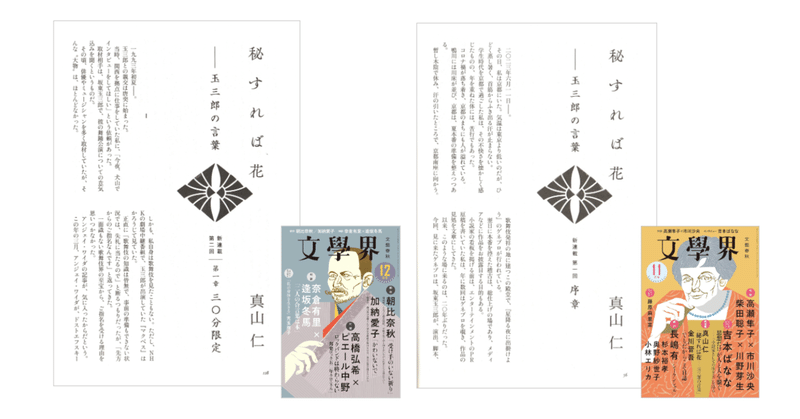
真山仁「秘すれば花――玉三郎の言葉/新連載第一回 序章」「第二回 三〇分限定」」(文學界)
☆mediopos3296 2023.11.26
小説家の真山仁は
坂東玉三郎と三十年の交友を持つ
その三十年のあいだに耳にした言葉から
坂東玉三郎の人と芸について伝えようとする
連載がはじまっている
交友のきっかけは一九九三年初夏
当時歌舞伎についての知識はまったくなく
事前の準備もできていなかったが
坂東玉三郎自身からの指名で
舞踏公演についてのインタビューを依頼される
ドストエフスキーの『白痴』に材を取った
アンジェイ・ワイダの映画『ナスターシャ』の上演に際しての
インタビュー記事が気に入ったからだという
マネージャーから三〇分厳守だといわれたが
玉三郎に「歌舞伎も玉三郎の舞台も観たことがない、
と正直に伝え、自分と同様の人に、
玉三郎の魅力を伝えたいと話した」ところ
「それは、楽しそうな取材だね。
ぜひ、そういう話をしましょう」ということで話が弾み
インタビューは一時間半にわたることになる
約一年後にまたインタビュー依頼が来る
有吉佐和子『ふるあめりかに袖はぬらさじ』上演のためのもの
移動の車中で関係者は運転手以外のほかにはいない
その三〇分ほどのあいだということだったが
結局その後もずっと話を続けることになる
そして帰りの車の中では今度は逆に
「フリーランスのライターは、大変でしょう。
なぜ、そんな職に?」
といった玉三郎からの「取材」が始まることになる
それから交友ははじまり
「以来、三〇年間、私は玉三郎の言葉を直に聞く幸運恵まれ」
「実に多くのことを、彼から学んだ。
そして、今も学び続けている」
この連載ではそれらについて
「様々なエピソードを交えつつ伝えたい」という
しかし玉三郎に
「敬愛する人物の生き様の片鱗を今の時代に刻んでおきたい」
「そろそろ玉三郎の哲学をまとめる時ではないかと尋ねると、
「自らを語るようなものを残したくない」と、言われ」
「快諾はされなかったし、
今でも「嬉しくない」と言われ続けている」なかでの連載である
そういえば玉三郎がじぶんそのものについて
語っているものはあまり目にしたことはない
ぼく自身は歌舞伎についても玉三郎についても
ほとんど無知でしかないのだが
はじまったばかりの連載記事からだけでも
玉三郎という人間の「秘」された「花」が
そこに垣間見えるような気がしている
現代はたしかな己を持ちながら
己を越えた真摯な探求を怠らないような
そんな稀有な人物を失いつつあるのではないか
この連載はその貴重な「秘」された「言葉」から
得難いなにかを得る機会となりそうだ
■真山仁「秘すれば花――玉三郎の言葉/新連載第一回 序章」
(文學界 2023年11月号)
■真山仁「秘すれば花――玉三郎の言葉/新連載第二回 三〇分限定」
(文學界 2023年12月号)
(「秘すれば花――玉三郎の言葉/新連載第一回 序章」より)
「二〇二三年六月一一日————。
(・・・)
歌舞伎座八章の地に建つこの殿堂(京都南座)で、『星降る夜に出かけよう』のゲネプロが行われている。
翌日に本番を控えた稽古は、総仕上げの場であり、メディアなどに作品をお披露目すう目的もある。
小説家の看板を掲げる前は、エンターテインメントのPR原稿を書いていた私は、年に数回はゲネプロを覗き、作品の見処を文章にしてきた。
以来、このような場に来るのは、二〇年ぶりだった。
今回、見に来たゲネプロは、坂東玉三郎が、演出、脚本、そして一部作詞まで務めた新作だ。
歌舞伎界の至宝と言われる玉三郎は、演出家や芸術監督として、これまで多くの名作を残している。
玉三郎の演出作品は、彼の「美意識」への飽くなき追求が通底し、観る人の心を奪うだけでなく、人生とは何かを考えてしまう強いメッセージを感じる。
久しぶりに演出を務める本作は、オリジナルで、初めて脚本も書いた。
これは、事件であり、観ないわけにはいかない。
ゲネプロの四日前も、私は京都で玉三郎と会った。
互いの近況を話しながら、新作の話になった。
「自分の好きな世界を一つにまとめて、お客様に観て頂ける機会を得られたので」
玉三郎は特別なことではないように言った。しかし、過去に玉三郎が脚本を手がけたことはない。
「脚本とクレジットには入っているけど、実際は、小説や戯曲の中から必要な台詞を抽出して、繋ぎ合わせただけだから」
異なる作品を繋いだだけだというが、それをオリジナル作品にまで仕上げるのは、相当に大変な作業だと、容易に想像できる。
題材となる三作品とは、サン=テグジュペリの『星の王子さま』と、ジョン・パトリック・シャンリィの『喜びの孤独な衝動』、『星降る夜に出かけよう』だ。ちなみにmシャンリィは映画『月の輝く夜に』の脚本でアカデミー脚本賞を受賞し、一躍世界に名が知られた作家だ。
(・・・)
三作品には、ある通底したテーマがある。尤も物語としては異なる点の方が多く、いったいこれをどうやって繋いでいくのだろうと興味が湧いた。」
「この三作品が流れるように繋がるとは、まるで予想していなかった。
しかも、次々と放たれるメッセージは、これまで、玉三郎は幾度となく口にしてきた人生観や美意識、矜持と重なる。
これは、紛れもなく玉三郎哲学の集大成だ————。」
「玉三郎の芸術観に大きな影響を与えた人物の一人である世阿弥の『花伝書』に記されているように、芸の真髄である「花」は、軽はずみに公表するようなものではなく、秘してこそ「花」となる。
だから、そろそろ玉三郎の哲学をまとめる時ではないかと尋ねると、「自らを語るようなものを残したくない」と、言われた。
それでも三〇年にわたり、彼と語り合い、その生き様を観てきた私は、伝えずにはいられない。
だから、こう請うた。
「敬愛する人物の生き様の片鱗を今の時代に刻んでおきたい」と。
快諾はされなかったし、今でも「嬉しくない」と言われ続けている。
しかし、私の中では、今こそ語る時なのだと、強く確信している。」
(「秘すれば花――玉三郎の言葉/新連載第二回 三〇分限定」より)
「一九九三年初夏————。
玉三郎との親交は唐突に始まった。
当時、関西を拠点に仕事をしていた私に、「今夜、犬山でインタビューをしてほしい」という依頼があった。
取材相手は、坂東玉三郎で、彼の舞踏公演についての意気込みを聞くというものだ。
その頃、俳優やミュージシャンを多く取材していたが、そんな〝大物〟は、ほとんどなかった。
しかも、私自身は歌舞伎を見たこともない。ただし、NHKの劇場中継番組で、玉三郎が出演していた『マクベス』はかろうじて見ていた。
正直に「歌舞伎の知識は皆無で、事前の準備もできない状況では、失礼に当たるので」と断るつもりだったが、「先方からのご指名なんです」と返ってきた。
一面識もない歌舞伎界の至宝から、ご指名を受ける理由を思いつかなかった。
アンジェイ・ワイダの記事が、気に入ったからだという。
この年の三月、アンジェイ・ワイダが、ドストエフスキーの『白痴』に材を取った『ナスターシャ』が、大坂・ギャラクシーホールで上演された。映画『地下水道』や『灰とダイヤモンド』、『鉄の男』などを代表作に持つ反体制派の巨匠、ワイダの野心作で、主人公のムイシュキン公爵tろ妖艶なヒロイン、ナスターシャの二役を、玉三郎が演じた。そのプロモーションで来阪したワイダに、私はインタビューしていた。
その時の取材では、「気難しい」と評判だったワイダから、何度か「良い質問だね」と褒められた。そして、別れ際には「本当に楽しかった」と握手まで求められて、恐縮したのを思い出した。
だとすれば、断るわけにはいかない。
(・・・)
マネージャーからは、「お疲れなので三〇分厳守でお願いします」と釘を刺されている。」
「玉三郎が現れた瞬間、部屋の中がパッと明るくなった。
名刺を差し出すと、玉三郎は覗き込むように、私の目を見つめてくる————胸の奥底まで見透かされているかと思うほどの不思議な磁力があった。
ほんの二、三秒だったはずだが、あの目の強さは、今もはっきりと思い出せる。
そして、歌舞伎も玉三郎の舞台も観たことがない、と正直に伝え、自分と同様の人に、玉三郎の魅力を伝えたいと話した。
「失礼な!」と叱られるのも覚悟したのだが、「それは、楽しそうな取材だね。ぜひ、そういう話をしましょう」と大乗り気の反応が返ってきた。
お手並み拝見ということなのだろうな、と思いながら、インタビューを始めた。
歌舞伎の舞台で江戸時代以前の世界を演じている人が、どのように現代社会と折り合っているのかに、興味があると伝えた。
「歌舞伎の世界に、ずっと没入しているわけではありません。私も、現代社会に生きているわけですから、それを忘れてはならないと思っています」
だから、歌舞伎座に通う日々の中で、街の様子や季節の移ろいを移動の車中から眺めたり、「新聞は、毎日時間を掛けて読みます」と。
歌舞伎のような伝統芸能では、日常生活を遮断して舞台を勤めているのではと、私は勝手に思い込んでいた。
どんなニュースが気になるのか、と尋ねると、「国内外の動きが分かるもの全て」と返ってきた。
(・・・)
「ファスト・フードをどう思う?」
いきなり話題が変わった。」
「玉三郎とはかけ離れた単語だったので、聞き間違えたのかと思った。確認すると、彼は、同じ疑問を繰り返した。
今やすっかり定着したお手軽料理の、いったい何が気にかかるのかと尋ねた。
「文化の問題です。あれは、日本の食文化を破壊している。特に子どもたちに人気があるようだけれど、子どもには、絶対食べさせたくない」
(・・・)
文化とは長い時間を掛けて徐々に形づくられ社会に浸透していく。したがって、社会環境が激変したとしてお、文化は簡単に変化しない、
それを無理やり変えようとすると、大きな歪みが生じる、
「目先があたし区手、他の思想で、人気だから子どもに与える。それが文化なんだろうか」
玉三郎には、その国独特の文化を理解し、守りたいという強い意志がある。
その延長線上にあるのが、彼の俳優としての佇まいではないだろうか。
彼はよく、「今を生きている者として舞台を勤める」と言う。逆に言えば、現代社会の中で、日本の伝統や文化をいかに守り、時に折り合いを考えるという意味だ。
話を聞いていく内に、彼の発想の源や、様々な事象についての考えを聞いてみたいと思った。
だが、そこで約束の三〇分が過ぎた。
時間なのでと、取材を終えようとした時、玉三郎が言った。
「どうして? あなたは時間がないの? もっと話しましょう」
それからさらに一時間、私たちは話を続けた。もはや取材者と対象者ではない。互いが考える日本の文化論を話しつづけた。」
「その日、別れ際に玉三郎から「また、ぜひ話をしましょう」と言われたが、私を含め、取材に立ち会った関係者らも、社交辞令としか考えていなかった。
ただ、あの濃密な一時間半の記憶のせいか、自分が風景や時代を見る時の目が変わった、ように思う。
犬山での取材から約一年後、再び玉三郎のインタビュー依頼が来た。今度は有吉佐和子の名作『ふるあめりかに袖はぬらさじ』上演のためのものだ。
取材場所は、大阪市のフェスティバルホール。映画化された『ナスターシャ』のトークショー付き上映会が行われるので、その後で「三〇分」と言われた。
イベント終了後、京都に行くので、取材は移動の車中で行ってほしいという。
取材には、担当者なりマネージャーなりが立ち会うのが常識だが、この時は、車中には他に同行者がいない。つまり、運転手以外は、関係者は誰もいない。
親しくもない無名のライターなど、信用していいのか、と思ったのだが、玉三郎が、前の取材を覚えていて、二人でいいと決めたらしい、
光栄なことだが、さすがに緊張もした。
(・・・)
三〇分なんてあっという間で、目的地が近づいてきたので、運転手に、その旨を伝えると、玉三郎に「この後も、予定が入っているの?」と尋ねられる。
何の予定も入っていない。
「一人だと退屈だから、京都駅まで付き合ってくれない?」
望むところだった。
録音を止めて、ノートも閉じて、雑談が始まる。
(・・・)
「玉三郎さんのムイシュキンは、本当に存在感がありました。玉三郎さんの、新しい一面を垣間見た気がしますし、女形とは思えなかった」と告げると、本人は嬉しそうに、私の感想を聞いてくれた、
そして現地での撮影の苦労を話してくれた。
ワルシャワは、寒くて慣れない場所だった・・・・・・と、
また、世界的な名監督であるワイダのこだわりとの衝突もあったという。
「言葉が通じないけれど、魂は通じることがある。アンジェイとは、そういう関係だった。だから、いくら作品作りで意見の衝突があっても、最後は分かり合える。それは、妥協とかではなく」
言葉より、魂か・・・・・・。」
「京都駅で降りるはずが、結局、玉三郎の目的地まで同乗し、帰りもそのまま車中で大阪まで戻ることんある。
帰りの車の中で、今度は、玉三郎からの「取材」が始まった。
「フリーランスのライターは、大変でしょう。なぜ、そんな職に?」
隠すほどのことではないので、私は正直に答えた。元は全国紙の記者だったが、そもそもが小説家志望で、記者はそのひとつのステップだったことも話した。
「小説家を目指す人に初めて会った」
なぜ小説家になりたいのか、どんな作品を書きたいのか、そして、そのためにどんなことをしているのか————と興味津々の質問が飛んできた。
私は、その問いに、熱意を込めて答えた。
(・・・)
包み隠さず、彼の問いに答えた。
それを受けながら思わず、この先もっと色んな話をうかがう機会を得たいと告げた。
「色々話したいね。じゃあ、一緒に山鹿に行かない?」
以来、三〇年間、私は玉三郎の言葉を直に聞く幸運恵まれている。
実に多くのことを、彼から学んだ。そして、今も学び続けている。
その多くは、私だけが聞くには惜しい「至言」ばかりだ。
それを、様々なエピソードを交えつつ伝えたいと思う。
その前に、理解しなければならないことがある。
いったい坂東玉三郎とは、何者なのか————」
○真山 仁(まやま じん)
・1962年7月4日 -
・日本の小説家。経済小説 『ハゲタカ』シリーズの著者として知られる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
