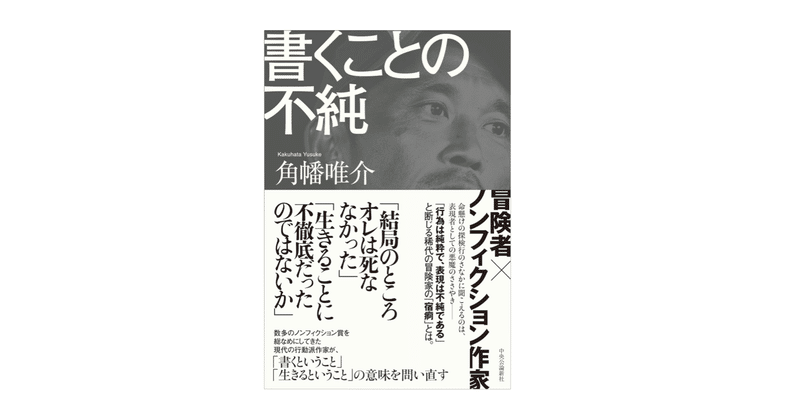
角幡唯介『書くことの不純』
☆mediopos3360 2024.1.29
今回は冒険家の角幡唯介の話なのだが
これは昨日のモンテーニュの話とも通底している
(mediopos3359(2024.1.28))
モンテーニュは
外的なさまざまなものを排しながら
「裸形」の「自分」を見いだすことで
「生きることの意味」を見いだそうとし
『エセー』を書き続けながら歩んでいったが
角幡唯介が本書『書くことの不純』で
問い直そうとしたのは
「なぜ書くのか」ということだ
モンテーニュは『エセー』を書いたが
角幡氏の「冒険」と同様に
表現し公に刊行したのはなぜだろう
モンテーニュは作家ではなく
その著作による収入が必要だったわけでもないだろう
それでも「表現」することを選んだ
角幡氏の著書のタイトルにあるとおり
そこには「書くことの不純」が
避けられなくあるのではないか
角幡氏は「基本的に行為(内在)は純粋で、
表現(関係)は不純だとの立場に立っている」
表現することそのものが不純だというのではなく
「表現は行為にたいして不純になる、ということ」
少なくとも冒険という
内在的な行為を書くということは
その行為に対する不純さを意識せざえるをえない
本書はその問いに対する自問自答である
角幡氏は若い女性記者から取材を受け
半ば雑談モードのなかで
「探検って社会の役に立っていないんじゃないか
っていわれませんか?」という質問を受け驚く
「社会の役に立たないことが、つまり見返りのないことが、
私がやっているような行為がなりたつための
最低条件なのだ、とさえ思っている」からである
冒険のような「自分にしか意味のない
極めて私的な行為をつづける」のは「個人の勝手」だ
しかし「問題はそれを書くこと」で
「書くことは他者に伝えること」であるがゆえに
「その時点で関係の視点にたった行為なので
必然的に社会性をともなう」ことになる
そこで問われるのが
「個人の好きでやっている無意味な行為を
社会にむけて書くとき、そこにいかなる理屈があるのか」
ということである
角幡氏はその「理屈」のひとつとして
「批評性」を挙げている
「冒険とは脱システムであり、
時代や社会の常識をゆさぶるのが使命」だからというが
いうまでもなく「理屈」としては不十分で
結局のところ
「喜んでくれる人たちのために書く。
書くとはたったそれだけのことなのだと、
最近はようやくそんな当たり前の考えができるようになった」
「内在的に生き、内在的に行為をし、内在的に表現する。
旅をして何かを感じ、心を揺り動かされ、
それを書くことで私は内部を外部に移しかえる。」
その記録を「一緒に喜んでくれる人がいただけで
私の旅は救われる。
だから私の行為を外に向かって発表する。」のだという
角幡氏にとっての純粋な行為である冒険は
みずからの内から迸る「生」の要請である
おそらくモンテーニュにとって
「裸形」の「自分」を見いだそうとする行為も
同様なものだったのではないだろうか
いうまでもなくその純粋な行為と
内的な論理からの要請を
「書く」ということで表現することとのあいだには
それなりの「距離」が生まれざるをえない
それを「不純」ということもできるが
その不純さを生きるのもまた冒険なのかもしれない
しかし「社会の役に立つかどうか」という
関係的な視点しか持てず
外側の価値観にしばられてしまえば
「自分の内部を根拠に生き方をつくりあげる」ことが
できなくなってしまう
政治も科学も医療も教育も
「社会の役に立つ」というキレイゴトの言葉で
実際のところ逆にどれほど人をスポイルしていることか
その意味でも「社会の役に立たないこと」を
「純粋」に行為することが
現代ではきわめて重要になっているといえる
■角幡唯介『書くことの不純』(中央公論新社 2024/1)
(「序 論 探検って社会の役に立ちますか?」より)
「夏のある日、私は鎌倉駅前のレンタルスペースで某紙の若い女性記者から取材を受けた。子供のころや若いときの経験がいかに今の自分につながったのかを聞き、それを今の子供たちに伝えて背中を押してあげるという教育面の記事の取材である。生い立ちや昔の思い出、大学探検部時代の活動を訊かれるがままに語り、二時間ほどたって、そろそろ取材も余談にシフトしはじめたころだ。その若い記者が急に質問の角度をかえた。
「ところであえて意地悪な訊き方をしますが、角幡さんの探検って社会の役に立っていないんじゃないかっていわれませんか?」
想定外の質問にぐっと言葉がつまった。(・・・)要するに、え、そんな感想をもつの?とびっくりしたのである。」
「なぜそこまで驚いたかというと、それは私の探検など頭の天辺から足の爪先まで、どこからどう見ても百パーセント、社会の役に立っていないことが明白だからである。むしろ社会の役に立たないことを全面に押し出している。はっきりいって、そこは前提なのだ。社会の役に立たないことが、つまり見返りのないことが、私がやっているような行為がなりたつための最低条件なのだ、とさえ思っている。
登山や冒険もふくめて、そういう無意味なことをなぜやるかというと。自分の内側からわきあがってくる抑えきれない思いがあるからやるのである。逆にいえば、それがなければできない。そしてその内側からわきあがる思いというのは、社会や時代の価値観とは別のところからたちのぼるものであり、それゆえその人にしか理解できない情動である。
だから登山や冒険の動機や目的は、社会や時代の価値観には決して還元できない個人的なものだし、それをやったらかといって社会の役に立つものでは、絶対にありえない。
(・・・)
もし登山や冒険に社会的意味が出てきてしまったら、その行為は生きることの個人的追求ではなく、社会的価値の追求という公的な行動に変質し、逆にとても胡散臭くなる。この山を登ったらみんなの役に立つから登る、という登山は、とても変だ。根本的なところでその登山のすべてを台無しにしている。」
「おそらく登山や冒険のように見返りのない行動がこの世界に存在することが、もっというとこの世界に存在することがゆるされることが、今の時代、とくに若い世代には理解できなくなっているのではないか。それぐらい、人はすべからく社会の役に立つべきだという公的価値観の力は肥大化し、この国をつつみこんでいるのではないか。」
「これは登山、冒険、探検にかぎった話ではない。同じように社会の役に立たない活動、営為というのは無数にある。それなのに、すべての人のいとなみい、社会の役に立つべきだという価値観が適用されると、それらの営みには居場所がなくなってしまう。
社会の役に立つべきだという圧力には、こうした、いわく言いがたい理不尽さがともなっている。」
*****
「外部の論理は本来、自分の外側から要請されるものだから。まったく関係がない、とまではいわないが、必ずしもしたがわなければならないものでもない。むしろ一人の人間の生き方として考えた場合、外部の論理に盲目的にしたがうのではなく、内からわきあがる思い、あるいは自己の良心にしたがって生きたほうが、自分の生の触れることができるはずだ。「社会の役に立て」と頭ごなしにいわれたら、ふざけるな、と心のなかで怒りつつ、「なぜそのようなことをする必要があるのですか」と霊性に反論するのがあるべき回答ともいえる。
ところが、今はそれがゆるされない社会になりつつある。少なくともやりにくい世の中になっている。
別に本心から社会の役に立ちたいと思っているわけではないが、風潮という外からの圧力があるから、仕方なく社会の役に立つことをしている。世の中の多くの人の行動基準はそのようなものだと憶測するが、だとするとこれは乃武のない外部、内側に支えるものがないのに外側だけ見栄えのいい外観でかためている、ということではないだろうか。」
「実際、世相をながめると、外側だけは美しい言葉で飾り立てているが、あきらかに乃武が存在しない空っぽな人間が満ち溢れている。」
「最近やたらと耳につく大人たちの感謝の言葉も同じようなおのだ。
競技のあとにインタビューをうけるスポーツ選手が口にする皆さまへの感謝や、ヒーローインタビューのお立ち台にたつプロ野球選手の感謝の言葉。理由はよくわからないが、彼らはまず感謝しなくてはならないことになっている。ファンへの感謝ならまだわかるが、世間や世相、関わりのない献身者に対する感謝に本当の内実があるのだろうか。」
*****
「私自身、これまでずっと内側からわきあがる衝動にしたがって生きてきたという思いがあった。
内在的な論理、それはたとえば、私のような者であれば、あの山に登ろうとか、あそこの人跡未踏の地を探検しよう、などというような、リスクを前提に何かことをおこすときに生じるある種の〈思いつき〉のなかに端的にあらわれる。
(・・・)
こうして私は、ひとつの経験がきっかけとなり次なる新しい〈思いつき〉が生まれ、それにぼみこまれて生きてゆく、ということをくりかえしてきた・
そのうえで思うのだが、これらの思いつきは、何もせずに机のうえでパッと頭に浮かんだだけの、本当に場当たり的な思いつきとは全然ちがう。つまり探検部に入り、ツアンポーに行き、北極に通いつめる、という具体的なプロセスが長々とあって、そのうえではじめて噴出する、いわば経験の結果生じる私固有の思いつきである。
(・・・)
内在的論理とはこのようなものだと私は思う。誰であれ、人は内在的に独自の決断をくだし、生き方の固有度を高めることで自分自身になってゆく。内在性がなく、外側の価値観だけにしたがい生きていくと、自分自身にはなれない。生き方の固有度は高まらず他人のコピーにしかなれないからである。
自分自身になるとは、言いかえれば自分の内部を根拠に生き方をつくりあげることだと理解できる。
(・・・)
それに対して、外側の価値観にしばられ、関係の視点から実人生をつくりあげてしまうと、他人に作ってもらった橇で旅をするときとおなじように、いつまでたっても価値観と生き方の距離を消すことはできないはずだ。そしてこの距離こそが生にまつわるあらゆる虚無感の正体だと思う。」
*****
「社会の役に立つべきという風潮が今、強まってきているとしたら、それは内在よりも関係重視の社会にかわりつつあるということだ。
今は関係偏重の時代である。生産性に寄与しないもの、公共的なものからははみだすもの、それらは社会の役に立たないという理屈でより低次なののとみられ、隅に追いやられ、忘却され、切断される。その関係の側からの圧力が、個々人の生き方におおいかぶさり、多くの人が関係に視点でしか生き方を決められなくなっている。ひと言でいえば、そっち方面の圧力がつよすぎる。バランスを欠いているのである。
今や内在の意味など誰も見向きもしないかのようだ。ただ、他人との関係ばかりに目がいき、自分が他人にどう映っているか、どのように思われるか、どのようなふるまいをすれば責任を追及されなくてすむか、どういえばその発言内容を咎められないか、いかなる行動をとれば他者との摩擦を少なくできるか、そうしたことばかりを気にして暮らしている。」
*****
「内在を突きつめると、かならず意味のある領域をこえて無意味な場所にたどりつくのだが、じつは純粋さというものはそこにしかない。純粋さはときに無気味でうす気味が悪かったりするが、しかし純粋さしかもちえない力というものは絶対にあり、その力が人に感動を与えたり。畏怖させたりする。
(・・・)
私にとって内在とは行為のことであり、関係とは書くこと、つまり表現である。
純粋な行為にとって書くことは不要なのか、否か。本書で考えたいのはこの問題だ。」
(「第一部 行為と表現/第一章 書くことの不純」より)
「書くことは不純であるという感覚は、書きはじめた時点で、すでに何となくあった。
行為は純粋で、表現は不純である————。
なぜこのような感覚が生じるのかはわからない。だが、この感覚は私一人のものではなく、ほとんどの人が同じことを感じるものらしい。」
「誤解されるとこまるので先にことわっておくが、私は書くために探検をしているわけではない。
(・・・)
だが、それも突きつめて考えれば、あやしいものだ。
たとえばこう訊かれるとする。
もし書く手段がなくなったら。それでもあなたは探検をするのか?
私は「する」と即答するだろう。実際、私がいまやっている探検や登山の多くは作品化するあてのまいものだ。書かないことが前提で、純粋に旅そのものが目的になっている。行為することが生きることそのものだ。
でもその一方で、そうした作品化するあてのない旅でも、私はきちんと日記をつけている。それは、この旅もやがて巡り巡ってどこかで書くことになるかもしれないと知っているからである。
だとしたら、やはり書くことも旅の目的の一部といえるのではないか?
(・・・)
はっきりしているのは、書くことが旅の目的ではない、と私が言いたがっているということである。それは行為に対して表現は不純だという考えた、私の意識のどこかにあるからだ。」
(「第一部 行為と表現/第二章 羽生の純粋と栗城の不純」より)
「書くこと、あるいは表現することは〈関係〉の視点からおこなわれることであり。どのように読まれるかという観点から逃れることはできない。読者のためではなく自分の書きたいことだけを書く、などと言いつくろったところで(私も以前はそういうことを言っていた)、それは詭弁にすぎない・どのように面白く書けるかと考えている時点で、それは読者の目で自分の行為を編集することにつながる。
でも行為はそういうものではなく、本来は〈内在〉から発動するものだ。経験によっておのずと生じる、これをやりたいという思いにしたがっておこなわれれば、その行為は生きることと一致し、おのれの生の瞬間に触れることができる。だから〈内在〉にしたがっれ生きることが〈よりよく生きる〉ための唯一の途だ。よりよく生きるとは、社会道徳や公益性から見た〈よりよく〉ではなく。新年をもって自分固有の生を生ききるという意味でも〈よりよく〉である。」
(「第一部 行為と表現/第三章 冒険芸術論」より)
「冒険というのは私的で内在的な行動であり、関係的な視点からおこなわれてしまうとおかしなことになる。最初から批評する意図があると、その冒険の立ち位置はかなりあやしい。しかし脱システムという本質上、冒険にはどうしても時代や社会の常識を外側からゆさぶるという性格がある。
私的行動である冒険に、もし社会に還元できる何かがあるとしたら。それはこの批評性しかない、というのが私の考えである。」
「芸術も冒険も社会通念に忖度して。勝手に自己規定して枠のなかにみずからを押しこめてしまえば、存在意義をうしなうだろう。あらゆる束縛や枠から飛びだして。飛びだした自分の姿を社会にさらし、「私は飛びだしたけど、その飛びだした私の姿を見て、飛びださなかったあなたは何を思う?」という挑発的な問いかけを発すること。そこに芸術や冒険の役割があるのはまちがいない。」
「自己の肉体と山をへだてる境界が消失し、山と調和うる。このように登ったとき。はじめて登山行為のなかに山そのものが現出するであろう。」
(「あとがき あらためて書くことについて」より)
「本書は基本的に行為(内在)は純粋で、表現(関係)は不純だとの立場に立っている。
こう書くと、では小説家や音楽家や画家は皆、不純なのか、という話になりかねない。この誤解を排するためにもう少し正確にいえば、表現は行為にたいして不純になる、ということである。あくまで本書で問いたいのは、表現それ自体というより、行為に対する表現の立ち位置だ。
ともかく私にとって書くことは不純になりうる営為である。」
「前提として行為者である私は、まず行為を純粋なものとして確立させたい。これまで一貫して主張したように、純粋なものは内在的なプロセスをたどらなければならない。最初から社会の役に立つことをめざしたり、世界最高峰だからという理由でエベレストを登るのは、行為の立脚点が関係の視点にたっているので純粋ではない。関係的視点が前提の不純な行為にはその人の人生を支えるだけの強度がない。だから、まずは徹底的に内在的に行為をつくりあげてゆく。これが必要だ。
内在的なプロセスをたどることに成功すれば、その行為はやがて、社会や時代の目から見て無意味な領域に突入するだろう。
(・・・)
このような無意味さは得体のしれなさ、無気味さにつながる。なぜなら意味のないことをひたすらこつこつ続ける人間は、周囲の目から見たらわけがわからず、気持ち悪いからだ。だがこの無気味さこそが、人にふりかえらせる力をもつのも事実だ。意味があることをやるのは、ある意味当たり前だ。常識的な行為に迫力はともなわない。独りよがりで無気味で得体がしれないからこそ、そこまでやるのか・・・・・・と人の心胆を寒からしめる力をもつのである。逆にいえば、そもそもそこまで行かないと書く意味がない、ということでもある。」
「自分にしか意味のない極めて私的な行為をつづける。それは個人の勝手である。問題はそれを書くことだ。書くことは他者に伝えることで、その時点で関係の視点にたった行為なので必然的に社会性をともなう。個人の好きでやっている無意味な行為を社会にむけて書くとき、そこにいかなる理屈があるのか。どのような論理で、私のひとりよがりな行為は意味的世界である社会に接続されるのか。彼女が発した質問の核心はここにあった。
(・・・)
一番わかりやすいのは、本書でも若干ふれた冒険の批評性だ。
(・・・)
冒険とは脱システムであり、時代や社会の常識をゆさぶるのが使命なので、私は本を書くときかならずこの批評的視点を意識して執筆する。
でも、本当にそうなのか? との疑問もある・そんな批評性がどうのこうのとわかりやすい理由で私は本を書いているのか? その思いはもっと深いところに根ざしているのではないか? そんな思いもあるのだ。
(・・・)
内在的に生き、内在的に行為をし、内在的に表現する。旅をして何かを感じ、心を揺り動かされ、それを書くことで私は内部を外部に移しかえる。この記録は私的なものなので誰にとっても面白いものではないが、なかには面白いと思ってくれる人がいる。かりにそれが十人しかいなくても、一緒に喜んでくれる人がいただけで私の旅は救われる。だから私の行為を外に向かって発表する。
喜んでくれる人たちのために書く。書くとはたったそれだけのことなのだと、最近はようやくそんな当たり前の考えができるようになった。」
【目次】
序 論 探検って社会の役に立ちますか?
第一部 行為と表現
第一章 書くことの不純
第二章 羽生の純粋と栗城の不純
第三章 冒険芸術論
第二部 三島由紀夫の行為論
第四章 届かないものについて
第五章 世界を変えるのは認識か行為か
第六章 実在の精髄
第七章 年齢と永遠の美
あとがき あらためて書くことについて
□角幡唯介
1976年北海道生まれ。作家、探検家、極地旅行家。早稲田大学政治経済学部卒業。大学在学中は探検部に所属。2010年に上梓した『空白の五マイル』(集英社)で開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞、梅棹忠夫・山と探検文学賞を受賞。12年『雪男は向こうからやって来た』(集英社)で新田次郎文学賞、13年『アグルーカの行方』(集英社)で講談社ノンフィクション賞、15年『探検家の日々本本』(幻冬舎)で毎日出版文化賞書評賞、18年には『極夜行』(文藝春秋)で本屋大賞2018年ノンフィクション本大賞、大佛次郎賞を受賞。著書はほかに『漂流』(新潮社)、『極夜行前』(文藝春秋)、『探検家とペネロペちゃん』(幻冬舎)など多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
