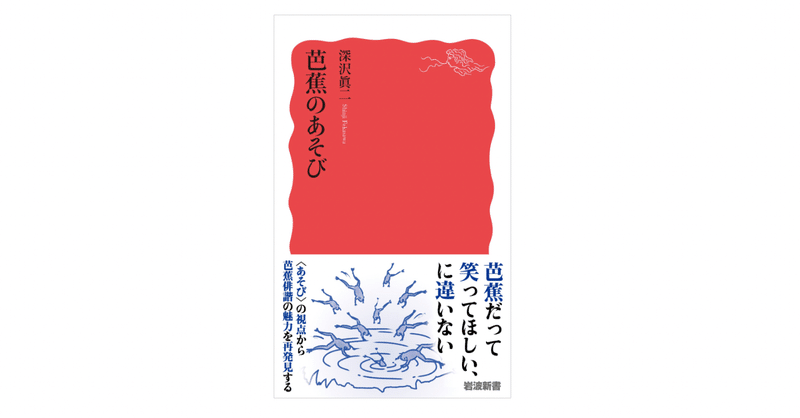
深沢 眞二『芭蕉のあそび』
☆mediopos2949 2022.12.14
芭蕉は俳諧師であった
俳諧師は「しゃれ」「もじり」「なりきり」
といった技法を使った〈あそび〉で
人々に笑いをもたらした
芭蕉は蕉風を確立した「俳聖」とされ
俳諧がほんらいもっている
「あそび」「笑い」のイメージは希薄である
そこで「芭蕉だって笑ってほしい」
というのが本書の呼びかけである
とはいえ難しいのは
芭蕉の句の背景にあった
当時「通じて当然」と思っていた「古典」の世界など
現代の私たちが芭蕉の句を鑑賞する際には
「芭蕉の時代の「文化の基盤」」を知る必要があることだ
とはいうものの時代を隔てた文化遺産を
現代において受容する際にはそうした手間は欠かせない
しかもそれは文芸の世界だけではなく
宗教・思想・哲学・政治・経済などにおいても同様である
そしてそれらを受容するときに
特定の視点だけに偏ってしまうことで
見えなくなってしまうものがある
とくに「あそび」や「わらい」といった要素は
「真面目」が好きな人間にとっては見過ごされやすい
ときには「笑い」が禁じられることさえあったりする
映画にもなったウンベルト・エーコの
『薔薇の名前』が思い出される
アリストテレスの『詩学』の第一部は「悲劇論」で
第二部は「喜劇論」だった
そう推定されているものの残ってはいない
その残っていない「笑い」に関わるページに
毒が塗られていたため
それをめくった者が舌を黒くして死ぬ…
その真実を見抜かれた犯人は『詩学』を火に投じ
その火によって僧院がすべて焼き尽くされる
という物語である
どんなに高尚に見えるもののなかにも
その根底には「あそび」や「笑い」があるはずなのだが
高尚=笑ってはならない
という固定観念のもとに生きる者にとっては
それらは危険なものと見えるようだ
教育や政治の世界ではとくにその傾向が強く見られる
もっとも「あそび」や「笑い」は
下世話な世界とも深く関わっているところが多分にあり
すべてが肯定されるものでもないだろうが
(それは「真面目」な世界でも同様である)
それらが意識的なかたちで
創造的に顕れることを忘れてしまったとき
私たちは生のなかで窒息してしまいかねない
この生が
聖なる笑いとあそびに満ちた
世界となりますように
■深沢 眞二『芭蕉のあそび』
(岩波新書 岩波書店 2022/11)
(「序章 いまこそ「芭蕉へ帰れ」より)
「俳諧というジャンルの史上最大の作者は芭蕉である。私は、芭蕉を研究対象とするようになって約三十年経つが、芭蕉は硬い人だったろうとつくづく思う。それでも芭蕉は今なお俳諧の世界の中心にいる。そこには、芭蕉自身の力によって芭蕉以降の俳諧を比較的硬いまじめな方向に軌道修正させたという事情がある。だが、そのせいで、芭蕉が人々に笑ってもらろうと思って詠んだはずの句が、現代人にはまじめにしか受け止められていないというねじれが生じているように思う。
芭蕉の、とくに若い頃の俳諧作品を、〈笑い〉を意識して読み直せば、そこからは「しゃれ」や「もじり」や「なりきり」や「なぞ」、それに謡曲をはじめとする先行文芸のパロディを拾い集めることができる。芭蕉は言葉や先行文芸を用いたさまざまな〈あそび〉によって、人にウケる冗談を言う技を身に付けていた作者であった。ところが、芭蕉以降の硬めの俳諧とそこから展開した近現代ハイクのフィルターがかって、芭蕉の〈あそび〉が見えにくくなってしまった。芭蕉以降の俳諧文学史が、対面授業におけるマスクとなったのである。
芭蕉は俳諧師である。そう自認し、周りもそう見ていた。「俳諧」という熟語は「たわむれ、おどけ、滑稽、諧謔」といった意味である。つまり、言葉などを介して人を笑わせようとする態度である。だからその意味通りに受け止めれば、今日の落語や漫才の師匠のように、人を笑わせることの先生ということになる。それもあながち誤りではないのだが、しかし、日本における「俳諧」の語には特定の文芸のジャンル名として使われてきた歴史があって、「芭蕉は俳諧師だ」とは「芭蕉は、「俳諧」という文芸の先生だ」ということを理解するのが普通である。」
「芭蕉は俳諧師であった。俳諧師の本文は、人々を笑わせ、人々の気分をほぐすことにある。芭蕉の俳諧作品を読むに当たり、彼が意図した笑いの所在を確認しないでは、「おどけ・たわむれ」であるはずの「俳諧」の範疇から逸れた解釈になってしまうのではないか。」
(「第一章 「しゃれ」/掛詞・付合語のあそび」より)
「日本の文学史の上で「しゃれ」はことばあそびの王道である。古典の授業で和歌の技巧として学ぶ掛詞だて本質的には同じだ。」
「近現代の注釈は象徴性や思想性を重視し、対象に対する芭蕉の真率な態度を読み取ることに熱心であって、「しゃれ」の仕掛けを見ようとしてこなかったと言えるだろう。「水とりや」の句しかり、「しばの戸に」の句しかり、そして「若葉して」の句しかり。今日、「しゃれ」はダジャレとかオヤジギャクと呼ばれくだらないものとして蔑まれている感がある。だが、芭蕉の当時に「しゃれ」は俳諧の基礎であった。芭蕉発句の「しゃれ」に気付かず通り過ぎることは俳諧作品の過半を見ないことであり、ひいては芭蕉という俳諧師を見誤ることになるのではないか。
あえていえば、それは近現代の俳句が「笑い」を遠ざけて、実景実情の写生を通じ新卒な境地を読もうとしてきたからにほかなるまい。現代俳句の評価軸で芭蕉を解釈してきた弊を、そろそろ脱すべきである。
芭蕉だって笑ってほしい、に違いない。」
※「水とりや」の句:水とりや氷の僧の沓の音(二重の文脈)
※「しばの戸に」の句:しばの戸にちやをこの葉かくあらし哉(たった一字の効果的掛詞)
※「若葉して」の句:若葉して御めの雫ぬぐわばや(「抜け」の技法)
(「第二章 パロディ/古典の世界にあそぶ」より)
「遠い過去の作者が「通じて当然」と思っていた元ネタを、私たちは知らずにいるか、部分的にしか理解していないかもしれないのである。私たちが三百数十年前の芭蕉の発句に向き合う際にも、そうした状況を想定することが必要になる。芭蕉が古典文学や世間周知の書物に基づいて発想した発句でありながら、現代の私たちとそれらの距離が遠いために、その典拠が見えにくくなっている句なのではないか、と。」
※「ゆふがほに米搗休む哀哉」/『源氏物語』と『枕草子』
※「たこつぼやはかなき夢を夏の月」/『源氏物語』と『平家物語』
※「初雪に兎の皮の髭つくれ」/『徒然草』の注釈を通じて
(「第三章 「もじり」から「なりきり」へ/謡曲であそぶ」より)
「芭蕉の若い頃から最晩年に至るまで、謡曲を利用した発句は枚挙にいとまがない。」
※「から崎の松は花より朧にて」/「鉢木」のもじり
※「木のもとにしるも膾も桜かな」/「西行桜」のやつし
※「おもしろうてやがて悲しき鵜舟哉」/「鵜飼」への没入
(「第四章 「なぞ」/頭をひねらせる遊び」より)
「芭蕉もけっこうな数の〈なぞ〉の発句を詠んでいる。」
※「元日やおもへばさびし秋の暮」/元日にどうして秋の暮?
※「ほとゝぎす正月は梅の花咲り」/梅の花にホトトギス?
※「誰やらが形に似たり今朝の春」/「誰やら」って誰のことやら?
(「終章 「芭蕉」の未来」より)
「「古池や」の発句」は「〈なぞ〉の句でもありパロディ句でもあった」
「本書は、序章で述べたように、
「芭蕉は俳諧師であり、彼の発句は笑いを目指して言葉で遊んでいる。現代の芭蕉の読まれ方はまじめに過ぎる。芭蕉の仕掛けた〈あそび〉を見直して、芭蕉をもっと笑って読もう」
という姿勢をベースにしている。芭蕉を「わび」や「さび」の詩人としてばかり読むのは、偏っている。私なりに言い換えるなら「わび」は欠落感の美学、「さび」は経年感の美学だと思う。そうした美学的なテーマからさらに老荘思想や禅の思想に踏み込むなどして「哲学する芭蕉」だけを探求するというのは、そうした探求の方向が誤りだというわけではないのだが、芭蕉にとってみれば不本意なことではないだろうか。
そしていま、終章を書く段になって、右に述べた基本的姿勢に、
「芭蕉の〈あそび〉を理解するためには、和歌の伝統の中で培われてきた技法や、謡曲を含む古典の知識など、当時の人々に理解され共有されていた「文化の基盤」というべきものごとを知らなければならない。それを知ってこそ芭蕉の俳諧を笑って読むことができるだろう」
と付け加えたいと思うものである。序章の題に掲げた「芭蕉に帰れ」を、「芭蕉の〈あそび〉を見直せ」ということに加えて、「芭蕉の時代の「文化の基盤」に立ち帰って芭蕉を読め」の謂いととらえてほしい。その方向に、私たちの貴重な文化的財産としての「芭蕉」が、ありありと立ち顕れる未来がある。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
