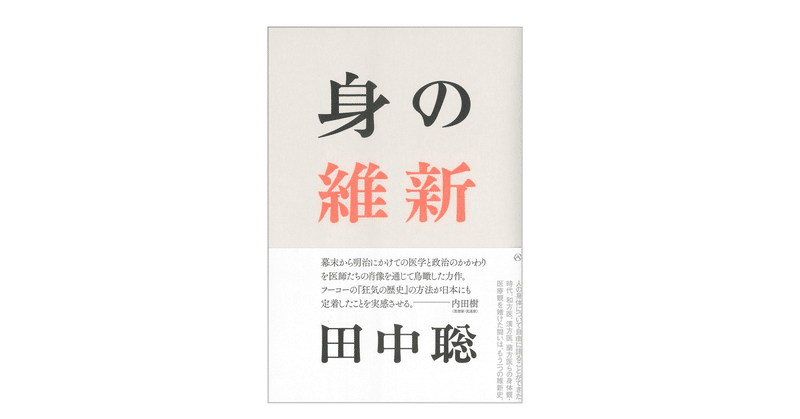
田中聡『身の維新』
☆mediopos3348 2024.1.17
「身の維新」とは
幕末から明治にかけ
医学と政治が深く関わりながら
多様な「身」のとらえ方が否定され
「一つの体」だけを事実だとするようになった
現代につながるようなエポックである
本書において「身体」や「人体」ではなく
「身」と表現されているのは
「それが「身を賭けて」や「身の上」と言うように
生命、人生、境遇までもあわせた全体性をもつ語」
だからである
日本の医学についての歴史の多くは
江戸時代後期の蘭方医学の歩みにおける西洋医学化を
「医学の曙」として描かれているが
かつて幕末から明治にかけての時代
和方医・漢方医・蘭方医たちは
それぞれの身体観・医療観をかけて闘ってきた歴史がある
かつては現代において常識化されているような
「一つの体」だけが「身」とされていたのではない
そしてそれらは政治と深く関わりながら変遷してきた
「身の維新」が完了した後
「医師が向かいあうべき相手は国家となり、
人の身は国民の体」となり
「数えられ、測られる体」となったのである
その典型は徴兵検査だが
「健康増進の啓蒙は、生産性の高い、
社会に役立つ体であれと要求し」
果ては現代における感染症対策のように
「病む体に社会的責任を突きつけ」さえするようになっている
「近代国民国家の基礎は国民の体にある」ということから
国民はそのための自覚が要求されるようになり
そのための「総力戦体制を支えるために厚生省が創設され」た
その趣旨を考えれば現在の厚生労働省のような
理解に苦しむほどの姿勢が理解されるようになる
その目的は国民の健康を守ることにあるのではなく
国民の「身」を一元管理することにあるのである
「医療や保健のシステムは国民を管理するのに
とても都合がいい」
「今は、巨大化した医薬産業の経済的な動機が
このシステムを動かしている」
そうしたシステムの内部にいる医師たちは
患者に向かいあうことによる治療ではなく
「システムの要求にしたがった治療」を余儀なくされる
そうしたほとんど自動機械のような医療システムが可能なのは
「体というものが原則として同じ構造体とされているから」である
そうでなければ「管理」することはむずかしくなる
養老孟司は現代の医者の多くは人に対しているのではなく
PCに表示されたデータに対しているという意味のことを語るが
「数えられ、測られる体」として一元化された「身」が
そのひとの「身」と化しているのである
そしてその身体観は「身の維新」の結果として
国家からメディアそして教育機関等を挙げての啓蒙によって
国民のすみずみにまで浸透している
言葉を換えていえば「洗脳」されてしまっている
シュタイナーの神秘学では
人間の身体は「肉体」「生命体(エーテル体)」
「アストラル体」「自我」から構成されているとされるが
「身の維新」による「身」はそのなかの「肉体」を
国家管理のもとにおけるシステム下の存在とするものである
身体は神秘学における上記のような身体だけではない
さまざまなレベルにおける「身」が存在し
それらが関係しあってひとの身体をつくりあげているのだが
いまや身体はじぶんの「肉体」であることさえも
医師や医師のシステムを支えている医療によって「評価」され
その「評価のために測られた数値」を
「体」だとするような刷り込みが行われている
その「数値」を計測するための機械が絶対化され
それによって測られる「数値」への信仰から
その「数値に誰もが一喜一憂するように」さえなっている
現代においては新たな「身の維新」が
必要とされているのだといえるが
果たして現在の信仰から自由になり得るだろうか
■田中聡『身の維新』(亜紀書房 2023/11)
*帯に記載されている本書の紹介文
「人の身体について自由に語ることができた時代。
和方医、漢方医、蘭方医らの身体観・医療観を賭けた闘いは、もう一つの維新史。」
*カバーのそでに記載されている本書の紹介文
「「古医道」を確立した権田直助は、倒幕の志士となり、岩倉具視のスパイとなった。
浅田宗伯はのちの大正天皇を救ったカリスマ漢方医。明治期も町の人々を無料で治療し続けた。
幕臣・蘭学医・松本良順は、戊辰戦争で負傷者を治療。軍医という概念をはじめて持った人。
西洋医・相良知安は、新政府でドイツ医学を採用させた立役者。最後は易者として貧民街に生きた。
幕末の動乱のなか、医師たちはその時々の情勢、自らの信じるもののために闘った 〉
[幕府側=漢方][新政府=西洋医学]──そのような単純な対立では語れない。
幕末の和方医、漢方医、蘭方医の群像を描く骨太の歴史ノンフィクション。」
*****
(「序 医師たちの幕末維新」より)
「幕末の動乱期に命をかけて闘った者たちのなかには、医師も少なからずいた。幕政改革のために奔走した者もいれば、倒幕をめざして暗躍した者、幕府の官医としての矜持をつらぬいた者もいた。
その闘いは、佐幕派と倒幕派というような二つの陣営に分かれただけの単純なものではなかった。たとえば同じ幕府医官という意識をもちながら、漢方医と西洋医とはひどく対立し、幕府陸軍の軍医だった松本良順などは戊辰戦争が始まるや、漢方を滅ぼす好機として利用している。医師たちは、それぞれの身体観や医療観をもち、その信ずるところをつらぬくための闘いを、幕末の騒乱に重ねていたのである。したがって維新の後にも、医療の新たなありかたをめぐる闘いはつづいた。
日本医学史の書を見ると、江戸時代後期の蘭方医の歩みの重きを置いて、西洋医学化を「医学の曙」として描いているものが多い。医学の西洋化をゴールとして、それまでの医学が価値づけられ、それ以降には西洋医学しか存在しなかったかのようにつづられがちだった。そのような現代人の価値観を前提にして書かれた歴史は、当時の人々が生きていた歴史からはずいぶん遠いものだる。いわゆる「勝者による歴史」に他ならない。」
*****
「本書は医学史ではない。医師の職にあった者たちが、その職はいかにあるべきか、診療の対象とすべきはいかなる身体化をめぐって争った足跡から、幕末維新史を見ようとしたものである。その群像を見れば、西洋医学への推移を、「漢方から洋方へ」と単純にはとらえられないことがわかるだろう。」
*****
「本書のキー・パーソンである権田直助(ごんだ・なおすけ)は、神代から伝えられながら古代に滅びた古医道の復古を主張し、幕末には草莽として暗躍、新政府の官吏になるや。大学(今の文科省に相当)に古医道を普及するための部局を設けさせた。にもかかわらず、医学史のうえではほとんど無視されてきた存在である。
しかし、天皇に臣民がしたがうという古代社会像を前提にした「王政復古」のスローガンが、中央集権的な近代国民国家の(日本的ん)理念を広める媒介となりえたように。医学の復古の主張も、医学の近代化に触媒のような働きをした可能性がある。そのことは、ドイツ医学を日本の医学の範とすべく尽力した相良治安(さがら・ちあん)が、直助ら平田派国学者の説く親和的な医史をたくみに利用して医事行政組織の創生をはかったという、紆余曲折する歴史の襞のうちにうかがうことができる。そして漢方を撲滅すべく奮闘した西洋医たちは、人を治療するだけの漢方医学がいかに国益のための用をなさないか、そして西洋医学が国益のための医学であるかを力説した。
身をめぐるさまざまな考えの医師たちの衝突は、「国民の体」が成り立つまでの葛藤でもあったのである。すなわち、身の維新史に他ならなかった。
ここで「身」とするのは、それが「身を賭けて」や「身の上」と言うように生命、人生、境遇までもあわせた全体性をもつ語だからである。また、古の聖人の教えは身に対するものだとした儒者の荻生徂徠の思想を、漢方医の吉益東洞(よします・とうどう)が医術で実践して医界に変革をもたらし、それが蘭方をふくむ新たな身のとらえ方の探求をうながしたという前史を踏まえてもいる。その多様な身のとらえ方を否定して一つの体だけを事実としたのが、身の維新だった。」
*****
(「第三章 維新後の医師の闘い」より)
「こうして身の維新は完了した。医師が向かいあうべき相手は国家となり、人の身は国民の体となった。数えられ、測られる体となった。
医師だけでなく、学校教育や啓蒙活動などによって近代的な身体観は常識となり、誰もがみずからを国民の体として律するようになる。たとえば感染症対策に重点を置いた衛生啓蒙は、病む体に社会的責任を突きつけた。健康増進の啓蒙は、生産性の高い、社会に役立つ体であれと要求した。人も国も生存競争を戦っているとされ、体はそのための道具として評価された。徴兵検査はその最たるものだ。体を評価するのは医師だが、やがて評価のために測られた数値に誰もが一喜一憂するようになる。
近代国民国家の基礎は国民の体にある。だから近代化する以上は、人々に国民としての自覚が要求されるのは当然だった。医学はそのために大いに役立ったわけである。総力戦体制を支えるために厚生省が創設されたように。医療や保健のシステムは国民を管理するのにとても都合がいいものだった。
しかし、一人ひとりに向かいあうべき治療と、行政による国民管理とが、同じシステムをなす必要は必ずしもなかったはずだ。それを一体化させたのは、石黒忠悳の主張にあったように、医学を統治の道具にするためであり、松本良順や相良治安が望んだように、医師の社会的ステータスを高めるためだった。今は、巨大化した医薬産業の経済的な動機がこのシステムを動かしている。その内部にいる医師は、患者に向かいあうことから見いだした治療をおこなうことはできず、システムの要求にしたがった治療をおこなわざるをえない。むろん、そのような仕組みが可能なのは、体というものが原則として同じ構造体とされているからである。
つまり身の維新からの結果でもある。このシステムはグローバルに形成されてきたものだから、維新の過程だけで問い直せるものではないだろう。だが、それがこの国ではいかなる動機や経緯で始まったかを知ることは、違う道もありえたし、今もありうると思わせてくれる。まずは。自分の体とは思わず、身としての自分を思ってみるところから、なにかしら新たな方向も見えてくるのではなかろうか。」
*****
(「あとがき」より)
「漢方学はもちろん滅びてしまったわけではない。ナショナリズムの高揚などの時流にも後押しされて、徐々に復興していった。今日では、補助的な位置づけではあれ、漢方治療を取り入れている病院も少なくない。
それは漢方が近代医学の身体観と折り合いをつけたということでもある。浅田宗伯は漢方と洋方との折衷派絶対に不可能だと断じていたという。そのことも漢方医のための医師免許試験を求めつづけた理由だっただろう。ならば頑固な宗伯のことだから、現状を見ても、漢方は復興などしておらぬと主張するかもしれない。」
「医療と行政の一体化が深まっている現代では。パンデミックが起こるや、一元的に国民の体を律しようとする強力な圧力が発動するが、一方で政府が空洞化しているために政策の矛盾あかりが目立つという事態が、この数年つづいた。もはや国民の体という常識が変わるしかない時代を迎えているのだろう。変わるのはいいが、今の時流では生命工学的な発想をベースにしたものになる可能性が高い。そうなれば身の消滅である。」
【目次】
序──医師たちの幕末維新
第一章・国を治す戦へ
一.古の医道を求めて
二.すべての医薬は皇国から
三.活きている身の理
第二章・病める国の医師の憂国
一.医師が国を治すということ
二.治療としての倒幕
三.幕府医官の漢蘭対決
四.薩邸浪士隊、西へ
五.戦のなかの医師たち
第三章 維新後の医師の闘い
一.追われゆく医師たち
二.古医道から国語学へ
三.漢方医の生存闘争
あとがき
参考文献
○田中 聡(たなか・さとし)
1962年富山県生まれ。富山大学人文学部卒業。同大学文学専攻科修了。「歴史と身体」についての関心を中心としつつ、様々な角度からのノンフィクションを著している。
著書に、『健康法と癒しの社会史』(青弓社)『陰謀論の正体! 』(幻冬舎新書)『明治維新の「噓」を見破るブックガイド』(河出書房新社)、『電気は誰のものか』(晶文社)、『電源防衛戦争』(亜紀書房)など多数がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
