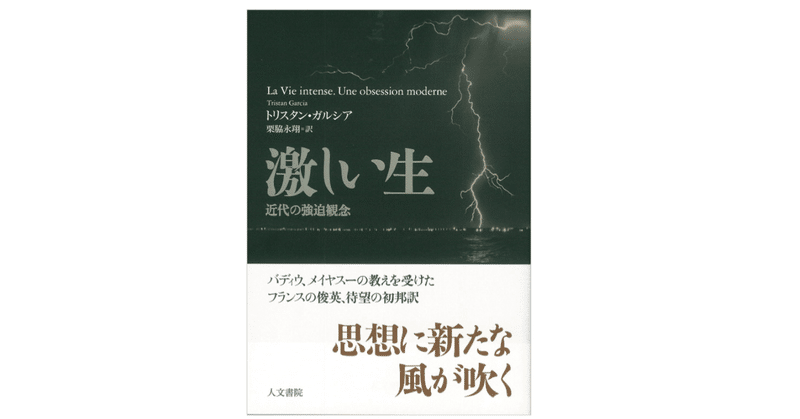
トリスタン・ガルシア『激しい生/近代の強迫観念』
☆mediopos2625 2022.1.23
トリスタン・ガルシアは著書『激しい生』で
近代の人間の生は「強さ=激しさ」に取り憑かれ
強迫観念のように刺激を求め続けていると論じている
現代の私たちは単調で平凡な生から脱するために
「スポーツのパフォーマンス、ドラッグ、アルコール、
賭け事、誘惑、愛、オーガズム、物理的な快楽、
ないしは苦痛、芸術作品の鑑賞、ないしは創造、
科学的探求、狂信、ないしは熱狂的なアンガジュマン」等
によって生の「強さ=激しさ」を求め続けてやまないが
そんな生を求める近代人の人間像とは異なり
「強さ=激しさの消滅のなかでの和らぎ
(霊感、涅槃、精神の平静)を認め」
「実存の至上の価値として至高の状態
(死後の生、輪廻、栄光、永遠性)による超克」を求める
別の人間像を求める文明も存在していた
そしてそのふたつを
「感じるもの」と「考えるもの」として
そのふたつの人間像が対置されているが
著書はその「倫理的な結論」として
前者か後者かという答えを導こうとしているわけではない
近代的な生を否定しているのでも肯定しているのでもない
そのふたつの相容れなさを確認しながら
「差異を保存すること」を意図している
「より強く=激しく生きるように生きるべきである」でもなく
「真理や救済、あるいは絶対的なものを知る仕方で
生きるべきである」でもなく
「生きる有機体であるという感情を失うことがないように
生きるべきである」と結論づけている
結論だけをみれば至極単純であり
あえて一冊を費やすテーマでもなさそうだが
読みながら感じたのは西欧のキリスト教が
グノーシスに対して危機感を抱いた感覚が
背景に強くあるのではないかということだ
キリスト教は地上及びその生を否定する
グノーシス的なものに対して
常に異端の匂いをかぎとってきた
その意味では本書はきわめて
キリスト教的であるともいえる
とはいえ
二項それぞれの差異をそのままにとらえながら
生きることが「要請」されているのは結果的に
二項対立的なものから離れてはいないように感じる
そのために本書の論述はある種の叫びのようでもある
しかしそのそれぞれが「差異」と同時に
その深みにおいて交差し
むすばれていくであろうような視点も必要ではないだろうか
たとえば禅が決して地上生を否定することなく
むしろ生のなかでの生そのものとしての超越的なものを
いわば「矛盾的自己同一」として求めてもいたように
■トリスタン・ガルシア(栗脇永翔訳)
『激しい生/近代の強迫観念』
(人文書院 2021/9)
「私たちには、絶え間なく、強さ=激しさ[intensité]が約束されています。私たちは生まれ、生を正当化する強い感覚の探求に曝されながら成長します。スポーツのパフォーマンス、ドラッグ、アルコール、賭け事、誘惑、愛、オーガズム、物理的な快楽、ないしは苦痛、芸術作品の鑑賞、ないしは創造、科学的探求、狂信、ないしは熱狂的なアンガジュマン、等々によってもたらされるあの即座の興奮状態は、単調さから、自動性から、同じことをどもることから、実存的平凡さから、私たちを目覚めさせてくれるのです。なぜなら、絶えず、快く居座る人間が生の活力が失われることを恐れているのですから。かつてはこの無感覚こそが、無為で満ち足りた至高者の、絶望的なまでに気晴らしを探し求めるものぐさな王たちの、ネロンの、カリギュラの、あるいは「カプアの歓喜」と呼ばれるもののうちでまどろむ征服者たちの強迫観念でした。上位の人間を脅かしていた逆説は、勝利をおさめながら、すべての欲望を満たしながら、すべての目標に達しながら、自身の内で実存的な緊張や神経の力強さが緩むのを感じ、生きるものにその実存の強さ=激しさを肯定的に評価することを可能にする、あの定義し難い感覚を失っていたことでした。
西洋の経済的な発展に応じて、個々人が存分に食べられるようになり、自身を保護する住居を所有するようになり、楽しむ時間を見つけるようになるにつれて、征服者の恐れは民主化され、その欲求がますます満足させられることに苛立つようになる近代的な個々人に引き継がれていったのです。」
「小説や映画、歌はこの二世紀以来、ほとんど同じことを語っています。「生きよ!何を生きようとも。」「愛せ!何を愛そうとも。」しかしとりわけ、「できる限り多く生き、愛せ!」−−−−なぜならつまるところ、この生の強さ=激しさ以外の何ものも重要ではないでしょうから。
ところで、私たちに明らかに思われることは、私たちが、しかし、別のタイプの人間像とは違うことを語っているということです。すなわち、実存の至上の価値として至高の状態(死後の生、輪廻、栄光、永遠性)による超克を認め、あるいは生の代わりやすい強さ=激しさの消滅のなかでの和らぎ(霊感、涅槃、精神の平静)を認めるような人間像とは別のことを語っているのです。私たちは、実存の最高の意味としての絶対性や超越の観想や期待からは逸脱したタイプの人間性に属し、支配的な倫理が、生の原理としての存在の絶えざる膨張に存するようなひとつの文明を採用していたように思われるのです。」
「近代の精神に馴染んだこうした考えは、私たちがそれを切り離して考える外側から見つめてみると、すぐに、興味をそそるものになります。古代の教養人、中世の精神、漢王朝で生きた人間、ベーダ文明のブラフマン、彼らは私たちがそうするように、(美学的、道徳的、政治的なものに関わる)彼らのあらゆる価値をこの強化=激化に従わせていたでしょうか? 私たちが望むことができる最良のものは、私たちが最も美、最も真と思うものは、私たちが信じるものは、すでにあるものの強化=激化なのです。世界の激化=強化、私たちの生の強化=激化。これこそが近代の偉大なる考えなのです。確実なことは、この強さ=激しさの考えには、私たちがこれを遠くから観察するとき、救済も英知もないということです。これは別の生や別の世界を約束するものではないのです。これはまた、数々の人間文化に存在する自己の均衡や小康、水平化のパースペクティブでもありません。これらは情熱やその不断の変異の内定な消滅に関わるものなのです。現代の世界の中で万物が私たちに約束する強さ=激しさは、私たちの全快楽の中で、全苦しみの中で、小さな声で囁く倫理的なプログラムなのです。「私は君に同じもの以上のものを約束しよう。私は君に生以上のものを約束しよう。」」
私たちが本書で試みたような仕方で思考することは、私たちの生に倫理的な結論を探すものではありません。ある議論の倫理的な機能は、それを読む者に強制的な効果を生み出すことではなく、生が混同しがちなもののあいだの差異を保存することです。よく考えられた事柄は、最終的には、異なるか平等なものとして、平等だが異なるものとして私たちの前に現れうるものなのです。これが思考の理想です。思考は生を拘束することはありません。思考は生にその統治を課すことはありません。そうではなく、思考は生に異なるが平等な諸観念を提示することを試みるのです。事情を理解した上で生きるために。
生きることと思考することはどちらも重要なことです。しかし、よく思考することは生きるように思考することではなく、よく生きることは思考するように生きることではありません。一貫することへの誘惑に抗さなければなりません。しかしそれでは、いかに生きるべきなのでしょうか? 私たちは、最終的に生を新たな法則に従属させるために、考えるものと感じるもののあいだの倫理的秩序に関する区別を行ったのではありません。私たちにとって重要なのは、近代の消尽した条件を置き換えることでもなく、別の服従によって生の強さ=激しさの要請に従属することでもありません。この探求の最後には、ひとは道徳の内容を確定することができないことを、法的な力としての思考に取り組むことを拒否することを理解することになるでしょう。その反対に、最終的には、私たちは思考によって規則を定められたり、生に従属したり、あるいは生によって秩序づけられたり、思考に従ったりすることから解放されるのです。「私たちはいかに生きるべきか?」という問いに対する唯一の正しい倫理的答えは「より強く=激しく生きるように生きるべきである」でもなく、「真理や救済、あるいは絶対的なものを知る仕方で生きるべきである」でもなく、「生きる有機体であるという感情を失うことがないように生きるべきである」なのです。」
「こうして私たちは、この探求の最後に理解します。私たちにとって重要な生の強さ=激しさを保持することを想像できるのは、強さ=激しさを思考に対置する限りにおいてであり、思考を強さ=激しさに対置する限りにおいてでしかないことを。この忌みにおいて、私たちが倫理的な生を考えるのは、観念が私たちの生きる仕方に対応することを頑なに拒むことによってのみであり、この生が私たちの大いなる観念に従うことを拒むことによってのみなのです。私たちの倫理的特性は、それよりももっとずっと繊細なものと考えられているのです。」
「生の力はとても繊細なものなのです。可能な限り長く生きていることを感じるためには観念と感覚の尾根の上に留まらねばならず、肯定の幻惑に譲歩することも、否定の深みに落ち込むこともあってはなりません。それをあまりにも強く肯定することは、終いにはそれを否定することになるのです。しかし、それを否定することがそれを肯定することなのではありません。単に、それ自体に抗して生の力強さを幾分か倒錯的に使うことなのです。それを横断する力強い流れに敏感でないときには、生き、思考する存在はいつも敗者なのです。その思考は、終いには、その存在の最も強い部分を無力化することになるのです。慣性的な生の幸運とは以下のようなものなのです。すなわち、感性において、他のいかなるものにも還元されることはないものなのです。これは何かを感じるすべての存在の親密な宝であり。その諸感覚の真珠であり、それにしか属さないそれの一部分なのです。生きるものの生を持たない普遍的な観察者でありことはできないという感情なのです。」
(「訳者解説」より)
「「初体験信仰」にとっての「ルーチーン」は少し複雑なものである。「第一回目」はすぐに失われ、同じ「音楽」を聞くのは「二度目」、「三度目」になる。しかし、「初めて二度目に」、「初めて三度目に」その音楽を聴くという意味においては、それは常に「第一回目」の経験なのである。こうした意味において、「初体験信仰」は「ルーチーン」と共生し得るものである。少し視野を広げれば、「ポストモダン」というのは「近代」に対し、「初めて、[・・・]何であれ初めて感じることはもはやできず、すべてを二度目に完遂させなければならないという不可能性を認めた」人類史的経験であるとされる。しかし、このルーチーン的な「強さ=激しさ」の探求としての「初体験信仰」も、いずれはその経験を弱体化させることになる。すなわち、「第一回目」が「反復」され「倍化」されることによって「強さ=激しさ」は「純化」することになるからである。
「変異」や「加速」はいずれ「強さ=激しさ」を維持できなくなりそれを失うことになるが、「初体験信仰」はそれを維持することによって、「強さ=激しさ」を維持するための「策略」がすべて、結果的には「強さ=激しさ」の喪失に結びつくという「逆説」は共有されている。(・・・)「強い=激しい生」がいずれは「鬱病」や「燃え尽き症候群」といった「内的な崩壊」につながるという意味での「逆説」が語られたが、(・・・)「強さ=激しさ」がそれ自体喪失される運命にあるという、いわば。「強さ=激しさ」の存在論が分析されていることになる。そしていずれにせよ、近代の「強さ=激しさ」は失われることが運命づけられているとすれば、求めるべきはまさに、その「近代」というものそのものの外部ということになろう。つまり、「近代以前」ないしは「近代以後」の「思考」に向かって。」
《目次》
イントロダクション
1 イメージ――電気が思考に対し行ったこと
2 観念――事物をそれ自体と比較するために
3 概念――「すべてを強さ=激しさのなかで解釈しなければならない」
4 道徳的な理想――強い=激しい人間
5 倫理的な理想――強く=激しく生きること
6 反対の概念――ルーチーン効果
7 反対の観念――倫理的な鋏に挟まれて
8 反対のイメージ――何かが抵抗する
訳者解説
第一節 トリスタン・ガルシア紹介
第二節 『激しい生』を読む
第三節 方法叙説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
