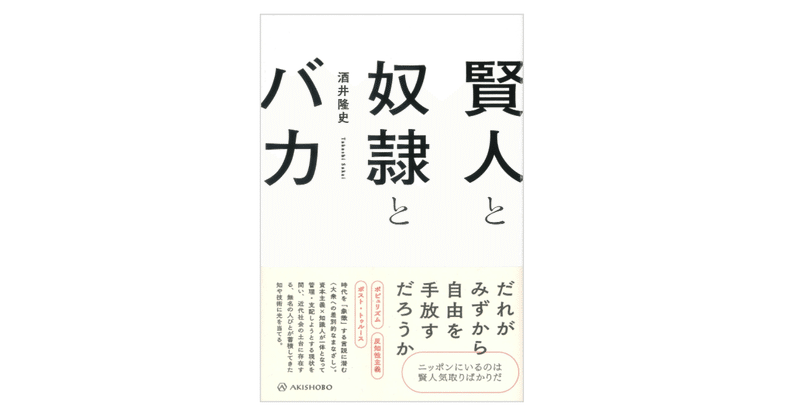
酒井隆史『賢人と奴隷とバカ』
☆mediopos-3115 2023.5.29
賢人と奴隷とバカの話
賢人になれというのではない
奴隷に賢人をめざせというのでもない
無論バカであることそのものを肯定しているのでもない
賢人きどりの知識人の多くは
「バカ」が嫌いだ
賢人になりたい奴隷の多くは
じぶんが「バカ」と思われないように
「バカ」を馬鹿にする
現在ことあるごとに「バカ」とされているのは
「反知性主義」「陰謀論」「反ワク」である
そうした「バカ」の構図をつくったのは
バカ=大衆への差別的なまなざしをもった
賢人と知識人のナルシシズムであり
それを方向づける「支配する知」である
「バカ」は支配されてしかるべきであり
「バカ」への同情から
「バカ」にならないように「知」を与えようとする者も
「バカ」への侮蔑から
支配に必要な「知」だけを教育しようとする者も
その「知」は「解放する知」ではない
二〇一一年以降
さらにはこの二〇二〇年以降
偽装されあるいは無自覚に機能させられてきた
「支配する知」がむきだしになってきている
(ある意味であまりに映画のような
ドラマチックなストーリーに充ちてもいるのだが)
それにもかかわらず
いまだにその「支配する知」に寄り添おうとする
賢人と奴隷はとくにこの日本では目覚める様子がない
目覚めてはいけないと政府もメディアも総がかりだ
みずからが知識人(おそらく賢人だと思っているのだろう)と
思い込んでいるひとたちの著作の多くは
「反知性主義」「陰謀論」「反ワク」を前提として
いまだ実質的に「バカ」をいかに啓蒙するかに忙しい
そのことでじぶんの確かな居場所を確保できるからだ
おそらくじぶんが「バカ」に見られることを
なによりも怖れているのだろうし
(「デクノボー」となんか呼ばれたくもないだろうから)
じぶんは決して「奴隷」だとも思ってはいないのだろう
そこに欠如しているものこそが
「無知の知」であることに気づくことなく・・・
しかしそんななかでも
賢人や奴隷が「バカ」とみなしているであろう
無名の人たちの蓄積してきた知や技術は
「解放する知」へと向けた動きもみせているようだ
おそらくそこにこそ私たちが
管理社会に潰されずに生き延びられる未来への希望はある
■酒井隆史『賢人と奴隷とバカ』(亜紀書房 2023/4)
(「00 はじめに————賢人とドレイとバカ 二〇二三年、春」より)
「二〇一六年くらいのこと、こういう寓話がウェブに転がっているのをみつけた。(・・・)
(・・・)
いまでは選択肢も賢い二つしかありません。この二つは賢いので、とても似ています。バカは選ぶことをやめてしまうか、自分も賢いとおもいはじめました(そうしてドレイと見分けがつかなくなってしまいました)。自分を賢人とおもっているドレイだらけですから、(・・・)そうだそうだと賛成します。バカと思われたくないからです・こうしてバカはこの国からいなくなりました。
主人の側の賢人たちもバカがなにより嫌いです。かれらは、ドレイの側の賢人はバカにだまされているか、実はバカである、と考えています。だから、正真正銘のバカがいなくなると、勢いにのって、バカ疑惑のある賢人のことなどかまう必要などないといいはじめました。バカを追いだせ、と。バカの話なんかいらない。なぜならバカだからだ。
おれたちはバカではない、と。賢人と賢いドレイたちは口ごたえをします。バカはおまえたちのほうだ。おれたちはこんなに賢いし、バカではないかた立派なふるまいかたも知っている。バカとはちがって、ゴミも拾える。だから、主人にはわかるはずだ。主人は聞いてくれるはずだ。
しかし、もうその言葉も空しく大空に消えていくだけです。(・・・)だれもとりあいません。
賢人と賢人のつもりのドレイたちは必死で叫びます。われわれはバカではない。
***
知る人が読めば一目瞭然であるように、この一文は魯迅の「賢人と馬鹿と奴隷」のパロディである。(・・・)
当のエッセイの翻訳者である竹内好は、この寓話をことさら愛し、しなしば日本の近代のありようをそこに読み込んだ。
いわく、日本の近代は、優秀な賢人たちによっておしすすめられた優等生の文化である。そこには、中国の近代のような抵抗が不在であるか、きわめて乏しかった。中国においては、進歩的近代に対し、あちらこちらで反動的な抵抗が起きて、足を引っ張った。それが、ひとつには日本に遅れた原因である。
ではなぜ、日本の先の大戦における敗戦、日本の近代そのものの破局にいたったのか。本来憂愁な文化であるにもかかわらず。
通説にいわく。それは優等生のなかに劣等生がひそんでいたから、あるいは大衆のうちに抱えた劣等性ゆえに負けたのだ。
しかし、と、竹内はいう。日本の近代はその優秀性ゆえに、「負けた」のではないか。」
「魯迅のような作家を生みだす土壌においては、人はいささか過大なほどに自己に固執している。だから、状況がどれほど変わろうが、にわかに方向を変えることはできない。わが道を歩くしかない。しかし、かれらはのろのろ歩きながら(生きていくには前へ歩かざるをえない)、自己を変えていく。歩くことは、成長したり、困難に遭遇してみずからを変容させたり、それ自体、人が変わることでもあるからだ。しかし、それは自己に固執するがゆえに、わたしがわたしであるために、変わるのである。「私が私であるためには、私は私以外のものにならなければならぬ時機というものは、かならずあるだろう」。それが個人にあらわれるとき「回心」(「転向」とは逆の)になり、あるいは社会にあらわれれば「革命」となる。
しかし、日本には、この固執する自己がそもそもない。したがって、自己であらんとして内側から変わろうとするのではなく、環境の変転にあわせて、外部の力によって変わっていく。これが日本の優秀さの秘密である。
いうまでもなく、魯迅は(そして竹内自身も)賢人を憎んでバカを愛していた。とはいえ、賢人がドレイを救うとは考えていないのは当然としても、バカがドレイを救うと考えていたわけではない。そこに注意でよ、と、竹内はいう。日本であれば、これらのキャラクターふぁそろえば、すぐに賢人かバカがドレイを解放するという物語を構成してしまうだろう。しかし、魯迅にとってはそうではない。そこで提示されているのは、だれが夢を充填してくれるかではなく、「夢から醒めても道がない」という苦痛をえがいた物語なのである。
賢人たちは、この幻想の空間をけんまいに補充しようとするだろう。バカも、語り方によってはそうした物語の一部を構成してしまうだろう。しかし、それたはいずれも、与えられる道の話、与えられる解放の話である。それは相変わらず主人だけあたらしくなったドレイの物語にすぎないのである。魯迅によれば、この苦痛を十全に受け止めることなしに、与えられる解放という幻想を破壊して、ドレイがドレイであることをやめる道はひらけないのである。」
(「第Ⅰ部 無知と知、あるいは「大衆の恐怖」について」〜「01.現代日本の「反・反知性主義」? 」より)
「これは筆者の印象なのだが、昨今の日本の状況が「反知性主義」に侵されているとみえてしまうその文脈には、排外主義やレイシズム、セクシズム、あるいは「ポピュリズム」の言説を、その根拠に乏しくとも、貧困層や失業者に即座にむすびつけようとする傾向が執拗にあることと関連しているのではないか。つまり、そこにはそれらの忌むべき「邪悪な情熱」が、知性の反対の産物であるという。それこそ「偏見」がひそんではいないだろうか。
そして議論がこうつづく。それらの「邪悪な情熱」は、近年の流行語でいえば「思考停止」の産物にほかならない。したがって「知性」を働かせるならば、あるいは「事実」を知るならば、「教養」を積むならば、そうした卑しむべき態度も必然的に解消するはずだ、と。しかし、こうした言説の軌跡をだどっていくなら、それらを練り上げ、メディアを通して流布し、時代の空気の形成を主導してきたのが、もっぱら「知識人」であることはあきらかだ。現在のこのような排外主義的/レイシズムの思考の型は、こうした知識人たちによって練り上げられてきたものの映しである。
さらに、こうした「知的」な排外主義やレイシズムがのびのびと成長するための栄養分を供給しつづけている普遍的権利への攻撃や「戦後的なもの」への否定と、その気分としてのシニシズムは、長いあいだかけて、制度内外の知識人たちによって耕されてきたものである。現代の排外主義やレイシズムの言説の構造や、さらにそれを醸成する知的気分というものは、あきらかに(狭義広義の)知識人、エリート、メディアの複合体によって「上から」主導されてきたものである。したがって、現代の知的雰囲気を、「反知性主義」と決めつけ、それをときに「群衆化した大衆」に重ねたりする前に、それこそアントニオ・グラムシに謙虚に立ち返り、「市民社会」に分散し、時代を支配する感情や価値にかたちを与えている知識人、あるいは有機的知識人たちの働きの分析、知的ヘゲモニーの分析を必要としているのではあるまいか。」
(「第Ⅰ部 無知と知、あるいは「大衆の恐怖」について」〜「02.「反知性主義」批判の波動──ホフスタッターとラッシュ」より)より)
「なぜ「反知性主義」のような現象が生まれるのか、かんたんにコメントをしておきたい。
知そのものは人を解放するために機能することもあれば、人を拘束したり押さえつけたりするために機能することもある。いっぽうで、ヒエラルキーを解体し、わたしたちの共にある条件をよりよくすること、促進することにも決定的に寄与することもあるが、いっぽうで、ヒエラルキーを形成・強化し、専制支配を正当化し、不平等な富の配分に寄与することもある。
一九六八年以降において、知や知性そのものになにか価値があるといった物言いはもはやできなくなった。日本でならば、たとえば、「大学解体」以降、自主講座運動がなにを問題にしたか、それを想起してみよう。二つの大戦をかろうじて生き延びた知の無垢への信憑も、この時代以降、もはやほとんど全面的に困難になる。問われるべきは、知識人そのものが知を介して組み込まれたヒエラルキーとどうわたりあうかにもなる。そして、知識人は、みずからの知について、どのような条件のもとで人を束縛するものとなるのか。どのような条件で解放的になるのか、自問を強いられることになる。」
「知が支配とむすびつくとき、それはどこかで暴力と縁をむすんでいる。たとえば、国家において、人はつねに動員の対象となっている。それは富の抽出の対象であり。賦役や軍事のための動員の対象であり、逃亡を阻止するために監視される対象である。人びとをそのような対象に仕立てあげるためには、なんらかの知が必要である。文字が必要であり、計算が必要であり、合理的配置が必要なのである。そのような知は、人びとをその生きる平面から抽象化し、それを通して操作的対象とする官僚の知でもある。ここには知でありながら、解釈労働における知の個別性や具体性を欠いている。わたしたちは、上司の顔色をうかがうとき、上司一般の行動パターンを知り、それをあてはめるわけではない。「この」上司の性格やくせをつかみ、「この」上司のいまの感情の動きをつかみ、それによって「この」上司の機嫌を損ねないようにふるまうのである。いっぽう、官僚の知、支配の条件と展開した知は、そうした具体性の平面には無知である。あるいは、その無知とそれによる冷酷を「合理性」と誇るのも、この知である。したがって、この知は、つねに国家の暴力にどこかで繋留している。」
(「20.あとがき」より)
「総じていえば、この時代にこの社会で起きたのは、ネオリベラルな世界秩序への遅ればせながらの全面的順応の過程であった。単一のゲームの勝敗、取り分の大小の競い合いにほとんどが収斂し、それをはみだしていく動きは、全方向から取り締まられてしまう。この世界のありようをひらいてみせるよりは、「政権」やそれを「支持する人びと」に与えるダメージを狙ったようなフレーズが知的にも好んで流布されたのは、そのような態度のあらわれにもおもわれた。内向と保守化が、批判的言説をも覆い尽くしていったようにみえたのである。それまでの実践や知的ないとなみがカッコに括っていた、躊躇なしにはいえなくなったはずの(そう、おもいこんでいた)語彙から、つぎつぎとカッコが外されていった。二〇一一年の「三重の破局」の直後に爆発的にひらかれたようにみえた諸可能性が、なぜそのような空気へと転じていくのか、茫然としながらも、せめて大勢とはちがってもじぶんの考えを記しておかなければと書かれたのが、ここに収めたテキストの大半である。
いっぽう。二〇一一年以降、世界をみわたすならば、民衆的実践が世界的に呼応し合いながら別の世界のありかたの模索をさらに深めていくにともない、わたしたちがいまどういう時代に、どういう世界にあるのかを大きくつきとめようとする動きが、知の基盤の変動を加速させていったようにみえたし、そこにはしばしば興奮を誘うものがあた。この世界はやはりおもしろいのである!
しかし、もういっぽうで、パンデミックを転換点として、本書でみてきた悪しき趨勢もより強化され、よりむきだしになっている。世界のエリート層は、破局を富のさらなる蓄積の機会に転じつつ、一手に集中させた膨大な富の防衛のために地球上の多数の人びととたたかう意欲をますます隠さなくなってきた。富裕層とその同盟者は、システムの正当化が困難になればなるほど、「切腹」や「安楽死」などを口にしながら、「たちどころ」の解決、つまり暴力による解決を求めていくだろう。それと同時に、膨大な富を投入して、システムから振り落とされていく人びとになおこのシステムには維持する価値があると夢想(魯迅=竹内好のいう「夢から醒めないことの救い」)を提供し、システムを回すにあたっての邪魔者をつくりだしてはそれへの憎悪を注入していくだろう。老いた恐竜の悪あがきに巻きこまれることなく、わたしたちが生き延びるためには、その「若づくり」に幻惑されないようにしなければならない。本書の目標は、正否はともかく、その幻惑に抵抗すること、そして、すでに地球上のあちこちではじまっている、つぎの世界の組み立ての過程に、いささかなりとも参加することにある。」
【目次】
◆はじめに賢人とドレイとバカ 二〇二三年、春
第Ⅰ部 無知と知、あるいは「大衆の恐怖」について
01.現代日本の「反・反知性主義」?
02.「反知性主義」批判の波動──ホフスタッターとラッシュ
03.ピープルなきところ、ポピュリズムあり──デモクラシーと階級闘争
04.「この民主主義を守ろうという方法によっては この民主主義を守ることはできない」──丸山眞男とデモスの力能
05.一九六八年と「事後の生(afterlives)」──津村喬『横議横行論』によせて
06.「「穏健派」とは、世界で最も穏健じゃない人たちのことだ」──「エキセン現象」をめぐる、なにやらえらそうな人とそうじゃない人の「対話」
第Ⅱ部 だれがなにに隷従するのか
07.「放射脳」を擁護する
08.「しがみつく者たち」に──水俣・足尾銅山・福島から
09.自発的隷従論を再考する
10.「自由を行使する能力のないものには自由は与えられない」──二〇一八年「京大立て看問題」をどう考えるか
11.「中立的で抑制的」──維新の会と研究者たち
12.「この町がなくなれば居場所はない」──映画『月夜釡合戦』と釡ヶ崎
第Ⅲ部 この世界の外に──抵抗と逃走
13.「ブラジルで のブレザーなんて着たがるヤツはいない。 殴り倒されるからだ」──二〇二〇年東京オリンピックをめぐる概観
14. 戦術しかない/戦略しかない──二〇一〇年代の路上における二つの趨勢
15.「わたしは逃げながら、武器を探すのです」──ジョージ・ジャクソン、アボリショニズム、そしてフランスにおける「権力批判」の起源について
16.ポリシング、人種資本主義、#BlackLivesMatter
17.パンデミックと〈資本〉とその宿主
18.「世界の終わりは資本主義の勝利とともにはじまった」──文明に生の欲動をもたらすもの
19.すべてのオメラスから歩み去る人びとへ──反平等の時代と外部への想像力
◆20.あとがき
○酒井 隆史(さかい・たかし)
大阪公立大学教員。専門は社会思想史、都市社会論。主要著作に『通天閣―新・日本資本主義発達史』(青土社、2011年)、『完全版 自由論―現在性の系譜学』(河出文庫、2019年)、『暴力の哲学』(河出文庫、2016年)、『ブルシット・ジョブの謎』(講談社現代新書、2021年)。訳書に、ピエール・クラストル『国家をもたぬよう社会は努めてきた』洛北出版、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ―クソどうでもいい仕事の理論』岩波書店(共訳)、『官僚制のユートピア―テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則』以文社、『負債論―貨幣と暴力の5000年』以文社(監訳)、マイク・デイヴィス『スラムの惑星―都市貧困のグローバル化』明石書店(監訳)、デヴィッド・ウェングロウ、デヴィッド・グレーバー『万物の黎明』光文社(近刊)など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
