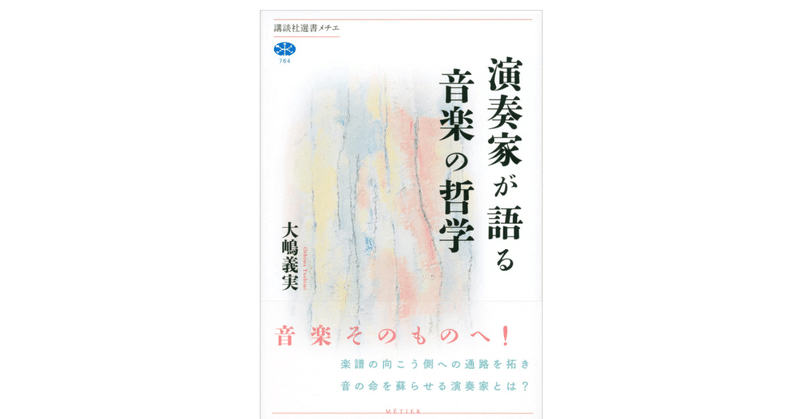
大嶋 義実『演奏家が語る音楽の哲学』
☆mediopos2738 2022.5.17
学ぶことは
覚えることではなく
教えられることでもない
問いに向かってひらかれることだ
知識が不要だとは言えないが
往々にして知識は知恵を殺してしまうから
教えられた知識から自由になる必要がある
とはいえ処世のためには
教えられたように覚え
専門の枠組みを超えた問いは持たず
知識のなかを生きぬくことが重要になり
そうでなきないときは多く
世に受け入れられることは難しくなる
うまく生きていくためには
すべてを既存の枠組みと知識のなかで
与えられた問いに
適切に答えられるようにすることが重要だ
しかしそこにはすでに
どんな驚きも感動も失われている
そこにあるのは未知ではなく
既知に対してどのように効率的で効果的に
処理することができるかという課題である
本書の著者・大嶋義実氏は
第一線で活躍中だというフルーティストでもあるそうだが
(寡聞にして本書ではじめて知ったが同年代だ)
「わたしたちはいつの頃からか、
音楽を消費することが当たり前の
世界を生きるようになってしまった」という
「音楽(芸術)とひとの出会いが感動的であるのは」
「それが新たな時間と空間を生成し、
そんなものがあるとは想像すらしなかった存在が
そこに立ち現れるから」なのだが
商品化された音楽は
「あらかじめ用意された物差しで値踏みされる」となり
「未知なる世界への扉を閉ざ」すものとなっている
もちろん音楽だけではなく
現代ではあらゆるものは「商品化」され
それを消費することでしかなくなっている
もちろん教育もその最たるものだ
そこで求められるのは効率のよい解答マシーンであり
未知の問いはむしろ忌み嫌われることになる
「この世界に感動を取り戻す」ためには
どんなものに対しても
もちろんひとに対しても
いつもはじめて出会うことではないだろうか
あらかじめ用意された答えを覚えるだけでは
どんな問いも感動もそこには生まれないだろう
音楽を聴くときにも
いつも「はじめて聴く」ことで
驚きと感動の経験へと開いていられる
■大嶋 義実『演奏家が語る音楽の哲学』
(講談社選書メチエ 講談社 2022/5)
「今となっては、通俗名曲に堕したともいわれかねないベートーヴェンのピアノ・ソナタ「月光」に、どれほどの愛好家がこころ動かされるだろう。
ことはオーケストラ曲でも同じようだ。愛好家にとっては、いまさら「運命」や「田園」ではないのだろう。「第九」ですら「一万人の第九」などと、ことさらに大仰なタイトルをつけなければ世間がふり向いてくれなくなってしまった。
かつてのように音楽のみに純粋に感動を覚えるひとびとがいるのだろうか。音楽に深くかかわっていればいるほど、素直にそれ自体に感興を覚えるのが難しい時代ではなかろうか。リサイタルで「月光」が奏されても、聞こえてくるのは演奏についての分析的な批評だ。音楽自体の素晴らしさを伝える声はなきに等しい。新録音がリリースされると「斬新な解釈」、「臨場感あふれる録音」等々、講釈ばかりが耳に入る。その楽器から紡ぎ出される音にこころ震わされた、などといおうものなら、「素人か」と小ばかにさえされそうだ。
こうした現状は、わたしたちの耳が肥えてしまったからなのか。立派な演奏や録音に接しすぎて、並の解釈や音では満足できない身体(耳)になったようだ。
(・・・)
だとすると、今を生きるわたしたちの感受性はいったいどうしたというのだろう。
おそらくその変化の根底にあるものは、音楽が商品となったゆえに違いない。わたしたちはいつの頃からか、音楽を消費することが当たり前の世界を生きるようになってしまった。いまや音楽に関するいっさいが市場にある。創ることにおいても、演奏することにおいても、聴くことにおいても、教えることにおいても、習うことにおいても、だ。そして、そこには市場のニーズなるものが存在する。ニーズというものは、既にそれが何であるか知られているところに生まれる。
ところが真の芸術は、それがひとびとの目の前に現れるまで、そのようなものがこの世に存在するとは想像すらされなかったがゆえに、芸術たりうる。したがって、そもそもニーズの存在しようがない。だって、まだ誰もそれを知らないのだから。
ならば、近ごろの音楽界に感動が足りないのは、真の芸術たりうる新たな響きが生み出されていないからなのか。
そんなことはない。話は逆だ。「それについては知っている」という消費者としての立ち位置が、わたしたち自身のこころ(耳)を曇らせているからだ。
「私は私が何を欲しているか、自分のことを知っている」という己に対する傲慢が、自身の感覚を鈍らせている。つまり自らニーズを生み出すことによって、かえってわたしたちは未知なる世界への扉を閉ざしている、といえはしまいか。
市場に溢れかえる音楽は、消費者としてのふるまいをわたしたちに求める。だが、いったんその立場を受け入れてしまうと「差し出された商品を自らの価値観で査定する」という消費の罠から抜け出せなくなる。あらかじめ用意された物差しで値踏みされる芸術(音楽)が、どうして誰も見たこともない世界を開示できよう。
レッスンだって同様だ。こころのどこかに「私は、これから私が何を習おうとしているか知っている」という思いはないだろうか。「私が何を学びたいと望んでいるかは、私にとって自明なことだ」と自らへの驕りが生じてはいないだろうか。
レッスンを、市場に提供された「演奏スキルを身につけるためのサービス」と捉えるなら、それもアリだ。でも、そうであるかぎり感動的なレッスンもなければ、音楽を奏するうえでのブレークスルーを経験することも難しかろう。「今はできなくとも、いずれそれができるようになると知っていること」ができても、嬉しくはあろうが感動はしまい。なにより、既に知っていることができるようになることを、ブレークスルーとはいわない。「それができるようになって、初めてそれが何かを知った」とき、ひとは真のブレークスルーを果たす。その経験は音楽的感動をも、もたらすはずだ。
音楽(芸術)とひとの出会いが感動的であるのは、(思想家・内田樹の表現に倣うなら)それが新たな時間と空間を生成し、そんなものがあるとは想像すらしなかった存在がそこに立ち現れるからだ。いま目の前にあるものとは違う世界との通路を穿ち、架橋することこそが芸術の本質にあるものだ。
(・・・)
「知っている」という思い上がりに、芸術が感動の扉を開くことなどあろうはずがない。
どうやら不足しているのは、音楽に対してへりくだる柔らかなこころらしい。
わたしたちは自らに向かってもう少し謙虚に生きたほうがよいのかもしれない。再びこの世界に感動を取り戻すために・・・・・・。」
[目次]より
第一章 音を奏でる人類
第二章 「音楽そのもの」との交歓
第三章 音楽に表れるのは個性か普遍性か
第四章 音符の奥に立ち上がる音楽
第五章 響かせること、響きを合わせること
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
