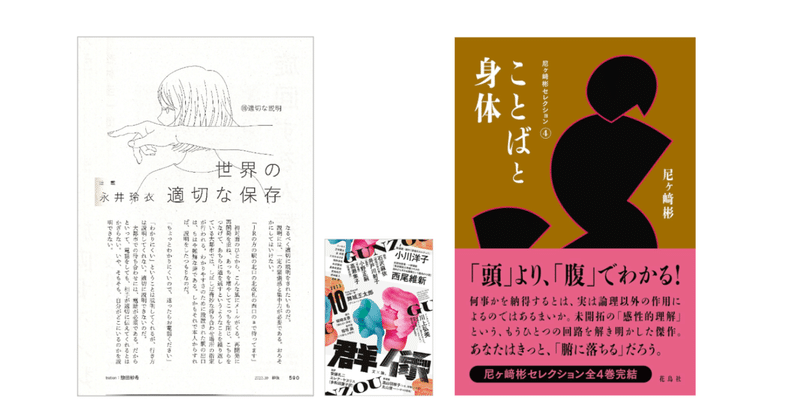
尼ヶ﨑彬『ことばと身体』/永井玲衣「世界の適切な保存⑱適切な説明」
☆mediopos3226 2023.9.17
昨日のmdiopos3225(2023.9.16)で
「身体」と「言葉」についてとりあげたが
そのことを少し視点をかえて考えてみたい
「群像」で永井玲衣が連載している
「世界の適切な保存」の今月号(10月)のテーマが
「適切な説明」だが
ひとに「適切な説明」をするということ
あるいは誰かからの「適切な説明」を
「理解」できるということは
どういうことなのだろうか
逆にいえば「適切な説明」ができない
あるいはそれが「理解」できないということは
どういうことなのだろうか
それについて尼ヶ﨑彬の『ことばと身体』が
それについて深い示唆を与えてくれる
最初の章には
子供に『三角形』とはなにかを説明する
という例が挙げられている
「正確な説明」あるいは「定義」では
「一直線上にない三つの点のそれぞれを結ぶ
線分によってできる図形」ということになるが
三角形がわからないでいる子供に
そんな説明は「適切」ではない
おむすびの形や図で説明するほうが
「適切」であるといえる
これは子供への説明だけにいえることではない
ふつう私たちが何かを理解してもらう
あるいはじぶんで理解するときに
概念による「定義」は「適切」だとはいえない
概念による「定義」がすんなりと理解できるのは
その前段階でそれについて
いわば身体的な理解が先立つときであり
逆ではない
「意味」には
「辞書的意味と「もの」の意味」の二種類があり
「「もの」の意味」とは
「「もの」に対した時の身心態勢に生じる感覚であり、
つまりは「らしさ」である
日本語には
「頭でわかる」と「腹でわかる」
というふたつのわかり方の違いがあり
まず「腹でわかる」必要がある
いきなり「頭でわかる」のはむずかしい
上述の「説明」が理解できるかできないかだが
新たな「意味」を定義から理解できるときには
すでに「「もの」に対した時の身心態勢」が
準備されている必要がある
知識として「意味」を覚えこむはできるだろうが
そうすることでは「意味」の源へと溯り
そこから生まれてくる「意味」を
身をもって「理解」することはできないし
「意味」は「世界」と切り離された
二項対立的なそれでしかなくなってしまう
いうまでもないが「腹でわかる」だけではなく
そのあとで「頭でわかる」必要もある
そうでなければ「意味」を伝えることはできない
しかし身心態勢のプロセスを経た「意味」は
たんなる概念的定義に閉じ込められたそれではない
創造的にポイエーシス/ポエジーへと開かれているからだ
■尼ヶ﨑彬『ことばと身体』
(尼ヶ﨑彬セレクション 4 花鳥社 2023/7)
■永井玲衣「世界の適切な保存⑱適切な説明」
(群像 2023年10月号)
(「永井玲衣「世界の適切な保存⑱適切な説明」より)
「なるべく適切に説明をされたいものだ。
説明には、一定の緊張感と集中力が必要である。おろそかにしてはいけない。」
「適切な説明をするひとは、集中している。言葉がやってくるのを注意深く待っている。落ちてくる流れ星を受け止めるように、ひとはそれをつかまえて、光ったまま、わたしに手渡す。言葉は光を放ち、わたしたちを包み込んでしまう。圧倒的な力で、共有させてしまう。だから心を動かされるのかもしれない。
探求はつづく。適切な説明には、どういうときに巡り会えるのだろう。光る、とりかえのきかない、そのままの言葉に、どうやったら出会えるのだろう。
ふと、あの短歌を思い出す。あれこそ、適切な説明ではないか。なぜ今まで思いつかなかったのだろう。
歌集をひらき、言葉に向かい合う。そして気づかされる。そう、適切な説明とは、言葉が用いられなくても、立ち現れるのだ。
海を知らぬ少女の前に麦藁帽のわれは両手をひろげていたり(寺山修司)
麦藁帽の少年は、黙っている。言葉を手放すという仕方で、言葉に向き合っている。ゆっくりと手を広げ、少女に示す。
何よりも、それは海だろう。少女は、海を見ることなく、そのままの海に出会ったのだ。」
(「尼ヶ﨑彬『ことばと身体』〜「一 「たとえ」の構造————隠喩と事例」より)
「 たとえば誰かが子供を連れてやってきて、あなたにこう訊ねたとしよう。
「あなたは『三角形』という言葉を知っていますか」
もちろん知っている、とあなたは答えるだろう。
「では、その意味はご存じですか」
もちろんわかっている、と答えるだろう。
「では、この子供に『三角形』の正確な定義を教えてやってくれませんか」
たいていの人はここで考えこむはずである。もし、たちどころに的確な定義を与えられるなら、あなたは辞書を書く資格がある。ちなみに広辞苑にはこうある。
「一直線上にない三つの点のそれぞれを結ぶ線分によってできる図形」
なるほど正確な定義である。しかし、正確ではあるけれども、本当にこんな説明で「三角形」がわかるのだろうか。ためしに子供に読み聞かせてみるといい。きっと「わからない」と言うだろう。
ではどうすればよいのか。たぶんあなたは「ほら、おにぎりの形だよ」と言ったり、紙に図を描いて見せたりするだろう。すると子供は(かなり下手な図であっても)「わかった」と言うだろう。もちろん、このようなやり方は便宜的な説明であって、定義のような厳密さを持たない。けれども子供は以後まちがいなく。あるものが「三角形」であるかないかを正確に言い当てられるだろう。つまり、子供は「三角形」の概念を「理解」したのである。そして実は大人の私たちの場合も、その理解の実状はこれとさして変わらない。誰が「三角形」という言葉から「一直線上にない三つの点云々」というような文を思い浮かべるだろうか。私たちが思い浮かべているものは、紙の上の図やおにぎりに共通なある図形のイメージであるはずだ。それが私たちが子供の時から知っている「三角形」の意味であり、概念なのである。ある意味で言語的定義はこのイメージをあとから説明するために公案されたものにすぎない。
このようにわたしたちは、自分のよく知っているはずのことを語ろうとする時でさえ、言葉の論理的使用だけでは追いつかず、何かに喩えたり、実例をあげたりする。いうまでもなくこれはレトリックの使用である。しかもこの「たとえ」は詩的言語によくみられるレトリックである。とすれば、詩歌のレトリックは、意味伝達という観点からしばしば無用の(あるいは邪魔な)飾りとみなされるけれども、実は何事かの「理解」のために多いな働きをしているのではないかと考えられる。」
(「尼ヶ﨑彬『ことばと身体』〜「二「らしさ」の認知————プロトタイプとカテゴリー」より)
「読者が隠喩を理解するとは、隠喩として与えられたプロトタイプとしてこの不合理なカテゴリーを自ら形成することである。彼は、ものを見る新しい視点を獲得し、ものは新しい意味を語りはじめるだろう。これはまた、既知のはずの言葉が、まさにその現場で独自の意味を生成してゆくことでもある。こうして創造的な隠喩(生きた隠喩)は、世界を異様な目で眺め、世界自身に新たな意味を語りださせるための手段となることができる。たとえば、
「世界は舞台。人はみな訳者」
この隠喩はシェイクスピ絵がどのような眼差しで世界や人を眺めていたかを告げている。この視点を私たちが共にするとき、人の振舞、世の有様は違った様相を示すだろう。そしてたとえばこの視点から『ハムレット』を読み直すなら、もはやそれはもったいぶった悲劇ではありえないだろう。」
(「尼ヶ﨑彬『ことばと身体』〜「三 「わかり」の仕組み————真理と納得」より)
「ロゴス的言語が語られるとき、私たちはそれに対して真偽を判定することができる。そこでは内容の真理が問題になるからである。しかし話し手が、ある視点から見た特定の〈見え〉を新しいカテゴリーの提示によって伝えようとするとき、私たちはそれを受け入れて同じ態度を共有するか、拒否するしかない。ここでは納得が問題になるのである。真理を伝える言葉と納得を求める言葉は同じではない。前者は、人間がいなくろも成立するような客観的事態として抽象的に語られるのに対し、後者はそのつどの個人の主体的な世界への構えが関与せざるを得ないからである。」
(「尼ヶ﨑彬『ことばと身体』〜「四 「なぞらえ」思考————概念の元型と共通感覚s」より)
「現代芸術を見て人はしばしば「わからない」と呟く。これは何よりも見方がわからないということである。新しい洋式の作品を前にすると、人はどのような構えをとればよいのかわからない。身体はなぞるべき図式を見失い。茫然と立ちつくすことになる。見方がわかるとは、作品への構え方が身につくということであり、自分の身体のうちに共通感覚を励起させ、その身心態勢の型を「らしさ」として理解できるということである。「わかりやすい」とは、簡単にその身心態勢に浸ることができるということである。」
(「尼ヶ﨑彬『ことばと身体』〜「五 「身にしむ」言葉————制度的意味と受肉した意味」より)
「言葉が意味を受肉するためには。まず現実の世界が意味を受肉したものとして立ち現れていなければならないということである。即ち、意味の発生の源にあるものは、個著場ではなく、世界そのものが(あるいは世界の中の諸々の事物が)意味に満ちたものとして私の前に立つかどうかということなのである。太初にあったものはロゴスではない。」
(「尼ヶ﨑彬『ことばと身体』〜「六 「なぞり」の方略————レトリックと身体」より)
「幼児は成長すると世界はロゴス的なものであると考えるようになる。そして世界を記述する言語もまたロゴス的であると思うようになる。とりわけ正確であるべき言述(たとえば論文)はひたすらロゴス的であることを要請される。即ち、客観的であること。論理的であること。概念は明確に定義されていること。ブラックが言ったように、哲学論文に隠喩を用いることは禁忌となっている(実は哲学だけではないが)。
しかし文学は、とりわけ詩歌は隠喩を用いる。いや隠喩だけではない。さまざまなレトリックを縦横に駆使する。その効果は何か、レトリックは読み手をロゴス的構造の世界から「らしさ」の世界へ、対照的認識から身体的認識へと引き戻すであろう。言葉はもはや外在的情報を伝えるものではなく、読み手の身体を場として改めて意味を受肉させ、理解させ、頭ではなくからだで納得させるであろう。だからこそ優れた詩は(そしてすべての芸術は)私たちを原初の意味生成の場へと連れ戻し、世界を新たな眼で見ることを、いや生きることを教えるのである。」
(「尼ヶ﨑彬『ことばと身体』〜「あとがき」より)
「古来レトリックに対する批判の一つに、読者の頭の悪いのにつけこんで理屈に合わぬ事をもっともらしく見せかけるトリックではないか、というものがある。確かにレトリックは論理の厳密よりも説得の効果のみを目指していると思えることがある。しかしこれを裏から考えれば、私たちが何事かを納得するとは、実は論理以外の作用によるのではあるまいか。昔から深く了解することを「腑に落ちる」とか「腹にはいる」とか言う。これら内蔵の比喩は、「納得」が論理の回路を超えた一種の新体感覚であることを示唆してはいないだろうか。つまりレトリックとは。言葉による身体への働きかけという一面をもっているのではないか。いや、むしろこう言おう。私たちの身体は頭のほかのもう一つの認識=思考回路をもっており、それを言葉に表そうとしたものがレトリックではないのか。とすれば、レトリックの問題は言葉の問題というより、言葉を窓口として現象する、私たちの身心内部の仕掛けの問題ということになる。」
(「尼ヶ﨑彬『ことばと身体』〜「『セレクション版』のためのあとがき」より)
「本書の目標は、精神と身体という西洋的二元論の枠組みから抜け出すことだった。」
「この二元論を言語の理性的理解と感性的理解というふうに言い換えると、日本にはおもしろい言い方があることに気がついた。「頭でわかる」に対シル「腹でわかる」とか「腑に落ちる」という言い方である。そして日本人の評価は「頭」よりも「腹」の方に軍配をあげる。つまり言語の理性的理解よりも感性的あるいは身体的理解のほうがほんとうの理解だとみなしているのだ。これは、概念を喚起する言葉よりも「身心態勢」を喚起する言葉のほうがより本質的だということではないだろうか。
「身心態勢」とは姿勢や運動などがもたらす肉体の内部感覚(体性感覚)だけでなく、視聴覚の感覚や外部環境の認知情報などを含めて得られる「今・ここ」の状況に対する反応として生起する身体と情動(emotion)の状態である。この「情動」を意識の対象として捉え、喜怒哀楽などのラベルを貼ると「感情」(feeling)となる。つまり感情は概念的認識の対象となるけれども、情動は私たちを摑み、突き動かしているものだからうまく対象化できないし、言語化もできない。」
「「意味」には二種類ある。辞書的意味と「もの」の意味である。辞書的意味とは概念であり、辞書に書かれているような意味である。「もの」の意味とは「もの」に対した時の身心態勢に生じる感覚であり、つまりは「らしさ」である。通常の文が「もの」の名をだすとき、それは辞書的意味と「もの」の意味と二つの意味を伝える。しかし比喩として「もの」の名前を使うとき、辞書的意味は働かず、ただ「もの」の意味だけが働く。(・・・)だから読者の身心を揺り動かしたい詩歌は「たとえ」をよく使うし、「たとえ」でなくと「もの」の意味を喚起しようとする。「春の花」はウキウキするものだし、「秋の夕暮れ」は身に沁みるものなのである。なお大事なことはこの二種の意味は同時に生まれたものではないということであり。はじめに「もの」の意味が学ばれ、そのあとで辞書的意味が学ばれる。動物や幼児は「もの」の意味の段階でとどまっている。つまり初めにあったのは「ロゴス」ではなく身心態勢の感じなのだ。理性的認識は身体的実感のあとにやってくる。だから「頭」でわかるよりも「腹」でわかるほうが人間にとっては深いとされるのだ。」
○尼ヶ﨑彬
1947年愛媛県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退(美学芸術学専攻)。東京大学助手、学習院女子短期大学助教授を経て2017 年まで同女子大学教授。美学、舞踊学。著書に、『利休の黒』(花鳥社、2022年)、『花鳥の使』(復刊、花鳥社、2023年)、『日本のレトリック』(復刊、花鳥社、2023年)、『縁の美学』(勁草書房、1995年)、『ダンス・クリティーク』(勁草書房、2004年)、『近代詩の誕生』(大修館書店、2011年)、『いきと風流』(大修館書店、2017年)など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
