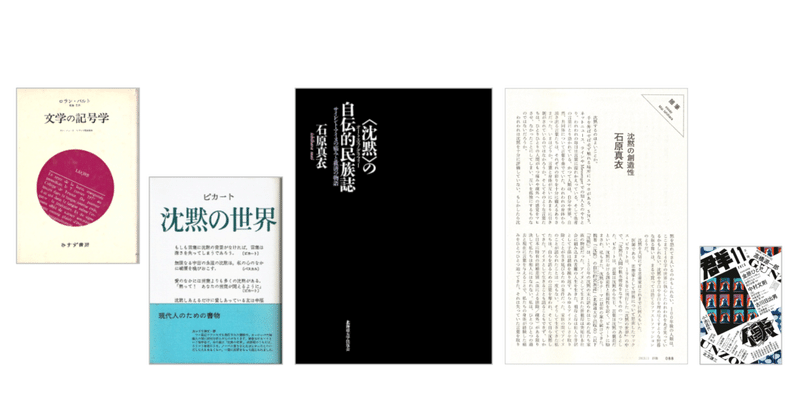
石原真衣「沈黙の創造性」(群像 2023年11月号)・『〈沈黙〉の自伝的民族誌』/ロラン バルト『文学の記号学』/マックス・ピカート『沈黙の世界』
☆mediopos3264 2023.10.25
言語について考えることは
沈黙について考えることでもある
アイヌに関して書かれた随筆(群像 2023年11月号)
石原真衣「沈黙の創造性」でも紹介されているように
マックス・ピカートは『沈黙の世界』で
「沈黙は人間の根本構造をなすものの一つ」であるとし
「言葉は沈黙から生じ、言葉は沈黙の裏面」であり
「沈黙における創造性と根源性」が説かれている
そんな沈黙について考えるときに
決して忘れてはならないのが
ロラン・バルトが『文学の記号学』で示唆した
「ファシズムとは、
何かを言わせまいとするものではなく、
何かを強制的に言わせるもの」だということ
そのことに関して思い出すのは
カントが『実践理性批判』において
自由の認識に関して挙げたエピソードである
残忍な君主が
ある人物を死刑にする口実を得ようとして
別の人間に嘘の証言を行うように強迫する
偽証を拒めば君主に殺されてしまう
強迫された人間は
「沈黙」していることができない
できるのは偽証するか
じぶんが殺害されるかである
これはかなり極端な例ではあるが
言葉を使うこと
あるいは沈黙することを考える時の
重要な問題提起にもつながる
私たちが言葉を使うとき
ロラン・バルトが示唆しているように
「断定からくる権威と、反復からくる群生性」から
まったく逃れていることはできないからだ
私たちはそのことを
ほとんど意識しないでいるが
外的な強制にせよ内的な自制の上にせよ
私たちはつねに語らせられている
あるいは「沈黙」を強いられている
いうまでもなく政治やメディアは
私たちにそのことを意識させないまま
与えたい情報だけを与え
その言葉にじぶんから従わせようとする
そして私たちはそれらの言葉の「権威」のもと
みずからもまたそれを「反復」することになる
つまり「嘘」か否かを問わず
「群生性」のもとで言葉を使う
(「嘘の証言」をさえそれと知らずに行う)
言語を自覚的に使うということは
そうした言語=ファシズムからは逃れられないことを
意識するということである
そして可能なかぎり「断定からくる権威と、
反復からくる群生性」から自由であろうとすること
そのためにこそ
強制された「沈黙」ではなく
「創造性と根源性」を湛え得る「沈黙」を
あらためて見つめなおす必要がある
そんな「沈黙」へとひらかれ
そこからあらたな可能性をもった言葉が見出せますように
■石原真衣「沈黙の創造性」(群像 2023年11月号)
■石原真衣『〈沈黙〉の自伝的民族誌(オートエスノグラフィー)
サイレント・アイヌの痛みと救済の物語』(北海道大学出版会 2020/2)
■ロラン バルト(花輪光訳)
『文学の記号学/コレージュ・ド・フランス開講講義』(みすず書房 1981/8)
■マックス・ピカート(佐野利勝訳)『沈黙の世界』(みすず書房 1964/2)
(石原真衣「沈黙の創造性」より)
「沈黙することはよいことか。
手を伸ばせば必ず触れる場所にスマホがある。SNS、ネットニュース、ラインやMessengerでの知人のやりとり。われわれの毎日は言葉に溢れかえっている。そして他者の言葉にとり憑かれている。かつて人類は、自分や世界、自然、共同体について言葉を奏でていた。われわれの身体から涌き出る言葉たちは、それぞれの彩りを十分に備えるありさまだった。いまはどうか。言葉と身体が互いにあまりに引き剥がされているのではなかろうか。そしてそのような言葉たちは、ひとりひとりの人間がもつ傷みや疎外への感覚をマヒさせ、なかったことにしてしまい、互いを孤独にするものなのではないだろうか。
われわれは沈黙を十分に評価していない。もしかしたら沈黙を恐れてさえいるのかもしれない。100年後の人類は、ここまで140字の世界に執心したわれわれをあざ笑っているかもしれない。沈黙や空白や余白を埋め尽くすような野暮な振る舞いは、まるで買っては捨てるファストファッションのようだ。
沈黙を大切にする思索家はこれまでに何人もいた。
医師であり、思想家として世界について思索したマックス・ピカートは、1948年に刊行した『沈黙の世界』の中で、「沈黙は人間の根本構造をなすものの一つ」であるとした。ピカートは、言葉は沈黙から生じ、言葉は沈黙の裏面だといい、沈黙における創造性と根源性を説く。ピカートに励まされ、私もまた、沈黙をテーマに思索の旅を続けてきた。拙著『〈沈黙〉の自伝的民族誌(オートエスノグラフィー) 』(北海道大学出版会)(以下『沈黙』)は、150年の沈黙の末に語られはじめた私たち家族の物語だった、アイヌとして生まれた曾祖母は突如日本社会に組み込まれ苦難の人生を生きた。祖母と母は和人を伴侶として子孫は混血を繰り返す。あらゆるアイヌらしさを取り除くことが生き延びるための条件だった、家族の間でアイヌのことが語られたことは一度もない。そうして生きてきた私たちは、自らを語るための言葉を奪われ、そして自ら沈黙してきた。アイヌとして生きることも語ることもできず、しかし日本に特有の結婚差別(血による排除/疎外)がある限り、決して私たちは和人にはなれない。私は、ひとつひとつの過去と現在に言葉を与えることで、私たちの身体が経験した痛みをひとつひとつ辿ってきた。それは失っていた言葉を取り戻すことにつながった。150年の沈黙は長い。その長い沈黙こそが、深く豊かな思索を生み、簡単には消えるこよのない言葉を生みだす土壌となった。ピカートが言ったように、沈黙は創造性と根原性をもつのだ。
私は沈黙をめぐる旅で、沈黙のさまざまなあり方を発見してきた。あるときは、沈黙は隠すことだった。それは社会的な状況がそうさせてもいるだろうし、本人がその事実や背景を恥じていることもあるのかもしれない。沈黙させられることがあってはならない。権力や権威をもって、人を黙らせることは暴力だ。しかし語りたくないことを無理やり語らせることも避けなくてはならない。沈黙する権利は護られなければいけない。
またあるときは、沈黙とは言葉の不在だった。語りづらいことを語りはじめるとき。ぎこちない言葉たちはばらばらとちらばってしまう。語っていても、自分にも語り掛けている相手にも届く言葉がどうしても生まれない。新しい言葉をつかもうと、生み出そうとするならば、身体と一緒に紡ぎださなければいけない。何度も何度も言葉を探し、試し、間違い、そしてまた探す。繰り返し紡ぎ続けることで、譜不在だった言葉が少しずつ彩りを獲得していく。
そうして生まれた言葉たちは、またもや沈黙の領域に押し込められることもある。私はそれを第三項の排除による沈黙と呼んだ。われわれは、物事を二元論的に考える。昼と夜、男と女、大人と子ども。かつての人類はこうした二つの構造のあいだにあるものを恐れたり、崇めたりして、儀礼をして生きていた。もはや儀礼なんてしなくなったわれわれは、「あいだ」にあるものに気がつくことすらできず、秩序に邪魔なものであれば無意識に殺してしまう。アイヌにも和人にもなれない私たちはそのようにして社会の中で消され続けてきた。構造と構造のあいだで消されている人たちが、言葉たちがたくさんあるのだと思う。
私が『沈黙』を著した後に、予期せぬ沈黙の姿に出会った。つながり合う沈黙だ。民族や人種的マイノリティの沈黙のみではない。性的マイノリティ、原発被害や公害被害に遭った人びと、女性として生きづらさを感じる人びとが、自分の痛みや沈黙と私たち家族の物語がつながると言ってくれた。しかしそれだけではない。一見すると社会的に疎外されていないかのように思える人びとも、自らの中に潜む沈黙や痛みを発見したと言ってくれた。われわれが生きる社会は、なんて沈黙が多いのだろう。しかし沈黙は創造性でもある。それぞれの沈黙がつながることは、われわれの社会を照らし出し、互いに疎外し合うことのない未来を展望するきっかけになるのではなかろうか。
人類学では、あいだの時間と空間は、危険で、恐ろしく、魔術的で、しかし自由で、開放的で、新たな活力を生むものでもあるという。言葉が生まれる契機となる沈黙という領域に、そのような解放的な予感を見出していきたい。」
(ロラン バルト『文学の記号学/コレージュ・ド・フランス開講講義』より)
「言語は、その構造自体によって、宿命的な疎外関係をもたらす。話すこと、ましてはや論ずることは、あまりにもしばしば繰り返し言われているように、伝達することではない。それは服従させることである。言語全体は、一個の全面的な制辞法なのである。」
「あらゆる言語活動の遂行形態としての言語は、反動的でも進歩的でもない。言語は、単にファシスト的なのである。というのも、ファシズムとは、何かを言わせまいとするものではなく、何かを強制的に言わせるものだからである。
主体のもっとも奥深い心のうちにおいてさえ、いったん発話されるやいなや、言語は権力に仕えはじめる。言語のうちには、必ず二つの項目が姿を現す。それは、断定からくる権威と、反復からくる群生性とである。一方において、言語はただちに断定的である。否定、疑問、可能性、判断の保留、などを表すには特殊な操作子が必要であり、これらの操作子はといえば、言語的な仮面の戯れに従って付け替えられる。(・・・)他方、言語を構成している記号は、再認されるかぎりにおいてしか存在しない。つまり、反復されるかぎりにおいてしか存在しない。記号は追随主義的であり、群生的なのである。記号という記号のなかには、ステレオタイプというあの怪物が眠っているのだ。私は、言語のうちに散らばっているものを拾い集めないかぎり、決して話すことができない。私が言表しはじるやいなや、以上の二つの項目は、私のなかで一つになり、私は主人であると同時に奴隷となる。私はすでに言われていることを繰り返し、記号の隷属状態のうちに安住しているだけではない。自分が繰り返し言っていることを、主張し、断言し、強調してもいるのだ。
それゆえ、言語のうちにあっては、隷属性と権力とは避けがたく混じりあっているのである・したがって、単に権力からのがれる力だけでなく、またとりわけ、だれをも服従させない力のことを自由と呼ぶなら、自由は言語の外にしかありえない。が、不幸なことに、人間の言語活動に外部はないのだ。それは出口なしである。その外に出るためには、代価として、不可能なことが要求される。」
○石原 真衣(イシハラ マイ)
1982年サッポロ生まれ。母方の祖母がアイヌ、父方の祖母は琴似屯田兵で会津藩士の出自。
アメリカ留学を経て大学卒業後、英語教員として勤務。
北海道大学大学院に進学し博士号取得。
北海道大学アイヌ・先住民研究センター助教。文化人類学。
※主要論文
「「サイレント・アイヌ」を描く──〈沈黙〉を照らすオートエスノグラフィーの可能性」『北海道民族学会』、北海道民族学会、14巻、2018年、1-31頁
The Silent History of Ainu Liminars, Critical Asian Studies Special Issue; Hokkaidō 150:Settler Colonialism and Indigeneity in Modern Japan and Beyond, Vol. 51. No. 4, 2019, pp. 17-21
「われわれの憎悪とは──「140字の世界」によるカタストロフィと沈黙のパンデミック」杉田俊介・櫻井信栄・川村湊(編)『対抗言論 反ヘイトのための交差路1号:ヘイトの時代に対抗する』法政大学出版局、2019年、185-195頁 など
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
