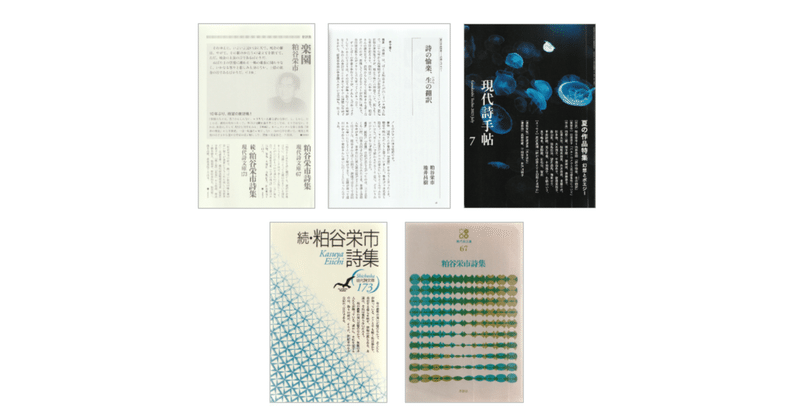
[対談]粕谷栄市+池井昌樹「詩の愉楽、生の翻訳」 (現代詩手帖2023年7月号)/『粕谷栄市詩集』/『続・粕谷栄市詩集』
☆mediopos-3150 2023.7.3
粕谷栄市の10年ぶりの新詩集『楽園』が近々刊行される
(前作は二〇一三年の『瑞兆』)
それにあたって
粕谷栄市と池井昌樹の対談「詩の愉楽、生の翻訳」が
現代詩手帖2023年7月号に掲載されている
雑誌の特集/テーマは「幻想とポエジー」である
嬉しいことに巻頭の作品は
山尾悠子の「バルトロメウス或は蝟集性について」
という連載の第1回目である
(詩というよりは幻想譚ということだろうが
ある意味では物語詩ということでもあるかもしれない)
粕谷栄市の詩や近刊の新詩集についての対談は
これまで40年以上にわたり
その詩を愛読してきた者として得がたい企画である
対談で池井氏が語られているように
そして谷川俊太郎が
「粕谷さんは生を詩に翻訳する」と評してるように
粕谷栄市の詩は
「ファンタジーじゃなくてイマジネーション」であり
そこには「生身の歴史」があり
「血肉の記憶から出発している」
それについて粕谷氏は
「詩を成立させるためには、
それに匹敵する現実認識がないとダメ」だという
そして「ぼくは肉体労働をしている人しか
信用できないところがあ」るともいう
血肉化された身体性がそこに必要だということだろう
粕谷氏の詩の言葉は
表向きには幻想的な物語詩のようにみえるけれど
それらの言葉は
「血肉」「生身」でできているからこそ
そこに不思議なリアリティが感じられるのだろう
そうしたリアリティ感というのは
もちろんベタな現実感というのではなく
生きたイマジネーションによって濾過され
変容されたかたちでのリアリティであり
それゆえにそこに
どこか深いところから訪れる否応のない「現実」と
そこに示される開けとでもいったものが
詩の言葉に「翻訳」されて語られている・・・
新詩集『楽園』は未刊行だが
そこには現在八十八歳の
粕谷栄市にしか訪れない
詩の言葉がひらけているのだろう
楽しみである
ぼくは詩人にはなれないけれど
もし「これを書いたら死んでもいいというような」
「自分の書くべき詩」の言葉が
「向こうからやって」くるときがあれば
そのときこそ詩を書いてみたいものだと思っている
粕谷栄市の現在の歳になるまでには
まだずいぶん時間がありそうだから
■[対談]粕谷栄市+池井昌樹「詩の愉楽、生の翻訳」
(現代詩手帖2023年7月号)
■『粕谷栄市詩集』(現代詩文庫67 思潮社 1976/6)
■『続・粕谷栄市詩集』(現代詩文庫173 思潮社 2003/7)
(『現代詩手帖2023年7月号』〜「Note」より)
「粕谷栄市、池井昌樹の対談は、詩を手で書くということをめぐって同人誌「森羅」の活動について話を聞きたいと数年前から企画をあたためていたもの。今回、粕谷氏の新詩集『楽園』刊行を前に対話が実現した。(F)」
([対談]粕谷栄市+池井昌樹「詩の愉楽、生の翻訳」〜「手で書く」より)
「池井/「森羅」は、ぼくと粕谷さんが出している同人誌で、三十七号から高橋順子さんが参加されています。限定百部の非売品ですが、隔月で年に六冊出ていて、間もなく七年目を迎えます。創刊は二〇一六年十一月九日で、粕谷さんの誕生日です。創刊からしばらくは粕谷さんとぼくだけだったのが、寄稿してくださるゲストが自然に現れて、谷川俊太郎さんがフラリと立ち寄ってくださったり。
ずっとぼくの手書き手作りですが、それもこだわってそうしているというよりは、そのほうが手っ取り早く面倒がなくて、あれこれ余計なことを企てずすぐに詩稿に没頭できるから、産業革命の手業職人みたいな気持ち。決まりごとの少ない自由な場所です。
粕谷/池井さんが最初に「森羅」をやろうと言ったとき、数号で終わるだろうと思っていました。池井ゴッホ先生と粕谷ゴーギャン先生がアルルの家みたいなところでふたりでいたら三号くらいで終わるだろうと(笑)。どういうわけかケンカにならず続けてこられた。」
([対談]粕谷栄市+池井昌樹「詩の愉楽、生の翻訳」〜「粕谷栄市の幻想性」より)
「池井/毎号、粕谷さんの作品を没頭して書写しているのですが、これは活字、文字以前の世界だと感じるんです。これはなんだろうと。今回のテーマが「幻想とポエジー」だそうですが、もし粕谷さんの詩がただの幻想の詩ならば、こんなふうにのめり込むことはないだろうと思う。粕谷さんの詩が、自分はこれを見た、と言っている。そういうところを書写しているうちに、ぼくもそれを確かに見たと感じる。どうしてこういうことが起こるんだろうと考えてみると、粕谷さんの詩は幻想力ではなくて想像力の所産だからではないかと思い。
粕谷さんはご自身の詩をどのように思っていますか。
粕谷/幻想的だと言われることはあるけれど、幻想を書こうと思ったことはないですね。一篇の詩が説得力を持つためにはリアリティが必要で、書いている人間と読者の共通する場所がないと詩は成立しないと思っています。ただし幻想的な要素があると言われれば、それはあると思います。
自分が詩を書いてきたなかでシュルレアリスムの影響が大きかった。ダリとかミロとかキリコ、たくさん作家がいますよね。彼らの作品が影響しているかもしれないですね。とくに『化体』にはそれがつよくあると思います。シュルレアリスムは絵画だけでなく詩の運動でもあったから、言葉の上での跳躍もあるし、そういう時代の流行や影響もあるかもしれません。
「歴程」に入る前は小野十三郎が好きで尊敬していて、影響を受けたと思っているんだけど、誰もそれを言わないから受けてないんだね(笑)。
池井/粕谷さんの詩は、ファンタジーじゃなくてイマジネーションですよね。粕谷さんの幻想には生身の歴史があって、そのなかにさまざまな記憶がいまも生きている。それを粕谷さんが汲み上げているんだと思う。
以前、谷川さんが「粕谷さんは生を詩に翻訳する」と言われましたが、粕谷さんの詩には、幻想という言葉でイメージされるような選択の余地がないんです。生(いのち)の翻訳と言えばいいか。血肉の記憶から出発している。
粕谷/詩というのは、世界認識の裏づけがないと説得力がないわけです。詩を成立させるためには、それに匹敵する現実認識がないとダメなんじゃないかと。幻想って視覚的な効果がひじょうにあるものですから、紙の上にそれを定着させるためにはそれに匹敵する言葉の力が必要になる。それがないと幻想でさえないし、詩が成立しない。
池井/粕谷さんを幻想の詩人として浅く勘違いされたくないですけどね。あとは。やっぱり働きながら書いてこられたことが大きいでしょうね。
粕谷/ぼくは肉体労働をしている人しか信用できないところがあって、いまはペンとパソコンで仕事している人が増えているけど。
池井/文学には重さや容量があって、パソコンでは掴めないものなんですけどね。ことに詩はね。掌に載せて、指先で玩味するものです。優劣や正誤を超えてただ愛でるもの。
粕谷/ぼくの場合、生活のための苦労というのがあって、家業が二律屋という老舗のお茶問屋で、若いときから家族の運命を背負っていた。親父が早く病気になってしまったから高校生の頃からお茶屋の仕事をしていたんですよね。お茶のよしあしを見極める仕事は、詩に通じている。
三十六歳のときに『世界の構造』という第一詩集を出して、それが高見順賞を受賞して、ちょっとした社会現象になってしまった。ところがその後、十五年くらい書かない時期が続いた。このまま死ぬのかなと思っていたら、ある日、猛然と詩が書きたくなったんです。」
([対談]粕谷栄市+池井昌樹「詩の愉楽、生の翻訳」〜「確かにこれを見た」より)
「池井/粕谷さんの詩の「やがて骨身に沁みる酔がやってくる」「行商をやっている男だけが、本当に酔うことができる。本当の一生を生きている。」(一日)といった表現は、詩の言葉なんだけど、言葉以上の大きな悲しみの力、粕谷さんの詩におけるある解決点、すべてが救われる一点のようなものがある。「すべてを見通している弦月」だったり、「どこかに咲いている水仙の花」だったり、粕谷さんの残酷な変身譚とか転落譚のどこかに必ずそういう救いの一点がある。それに触れたときに私は確かにこれを見たという作者の声が聞こえるし、ぼくも確かにこれを見たと答えることができる。
粕谷さんの詩に対する感動というのは一体なんだろうとずっと考えていたのですが、ダリでもミロでもボードレールでもなく森鴎外の『渋江抽斎』に近いと感じた。森鴎外が書いたのは小説とは言えないような伝記でしよね。「渋江抽斎」と名乗らせているけれども、抽斎が主役ではない。大勢の人が亡くなって、大勢の末裔が生まれ育って、その末裔には名もない人もたくさんいて、その末裔がまた育つ。その繰り返しを淡々と記す。その淡々とした客観のなかに、でもどこかのドブ板で私はその大勢の亡くなった誰かの袖とちょっと触れ合った気がする、と。めずらしく作者、鴎外が主観を述べているところがあって、そこにびっくりする。粕谷さんの詩の感動の要点もそこだろうと思います。粕谷さんはよくご自身の詩を卑下されるけど、ぼくにはそれがいつも疑問です。
粕谷/自分の書くべき詩というのがあるわけです。これを書いたら死んでもいいというような詩が。そうじゃないから。池井さんに責められて、締切が来てしまって。泣く泣く終わりにする、こんな悲しいことはない(笑)。いつまでも延長戦をやっていたいんだよね。」
([対談]粕谷栄市+池井昌樹「詩の愉楽、生の翻訳」〜「持ち時間を考える」より)
「池井/今回の詩集に収録される「森羅」の作品をまとめて読んでつよく思ったことは、たとえば粕谷さんの『鄙歌』『轉落』の時期の詩集にくらべて、ここまで書くんだという、作者がこちらから書きにいったのではなくて、詩が向こうからやってきているのを感じます。粕谷さんの最近の詩は、読んでいるというよりも逆に詩に見られているような感じがする。詩が見ている、見入られている。何か怖ろしいような。これはなんだろうと思う。
粕谷/それはぼくにはわかることじゃないけど、『鄙歌』『轉落』は七十代から前の作品で、「森羅」の作品は八十二歳からあとでしょう。一番考えるのは自分の持ち時間のことですよね。この歳で詩を書いている詩人が、とても少なくなってしまった。九十五とか百まで詩を書いていられるとは思えないし、生きているかどうかもわからない。いま書いていることはその持ち時間のなかでやっていることだという意識がつよくあります。ブラマンクの言う「死ぬ前の肖像」だね。そういう感じで詩を書いていることは変なことだけど、現実にそうだから、こういうことがあるんだな、と。これは八十八歳で詩を書いている人間にしかわからないと思う。」
(『粕谷栄市詩集』より)
(谷川俊太郎)
「粕谷さんは生を詩に翻訳する。選択の余地はない。言語によって人間の生きている現実をとらえようとすれば、少なくとも彼にとって、それがただひとつの途なのだ。この宇宙に存在する物質がそれ自身の引力で、光すら曲げてしまうように、粕谷さんの想像力は絶えず現実の引力によって曲げられる。そのせっぱつまった曲率こそが詩だ。ミショーの詩を〈生きゆくための詩〉と呼んだ粕谷さんは、現実というブラック・ホールの謎と恐怖を誰よりも知っているにちがいない。」
(『続・粕谷栄市詩集』より)
(松浦寿輝)
「一度か二度、車で古河を通過したことがある。この町に現代日本の最高の詩人が茶舗を営みつつ静かに暮らしているのだと考えると、何やら奇妙な感慨が込み上げてきたが、それが言葉にならないうちに車はあっという間に町の外に出てしまった。粕谷栄市の死は、酸っぱい狂気の味と血の甘い馥りが濃密に立ち込めた美しい反世界だ。陸橋の上では帽子と外套だけになった透明な老人たちが微かに笑い、劇場の舞台では奇術師が巨大な卵と化しそのつど死んでみせる。小さな歪んだ部屋では逆さに吊られた馬が恐怖の瞳を見開き、皿に載った幼女の下着は毒のある白鱏の料理へとゆっくり変化してゆく。詩人はそれらすべてを「生きて」いるのだ、「他人には、全てが、邪悪な偽りだったとしても、私は、私を生きなければならない。私は、私を、生きなければならないのだ。」
◎粕谷/栄市
1934年茨城県古河市に生まれる。現在まで同地に居住。1956年、早稲田大学商学部卒業。在学中「早稲田詩人会」所属。1957年「ロシナンテ」参加。石原吉郎を知る。1972年「歴程」同人となる。1995年、高貝弘也、江代充、法橋太郎と「幽明」創刊。著作に、1971年詩集『世界の構造』(詩学社)第2回高見順賞受賞。1976年現代詩文庫『粕谷栄市詩集』(思潮社)。1989年詩集『悪霊』(思潮社)第27回藤村記念歴程賞受賞。1992年詩集『鏡と街』(思潮社)。1999年詩集『化体』(思潮社)第15回詩歌文学館賞受賞。現在「歴程」同人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
○著書
『世界の構造』詩学社、1970年。
『粕谷栄市詩集』思潮社〈現代詩文庫〉、1976年。
『詩集 悪霊』思潮社、1989年。
『鏡と街』思潮社、1992年。
『化体』思潮社、1999年。
『続・粕谷栄市詩集』思潮社〈現代史文庫〉、2003年。
『轉落』思潮社 2004
『鄙唄』書肆山田 2004
『遠い川』思潮社、2010年。
『瑞兆』思潮社、2013年。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
