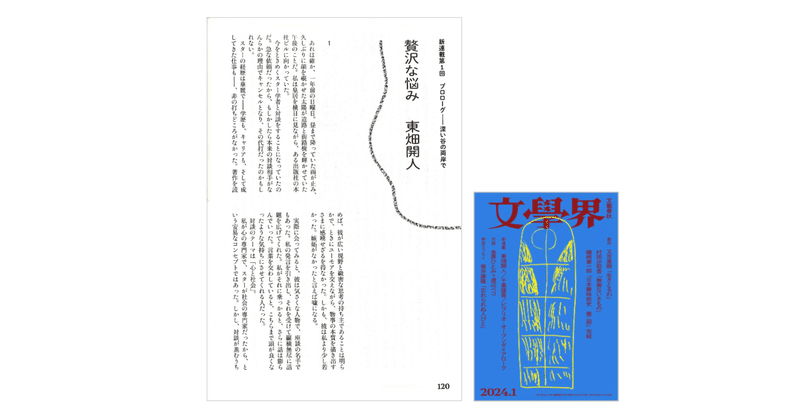
東畑開人「贅沢な悩み」「新連載第1回 プロローグ――深い谷の両岸で」(文學界 2024年1月号)
☆mediopos3310 2023.12.10
「文學界」(2024年1月号)で
心理療法家の東畑開人の連載
「贅沢な悩み」が始まっている
東畑開人はある(スター)社会学者との対談を終えたあと
ともに東京の中学受験に落ちた話を共有することで
親密な会話をしていたのだが
若き編集者の言葉に水を差され我に返る
「私とスターが舐め合っていた甘美な傷は、
恵まれた環境においてのみ成立する
「お坊ちゃん」たちの苦労話に過ぎなかった。」
ということに気づかされ
「親密だった内輪ネタは急に社会へと開かれ」
そこにあった社会的文脈が明るみに出され」ることに
そこで「スターは自嘲気味に」言う
「まあ、贅沢な悩みなんですよ」
しかし東畑氏はその後
「贅沢な悩みとは何か」について考え
それは「贅沢な悩み」ではなく
「それこそが心じゃないか」と捉えるようになる
「社会的には取るに足らないことでも、
個人にとっては切実でありうる。
外からはうかがい知れない内面の苦しみ、
それこそが心じゃないか。」と
そこでは「心とは何か。社会とは何か。」
そして「その二つの間にある深い谷の奥には
一体何があるのか。」という問いが示唆されている
「「お坊ちゃん」たちの苦労話」は
「社会」からみれば
「恵まれた環境においてのみ成立する」
甘味な傷とその舐め合いだろうが
「心」からみれば切実であり
「そこには家族の呪いがあり、
人に言えない地獄があり、
誰にもわかってもらえない後遺症がある。そ
して、そういうものが心を損なっていく。
あるいは個性を作っていく。」のだ
「贅沢な悩み」だというのは
「社会」からみた視点であって
「心」からみたそれではない
そのように心と社会のあいだには「深い谷」がある
東畑氏は人間の苦悩は
心の問題でも社会の問題でもあるが
ルビンの壺のように
「どちらかにしか焦点を合わせられない」で
「心と社会のどちらかに寄りすぎてしまう」という
この連載ではその
「深い谷の奥には一体何があるのか。」
という謎に取り組んでいくというが
個人的にふりかえってみても
少しばかり興味をひかれる謎である
ぼくはどちらかというと
「お坊ちゃん」とはまったく逆の立場で
育ってきたところがあって
どちらかといえば「お坊ちゃん」たちに
少しばかり辛い皮肉な視点を投げてしまうところがある
以前そうしたネットのなかで
「お坊ちゃん」的な方の発した
「甘やかされたものの気持ちがわかるか?」
という「名言」に笑いつつも
妙に納得させられたことがあるのだが
その「お坊ちゃん」や「甘やかし」というのも
心と社会との「深い谷」にあるなにかが
そうした表現をとらせているのかもしれない
この連載とともにぼくも
「深い谷の奥には一体何があるのか。」について
問いを深めていければと思っている
そこにはおそらくぼくじしんのなかに潜んでいる
屈折したある種のルサンチマンを問いなおすことにも
つながってくるだろうからである
■東畑開人「贅沢な悩み」
「新連載第1回 プロローグ――深い谷の両岸で」
(文學界 2024年1月号)
「心と社会には水と油のように相容れないところがある。それらはコップの中に置かれるならば、分離して、層構造を成す。あるいは熱して状態でかき混ぜようとするならば、互いに反発して、炸裂する。一方を見ようとすれば、他方が見失われてしまうのだ。
もちろん、心は常に社会の中にあって、社会は心たちによって構成されている。社会が心を作り、その心が今度は社会を造り出す。かつてマルクスとフロイトを綜合しようとしたエーリッヒ・フロムが見抜いた通りだ。心と社会は循環する。だから、個々人の心を治療することは社会を治療することにつながっていくはずだし、社会が改善されるならば、心に善き影響を与えるはずだ。少なくとも、理論的にはそうだ。
しかし、プラクティカルな次元になると、話は変わってくる。具体的な事案のことを考えるならば、話は複雑になる。ある人が苦しんでいるとき、それを社会の問題と捉えるか、心の問題と捉えるかで、そこでの介入や予後は大きく変わっていくからだ。
たとえば、社会運動を継続していくためにはある種の怒りが必要だが、その怒りが社会の歪みではなく、個人の生育歴がもたらされたものだと見て、心理療法がなされるならば、社会運動へのモチベーションは下がってしまうかもしれない。逆に、心に刻まれた傷つきが社会のせいだとされるときには、そこにあった複雑な生い立ちとそれに対するアンビバレントな思いは背景に退いてしまいやすい。
もちりん、ほとんどの場合、苦悩は個人的なものでもあり、社会的なものでもある。心と社会はいつだって渾然一体となって存在している。しかし、その混合物を「心が32%、社会が68%」という風に正確に切り分けることはできない。人間の苦悩は水溶液ではない。
ルビンの壺みたいなものだ。あの心理学史上最も有名な絵は、壺に見ることもできれば、対面している二人の横顔に見ることもできる。しかし、私たちは壺と横顔を同時に見ることはできない。図と地。私たちのまなざしはその都度、どちらか一方しか捉えられない。
同じように、人間の苦悩は心の問題でもあるし、社会の問題であるにしても、私たちの目はその瞬間瞬間には、心と社会のどちらかにしか焦点を合わせられない。だから、治療を試みようとするとき、あるいはなんらかの問題を考えようとするとき、私たちはいつだって心と社会のどちらかに寄りすぎてしまう。
心と社会には断絶がある。溝がある。深い谷がある。」
*******
「あれは確か、一年前の日曜日。」
「今をときめくスター学者と対談をするこよになっていたのだ。」
「対談のテーマは「心と社会」。
私が心の専門家で、スターが社会の専門家だったから、という安易なコンセプトではあった。しかし、対談が進むうちに、「心を治療すること」と「社会を治療すること」、つまり心理療法と社会運動の対比へと話題は収斂していった。そして、これが実に不穏なテーマであることがわかってきた。」
「対談の時間は瞬く間に過ぎた。結論が出るわけではなく、提言が導かれたわけでもない。心と社会は断絶したままだった。そういうものだ。対話とは、問いを持ち帰るためになされるものだ。心理療法と同じだ。結局のところ、自分の中で問いを熟成させるために、私たちは誰かと喋るのである。」
「さて、問題はその後だ。
対談の収録を終えてから、編集者も含めて、しばし世間話をする流れになった。(・・・)
その間、私はずっとタイミングを窺っていた。ひとつだけ、どうしても訊いてみたいことがあったのだ。(・・・)
私は尋ねた。
「Aさんって、東京出身ですよね? 中学ってどこに行かれていたんですか?」
彼は少し表情を曇らせた。
「○○中学ですよ」
(・・・)
「中学受験されたんですよね。そこって第1志望だったんですか?」
「違います。第1志望も第2志望も落ちたんです」
(・・・)
それは私も昔落ちた学校だった。
「そこ、僕も落ちたんですよ」
そう伝えると、スターは突如満面の笑みを浮かべた。
「え? 本当ですか? じゃあ、中学はどこに行ったんですか?」
ここからは楽しかった。思い出話が花開き、深い谷に橋が架かったのだ。東京の中学受験にあった苦しさや悲しさ、そして切なさが語り合われた。そこには同じ傷つきを抱えた者同士のローカルな親近感があって、スタートそてをシェアできることには喜びがあった。
(・・・)
でも、幸福な時間は長くは続かない。突如、水が差される。
傍らで聞いていた若い編集者が言ったのだ。
「へー、お二人にもそういう経験があるんですね。東京の中学受験文化って、話には聞くんですけど、よくわからなかったんです。僕は地方なので、全然縁がなかったから」」
「親密だった内輪ネタは急に社会へと開かれた。そこにあった社会的文脈が明るみに出されたのだ。
中学受験が可能であることの背景には、家庭に蓄積された経済的な余裕があり、親自身が受けてきた教育の厚みや文化資本がある。無論、都市部でなければ、そもそも受験という選択肢自体が存在しない。
私とスターが舐め合っていた甘美な傷は、恵まれた環境においてのみ成立する「お坊ちゃん」たちの苦労話に過ぎなかった。編集者の一言で、私たちは我に返らざるをえなかった。
だから、スターは自嘲気味に言った。
「まあ、贅沢な悩みなんですよ」
その場にいたみんなが笑った。私は笑ったふりをしていた。世間話は幕を閉じ、架かっていた橋はそこで途切れた。」
*******
「「贅沢な悩み・・・・・・なのだろうか?」
そう、スターの最後の言葉に私はひっかかっていたのだ。
しかし、すかさず、別の頃が時ビク。
「そうなのだろう。たしかに、それは社会的には取るに足らない不幸だ」
私たちの社会には日々生存が脅かされるような、切実な悩みが存在している。暴力が吹き荒れていて、切迫した欠乏が満ち溢れている。それらの危機に比べたら、私たちの中学受験の失敗など、砂糖菓子のような喜劇でしかない。しかも、それはすでに過ぎ去り、社会的にはなんらかの形で回復されたものなのだ。
「そう、贅沢な悩み・・・・・・なのだろう」」
「「いや、違う」
私の奥の方から言葉がせりあがってくる。今度は前よりも力強い。
「だって、それこそが心じゃないか」
社会的には取るに足らないことでも、個人にとっては切実でありうる。外からはうかがい知れない内面の苦しみ、それこそが心じゃないか。
そして、ときにその誰にも理解されない切実さが、生活を破壊し、人生を空虚にしてしまうことがある。絶望を蔓延させ、最悪を選ばせることだってある。だからこそ、心理療法家という個人的な切実さに耳を傾ける職業が存在するんじゃないのか?
私たちの中学受験だって同じだ。少なくとも私はそうだ。それは社会から見たらお坊ちゃんの苦労話にしか過ぎないのかもしれないが、そこには家族の呪いがあり、人に言えない地獄があり、誰にもわかってもらえない後遺症がある。そして、そういうものが心を損なっていく。あるいは個性を作っていく。」
「ここから、この連載は出発する。
贅沢な悩みとは何か。
この問いには、一群の本質的な問いたちが孕まれている。
心とは何か。社会とは何か。そして、その二つの間にある深い谷の奥には一体何があるのか。
それこそが、これから私たちが取り組もうとしている謎である。」
□東畑 開人
1983年東京生まれ。専門は、臨床心理学・精神分析・医療人類学。京都大学教育学部卒、京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。精神科クリニックでの勤務と、十文字学園女子大学准教授を経て「白金高輪カウンセリングルーム」主宰。博士(教育学)・臨床心理士。
著書に『野の医者は笑う―心の治療とは何か』(誠信書房2015)『日本のありふれた心理療法―ローカルな日常臨床のための心理学と医療人類学』(誠信書房2017)『居るのはつらいよ―ケアとセラピーについての覚書』(医学書院 2019)、『心はどこへ消えた?』(文藝春秋 2021)、『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』(新潮社 2022)、『聞く聞く技術 聞いてもらう技術』(筑摩書房 2022)など。訳書にDavies『心理療法家の人類学―心の専門家はいかにして作られるのか』(誠信書房 2018) Robertson『認知行動療法の哲学』(金剛出版 2022)。2019年、『居るのはつらいよ』で第19回大佛次郎論壇賞受賞、紀伊国屋じんぶん大賞2020受賞。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
