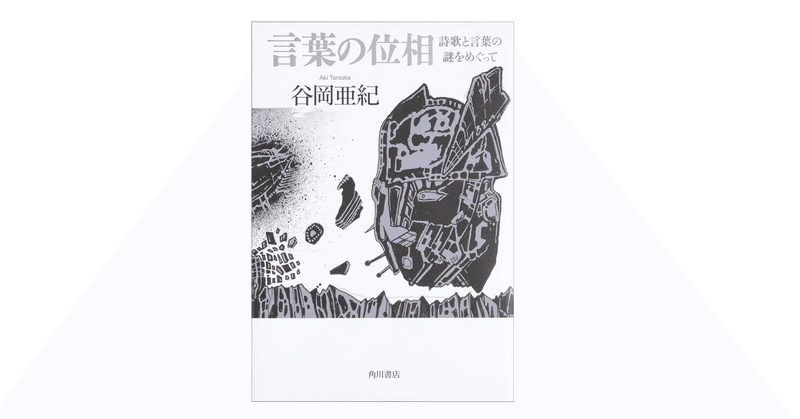
谷岡亜紀『言葉の位相/詩歌と言葉の謎をめぐって』
☆mediopos3347 2024.1.16
五年程前の刊行だが
歌誌「心の花」での長期連載(コラム)が
「言葉の位相」(1〜102)としてまとめられている
そのなかから
「仮名遣いをめぐる冒険」(1〜32)をとりあげる
ここで主に扱われているのは
文語/口語という文法の問題と
旧仮名/新仮名という仮名遣いの問題である
主に短歌における表現の問題として論じられているが
現代において日本語を話し書く人間にとって
理解しておく必要のある事柄が
コンパクトにまとめられ論じられている
まず文語/口語という文法だが
「文語」とは書き言葉(文章語)
「口語」とは話し言葉(会話語)を意味するが
そこには三つのレベルの言葉が混在している
まず平安時代の語法を規範とした
旧い書き言葉である「文語」(文語文)
話し言葉を元に明治以降に作られた
新しい書き言葉「口語」(口語文)
そして「生活の現場で日常的に話される
(文字どおりの)「会話語」である
表記には中国の漢字(真名)
そしてそれをもとに作られた仮名(片仮名・平仮名)にょり
漢字仮名混じり文という形で「文語」として書かれた
明治になると話し言葉の統一をはかることが求められたが
言文一致としての共通語が制定されたのは
ようやく大正二年になってからのこと
しかしその後も文語/口語のねじれは
とりわけ和歌における表現において現在まで続いている
続いて旧仮名/新仮名という仮名遣いだが
日本語においていちばん最初に
仮名文字の運用規則である「仮名遣い」を
制定する役割を担ったのは藤原定家であり
それは「定家仮名遣い」と呼ばれ
その後それが江戸時代になって
契沖がその誤りを正し仮名遣いの規範が確定される
その後仮名遣いは
昭和二十一年の「新仮名遣い」の制定による変更されたが
その改変の基本理念は
「仮名とはあくまで発音を表す表音文字である」
ということである
いうまでもなく「規則」には例外があり
解決しがたい問題が存在する
「文法とは本来、言葉自体に先んじて存在する
憲法や法律のようなものではな」く
「まずは言葉ありき」だからである
そして「言文一致」とはいっても
言葉は変わり続けているため
既存の「文法」からなにがしか逸脱せざるをえない
「和歌」における言葉の使用が興味深いのは
通常の現代語使用の際にはあまり必要とされない
歴史的な仮名遣いが存在するということである
その背景には万葉集・古今和歌集以来の
日本語(表記)の豊かな歴史が内包されている
近年においては英語表現等も
日本語に組み込まれてきているが
日本語という言語が豊かになるか貧しくなるかは
それが表面的なものにとどまらず
その奥行きを持ち得るかどうかではないだろうか
和歌(短歌)や俳句が重要なのは
それにかかわる人たちの裾野の広さとともに
そこで用いられる言葉への視点が
日本語の豊かさを担保し得るところにあるだろう
そこには自動翻訳機でも可能なような
単なる実用的なコミュニケーションの言葉では
得られない言葉の豊かさの可能性が秘められている
■谷岡亜紀『言葉の位相/詩歌と言葉の謎をめぐって』
(KADOKAWA 2018/12)
(「言葉の位相 3 文語文法あれこれ」より)
「文法とは本来、言葉自体に先んじて存在する憲法や法律のようなものではないだろう。まずは言葉ありきである。たとえば短歌語法の基本とされる「文語」文法とは、平安時代の(限られた階級の限られた場所における)実際の言葉の運用を検証して、そこに法則性を見出した規範と言うべきものである。もう少し細かく言えば「平安時代の言語体系を基本にして、奈良時代以前の要素を加味したもの」(安田純正『現代短歌のことば』)ということらしいが、平安時代の現場の言葉を基本として成立したものであることに変わりはないだろう。とすると、万葉の時代の言葉は厳密には「文語文法」ではないわけである。だから「美(うま)し国」「ながながし夜」というふうな、終止形で連体修飾する例が上古には有り得たのだと理解すると、納得がいく。
平安時代は書き言葉が話し言葉がほぼ同じ、つまりほぼ言文一致だった(むろん文字が欠ける都の一握りの階級に限られた話だが)という。「けるかも」とか「なりにき」とか喋っていたわけである。これもちょっと驚く。むろん話し言葉と書き言葉が全く同一だった、ということはないだろうが、「古今集」は「口語」歌集であった、と言っても間違いではないことになる。ちなみにイントネーションも、現在の標準語や東京言葉とは明らかに違っていただろう。(・・・)普通に考えれば京都弁や関西弁に近かったと考えるのが合理的だ。」
「平安時代の語法であり文語文法が、その後これほどまで長く規範となった大きな理由は「源氏物語」と「古今和歌集」(以下、古今集)だろう。特に和歌の規範としてんお「古今集」の存在は絶大だ。だからこそそれに続く勅撰和歌集は「後撰集」「拾遺集」と名付けられた。あくまでも「古今集」の「後撰」であり、「拾遺」なのだ。そして「新・古今」「続・古今」だらには「新・続・古今」などという勅撰和歌集も生まれたのだった。「古今集」は、まこと長きにわたって和歌の手本であり元祖だった。その美的世界の真髄をわれわれは現在。花札に見ることができる。紅葉と鹿。すすきと満月。花札をやくざな博打の道具と軽んじてはいけない。
だから「古今集」を手本とする和歌が、その語法である文語文法を尊び遵守したのはよくわかる。だが近代以降ではどうか。明治の和歌革新の理念は和歌的な世界の否定と革新だった。なのに、一方では「古今集はくだらぬ集」と言いつつ、相変わらずその語法を模倣することには、一つの矛盾、ねじれがある。」
(「言葉の位相 4 文語という迷宮」より)
「古文を読むのに、その規範言語である文語文法を基準とするのはまったく当然である。問題はいまを生きる我々が、いまの我々の生活に根ざす「近代・現代」短歌を読み、作るときに、どこまで「文語」を絶対視するかである。ただし、明治になって登場した口語文法以外には、現実的に文語文法しか体系的な規範がないこともまた確かだ。我々が「口語文法」と呼ぶものは「国家を統一するには、日本のどこでも通用する話し言葉の制定がまず何より必要」(山口仲美『日本語の歴史』)とかの政治的・国家的理念から、いわば人工的に作られた言語体系である。ここにおいて我々は、文語か口語かというハムレット的二元論で懊悩することを運命づけられる。こんなことは和歌の時代の歌人にはなかった。古典学者・国語学者を除いては、近・現代歌人(と俳人)だけが、こんな手に余る問題に日々直面することになっている。これを理不尽と言うべきか、試練という呼ぶべきか。
文法の問題はとかく、「正しい」か「間違い」か、白か黒かという議論になりやすい。厳密さと柔軟さの加減が難しい。(・・・)学問的に厳密であろうとすると、逆に柔軟に対応せざるお得ないところに、我々の〈文語〉の今がある。」
(「言葉の位相 6 「口語」夜明け前」より)
「元々は、文語とは書き言葉(文章語)、また口語とは話し言葉(会話語)の意味だが、現実はもう少し複雑だ。実際には三つのレベルの言葉が混在している。まず平安時代の語法を規範とした旧い書き言葉である「文語」(文語文)、話し言葉を元に明治以降に作られた新しい書き言葉「口語」(口語文)、そして生活の現場で日常的に話される(文字どおりの)「会話語」である。古代、日本には書き言葉(文字)がなかった。それで先進国である中国大陸の文字=漢字を借りた。すなわち、我が国最初の書き言葉は中国語(漢字)だった。以後、漢文は長く正式文書として用いられ、それを読み書き出来ることが、エリートの条件ともされた。そののち中国の文字(漢字)から仮名が作られ、漢字仮名混じり文という形で、当時の話し言葉が文章語化された。これが文語ということになる。実にややこしいが、文語とは平安期における口語(口語文=話し言葉に基づく新しい書き言葉の規範)だったのである。
やがて、その「新しい書き言葉の規範」は時代と共に古びて、日常的な話し言葉と大きく離れて行き、ついに明治になって再度の言文一致と「共通語」の必要が叫ばれた。」
「言語の全国統一は、まず話し言葉の統一から始められた。全国で通じる平易な話事が=「共通語」の制定である(書き言葉が後回しになったのは当時の識字率と関係すると思われる)、いずれにしろ、そこでどのような言葉を基準とするかが問題となった。(・・・)ともかく様々な議論の後、東京の中流社会の言葉=山の手言葉を基準とすることが法的に最終決定されたのは大正二年。明治新政府になってから実に四十五年かかったという。
そうした公的な動きの遅さに先んじて、新しい共通語としての口語を牽引したのは文学者だった。まず小説。さらに文語の牙城とも言える短歌でも、明治末から大正にかけて口語運動が大ブレイクしてゆく。」
(「言葉の位相 8 文法はむつかしい1」より)
「私の経験からも、選歌や歌会、市民短歌講座やカルチャーセンターなど、歌の現場で出会う文法上の問題(あえて「間違い」「誤り」という言葉は避けておきたい)んは、一定のパターンがあるようだ。逆に言えば、そこだけ押さえておけば、ほぼ文語文法と無難に付き合える要点でもある。
まず、過去の助動詞「き」(特にその連体形「し」)にまつわる問題。一番多いのは、たとえば「晴れた空」の「た」の代用として機械的に「し」が使われる用例だろう。すなわち「晴れし空」。「き(し)」は過去(回想)の助動詞というくらいで、最低限、一定の時間経過が必要とされる。(・・・)この助動詞「き」にはもう一つ、(過去ではなく)現在の発見・驚きを表す用例も指摘されている。その女性はなんと「エリスなりき」(森鴎外『舞姫』)といった形である。」
「次に過去の「し」がサ変とカ変に付く場合。まず「せし」と「しし」。教科書的にはサ変は「せし」(為し)、四段(で語尾が「す」の動詞)では「しし」と使い分ける。「議論せし」「決闘せし」・・・・・・。「残しし」「話しし」「乱しし」という具体に。ただし連体形が「議論せし」ならば、理屈としてはその終止形「議論せき」もあってしかるべきだが「為き」という用例にお目にかかったことはない。不思議だ。
次にカ変と結び付いた「来し」。これを「きし」と読むのか「こし」と読むのかなかなか悩ましいが、安田純正は「それは誤りだからよくないとか、こうしなければならないとか、いっているのではない」と断ったうえで、歴史的には「キシとならずコシとなるのが原則」だったと述べる。(・・・)なお、「来し」の終止形は、やはり理屈では「来き」だが、私は見た事がない。う〜ん。
過去の「き」の次に問題となるのが、完了の助動詞「り」。文語の助動詞には「つ」「ぬ」「たり」「り」があるが、「り」が最もクセがあり、サ変に付く「せ(為)り」以外は四段動詞の未然形のみに付く(「思へり」等)とされる。下二段活用に無理やり付けた「耐えり」「終えり」「植えり」「食べり」等々は、何よりも美学の問題としてみっともない気がする。」
(「言葉の位相 9 文法はむつかしい2」より)
「教室などでよく見る形容詞の困った用例は「高ける」「美しけり」といった形。ややこしいが形容詞の活用は「けれ」か「かり」のみで「けり」は無い。「けり」は伝聞過去の助動詞で、形容詞に付く時は「高かりかり」「美しかりけり」となる。」
「安田純正は『現代短歌のことば』の中で「集めり」など、下二段動詞に、本来付かない完了の助動詞「り」が付いた「誤用」について、そうした例は中世では珍しくないと言い、「誤用であるとしておm、九百年ほど前から存在した、いわば由緒ある誤用なのである」と述べている。」
「雑誌の特集などで「作歌のための文語文法」みたいなのを見る。そこには、これはこうと断定的に羅列するだけで、なぜそうなのか、例外はないのかといった探求がない。決まっているから、というのは読者も迷いがなくて楽だが、じゃあいつ誰が決めたんだろう。そこで思考停止しては文法の醍醐味には到達できない。「教科書文法」は本来、文法の入口にしか過ぎないだおる。〈正しい文語文法〉とはひとつの幻想であり、文法とはもっとしなやかでやっかいで奥深いものだと思う。「一般に国語の先生は文法が好きでない」(『日本語の文法を考える』)。大野晋の言葉である。」
(「言葉の位相 14 文語と口語、まとめとして2」より)
「本来は和歌革新運動では、まっ先に用語改革の徹底(つまり言文一致=口語化)をすべきだったかもしれない。少なくともその時点が、文語/口語のねじれを解消する最大のチャンスではあって。だがそうはならなかった。まざその段階では、明治新政府の国策である、言文一致による新しい国語(口語文)の制定作業が、追いついていなかったのだった。それで現在まで、なんとなく曖昧なまま来てしまった。」
「このように書くと強硬な口語化推進論者のように聞こえるかもしれないが、違う。実際に歌を作る場面では、文語脈ならではの利点を感じることも多い。私の現時点での個人的な立場は、いわばソフトな文語脈を基本としつつ、時き口語を織り交ぜる折衷派、柔軟派である。いや私だけではない、現在多くの歌人がそのような現実的な選択をしている。そこに短歌の現在がある。」
「文語を用いる上での最大のネックは、上二段・下二段動詞の扱いだ。浴ぶ・浴ぶる、始む・始むる、食ぶ・食ぶる。その終止形と連体形は、現在かなり奇異に響く。さらに「跳びはぬ(る)」「夕焼く(る)」といった複合動詞になると、奇異な感覚はいよいよ強まる。「引っ掛ける」なんていう語を無理に文語にしようとすれば終止形は「引っ掛く」、「引っ掛くる」であr。「おもしろ過ぎる」「楽し過ぎる」の終止形に至っては「おもしろ過ぐ」「楽し過ぐ」・・・・・・まさにおもしろすぎる。
いずれにしても、上二段・下二段動詞が口語と文語の落差を最も印象づける。」
(「言葉の位相 15 仮名遣いをめぐる冒険1」より)
「短歌においては、文語/口語という文法の問題と並んで、旧仮名/新仮名という仮名遣いの問題が、話を非常にややこしくしている。定型による音数制限と併せてこの三つを「短歌の三重苦」と呼ぶ人もいるらしい。というのはもちろん冗談だが(少なくとも定型は恩寵である。(・・・))。ではわれわれは仮名遣いの真実について、それだけ知っているだろうか。」
(「言葉の位相 16 仮名遣いをめぐる冒険2」より)
「仮名文字の運用規則である「仮名遣い」はいつどのように成立したのか。(・・・)実はわれわれが「旧仮名遣い」と呼ぶ、伝統的な仮名文字運用の規則・規範が確定されたのは、なんと江戸時代(!)である。(・・・)
仮名文字の運用規則である「仮名遣い」。その制定に大きな役割を果たしたのは、われれが藤原定家である。(・・・)定家が整理・策定した仮名遣いの法則は、「定家仮名遣い」と呼ばれる。それまで実は哉の運用には特に普遍的絶対的な規則がなく、かなりアバウトなものだったらしい。」
「「定家仮名遣い」は行阿の『仮名文字遣』という書物によって増補され、江戸時代に契沖がその誤りを正して仮名遣いの規範を確定するまで、広く信奉されてゆく。」
(「言葉の位相 17 仮名遣いをめぐる冒険3」より)
「そしてそれからわずか二百五十一年。仮名遣いにとって革命的なことが再び起こる。昭和二十一年の「新仮名遣い」(・・・)の制定である。何せそれまで用いたり学校で教えたりしていた仮名の運用の約束を、一気に新しいものに変更すると政府が言いだした(というか強制した)のだった。教科書も新聞も出版物も個人的な手紙も何もかも、ともかく今日から新しい言葉遣いで書け、というわけである。」
「その「新仮名遣い」への改変の基本理念は〈仮名とはあくまで発音を表す表音文字である〉という原点に立ち戻ることにあった。一例をあげれば現在「ぢ」と「じ」はともに、日本語ローマ字表記におけるZI(またはJI)と発音し、「づ」と「ず」はともにZUと発音しているが、当初はそうではなかった。「ざ」行のZ音に対して、「だ」行はすべてD音、つまり「ぢ」はDI(ディ)、「づ」はDU(ドゥ)と発音していた。発音が違うからこそ仮名表記が「ぢ」と「じ」、「づ」と「ず」二つに分かれているのだ。
ところがいつからか発音が変化して、現在のように「づ」も「ず」も同じZ音系列の発音になってしまった。そうなればもはやDUという発音を表す仮名「づ」は必要なく、本来のZUに対応すうr「ず」だけでいい、また表音文字という原点からもそうすべきである、ということでなされたのが「新仮名遣い」への広範な変更だった。「ゐ」(WI)から「い」(I)への変更、{ゑ」(WE)かえあ「え」(E)への変更、「ふ」(FU)から「う」(U)への変更も然り。つまり簡単に言えば、ずれてしまった発音を現状に合わせる(可能な限り近付ける)、というのが、この昭和二十一年の国語大改革の骨子である。」
(「言葉の位相 20 仮名遣いをめぐる冒険5」より)
「現在、短歌が直面する旧仮名遣いのややこしさも、まさに「表音」文字という部分に起因する。現場の発音院基づいているので明確な法則性がない。「青」に何故「あを」と仮名を振るかと言えば、旧い時代に単にそう発音していたからである。現実が先であり、そこに法則性は生じようがない。場当たり的だからややこしい。
だが次第にその発音も変化し始める。いくつかの古い発音は早く平安時代から変化を始め。それ以降も様々な発音が時代につれて段階的に変化した(白石良夫『かなづかい入門』)という。しかし、書き言葉は規範性が強いので、おいそれとは変化しない。そこにズレが生じる。フットワークがよく現場に密着して軽やかに変化する話し言葉と、いかめしく保守的な書き言葉。(・・・)その乖離を解消しようとしたのが、文法では文語文法から口語文法への大改革であり。仮名遣いでは、旧仮名遣い(歴史的仮名遣い)から新仮名遣い(現代仮名遣い)への一大改革だった。
だが、およろそのような改革でも、完璧ということはなかなかなお。「改正」と銘打たれて成立した新仮名遣いにも、どうしてもいくつかの矛盾点た錯綜部分が見えてくる。それを現在急先鋒として批判している一人が丸谷才一である。」
(「言葉の位相 30 仮名遣いの課題1」より)
「仮名表記と発音との乖離をなんとか修復し、仮名と発音を可能な限り近付けるというのは、旧仮名遣いから新仮名遣いへの一大改革の最大の骨子であり理念だった。幾度も述べてきた通り「表音文字」であるというのは「仮名」のアイデンティティである。であれば新仮名遣い/旧仮名遣いの論考には、是非その視座を加えて、さらに議論を進めてもらたいと思う。
もう一点、これもこのコラムで繰り返した「字音仮名遣い」の問題。さすがに武藤康史が「字音語旧かな」表記への疑義を提出しているが、なんtなく敬遠された感がある。旧仮名遣いの歌で「さざんくわ」か「さざんか」か「れんげう」か「れんぎょう」か。これは「旧かな派」の歌作にすぐにも直結する待ったなしの大問題である。」
(「言葉の位相 32 仮名遣いの課題3」より)
「文語文法という、現代社会では想定外の語法を基礎とする短歌において、仮名遣いの問題に(新旧ともに)曖昧さが残るのは当たり前だる。特に一部の旧仮名遣いについては学者にも諸説があり、それが辞書にも反映されて、ハギ例の悪い記述が散見される。」
「仮名遣いがそのように曖昧な部分を残すことを知った上で、ではどういう対応を取るか。最も現実的な選択は、最新の研究成果が反映された複数の辞典辞書に当たることだろう。辞書によって表記が割れる時は・・・・・・仕方ない、多数決である。一国の言語の問題を一現場の判断で決定することはできない以上それはいたしかたない。
大勢につく、無難な方につく、と言えば言葉は悪いが、もともと「言葉」はそういう要素を持つ。仮名遣いや文法は、どちらの用例が多いか(一般的か)という多数決によるマニュアルでありガイドラインであり、慣例であり有用な方便なのだ。しかも文語文法も旧仮名遣いも、時代に流通する表現であるために。或る意味時代の変化とともに微妙に変えて来ている。それを便宜的と言えばそうだが、その柔軟性(丸谷才一流に言えば「複数の正しさ」)も、言葉の大きな特性だろう。だからそれを運用する我々も、グレイゾーンを認め、そのフレキシブルでファジーな特性に応じた柔軟な許容性を持つべきだろう。」
○谷岡 亜紀
1959年11月19日、高知県高知市生まれ。父は美術教師。高知学芸高等学校卒業後、19歳で上京。1980年、「心の花」に入会し、佐佐木幸綱に師事。同門の俵万智らと交友を持つ。早稲田大学第一文学部哲学科中退。1987年、『「ライトヴァース」の残した問題』で第5回現代短歌評論賞受賞。1990年、大辻隆弘、大野道夫、加藤孝男らと短歌評論誌「ノベンタ」を創刊。1994年、歌集『臨界』で第38回現代歌人協会賞受賞。2006年刊行の歌集『闇市』で第5回前川佐美雄賞、第12回寺山修司短歌賞受賞。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
