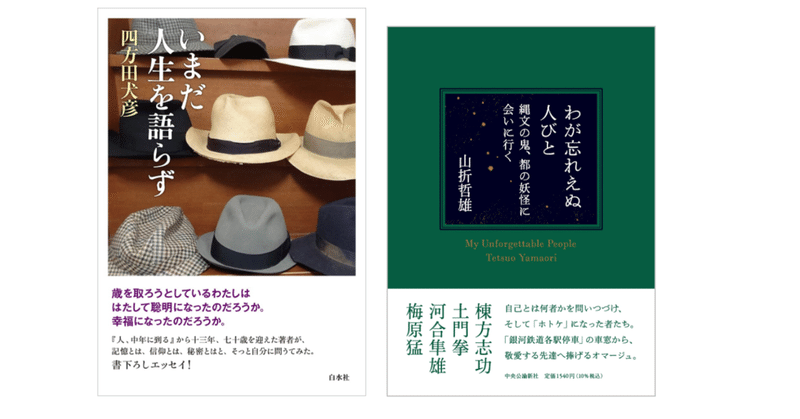
山折哲雄『わが忘れえぬ人びと/縄文の鬼、都の妖怪に会いに行く』/四方田犬彦『いまだ人生を語らず』
☆mediopos-3156 2023.7.9
mediopos-3138(2023.6.21)でとりあげた
四方田犬彦『いまだ人生を語らず』の
「蝸牛のごとき勉強について」の章に
山折哲雄に会いにいく話がある
そこで山折氏について
「これはもう次元が違う、
とうてい自分の及ぶところではないと
観念した人物」だといっている
最初に会った時
親鸞について『歎異抄』を読んだというと
親鸞が五十二歳のときに完成した
『教行信証』を読まねばならないといわれ
四方田氏は十年後に親鸞についての著作を書きあげる
その著作を手にもう一度会いに行くと
親鸞の話ではなく『シン・ゴジラ』のことを話し始める
かつて教示された『教行信証』についてふれると
「親鸞の本当の境地は、彼が八十歳以降に執筆した和讃、
それに奥さんに向けて書いた手紙です」と言われる
しかもそのとき山折氏は親鸞全集をはじめとした
貴重な全集なども手放してしまっていたことがわかる・・・
四方田氏はじぶんが山折氏の年齢になったとして
はたしてその境地になり得るだろうかと自問しているのだが
それが四年前の出来事だという
山折氏は昨年卒寿を越えている
この四方田氏のエッセイが気になっていたところ
折良く山折哲雄の最新刊『わが忘れえぬ人びと』を見つける
四方田氏はエッセイのなかで
山折氏の著書に書かれていた師と弟子の関係について
その東洋的な三番目のありようとして
「人は師に出会っては師を殺し、祖に出逢って祖を殺せ」
という臨済のそれを挙げているが
山折氏の新刊で繰り返し熱く語られているのは
まさにその臨済のことで
その過激な臨済を棟方志功・土門拳・河合隼雄
そして梅原猛のなかに見出していたのである
四方田氏が二度目に山折氏を訪ねたとき
『シン・ゴジラ』のことを話し始めたことについても
その新刊について書かれてあることから想像できる
AI神の誕生による人間の未来を危惧していたのだ
四方田氏はかつて教示されていた「教行信証」に基づく
みずからの「親鸞」の理解について問おうとしたが
山折氏の視線はすでにそこにはなかった
「親鸞」の理解についてもその晩年の境地を問題にし
さらにはそうしたことさえ
山折氏にとってはすでに問題意識から離れていた
四方田氏と山折氏の二度の邂逅は
禅問答のようなものかもしれない
四方田氏は師を礼拝しようとしたが
山折氏はそれにはかまわず
「師に出会っては師を殺し、祖に出逢って祖を殺せ」
という自らの道を歩みつづけているようにも思われる
ぼく自身でいえば生まれてこの方
師も祖も先生でさえもったためしがないため
「殺」す必要さえないのだが
ある意味でいえばこれは「水の試練」なのかもしれない
縋る岸もなくどこにも足場さえもてない水中で
みずからがそれに代わるものを
見出しあるいはつくらなければならないように・・・
歩み方はひとそれぞれで比較することはできないが
どちらにせよだれかに
あるいはどこかに依存するわけにはいかない
尊崇することは依存の反対だからだ
そのとたん「仏」はむしろ悪魔と化してしまう
■山折哲雄『わが忘れえぬ人びと/縄文の鬼、都の妖怪に会いに行く』
(中央公論新社 2023/5)
■四方田犬彦『いまだ人生を語らず』(白水社 2023/6)
(山折哲雄『わが忘れえぬ人びと』〜「まえがき」より)
「私の人生は旅の明け暮れだったようにも映る。遊びながらただ遍歴していたようにも見える。何者にもなれずに、ただあがいていた姿が浮かびあがってくる。
いつも逃げ出す用意をからだのどこかに残して生きてきたような気もするのである。
しかしもちろん、そんな暮らしがいつまでも許されるはずはなかった。
移動と転職のくり返しがはじまっていたのだ。失意と愉悦、挫折と船酔いのくり返しだったような気もする。
そんな不安定な生活のなかで眼前にあらわれてきたのが、わがふるさとの宮沢賢治、青森の棟方志功、同じく東北・山形の土門拳の三人の存在だった。
なぜ、そんなことになったのか、はじめはそれが謎だったが、やがて腑に落ちた。その三人が三人とも「何者」であるかわからない、不穏な人物であることがすこしずつみえてきたからだった。そのうち、その三人が、そもそも「何者」かになろうとはしない人間であることに、ふと気がついたのだ。
その謎の扉を開けてくれたのが、宮沢賢治である。かれはその人生の終わりに、自己のことにふれて「デクノボー」と呼んでいた。「デクノボーになりたい」といって、死んでいった。そういって短い人生を終えていた。
かれは、「自分は何者かになることを選ばない」といって死んだのだ。それが「私はデクノボーになりたい」といって死んだ賢治の最後の真意だったような気がしてきたのである。
賢治が扉を開けて光が射したとき、その向こうの雲間に棟方志功、土門拳の二人のシルエットが浮かび上がっていたのだ。」
「私がたどりついた仕事場が、京都西郊の丘に建つ国際日本文化研究センターだった。各地から集まってきたスタッフがビルの一室をかりて仮住まいし、やることなすこと枠のようなもの、制約のようなものは一切なかった。
われわれはいったい何者————そんな問いからはじまっていたような気がする。
何者になってもよい、それが不文律だったのかもしれない。現場にはそんな雰囲気がはじめから漂っていたのだ。
梅原さんはそんな現場の親玉だった。みごとな大将だった。
(・・・)
そんな時節だったと思う。もうひとつ、京都の空には変幻自在の舞を舞う人がいることに気がついた。ときに布袋の笑いをふりまく。いつのまにかシテのような、ワキのような舞を舞っている。自称「日本ウソツキクラブの会長」と宣伝し、いつでも物語の主人公になりすましている。そして無意識世界の主人公然としている。
河合隼雄さんである。」
(・・・)
今いった「デクノボー」論を書きあげた頃のことだったと思う。それまでの私の仕事を見て、河合さんが、
「ああ、銀河鉄道各駅停車だね」
とつぶやくようにいわれたことがあり、それが耳の奥にのこっていた。その声が今回、ときどき私の脳中に甦ってきた。
以来、頭の中に「人間発見図鑑」「銀河鉄道各駅停車」の二つのタイトルが出没し。点滅するようになってもいたのである。」
「そんな企てを思いついたころ、われわれを取り巻く環境には思いもかけない異変がおこっていた。AI(人工知能)の想像を絶する発展だった。その技術の進歩が異様な速さでわれわれの生活の足下を襲いはじめている。
それは、まさにシン・ゴジラの襲来に似ていたのだ。」
「ちょっと待てよ、それでいいのか。地球の運命とわれわれの未来をそんな風に預けてしまって大丈夫か。
(・・・)
その退化・沈衰のはてにAI神が誕生するこよになったのではないだろうか。その技術が開発される過程では、無数の怪獣たちも死に絶えていった。それをわれわれ地球人を代表する科学者や技術者たち、そして哲学者たちは何と呼ぶのだろうか。
本書にとりあげた縄文の鬼、都の妖怪たちはこのような進化と退化のあわいにあって立ち止まり、考えつづけ、行動しつづけらレジェンドたちだったと私は思っている。
そんな苦境の真ん中にあって、自己とは「何者」かと問いつづけた人々だった。
かれらは、いったい何?
そういう問いを掲げながら、どうかこのまことに小さな銀河鉄道各駅停車にお乗りいただくことができれば、私にとってこれ以上の幸いはないのである。」
(山折哲雄『わが忘れえぬ人びと』〜「一、棟方志功 板を彫る」より)
「中国の漸増に、臨済という眼光鋭い坊主がいた。日ごろ、過激なことをいって、周囲を驚かせていた。
師に会うときは 師を殺せ
主に会うときは 主を殺せ
そんなものにはこだわらず、さっさっとのり越えていけ 先に進んでいけということだろう。その臨済和尚の死後、弟子たちがその師の言行を集めて、『臨済録』をつくった。
棟方志功は、この『臨済録』の一節を日ごろ口ずさんでいたような気がする。口にするだけではなく、生まれながらにその言葉を生きていたような気がする。」
(山折哲雄『わが忘れえぬ人びと』〜「二、土門拳 闇を撮る」より)
「私はかねて、上記の棟方志功の作品には「仏」殺し、「耶蘇」殺しの主題が隠されていると思ってきたのであるが、それはこのたびあらてめて土門拳の作品をみていて、同じ主張が氏の仏像写真の背後に色濃く流れていることに気がついたのである。
仏に逢うては仏を殺し。祖に逢うては祖を殺す、といった臨済和尚の生き方である。その必死の生き方を、土門拳も土門拳なりに写真撮影の仕事のなかで実践していたということになるのであろう。」
(山折哲雄『わが忘れえぬ人びと』〜「三、河合隼雄 夢を生きる」より)
「ワキは聞き役に徹している。控え目に耳を傾けている寡黙なワキだ。その「諸国一見の僧」の姿が。あるとき私には今日いうところのカウンセラーの振るまいに重なってみえたのだ。
亡霊という名のクライアントの訴えを黙って聴いているカウンセラー、それがこの旅僧の重要な役割だったのかもしれない。もしかする「諸国一見の僧」こそは、中世における練達の魂の治療者だったのだろう。」
「患者たちの理不尽な問いは、たしかに老師におって提出される理不尽な問いとよく似ている。
たとえば『無門関』にこんな問いがもち出されている。仏陀が異教徒(外道)に出会ったときのこおだ。その異教徒がブッダに問いかける。
「言葉(有言)でもなく、沈黙(無言)でもないもの、それは何か」
異教徒を患者、ブッダを医師として考えてみよう。医師(ブッダ)はどう答えるか。ブッダは「しばらく黙って坐っていた」とあるだけである。その姿をみて、患者(異教徒)はハッと気づく。迷いの霧がはれた、というわけである。
コトバでないもの、沈黙でないものはなにか、という問いは、「悪くなると治る、治ると悪くなる」と駄々をこねている患者の口吻に似ている。公案ではよくいわれる「犬にも可能性(仏性)があるのか」の問いは。「死ぬためにあなたのところにきた」と問いかける甘えの告白に似ている。
答える側は、そうだともいえない。そうでないともいえない。立ちつくし、立ちどまり、静かに黙っているほかはない。
(・・・)
そのとき、心と心のあいだに「橋」がかけられる。東の心から西の心へと開通する時がくる。その可能性が開かれている。
まさに開かれている、と考える。」
(山折哲雄『わが忘れえぬ人びと』〜「四、梅原猛 歴史を天翔ける」より)
「梅原さんは晩年になってから、よく「オレはホトケになる」といっていた。はじめ、あまり聞きなれない言葉なので、おやっと思っていたが、梅原さんはそんなとき、いつも本気だった。
考えてみれば、仏教の根幹は、まさにそれが当たり前のことだった。(・・・)
やがて私は、梅原さんの「オレはホトケになる」に合点がいくようになった。そのことを梅原さんはいつも「わがこと」としていっていたからだった。何か大事なことを「他人ごと」としていうようなことは、おそらくなかったように思う。
その梅原さんの生きようは、どこか版画家の棟方志功に似ていた。(・・・)かれは青森のふるあとを立ち去るとき、「わだばゴッホになる」といって、家を出て行った男である。「わだばゴッホのような画家になる」といって出ていったのではない。
梅原さんはどのような場合でも、他人ごとではなく、自分ごととしてものを考え、そして語る哲学者だった。そのため梅原さんは棟方志功や土門拳と同じように、一人の師ももたず、一人の弟子ももたない生き方を最後まで貫いた。」
(山折哲雄『わが忘れえぬ人びと』〜「あとがき」より)
「私は昨年、卒寿という歳の区切りを越えたが、思い返すと、還暦や古稀を越えたとき、そのような区切りや垣根を意識することはなかった。ほとんど新幹線の「のぞみ」に乗っているようで、あっというまに通り過ぎていった。
それにくらべると米寿とか卒寿とかいわれると、かつての還暦とか古稀の場合とは打って変わり、むしろ銀河鉄道の各駅停車に乗って、ゆっくり周囲の景色を楽しみながら旅をしている気分になっていた。時間がゆるやかに流れ、過ぎていったはずの光景が何ともなつかしく甦ってくる。梅原さんや河合さんの立ち居振る舞いが棟方志功や土門拳のシルエットと重なり合い、たがいに対話している姿までがみえてきた。それがまた私の心のうちに不思議な元気を誘い出し、思いもしなかった恍惚感に包まれるようになっていたのである。」
(四方田犬彦『いまだ人生を語らず』〜「蝸牛のごとき勉強について」より)
「私淑する人物がいたなら、一度でもいいからその人物の謦咳に接しておくこと。これは重要なことである。(・・・)わたしの人生にはそういったことがいくたびかあった。 わたしから手紙を出して会いにいったところ、これはもう次元が違う、とうてい自分の及ぶところではないと観念した人物が、何人が存在している。知識の量や体験の壮絶さに圧倒されたというのではない。その人物の思考の身振り、その虚心にして自在な振舞いにただただ感嘆し、そのにこやかな表情の奥に深い叡智が宿っていることを知ったということである。
(・・・)
わたしが出逢ったもう一人の人物は、宗教学者の山折哲雄である。わたしは東洋と西洋では、師と弟子の関係をめぐって大きな認識の違いがあることに思い当たった。一般的に西洋では、両者の間に基本的に三通りの関係がありうると考えている。弟子が師に反逆し、師を破滅させてしまう場合。逆に師が弟子を心理的に追い詰め、破滅させてしまう場合。最後に、両者が長い間の対立と反目の後に和解しあい、相互に深く信頼しあう場合。もっとも最後のものが稀有であることは、ここに書くまでもあるまい。山折さんはこうした事実を念頭に置きながら、東洋にはこの西洋的な類型学とはまったく異なった、三通りの師弟関係が存在していると、著書のなかで説いた。
ひとつは数多くの弟子に囲まれ、彼らを率いて諸国を遍歴するという孔子の道である。二番目は、徹底して弟子を持つことを拒み、晦渋な真理を説く孤高の賢人として生きる、老子の道である。三番目のものはきわめて難解であるが、禅宗の説く道である。臨済の説教には、人は師に出会っては師を殺し、祖に出逢って祖を殺せという一節がある。仏弟子を称するならば、仏の屍を乗り越えていくほどの気力と大胆さをもって修行を続けないと、とうてい悟りは覚束ないという怖ろしい決意が、そこには語られている。
わたしは京都に山折さんに会いに行った。
彼は単刀直入に、親鸞を読んだことがあるかねとわたしに訊ねた。
はい、『歎異抄』を一応読みましたと返事をすると、あんな短いものはあだめだ。あれは親鸞が死んで何十年も経った後、弟子の一人が想い出して纏めたものにすぎない。本当に親鸞があのように語ったかどうかも怪しいものだと答えが戻ってきた。山折さんはわたしに『教行信証』を読まなければいけないといった。『教行信証』は親鸞が五十二歳のときに一応の完成を見た理論的著作で、全六巻。夥しい仏典を自在に参照しながら、いかなる極悪人でも救済されるのであれば、それはどのような条件のもとにおいてであるかという難問を解き明かそうとした大著である。
この出逢いから十年が経ち、わたしはついに『教行信証』を読破し、親鸞について一冊の書物を著した。(・・・)
ともあれわたしは自分の親鸞論を片手に京都に向かい、山折さんにもう一度会った。
山折さんはわたしの新著を見て、「あっ、そう」という表情を見せただけである。口を突いて出たのは、『シン・ゴジラ』のことだった。(・・・)いつまで経っても親鸞が出てこない。
わたしはついに痺れを切らし、自分は十年前におっしゃられた通り、『教行信証』を読みましたと報告した。すると山折さんは、「あれはねえ、五十歳くらいのまだ若い頃に書いた書物だということですよ。親鸞の本当の境地は、彼が八十歳以降に執筆した和讃、それに奥さんに向けて書いた手紙です。それを読み解かなければ親鸞のことはわかりませんね」と、スラリといった。
わたしは柔道の組手でいきなり足を外されたような気持ちになった。(・・・)
驚くべきことはそれだけではなかった。しばらく話しているうちに判明したのだが、山折さんの手元にはもう柳田国男全集も、長谷川伸全集もないのだという。あっても邪魔になるばかりだから人にあげちゃいましてねと、笑いながらいう。
「でも親鸞全集だけは手放すわけにはいかないでしょう」と、わたしは訊ねた。
「なあに、あれも若い人が読みたいというので、この正月にあげちゃいましたよ」
もうこれは次元がまったく違いと、わたしは観念した。(・・・)長年にわたって読み続け、何冊もの著作の対象としてきたというのに、その親鸞への執着からみごとに解放され、飄々として怪獣映画の話をしているのだ、これではいつまで経っても追いつくことができないではないか。
ここまでは四年前の出来事である。山折さんはこのとき八十九歳。もう人生において充分に読んだ。充分に思考し、充分に書いた。書物に未練はなく、自分の解放のためにはすべてのものを周囲から遠ざけておきたいという心境なのだろう。
(・・・)
仮にわたしが同じ年齢に到達することがあったとして、すべての書物を処分してしまうという決断を下すことができるだろうか。おそらくそれを実行したならば自分が大きな解放感に見舞われることは確実だろう。だが自分はそれだけの勇気を持つことができるだろうか。そのためにはあまたの書物を前に、後悔が残らないまでに思考を続けておかなければならないのだが、こればかりはわからない。」
◎山折哲雄
1931年生まれ。東北大学文学部卒業、同大学院文学研究科博士課程単位取得退学。宗教学者。国立歴史民俗博物館教授、京都造形芸術大学大学院長、国際日本文化研究センター所長などを歴任。2002年『愛欲の精神史』で和辻哲郎賞、10年瑞宝中授章、南方熊楠賞受賞。20年京都市文化功労者。主な著書に『仏教とは何か』『こころの作法』『法然と親鸞』『能を考える』『勿体なや祖師は神衣の九十年 大谷句仏』『老いと孤独の作法』など多数。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
