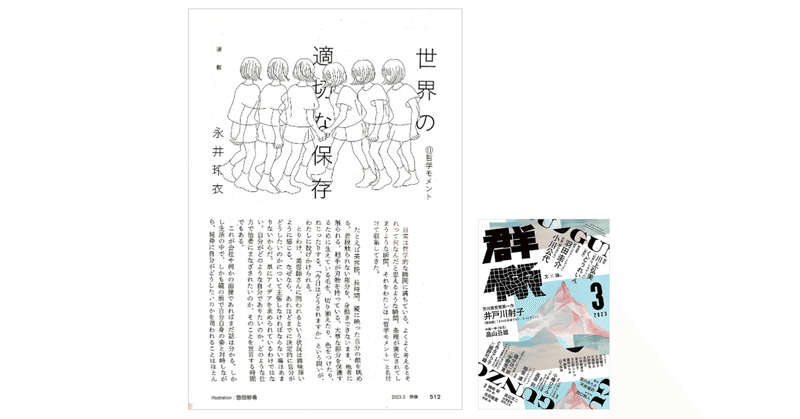
永井玲衣「世界の適切な保存 ⑪哲学モメント」(「群像 2023年 03 月号」)
☆mediopos-3018 2023.2.21
それをあえて
「哲学」と呼ぶ必要もないかもしれないが
「よくよく考えると
それって何なんだと思えるような瞬間、
条理が異化されてしまうような瞬間」は
たしかにある
しかもそれは日常における瞬間である
そんな瞬間を
ここでは「哲学モメント」としている
ここで挙げられている例のひとつが美容院
鏡に映った自分の顔を眺めながら
「今日はどうされますか」という問いがなげかけられる
鏡を前にして
「どうされますか」と問われることは
その文脈から切り離されたとき
切実で当惑させられる問いにもなり得る
洗面所でじぶんの顔が映っている
その鏡のなかのじぶんが
「どうされますか」と
問いかけているようなそんな
天気予報の例も挙げられている
未来の天気を預言する天気予報
ある予測可能なデータにもとづいて
天気は予報されるのだろうが
それが天気予報という常識とされている文脈から
切り離されたときはどうだろう
未来の時間を「予報」するとは
ふしぎではないか
また「カレンダーめくり忘れていた僕が
二秒で終わらせる五・六月」という短歌で
時間を「ものすごいスピードで進めてしまう」僕のこと
予報する時間
止められる時間
進められる時間や
はたまた
過去と現在と未来を
さまよってしまうようなそんな時間・・・
日常において
あたりまえとしか思えないことのなかに
ふしぎな瞬間はあふれている
そんな「哲学モメントは、
つねにあるのに、つねに隠されている。
つねに隠されているのに、つねにあるのだ。」という
ある意味それは
わたしたちの意識そのもののことだともいえる
無意識をふくめた意識のなかで
あたりまえのように起こっているさまざまなことは
ほんとうはその瞬間瞬間が謎に満ちている
いつもいつも謎に囲まれて生きていると
あまりに生き難いので
わたしたちはそれらの多くを「あたりまえ」として
とくに気にも留めなかったりもするのだが
ときには「あたりまえ」に呑み込まれすぎないように
その「モメント」を問いにしてみる必要がある
■永井玲衣「世界の適切な保存 ⑪哲学モメント」
(「群像 2023年 03 月号」所収)
「日常は哲学的な瞬間に満ちている。よくよく考えるとそれって何なんだと思えるような瞬間、条理が異化されてしまうような瞬間、それをわたしは「哲学モメント」と名付けて収集してきた。」
「たとえば美容院。長時間、鏡に映った自分の顔を眺める。普段触られない部分を、身動きできないまま、他者に触られる。相手が刃物を持っている。大事な部分を保護するために生えている毛を、切り揃えたり、色をつけたり、ねじったりする。「今日はどうされますか」という問いが、わたしに投げかけられる。
(・・・)
これが会社や何かの面接であればまだ話は分かる。しかし生活の中で、しかも鏡の前で自分自身の姿と対峙しながら、純粋に自分がどうしたいのかを問われることはほとんどないのだ。」
「天気予報もまた、哲学もメントを感じさせる。「天気」という、人間が左右することのできない事象を「予報」するとは、まるで預言者ではないか。
(・・・)
わたしたちは天気予報という存在を、全く疑っていない。天気予報が必要がないとか、意味がないとか言っているのではない。わたしたちはあまりに当然だと思っている。そのふしぎさを味わいたい。」
「あらゆる科学が発展した現代でも、なお人間が直接触れることのできない領域が「時間」なのだろう。だから時間に少しでも触れることができる営みは、どこか神めいている。」
「神は時間を止めるだけではない。ものすごいスピードで進めてしまうこともある。
カレンダーめくり忘れていた僕が二秒で終わらせる五・六月(木下龍也)
日常的なふるまいである。そして、ユーモラスで、だがどこか傲慢な行為である。歌人の穂村弘と東直子もまた、この啖呵に神の姿を見ている。
穂村/神のごとき振る舞いです。時間というものは、本当は神の領域のもの。時間だけは人間がどういぇっても触れられない摂理の中の最大のもののひとつでしょう。なのに、「僕」は、二秒で五・六月を終わらせた。
東/カレンダーをめくるという行為そのものは、なんでもない行為なんですけどね。日常のなんでもない行為の中に、時間が見えることがあるってことですね。それを見つけだすだけで、一首が成立する言葉が見つかりそうですよね。(東直子・穂村弘『しびれる短歌』ちくまプライマリー新書、二〇一九年、筑摩書房、一一五ページ)
もう誰も来なくなった祖父の家などに入り、時間の止まってしまったカレンダーを見つけることがある。ひっそりと冷えた剥製のようだ。人間がいないと、時間は進むことすらできない。(・・・)
しかしその時間をふいに進めたくなったとき、わたしたちは突然、高慢になる。びりっ、びりっ、と勢いよく紙を破り、時間を無理に進ませる。足下にはばりばりの裂け目をした紙が折り重なっていく。進むことを強いられた時間は、おとなしく従っている。」
「止めたり、急速に進めたり、意図せず「時間」という神の領域に介入していることがある。そんなものが日常にありふれている。知らず知らずのうちに、わたしたちは人間の外に一歩出ている。ひとならざる者へと、踏み込んでしまっている。
そうは言っても、わたしたちは、英語の時制を習ったときのように、左から右へと矢印がひかれるような時間軸を、本当に生きているのだろうか。
たしかい生きてはいる。自らを語るとき、わたしたちは生い立ちとして、いつ生まれ、何があり、何歳でどうなったか、順を追って話そうとする。それが「わかりやすい」とされているし、伝わりやすいからだ。
だが哲学対話では、しばしば過去の思い出が語られる。「はじめて思い出したんですけど」という前置きで、語り出される言葉がある。対話の場では、ひとは互いの言葉をよくきいている。よくきくということは、それだけ他者がわたしの中に流れ込んでくるということだ。流れ込んだ他者を、わたしと出会わせて、言葉を見つけていく。そうすると、わたしの中の他者がうごめいているのを見つける、なんとか引っ張り出して、少しずつその感触を確かめる。困難な作業だ。うろうろと視線がさまようように、語りもそこら中をうろつくことがある。
あちこちをさまよってしまうのは、話題や問いだけではない。過去なのか、未来のことなのか、いま考えているのか、語りは時間を飛び越えて、いろいろな場所を歩きまわる。それをよくきこうとすると、わたしたちもまた、そのひとの時間を生きることになる。
過去の話をするならば過去へ、別の過去の話をするならそこへ、などといった行儀のいいものでもない。ある過去と、その過去と、あの過去が、同時に存在するかのように語られることもある。互いに混入し、境目がわからなくなってしまうことも多い。
そんな語りは、神のふるまいというよりは、むしろ地を這う人間のもがきのようにも見える。なぜだろう。
時間を止めたり、急速に進めたりなど、時間を意図せずとも手中に収めるようなふるまいではないからだろうか。それよりも、てのひらに収めきれず、こぼれてしまうように語るからだろうか。領域を侵しているというよりは、時間そのものに翻弄されているからだろうか。
翻弄されながら、わたしたちはなおも願うときがある。時間をどうにもできないからこそ出てくる祈りだ。」
「人間は神のようにもなれるし、やはり神のようにはなれない。だがどちらも、本人にとっては劇的であっても、ひっそりと生じている。わかりやすい形で、仰々しく行われはしない。当たり前の顔をして、歩き去っていくこともある。
哲学モメントは、つねにあるのに、つねに隠されている。つねに隠されているのに、つねにあるのだ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
