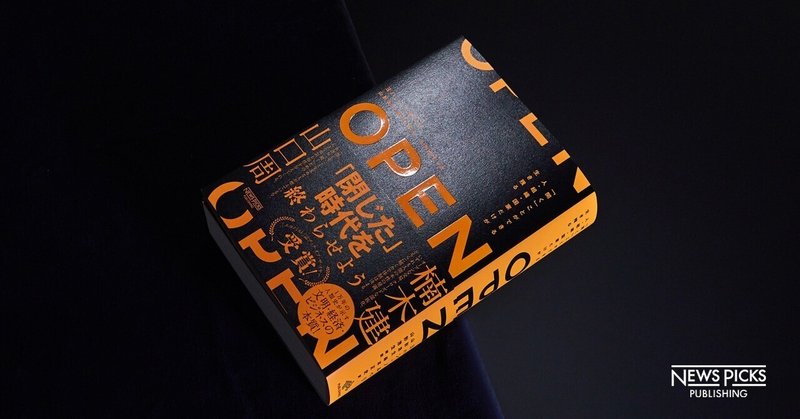
【山形浩生】賢い人ほど「偽オープンの罠」にはまる理由
いま世界が注目するスウェーデンの知性、ヨハン・ノルベリの新刊『OPEN:「開く」ことができる人・組織・国家だけが生き残る』。楠木建氏や山口周氏が賛辞を寄せる本書の日本語版が4/29に発売された。
見知らぬ他人やアイデア、変化に対しオープンであってこそ、文明も組織も繁栄する。ではなぜその試みはつねに「失敗」し、われわれは今日も戦争に明け暮れるのか? どうすれば「偽オープンの罠」を回避できるのか? 本書はその謎を圧倒的なエビデンスで解き明かし、世界に衝撃を与えている。
今回は本書の訳者・山形浩生氏から寄せられた、わかりやすく痛快無比な6000字解説をお届けする。

1 本書のまとめ
本書『OPEN』の主張は単純明快。社会でも何でもオープンがいいよ、閉鎖的なのはよくないよ、ということだ。
オープンにしておけば、新しいモノに出会う。新しい体験と、新しいアイデアが出てきて、既存のものについても新しい組み合わせ、新しい見方が出てくる。それが発展につながるよ、という話だ。
でも、そのよいはずのオープンがなぜ続かないのか?
本書はこれまでの歴史でオープン性を妨害し、せっかくの発展を停滞と退行に追い込んだ様々な要因を検討する。そしてそれをもとに、いまのぼくたちが、せっかく続いてきたオープン性とその果実を、今後もつぶさないで維持し続けるためにはどうするべきかを考察する。
2 著者について
著者ヨハン・ノルベリは、1973年生まれのスウェーデンの作家・歴史家だ。
2000年頃から、各種の反グローバリズム運動に対する批判を開始し、それをまとめて『グローバル資本主義擁護論(In Defense of Global Capitalism)』(未邦訳、2001)として発表した。もちろんグローバリズムを擁護し、自由貿易推進をうたうものだ。
その次に発表された『進歩:人類の未来が明るい10の理由』は拙訳で邦訳(晶文社刊)もある。そしてその次に発表されたものが本書だ。

基本的な立場は、かれが古典的なリベラリズムと呼ぶものだ。
経済的な自由主義の立場にたち、非常に明解な主張を展開している。スウェーデンのリベラル系シンクタンクであるティンブロに所属し、その後2007年からはアメリカの保守派シンクタンクとして知られるケイトー研究所でシニアフェローを務めている。2020年の本書は、かれの現時点での最新作となる。
3 本書の概要1:オープン性のすばらしさ
著者は自由主義リベラリズムの立場に立つ。最近では「リベラリズム」というのはあまりに様々な意味を持つようになってしまっているが、著者の場合は政府介入をなるべく避ける、自由放任型のリベラリズムと言うべきか。
だから本書で支持される「オープン性」というのは、取引、貿易、研究、言論、開発など各種の分野において規制を避け、なんでも自由な発展と取り組みを推奨する、ということになる。そうすればイノベーションが開花し、文化と産業が花開いて社会も経済も栄えるのだ、と。
本書はそれを、歴史をさかのぼることで示す。そのときのポイントになるのが、18世紀頃からのイギリス産業革命、それに先立つ17世紀ヨーロッパ啓蒙主義のとらえかただ。
歴史、経済学、社会学、その他あらゆる分野で、イギリス産業革命以来の200年ほどは人類史上で類を見ない異様な時期だ。
人類の生産力は異様に高まり、人口増と食料生産のイタチごっこによるそれまでのマルサスの罠をいきなり突破し、人口は激増しても栄養状態は大幅改善、医療も改善(というかまともな医療そのものが誕生)して、寿命も健康状態も以前とは比べものにならない。
生活は豊かになり、みんな幸福になり、そこらのパンピーまでが教育を受けて多少なりとも文化的な生活ができるようになり、その恩恵がなんだかんだで世界中に広がるようになった。
自由、平等なんていう絵空事のお題目ですら、曲がりなりにも実践されるようになってしまい、女性や少数派までがその果実を(完全にといえるかどうかは議論が残るが)大きく享受できている。
いや公害が、いや人口増が、いや温暖化が、いや植民地主義が、いや奴隷制の悲劇が、いや差別が、いや戦争が、という声はある。
だがそれらはどれも、すべては完璧ではないというだけの話。全体としての改善傾向は否定しようがない。そう言っても、否定したがる人たちはいるけれど、そんな連中の言うことはたいがい、変なおとぎ話を真に受けた妄想でしかない。
この状況を見れば、やっぱり産業革命には何か特別なものがあった、と考えたくなるのが人情だ。
なぜヨーロッパでだけ産業革命が起きたのか? さらになぜそれに到るさまざまな技術、学問、思想がヨーロッパに集まったのか? なぜヨーロッパでなければならなかったのか? それがこれまでの多くの分野における問題設定ではあった。
そしてこっちの方向での分析が様々なおもしろい発想(ついでに一部のろくでもない人種差別的な考え方)をもたらしたのは事実ではある。プロテスタンティズムの倫理が、とかスコラ学派が、ギリシャ思想の伝統が、森林資源と石炭資源のバランスが、軍事的なバランスが、等々。
その一方で、どれも決定的ではなかった。確かにそれも効いてはいるが、探すと他でも見つかる。それがヨーロッパでなければいけない決定的な理由はちっとも出てこない、というものがほとんどだ。
そして本書は(そして本書に限らず最近の思想の大きな流れは)、まさにその通りなのだ、という。産業革命、科学革命、啓蒙主義がヨーロッパでなければいけなかった理由はない。実はそれまでも世界の様々な場所で、似たようなものは起きていた。
急激に学問と文化が花開き、産業が栄え、新しいものが次々に生み出された時期が、イスラム文明にも、中国文明にも、インド文明にも、おそらくはぼくたちの知らない他の様々な文明にも大なり小なり存在していた。
それらに共通する大きなポイントこそ、本書の最大の主題であるオープン性だ。
新しい思想、新しい人々、新しい文物、新しい取引にオープンな社会は、おおむね発展を遂げた。というより、人間はそもそもがオープンな取引を通じて発展してきた存在なのだ。氷河期の石器時代にもすでに、広い地域にまたがる交易があった。いまの発展は、その延長でしかないのだ。
でも、そんなに良いならなぜみんなオープンにしないの? それが本書後半の問題設定となる。
4 本書の概要2:オープン性をつぶすものとは?
オープン性も常にいいことばかりではない。
変な病気、まったく異質な慣習、ときには外敵さえもたらすこともある。さらにオープン性がもたらす発展は、既得権益を脅かすことが多い。全体としては発展でも、一部の人には脅威となる。すると、それをつぶす力は強まる。そしてそれまでの発展が成功していると、その既得権も強まり、新たな変化を面倒に思う気分も強まってしまう。
惰性、過去をありがたがる習性、見知らぬ人や存在への本能的な反発などが、クローズドな社会をもたらし、文明は停滞するにとどまらず、ときに破壊と退行にすら陥ってしまう。そしてこれまでのあらゆるオープンな文明発展は、必ずこの罠に陥って自爆してしまった。
だから本書は産業革命について、むしろ逆の考え方をすべきなのだ、と述べる。
問題はなぜ、ヨーロッパで産業革命/科学革命/啓蒙思想が生まれたか、ではない。むしろ、なぜそれが(まだ)続いているのか、ということなのだ、と。
他のオープンな文明や文化は、これまですべてつぶされてきた。それがなぜヨーロッパに限っては続いたのか?
それは、ヨーロッパが狭いところに小国が乱立し、どこかでクローズドな気運が盛り上がったら人材も知識も産業も他の国や地域にあっさり引っ越してしまい、さらに知識人たちは独自のネットワークで結ばれて盛んに交流し続けたことで、発展が途切れることがなかったからだ、というのが本書の主張となる。
どの権力も中国の皇帝のようにすべてを司る強大な力は持てなかった。ヨーロッパが栄えたのは、ヨーロッパが偉かったからではない。むしろヨーロッパの権力者がみんな弱小で無能だったからだ、というわけだ。
が、それがいつまで続くかはわからない。様々な分野でクローズドな気運が盛り上がり、規制と許認可、右でも左でも言論の統制や思想の検閲が行われ、排外主義、移民排斥、新規事業の参入ハードル、公共の余計な介入が至るところで見られる。
ヨーロッパさえも、EUができてしまい、なんでも規制が横並びになって、かつてのような競争環境が維持できているかどうかも怪しい。
そして一方で、中国のような(あるいはかつてのジャパン・アズ・ナンバーワン論のような)統制型の政府主導の研究開発や産業発展がよいという声も出てくるし、独裁者待望論も出てくるし、コロナ禍でグローバリズム否定の声もあがるし、オープン性をつぶす力がますます強まっているようにさえ見える。
さて、今回のオープン性の大成功は今後も続くだろうか?
5 本書の位置づけ:実証的リベラリズムの流れ
本書はある意味で、著者の前著『進歩』の続きではある。『進歩』では、変な悲観論者による、世の中悪くなっている、文明なんて幻想だ、グローバリズム反対等々の主張に対し、そんなことはないのだ、というのを述べた本だ。
世の中は確実によくなっている。人々は豊かになり、社会は自由と可能性が高まっている。だから、怪しげな悲観論にだまされて、この豊かさをつぶそうとしてはいけない、というのが『進歩』だ。
本書はそれを受けて、なぜそもそも進歩が起きているのか、そしてそれなのになぜ、その進歩と改善を見ようとせずに、したり顔で悲観論と懐古趣味をふりかざす連中が登場するのか、というのを述べた、『進歩』の原因分析の本といえるだろう。
そして、主張されている内容は『進歩』と同じく、スティーヴン・ピンカー、ビョルン・ロンボルグ、マット・リドレーなどに代表される、人類の叡智と理性と啓蒙主義を信じる立場だ。その他、『ファクトフルネス』(邦訳日経BP刊)のロスリング夫妻やエネルギー問題のヴァーツラフ・スミル、温暖化や環境問題のマイケル・シェレンバーガーなどもここに入れてもいいだろう。
いずれも、長期的なトレンドのデータを重視して、それをもとに進歩、技術、社会発展と自由の可能性をうちだす、実証的リベラリズムとでも言うべき一派だと訳者は考えている。
「一派」とはいっても、この中でも様々な立場はある。政府規制の役割をかなり期待する左派リベラリズム的な立場の人もいる。一方で本書のノルベリのような、最近では悪者視されがちな新自由主義的リベラリズムを主張する人もいる。
それでも、そうしたイデオロギー的なポジションの差にもかかわらず、彼らの見通しは共通しているし、その処方箋も似ている。
恣意的な規制はやめよう。人間の問題解決能力を信じよう。新しいものを試し、イデオロギーにとらわれずに実証的によいものは採用しよう、と彼らは主張する。
一方で環境や気候変動問題などで顕著なように、何かイデオロギー的に解決策を決め打ちする方針は、硬直して破綻する可能性があまりに高い。「コンセンサス」だのお手盛りの「正義」だのをふりかざすのではない、自由な可能性の探究を許し、そのためには異端の邪説(とされるもの)も容認すべきではないか?
個人的には、かつては少数派だったこの一派も、ジワジワと支持を高めてきているようには思う。
その一方では、確かにメディアや社会の一部ではキャンセルカルチャーが猛威をふるい、規制は強まり、「コンセンサス」に反することを言うやつは黙らせていい、という風潮も高まりつつある。風が吹くたび気分も変わる、そんな年頃ではある。だが最終的にはどこかで、事実に反する教条主義は破綻せざるを得ないと思いたいところだ。
6 雑感:えせオープンがもたらすクローズドの危険
さて、本書を読んでそれがまちがっていると全否定する人はあまりいないはずだ。たぶんほとんどの人が、ふんふん、その通りだねと言うだろう。あたりまえじゃないかとせせら笑う人だっているはずだ。
そして、いやあみんなが自分のようにオープン性に理解がある寛容性の権化であればよいのになあ、と思うだろう。
ある意味で、それがこわいところでもある。
だれも、自分が頑固で保守的で新しいモノすべてを否定する進歩の敵だとは思っていない。だれも自分がクローズドだとは思っていない。多くの人は、自分は心が広くオープンなのだと思っている。新しいものを受け容れるのはまったくやぶさかではないと考えている。ただ……
明らかにまちがっていることを平気で言うあいつらは、フェイクニュースの悪者どもだから、それは取り締まるべきだ。あれは人々のお気持ちに配慮しない無遠慮な発言だからヘイトスピーチとしてつぶすべきだ。あんな成功するかもわからない技術が出回ると人々が混乱するから、規制すべきだ。こんな邪説を流すやつがいるが、それは人々が正しい理解をする邪魔なだけだから黙らせよう。このマンガは青少年に有害だから発禁にしよう。もちろんこれは、自由を否定するものなんかではない。どうせまちがっているから無価値か、有害なものを除去するだけ。
それ以外はすべて自由にしてもらってぜーんぜん構わないんですよ、ね、ワタシってオープンでしょ?
「あー、あの人ね」と具体的な顔を思い浮かべた人もいるはずだ。そしてその印象はおそらく決してまちがってはいない。だが、それで安心してはいけない。実はほとんどの人は何かしらこれに類することを、どこかの場面で口走っているのだ。しかもその自覚がある人は意外に少ない。
そしてもちろん、そういう人々こそ、つまりは自分自身こそがオープン性の最大の敵で、クローズドの急先鋒だったりするのだ。
本書で自由主義とオープン性の圧倒的な支持者としてしばしばひきあいに出されている、フリードリッヒ・ハイエクという人がいる。
この人は社会主義による統制経済と社会を大いに懸念し、自由市場と自由主義の一大論客となる。
だが、社会主義と政府統制を恐れるあまり、社会党、労働党系の政権すべてを懸念するようになり、そしてそういう左翼がかった政権や政策を選挙で支持してしまいかねないバカな愚衆による民主主義と議会政治すら疑問視するようになる。
晩年の1980年代に発表した大著『法と立法と自由』(春秋社)では、バカな議員どもが気まぐれな法律を決める議会なんか許せんので、法律の重要な部分は歳寄り賢者の仲良しクラブが密室で決めるべきだ、などというトンデモな主張を真顔でしている。
そしてさらに反共をこじらせて、チリの独裁者として悪名高いピノチェト政権を支援するばかりか、そのブレーンにまでなり、究極の不自由さの手先と化してしまう。
ハイエクは、ある一つの市場や経済の自由にこだわるあまり、結局それ以外のオープン性を否定してしまったわけだ(そしてもちろんピノチェト政権下では縁故主義が横行して、ハイエクの好きな自由市場もまともには維持されなかった)。
なんだか、それと似たような自縄自縛の状況に自らを(そして周囲を)追い込んでしまう人は結構いる。ぼくは本書に描かれたクローズドの様々な要因分析とともに、この点を忘れてはいけないと思っている。
自由はすばらしい──自分のやりたいことである限りは。
でも実際には、社会での自由というのは、自分が嫌いなものでも容認するということなのだ。言論の自由というのは、自分の嫌いな発言、聞きたくない発言でも認めるということだ。表現の自由というのは、あんな低俗なエロまんが、と思ったものでも認めるということだ。
自分たちの嫌いなもの、なじみのないものをどこまで許容できるかが、文化や社会としてのオープン性を決める。
するとおそらく大事なのは、ぼくたち一人一人が「あんなもの!」「そんなのダメ!」「規制しろ!」と言いたくなる気持ちを少し抑えることなのだろう。
「あれはよくない」と言うのはかまわないけれど、「禁止しろ」「排除しろ」と言ってはいけないのだ。同時に、人にそういうことを言われたときに、安易に空気に流されず、無視したり抵抗したり、すっとぼけたりして、やりたいこと、やるべきことをとにかくやることだ。
本書で分析されている、人間の身内びいきや仲間びいき、部外者不信、官僚制のことなかれ主義や懐古趣味といった特性は、どうにかしようと思っても、なかなかむずかしい。でも、そこから出てきた気持ちの表し方は、多少は変えられる。その積み重ねで少しずつ自分の許容範囲を人々が拡大すれば、それが社会のオープン性拡大だ。
本書をきっかけに、少しでも多くの人がそれを認識して、実践してくれれば──そこまでいかなくても、そういうことができるのだ、ということを認識してくれれば、本書の元は十分にとれたと言えるのではないだろうか。

【目次】
はじめに
第一部 オープン
第1章 オープンな交流
第2章 オープンな門戸
第3章 オープンな精神
第4章 オープンな社会
第二部 クローズド
第5章 「ヤツら」と「オレたち」
第6章 ゼロサム
第7章 将来への不安
第8章 戦うか、逃げるか
第9章 オープンかクローズドか?
訳者解説
