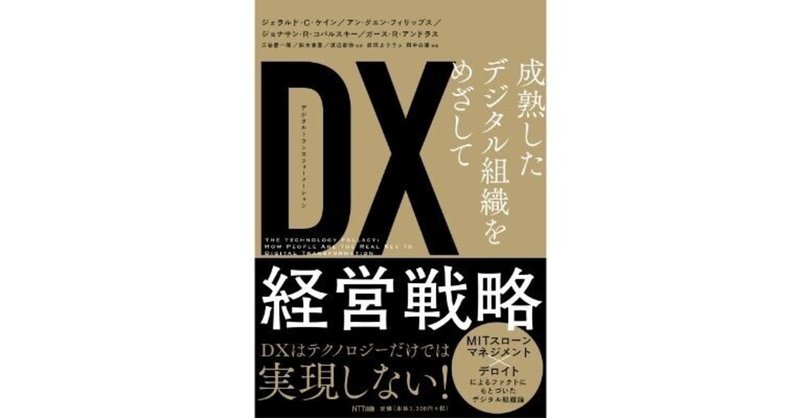
デロイトと『MITスローンビジネスレビュー』誌の共同研究から生まれた『DX経営戦略』より、全章を要約した解題を公開
本書は、『MITスローン・マネジメント・レビュー』誌とアメリカの名門コンサルティングファーム「デロイト」が提携して実施した、テクノロジーが企業経営をどのように変えたかに関する4年間の調査に基づいた1冊です。グーグル、ウォルマートをはじめとするアメリカ企業の1万6000人以上を対象に、デジタルディスラプションの経験、その性質の理解、彼らの所属する組織の対応の妥当性がエビデンスをもとに多角的に分析しています。
本書は、DX化成功のためには、テクノロジーの導入ありきではなく、組織的な再編、文化形成、メンバーそれぞれのマインドセットの変更にどれだけエネルギー注げるかにかかっている、と強調します。そうして成功した組織を、「成熟したデジタル組織」と呼び、その特徴を明らかにします。
コロナの今、日本でもDX化は、産官学共通の大きな課題となっておりますが、まさにこの状況にうってつけの骨太な一冊です。ここでは、デロイトトーマツコンサルティングの田中公康氏による、本書の内容をコンパクトにまとめた解題をご紹介します。
【解題】「デジタルDNA」を実装する
田中公康(デロイト トーマツ コンサルティング)
〝デジタルトランスフォーメーション〞という言葉が、一部の人たちが話題にする言葉から、政府が取りあげるまでに一般化し、ある種のバズワード化して久しいが、その実態はどうであろうか。言葉だけが先行し、なかなか前に進まない、または成果が上がらない企業が多いのではないだろうか。
本書は、原文タイトルがThe Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformationとなっているように、デジタルトランスフォーメーションの鍵は、実はテクノロジーではなく人であると述べている。これは、世の人々がデジタルというキーワードから想起しがちなイメージとは真逆だ。たとえ適切なテクノロジーを選択しても、導入のみに焦点を当てる限り成功につながる可能性は低い。デジタル時代の混乱に対応するためには、企業文化をよりアジャイル(俊敏) で、リスク許容性が高く、実験的なものに変えていくことが鍵となる。
この三つの特徴は、まさに昨今の日本企業が必要と感じながら苦手としていることそのものであろう。AI、ビッグデータなどの派手な先端テクノロジーには興味・関心を示すが、どのようにそれらを実ビジネスにつなげていくのか、という局面において考えあぐね、行動に移すことができないというのが多くの日本企業の実態ではないだろうか。
この状況に対する一つの解となり得るのが、本書のキーワードとも言うべきデジタル時代に求められる組織的な特徴である「デジタルDNA」を実装していくことにほかならない。詳しくは本書第3部を読んでいただきたいが、デジタルな業務環境を構築し、意図的なコラボレーションを実現しながら、アジャイルで実験的な考え方を育んでいくべきという、まさに今の日本企業がデジタル時代に対応していくために強烈に求められている要素が解説されている。特に、デジタル特区などでデジタルトランスフォーメーションを推進しようとしている担当者(IT部門、経営企画部門、新規事業・イノベーション部門の方)にとって参考になるだろう。
また、第2部にはデジタル時代に対応した優秀な人材を定義・採用・確保するためのヒント(特にリーダーシップやマインドセット)が散りばめられているので、特に企業で人事関連業務に従事している方にはぜひ詳しく読んでいただきたい。
本書は、広くビジネスパーソンにとっても、今後のキャリアを考えるうえで示唆に富んでいる。スキルが陳腐化するスピードが速まっていくこれからの時代、ビジネスパーソンには学習し続けること(生涯学習)がより強く求められる。終身雇用・年功序列が制度疲労を起こす中で、自らのキャリアを主導的に構築していくためにどのような企業・職場を選んでいくべきか、考えさせられることも多いであろう。デジタル時代に対応した企業(本書では〝デジタル成熟度〞が高い企業)は、当然のごとく関連施策を積極的に打ち出しているが、どのようにそういった企業を見極めるかのヒントになるだろう。
残念ながら、日本企業のデジタルトランスフォーメーションに向けた取り組みは、海外企業と比較して相対的にかなり遅れている印象を受ける。その大きな要因はデジタル化に対する全社的な危機感の欠如、もしくは危機感の共有が不十分である点だ。特に、様々な日本企業との意見交換や議論を重ねるにつれて、現場レベルでの危機感とマネジメント層との意識の乖離が大きい点は否めない。本書の著者の一人で、デロイトの同僚でもあるガース・R・アンドラスとデジタルトランスフォーメーションについて議論した際も、日本企業の危機感の希薄さと動きの遅さに驚きを隠せない様子だった。企業でマネジメントを担っている方は、第1部をぜひ詳しく読んでいただき、世の中で起きている大きなうねりを感じていただきたい。本書を通して、いま一度読者の企業内でのデジタルトランスフォーメーションの必要性の喚起や、具体的なアクションへと繋げていって頂ければ幸いである。
第1部 デジタルディスラプションを乗り切る
第1部は、デジタルディスラプションが「これから起きること」ではなく、「既に起きている現在進行形の出来事」であり、対応・行動できないのはテクノロジーの問題ではなく、自分たち自身の意識の問題、特にリーダー層の問題であると述べられている。
まず、デジタルディスラプションが起きていることは認識しているが、マネジメント層・従業員ともに対応できていない。要因としては、テクノロジー知識が欠如しているマネジメント層が、この脅威を喫緊の課題として認知できておらず、またこの破壊的な変化によりビジネスのスピード感が従来のものと全く異なっていることも理解できていないことが挙げられる。また、従業員も過去の成功体験(能力の罠)に縛られ、特に大手企業ほど将来のために仕事のやり方を変えることを好まないことも大きな要因だ。デジタルビジネスがこれまでのビジネスと大きく異なるのは、より速いビジネススピード、学習しコラボする文化・マインドセット、多様な人材と柔軟なチーム組成、価値創出に焦点を当てた生産性の四つとなる。その中でも、今後は学習しコラボする文化・マインドセットが特に重要になる。これからの日本企業も、特に四〇代後半から五〇代のバブル世代の人材にとっては、この学び直しが生き残りの鍵になる。テクノロジーの基礎的な知識を常識として身につけ、過去の成功体験に縛られずに新しいスキル・仕事の仕方を学んでいくことを真剣に考える必要に迫られていると言える(第1章 デジタルディスラプションは周知の事実)。
コンシューマライゼーションという言葉に代表されるように、技術革新のスピードについていき、積極的に生活に取り入れているのは、企業ではなく個人だ。特に日本においては、従業員として働く環境よりも、個人として生活する環境のほうが、はるかに技術革新の恩恵を受けている(第2章 デジタルディスラプションで肝心なのは人間だ)。
デジタルディスラプションの脅威に対応するためには、デジタル成熟度を上げていくことが一つの解となる。デジタル成熟度とは、ゴールを定義して達成することを重視する考え方ではなく、絶え間ない継続的な取り組み・プロセスを通して環境変化に適応し、ギャップを埋めていくという考え方だ。技術環境の変化に対応するため、人・文化・業務・構造も一気通貫で足並みを揃えながら変化させ続けていく。特に日本企業は、過去一〇年の技術革新にすら組織が十分に適応しきれておらず、取り組み自体も散発的なものに留まっているように見受けられる。周回遅れ感は否めないが、動きだしたら早い日本企業の特徴に期待したい(第3章 デジタルトランスフォーメーションという誇大な表現を気にしない)。
デジタル成熟度を高めるためには、デジタル戦略が鍵となるが、これは必ずしも旧来型の戦略を示すものではない。短期構想を立てて実行に移し、そこから学ぶことで目標も再検討する。その過程を通してデジタルビジネスの全体目標を明確にする再帰的プロセスにほかならない。決して短期的思考だけをすればよいと言っているのではなく、一〇〜二〇年の長期的視野を持ちながら、一〜三年の短期のことを考える。環境変化が激しい時代にあって、めざす目標が絶えず動いていくのであれば、それにあわせて計画の立て方も変えるべきであろう。これは決してテクノロジーの話ではない。製造業型の計画策定・マネジメントアプローチに固執する日本企業にはパラダイムシフトが求められる(第4章 不確実な未来のためのデジタル戦略)。
デジタル戦略を考えるうえで、テクノロジーの特徴ではなく、テクノロジーが人と組織にどのような可能性をもたらすのか、という観点が重要となる。テクノロジーがもたらす可能性により、当初想定された活用方法以外のものが発見され、意外な効果を発揮する。ゆえに、単に目新しいテクノロジーを導入しても、効果や価値を創出していくのは難しい。むしろ、どのような価値を創出したいのか、そのために必要なテクノロジーは何か? というアプローチのほうが適切だ。最近の日本企業がデジタルビジネス系の取り組みを推進しながら、うまくいかない原因やヒントは、このあたりにありそうな気がしてならない(第5章 デジタル戦略に対するダクトテープ的アプローチ)。
第2部 デジタル時代のリーダーシップと人材を再考する
第2部は、デジタル成熟度を上げるためにはリーダーシップがもっとも重要な要素となるが、(デジタル)リーダーシップの在り方は本質・基本もこれまでとはなんら変わらないと述べられている。ただし、リーダーシップ発揮の仕方はこれまでと異なっており、そこを理解したうえで正しく行動できるかが鍵になる。
まず、環境変化が激しいデジタル時代において、組織は測定可能な効率性から学習に重視するポイントを変えていく必要がある。リーダーには、答えを持っていることではなく、失敗も含めた様々な取り組みを通して早く学んでいくことを奨励しチームが答えを見つけられる環境を作れることが求められる。デジタルリーダーシップは、単にデジタルツールを使うことで魔法のように発揮できるものではない。しかし、日本企業の場合はもう少しデジタルツールを活用したリーダーシップの発揮・コミュニケーションを考えてもよいのかもしれない。第1部で述べたように、技術革新への対応の遅さ(技術音痴)は、今後のリーダーシップの発揮においても大きな課題となりうる(第6章 デジタルリーダーシップは魔法ではない)。
これからのデジタルリーダーに求められるスキルのうち、日本企業では、「ビジョン」「デジタルリテラシー」「変化指向型」の三つが課題となりそうだ。漸進的なアプローチや業務遂行を得意としてきた日本企業のマネジメント層・従業員にとって、この三つは大きな壁だ。しかも、デジタルリーダーシップは、フラット化がより求められるデジタル時代の組織においては、より幅広い層に求められる。組織の形を変えるだけでなく全員がデジタルリーダーシップの要素を意識して行動することが必要となる。具体的には、下位層ほど現場に近く多くの情報を得やすい環境にあるため、意思決定権限を与え、主体的にリーダーシップを発揮していくことを後押しする。ミドルアップ文化が根強い日本企業にとって、この点はむしろメリットかもしれない。前提として、無駄なすり合わせをなくし、意思決定プロセスを整理し、現場に権限委譲することが前提になることは言うまでもない(第7章 デジタルリーダーシップに違いをもたらすものは何か?)。
優れたデジタル戦略を実現するためには優秀な人材が必要となるが、必ずしもスキルフルな人材を指すわけではない。むしろ、継続的に学習していく志向をもつ人材が重要となる。デジタル時代はスキルの陳腐化が激しい社会であり、時代に即した新しいスキルを都度身に着ける生涯学習が大事となる。知能は後から身に着けられる(先天的ではない)ということを意識付け、組織自体の風土として、継続学習を後押しする「しなやか﹇成長﹈マインドセット(growth mindset)」を育てていくことが、優秀な従業員を確保するうえで特に重要となる。研修の機会のみならず、新しい業務経験を積める機会を積極的に提供することや、日本企業も新人の時だけ重点的に教育コストを払うのではなく、広い世代に学習を後押しする組織に変わっていくことが求められる。個人レベルで見ても、一部の元気なシニアは「しなやかマインドセット」を持っているように思われる。今後は、現役世代(特に四〇・五〇代)も積みあげた実績や経験を活かしながら、常にスキルをブラッシュアップしていくことが求められるようになる(第8章 デジタル人材のマインドセット)。
デジタル成熟度が高い企業は、人材獲得を教育で補っており、外部からの採用だけに頼っていない。十分に人材がいるかどうかではなく、人材開発のために何をしているかが今後はますます重要となる。人材開発に熱心ではない会社は、優秀な社員が流出するリスクが増大する。言い換えれば、人材流出を食い止めるためには、成長と発展の機会を与えることが有効となる。学びなおしには企業と従業員の双方にそれなりの覚悟が求められるだろうが、終身雇用が足かせになって人材ポートフォリオの再構築が進みにくい日本企業にはヒントとなるだろう。なお、本書では高頻度で意図的に様々な仕事に関与させることを「異なる職務の体験(ツアー・オブ・デューティ)」として紹介しているが、これは日本企業がこれまでやってきたジョブローテーションを、もう少し意図的かつ高頻度に行う取り組みだ。スクラムやアジャイルもそうだが、これまで日本企業がやってきた取り組みの良さを時代に即した形にアレンジしたともいえる(第9章 人材を引きつける組織にする)。
急速に発展するテクノロジーの進化によって、仕事の中身は変わり続けるだろうが、継続的に学習していく生涯学習者にとってはキャリアチェンジのチャンスとなる。硬直的な採用慣習や転職意識が残る日本において、キャリアを逆転させるチャンスが来ることを暗示している。いつの時代でもピンチはチャンスなのだ(第10章 仕事の未来)。
第3部 デジタル組織になる
第3部は、デジタル時代に対応した組織になるためには、デジタルな文化(アジャイル・コラボ・反復)を意図的に醸成していくことが不可欠であり、これまでの文化にデジタル組織の特徴「デジタルDNA」を組み込んでいくことが重要であると述べられている。
まず、デジタルトランスフォーメーションを推進していくためには、トップダウン型だけでは不十分で、文化主導型のボトムアップアプローチも重要となる。デジタル文化は決して自然発生的ではなく、かなり意図的に創られ、そして維持されている。グーグルの二〇%ルール、電子メール廃止などの例からも、環境整備による文化醸成は意図的であり強制力も伴う。日本企業の場合は、もう少しデジタルツールの活用を強制してもよいかもしれない。デジタルツールの活用があまりにも遅れており、いまだにメール依存の会社が多い状況を見ると、その必要性は明らかだ(第11章 デジタル環境を育てる)。
日本ではまだ馴染みがない言葉かもしれないが、アジャイルこそが組織が変化に対応していく手段となる。少人数・多様なメンバーでコラボし、特定テーマについて現場主導で解決にあたるクロス・ファンクショナルチームの考え方もヒントになる。野放図にならないように、価値観や倫理観の共有などを通して一定の規律を保てるマネジメント手法も併せて身に着けていく。日本ではPJ型組織の導入が一つの解になるかもしれない。その際、外部人材とコラボしていくスキルが特に重要となる。タレントマネジメントの観点からオープンタレント・ギグエコノミーの要素も組み込んでいく。年功序列・終身雇用を前提にした業務運営のままでは、日本企業はこれからの時代に勝ち残れない(第12章 アジャイル方法論で組織する)。
クロス・ファンクショナルを機能させるためには、偶然に頼るのでなく意図的なコラボレーションが求められる。推進に際しては、必要性の喚起とデジタルツールが鍵となる。誰がどのような情報をもっているのか、誰とどのようにつながっているのかは、デジタルプラットフォームで簡単に可視化することが可能だ。必要な情報やそのやり取りについても、同様に簡単に検索し閲覧できる。少し前までの日本企業は、新卒一括採用・終身雇用で会社とプライベートが一体化し、顔が見える関係を構築することで対応してきた。しかし、採用の多様化・入退職の多頻度化などで、今後は難しくなるだろう。働き方改革(コロナ対応によるリモートワークの急速な進展)などで薄れがちな職場内の人間関係・コミュニケーションを意図的に構築していくことが求められる(第13章 強さ、バランス、勇気、良識―意図的なコラボレーション)。
「速く失敗する。」これは伝統的な日本企業にとって一番苦手なことだ。安定が一番で変動や変化を少なくすることが美徳の企業にとって、大いに苦痛が伴う要素であろう。シックスシグマで有名なGEも時代の要請に応える形でファストワークというプログラムを開発した。成功か失敗かではなく、何を学んだかを重視・評価する意識に変えていかねばならない。学習がデジタル人材のマインドセットに不可欠であるように、成功・失敗の経験から学んでいく組織風土が不可欠になる。減点主義的な要素が色濃く、失敗を恐れる日本企業の意識・考え方を改めていく必要がある(第14章 速く試し、速く学習し、速く評価する)。
デジタル時代に求められるデジタルDNAを組み込み、これまでの強みを生かしながら新しいデジタル風土に変えていくことが重要だ。金太郎飴のようなステレオタイプ的な企業風土ではない、独自のデジタル風土を創造していくことが求められる。23個の特徴を把握し、何が足りなくて何を伸ばすべきなのかを把握・特定しよう。そのうえで、MVC(実用最小限の変化)の考え方を取り入れてまずは小さな成功体験を積み重ねていく。失敗を恐れずに、アジャイルに反復して経験を積んでいくことで、デジタル成熟度は高まっていくはずだ(第15章 前に進む̶̶実践ガイド)。
田中公康(たなか・ともやす)
デロイトトーマツコンサルティングアソシエイトディレクター。外資系コンサルティングファーム、IT系ベンチャー設立を経て現職。Digital HRとEmployee Experience領域のリーダーとして、デジタル時代に対応した働き方改革や組織・人材マネジメント変革などのプロジェクトを多数手掛けている。 直近では、HRテック領域の新規サービス開発にも従事。講演・執筆多数。
著者:ジェラルド・C・ケイン、アン・グエン・フィリップス、ジョナサン・R・コパルスキー、 ガース・R・アンドラス
監訳者:三谷慶一郎、船木春重、渡辺郁弥
訳者:庭田よう子
解題者:田中公康
発売日 : 2020/10/31
装丁:山之口正和
単行本 : 408ページ
価格:本体3300円+税
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

