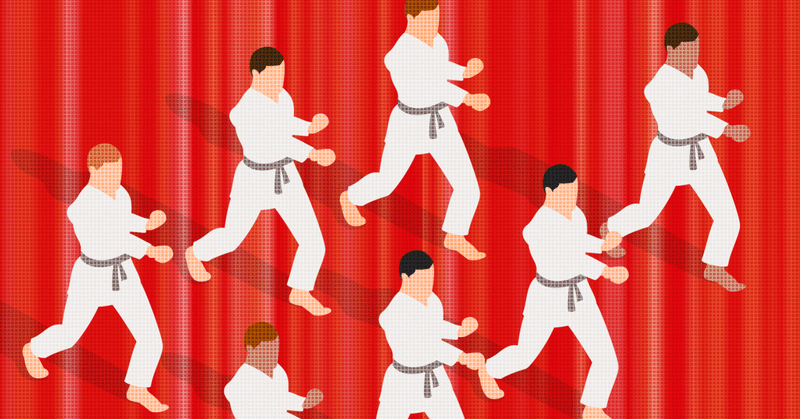
コーチングを学ぶ
こんにちは。
今日は最近勉強を始めたコーチング スキルについてシェアします。
「コーチという言葉は、もともと「馬車」のことを指し、「大切な人をその人が望むところまで送り届ける」という意味で使われていました。そこから「人の目標達成を支援する」という意味で使われるようになりました。
コーチングをする人(コーチ)はコーチングを受ける人(クライアント)に、
・新しい気づきをもたらす
・視点を増やす
・考え方や行動の選択肢を増やす
・目標達成に必要な行動を促進する
ための効果的な対話を作り出します。
ここで重要なのは、コーチがこれらを先導したり強制したりするのではなく、相手が主体性を持ちながらそれを実現するところにあります。
そのため、
コーチングでは、基本的に「教える」「アドバイスする」ことはしません。
その代わりに、「問いかけて聞く」という対話を通して、相手自身から様々な考え方や行動の選択肢を引き出します。 引用:コーチエィアカデア HP
コーチングを知ったきっかけ
私が勤める会社は、比較的に社内教育制度が充実しており
様々な研修コースがあります。その中で”コーチング”と言うものを知りました。
興味を持つきっかけとして、会社で中堅社員をまとめるリーダー的な業務に就任し
いきなり直属のチーム員4名 しかも、その4名は3名のチームを纏めている
総勢16人のリーダーになりました。
直接的な人事権はないもの、リーダーとしてチームを動かしていくにあたり
どうチームメンバーと接するのがいいのか、考えました。
一方で、最大のミッションのこの組織での活動をするのかの方向性も考えます。
ここで一つの葛藤が生まれます。
自分がプランを考え、伝える。その事がこの組織の活動として最良のものなか?
確かに自分自身はリーダーとして、メンバー1 考えている自身はありました。
しかし、それを伝え、納得してもらい。動いてもらう。
これが最良なのか。。。??
この時点で、メンバーは僕の中でコマ的な存在になるな
けど、一番考えている私の考えで進めるしかないよな。。。
逆に、なぜメンバーはアイディアを出してくれない。受け身だよな と
さえ思っていたかもしれません。
しかし、コーチングを知り私の中で気づきが一つありました。
相手が受け見なんじゃなくて、主体性を持てる環境を作れていないのでは??と
もちろん、理想的な姿は環境は与えられるものではなく、作るものです!!と
主体的に動ける人材が理想的かもしれません。
しかし、それは自分の好みであるだけで(自分自身はそうして来たから)、
私のチームに必要な能力ではないかもしれないと思えました。
私は強いチームを作るのではなく、自分な好きなチームを作ろうとしているのかも。。
この気づきはコーチングの中の新たな視点を持つ事で気づくことができました。
コーチングで得たもの
上記で記載した新たな視点をもとに改めてチームとしてすべき事、
また、チームがどうしていくべきかを考えました。
結論としては、
会社が主体性を持つ人材の集団になるように、
我々の組織から主体性を持って行動していこうと思うようになりました。
企業で働くと、主体性を出しにくくなります。
会社の方針や、制度は上位層で作られ決定事項が下される。
その決定事項に自分の意見や反論の余地はなく、ただ従うのみ。。
しかも、上位層は現場の状況をわかっているのか??と疑問もある。。
このような事を思いつつも、会社は我々社員に一辺倒に、
もっと多角的に考えて主体的に経営者目線で考えてくれ。と要求します。
この会社と社員の考えのギャップを感じ
そのギャップを埋めるには何が必要なのかを考えました。
そこにもコーチングの傾聴の姿勢をもった対話が答えの一つだと気づきました。
今や、会社も組織も部長も課長も担当もそれそれの立場で、様々な考えを持っています。良くも悪くもただガムシャラに働けばいい時代ではなく、
何かしら、意味や意義・効果を考えながら働いています。
しかし、その考えは各々の立場(視座)での考えだけに陥りがちです。
その結果、意見の対立や正解と不正解という二分化が起こってしまいます。
もしかしたら、最良の答えは双方のいいところを活かした答えを導く事で出るものではないでしょうか?
もっと極端な事をいえば、どちらも正解であり不正解であって
導き出した答えをお互いが腹落ちして、全力で取り組むことが最良の答えかもしれないと思うようになりました。
その為には、傾聴の姿勢(相手の話をじっくりと聞く)を持った対話(相互的な会話)が必要になると思います。
POINT1. 自分の考えを理解して貰うのではなく、自分が相手の考えを理解する。
POINT2. その上で、相手に新しい気づき(私の意見を知り、考えて貰う。)
*順番も非常に大切です。まず相手の考えを十分に理解しましょう。
我々は、最良の答えを出したいと思います。
その答えもとに、役割分担し遂行することが、一番効率的かもしれません。
しかし、その答えにはメンバーの想いが詰まってなく、発案者の想いのみです。
その答えには強さと発展はありません。
今必要なものは、
メンバーが自分も関わったと自分事できる導き方をした答えだと思います。
深くコーチングの勉強をする必要は無いかもしれませんが、
一度会議や打ち合わせの場で、相手を納得させる事より、相手がどうしたら自分毎化して取り組んでもらえるかという視点で臨んでみてください。
新たな発見があるかもしれません。
では、また次回
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
