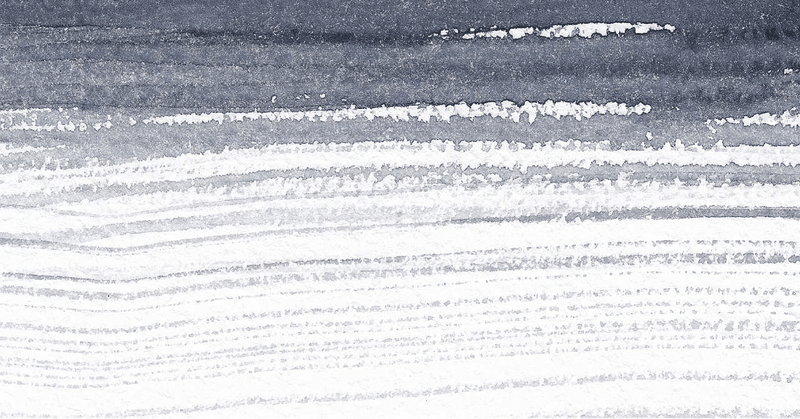
夕映えの恋 3
敦子は帰宅するとすぐに子供部屋ですやすや眠る息子二人を確認し、家政婦を帰し、シャワーを浴びた。このところ肌が老いてきたことを自覚しつつある彼女だったが、その夜はいつもと比べ肌が瑞々しく艶があって、これはもしかすると自転車で若い男に触れていたからかもしれない、と一人鏡の前で笑った。彼の身体にしがみついていた時の感触はまだ手や腕や頬に残っていた。細身だが密度のある筋肉が感じられる若々しい身体で、当然、夫とはまるで違った。自分を女優だと勘違いし、無邪気に家まで自転車で送り届けてくれた金髪の店員の可愛らしい笑顔を思い出しながら、敦子は彼が好みそうなお土産を持って喫茶店にお礼に行く計画をあれこれ立てて眠りについた。
しかし翌朝、息子二人にけたたましく起こされいつもの忙しない日常が始まると「店員へお礼がしたい」という昨夜の衝動は少しずつ薄らぎ、そのうち、店に店員が不在の可能性を危惧したり、彼もそんなお礼をされるのは寧ろ迷惑なのではと心配したり、敦子は喫茶店への再訪に気後れするようになった。その感情の変化が忙しさ故の余裕のなさから来ているのか、薄暗い夜に着飾った自分しか見ていない若者に再会する躊躇から来ているのかはわからない。が、無為な葛藤を繰り返しているうちに一週間、二週間と時は過ぎお礼のタイミングをすっかり失ってしまった。そもそも敦子の日常はそのほとんどが家族への奉仕で成り立っている。夫が出勤し子供たちが幼稚園や小学校に行っている間も彼らのための事務仕事や買い物、断りきれないママ友との交友や夫の病院関連の付き合い、義母が自宅に来ることもしばしばで、二駅先の喫茶店にふらっと立ち寄るくらいのことが彼女にとってはなかなか難しかった。
・・・
あの夜からすでに1ヶ月以上経ち、梅の見頃も終わるほどに春が近づいていた。ある日、敦子は朝起きた瞬間から物憂い気分で、憂鬱が肩に重くのしかかっているような調子の悪さを覚えた。キッチンダイニングから見渡せる大きな窓からは外のどんよりと重い灰色の雲が見え、このモヤモヤは昨日の義母との会話のせいでも、疲れのせいでもなく、天気のせいなのかもしれないと自分を慰めた。
「どうした?体調悪い?」
身支度を終えた敦子の夫は立ったままコーヒーを啜り、そう声をかけた。
「あぁ、なんか、うん。気分がちょっと」
「熱は?」
「ううん、ほんと、気分だけなの」
「アレ、近いんじゃないの?」
「あー、うん、そうか。そうかもね」
夫は飲み終えたコーヒーをテーブルに置くと敦子の腰に手を回し「今日は何もしないでゆっくり休んで」と囁いた。優しい夫だ、と敦子は思ったが、もし夫が「何か嫌なことでもあった?」と聞いてくれれば、ここ数日彼女を少しずつ疲弊させた出来事を吐き出すことで澱のように心に沈んだ虚しさを少しは解消できたかもしれないとも思うのだった。
「そうだ。敦子、疲れてるのに申し訳ないんだけど」
「なに?」
「悠斗との約束。犬の件」
「あぁ」
「犬飼いたい気持ちは揺るがないみたいだから、やっぱりちょっと探しておいてもらえないかな」
「あー、もう。なんでそんな約束しちゃったのよ」
「ごめんごめん。でも、子供ん時に犬飼うのっていいらしいよ」
「どうせ面倒見るのは私じゃない」
「ははは、まあね」
夫は苦笑いしながら「ごめん、よろしくね」と言い、逃げるように家を出た。夫は次男の悠斗と小学校受験を終えたらペットを飼うという約束を敦子の知らないところで交わしていたらしく、悠斗はここ最近になって一年近く前のその約束を思い出し、毎日のように「わんちゃんはいつ来るの?」の質問を繰り返していた。敦子は動物嫌いではないがペットを飼うことには気乗りせず、夫からの依頼を聞いてさらに憂鬱になった。
・・・
子供二人を送り出してもなお、空には重い雲が広がったまま雨を持ちこたえていた。敦子はふとあの喫茶店に行くことを思い立った。ちょうど何も予定の入っていない日で幼稚園のお迎えまで時間的余裕もあるし、心からほっとするにはあの珈琲の味が必要だと、無性にあの場所に身を置きたくなったのだ。身綺麗にして行きたいという変な虚栄心はすでになくなっており、敦子はカジュアルな装いのまま、一見それとはわからない洒落たレインブーツを履いて喫茶店へ向かった。
喫茶店に入るやいなや、敦子は店内を見回し金髪を探した。しかし、あの店員は奥の部屋から出てこず、彼女を案内したのは感じのいい女性店員だった。敦子は珈琲を頼み、持ってきた本を開いた。でも、人気を感じるたびに顔を上げてしまい本に全く集中できない。それで結局先ほどの女性店員を呼び止め金髪の店員について尋ねた。
「すみません、こちらで働いている方にお礼を言いたくて来たんですが」
「はい…」
「金髪の若い、男性の店員さんなんですけど、今日はいらっしゃらないですか?」
「金髪?あー。そうですね、今日はシフトが入ってないはずです」
「そうですか。ありがとうございます」
出された珈琲は期待通りの味だったが、敦子は何か物足りなさを感じた。本当は店員のあの笑顔が見たかったと、もっと早く来るべきだったと少し反省した。しかし、彼はバイトを辞めた訳ではなさそうである。今日は本をお供にゆっくりと自分のために時間を過ごそうと敦子はまた本を開き、そのうちにどんな物音や気配にも反応しないほどに物語の世界に入り込んだ。
敦子は若い頃、"超"のつく活字中毒だった。特に恋愛小説が好きで、だからこの喫茶店にはいくつもの恋物語の記憶があり、漂う香ばしい匂いは敦子にとってはイコール本の中のドラマチックな恋の匂いでもあった。しかし、結婚し子供を産んで、いつの間にか小説自体をあまり読まなくなった。正確に言えば年に数冊程度は読んでいたが、恋愛小説でないことが多かったし、たまに読む程度だから活字の海に溺れる恍惚もなかった。敦子は今日この店に来る途中、平積みされた新刊本の中に心奪われる装丁と美しい紹介文が帯に書かれた本を見つけ久しぶりに恋愛小説の世界にトリップした。珈琲の薫りに包まれてページをめくれば日常の憂鬱なんてすっかり忘れるほど夢中になり、敦子はここ十数年の間に忘れてしまっていた幸せを今、感じていた。だから、昼食代わりに頼んだ玉子サンドも大して味わえなかったし、店の扉が勢いよくバタンと開く音にも全く気づかなかった。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
