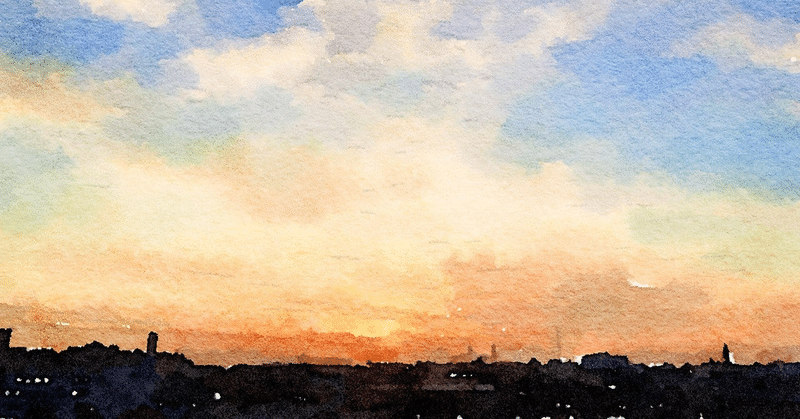
夕映えの恋 1
序
この物語の主人公、村崎敦子さんに出会ったのは2019年の12月、大韓航空の機内だった。ソウル行きの飛行機で私の隣にやって来た彼女は質の良いコートを羽織り背筋がピンと伸びていて、コートを脱ぐとシンプルなグレーのカシミアニットに趣味のいいアクセサリーと赤みの強いリップが丁度良い調和をもたらしていた。要するに、彼女は見るからに素敵な「現役」の女で、私は率直に自分の隣席がくたびれたおばさんではなく彼女であったことを喜んだ。いくら美人でも肌の質感や空気感で年齢は大体伝わってくるものである。彼女はなんとなしに自分と同世代のような匂いがしたのでシートベルトの片方を見つけられずにいた彼女に私は思い切って声をかけた。お互いに連れのいない二人は年齢も同じ三十八歳で、およそ二時間半のフライトで意気投合し、古くからの知人になら寧ろ話せないようなことまで打ち明け合い、ソウルに降り立つ頃には完全に友人のような関係になった。
彼女は笑い上戸で明るい人だった。一人で韓国へ旅行するのだからきっと韓国のドラマやアイドルのファンなのだろうと思ったのに呆れてしまうほどにそういったことには何の関心もないようだった。私は当時の日本人ならいくらかは知っていそうな有名人の名前をあげ、でもどれに対しても「うーん」というような反応をする彼女を笑った。
「出張でもなく韓国の誰かのファンでもなく、じゃあ一体どんな目的でたった一人でこの飛行機に乗ったんですか」
私が笑ってそう尋ねると、笑顔だった彼女の顔に薄いヴェールのような影が差した。秘め事を抱えたような頬と口角は柔らかい熱を帯びたように見えた。
「人に、会いに行くんです…」
彼女は俯き気味に静かに答えた後、あまり根掘り葉掘り聞いてはいけないと直感し口ごもった私の目をしっかり見据え「実はね…」と、とある男性の話を聞かせてくれた。
正直に言うと、私は最初彼女の話を聞き続けることに多少の抵抗を感じた。まるでフランス映画のように退屈で酷くロマンチックな恋の話は美化された作り話のようにも聞こえたし、彼女の薬指に指輪が輝いていることには彼女が隣に座ったその瞬間から気づいていたから、その恋のお相手がどうやら夫ではないと気づいた辺りで私の方に多少ながら嫌悪感が生じたのだ。それでも、過去の感情を丁寧に反芻するように語り続ける彼女の、未だ葛藤しているような瞳を見ていたら、いつの間にか私は彼女の経験を自分の経験に感じてしまうほどに引き込まれた。いや、飲み込まれた、と言った方が近いかもしれない。
私はその後、ソウルでも東京でも彼女に会った。その男性にも、彼女の夫にも会った。だから余計に、初めて話を聞いた時に腑に落ちなかった点も全て、あまねく細胞に吸収されるように理解ができ、あくまでも断片的にしか知らないはずの彼女の恋愛に囚われ、時折「私ならどうしていただろうか」という疑問をぐるぐると何度も考えたりした。
今から私が書こうとしている物語は全てが事実に基づいている訳ではない。そもそも私は当事者ではないし、彼女から聞いた話すらもどこまでが本当なのかわからない。それに私は決して彼女に起きた出来事を詳らかにして彼女が「どうすべきだったか」を考えたいなどという変な使命感でこれを書くのではない。寧ろ、ただシンプルに、彼女から聞いたその恋を私が美しいと感じたから、その美しさを追体験するべく筆を進めるのだ。
・・・
第一章 出会い
2016年1月、村崎敦子は夫とバレエを観に来ていた。代々医者の家庭に育った彼女の夫はオペラやらクラシックやらの高尚な趣味を持つ男で、その日も敦子は二人の子供を家政婦に預け、クリスマス頃に夫と出かけた時に買ったマックスマーラの上品な白いドレスとふっくらとした厚手のコートを着て、腕を組み、会場に向かった。
開演前のホワイエは談笑する客で混み合っており、その中には夫の知人もいた。まるで外国人のようにハグで挨拶し、いつも通りの優雅な会話を始める。ただし、途中ですぐにバレエとは関係のない下世話な話題になった。数日前に国民的アイドルグループの解散話がスクープされて以来日本中がその話題で持ちきりになっていた。夫も知人も例に漏れず、5人の人気者のスキャンダルと謝罪会見の話題で盛り上がった。
「会見は気の毒だったけど、でもやっぱり残って良かったんじゃない?あれだけの大きな組織に楯突いても身を滅ぼすだけだから」
知人は敦子の夫と全く同じ意見を述べた。夫は敦子の方を一瞬「ほらね」とばかりに見やり、知人と話を続けた。実のところ、彼女にとってこの解散スキャンダルはその内容以上に何か色々と考えさせるきっかけを与える出来事であって、それはすなわち夫との感じ方考え方の不一致だった。すぐ身近にいる家族が同じニュースを見て全く別の感情を持っていることに驚き、居心地の悪さを覚えていた。
「敦子はずっと会社が恐ろしいと、そればっかり言っててね。たとえ4人だけでも脱退して自由になるべきだって言うんだよ」
「敦子さん、誰かのファンなの?」
「いえ、そういう訳ではないんだけど」
「ふーん。でも、敦子さんらしいね」
館内放送が流れると夫婦は流れるように会場へと入った。敦子の中に生まれた取るに足らない不満の感情は燻ったまま、夫の完璧な立ち居振る舞いと目の前の完璧な芸術に押し潰される。こんな小さなことで不満を感じる自分に寧ろ問題があるのかもしれない、と思わされる。考えてみれば夫との日々はそういったことがいくつも何度も繰り返される生活であったなぁと、彼女はバレリーナのグランフェッテを眺めながらぼんやりと思った。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
