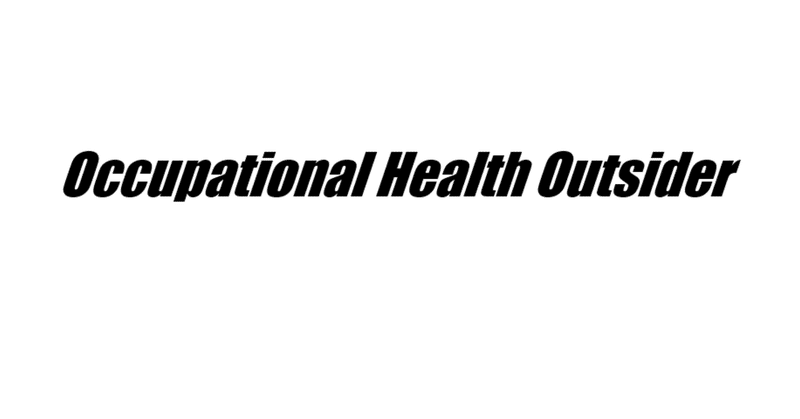
1.とりあえず法人化するという産業医の闇
※ほぼ全文無料で読めますが、気が向いたら課金してもらえるとやる気が出ます
自分は産業保健業界で知り合いも少なく、いわゆる光の当たる表舞台に出てくるような産業医ではないアウトサイダーです。
その細々とした活動の中でも、当然今まで「危ねえな」と思った経験は幾度もあります。主にそれらについて書いてみようと思っています。
この記事はガチ産業医先生の産業保健の落とし穴シリーズにインスパイアされて書きました。
いってみれば、そちらが「光の落とし穴」なら、自分のは「闇の落とし穴」をイメージしています。
※ガチ産業医先生のnoteは産業医はじめ産業保健に携わる方ならとても勉強になるし、まとめて購入すれば2,000円と、認定産業医の更新単位1単位よりも全然安くてとってもお得なので買いましょう
はじめに
嘱託産業医をある程度やっていると、合同会社とか株式会社を作っている医者が多いことに気づくと思います。
先輩や知り合いに「法人化したほうがいいよ!」と誘われたことがある方もいるのでは。
なんか法人化するとお得なのかな、やってみようかなということで、よくわからないまま会社を作る人もいるのですが、それはよく考えてからのほうがいいんじゃないか、という内容です。
※医療法人を作りたいという方は、また全然別の話になります
なんでみんな会社を作るのか
これは一言でいうとお金の問題です。
いやいや、私はお金じゃなくて崇高な意識をもって会社を作ったんだ、と言う人もいますが、とりあえずお金は会社設立のモチベーションの原動力としてかなり大きいはずです。
そもそも基本的に株式会社・合同会社は営利を目的とする法人なので、お金のことは一切考えてない!というのはきれい事です。
マイクロ法人(自分だけ、または家族等が役員なだけの会社)を作ったという医者に、「なんで会社作ったんですか?」と聞いて、お金の話が一切出てこない場合、きれい事しか言わない人なのか、あなたはまだそんな事話す間柄じゃないと思われているか、どっちかです。
どうしてお金が得になると言われているのか
まず、一番大きいのは、法人税の税率の方が、一般的な医者の所得税率+住民税率+社会保険料率 より安いから。
細かい計算は省きますが、1400万円の給料もらっている医者と、給料1000万円+自分の法人で法人所得が400万円の医者で比べると、トータルの稼いでる額は同じでも、後者の方が払う税や社会保険料は少なくなります。
くわしくは例の「医学生・若手医師のための なんとかかんとかおカネの話」でも読めば書いてあるんじゃないかと思います(自分は読んでないので書いてあるか知りません。)
また、二番目の理由として、会社を作ったらとにかくいろいろ経費にできて得だよ、とよく聞くと思います。これ、医者があまりにその辺にうといことが多くて、下手すると喋ってる方もわかってないこともあるんですけど、
原則は
あくまで事業による収入があって、その中から経費となる支出があれば、
その収入に対する税金が減る
という仕組みですからね。
これを、一番目の理由と合わせて考え、むちゃくちゃ簡単に言い換えると
会社としての収入がある程度なければ会社作っても得しようがない
ということです。「何当たり前のこと言ってんだ?」という感じだと思いますが、これを理解してない人意外といます。それで、個人のお金から資本金を出しているのに、そこから高い買い物しまくって「経費になってお得!」とか勘違いしたりしてしまうわけです。
そのお金はもともとしっかり所得税ひかれた後のお金なので、全然得になってませんし、そういうことしている人に限って経費として認められないようなものを経費にしようとします。
事業所得って
いま事業所得がある方なら、それを会社としての所得に変換できる可能性があります。
事業所得って何ですかということですが、医者の中でいえば「給与所得じゃない収入」です。つまり勤務先の病院からもらっているお金、バイト先の病院からもらっているお金、スポットバイトのお金、これらはよっぽど特殊な場合を除いて全部給与所得です。事業所得にはなりません。
あなたがバキバキの整形外科医で病院から年収2000万円以上もらっていたとしても、その中で事業所得にできるお金は1円もありません。
ざっくり言えば病院以外からのお金、製薬会社での講演料、医学原稿の執筆料、そういうのが事業所得になりうるお金です。あと不動産投資やっている人なら不動産収入、コンサルティングをやっている人のコンサル料なども事業所得になりうるお金です。youtuberとか、あとこのnoteの有料記事とかも事業所得にできそうですね。
産業医の収入は事業所得か?
あくまでこの記事は「産業医の闇」なので、産業医としての収入が事業所得なのかどうかが大事なところです。
結構センシティブなんですが、結論はしっかり出ています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm
(注) 個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。
これ、国税庁HPにこう書いてありますんで、もうひっくり返りようがありません。給与です。
ただ、「原則」というのが気になるというか、どうしても諦めきれない人もいると思います。
クリニックの経営に強いという税理士事務所のHPを見つけました。
(マジで強そう)
https://www.nagai-consulting.com/clinic/2017/10/11/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%8C%BB%E3%81%AE%E5%A0%B1%E9%85%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
>この点、国税庁の質疑事例によれば、個人の医師(勤務医・開業医)が派遣先の会社などから受け取る産業医報酬は、原則として給与になるとされています。
>ただし、医師と派遣先の会社の間に仲介会社が入っており、仲介会社から医師に対して報酬が支払われる場合には、仲介会社と医師との間に業務委託契約が結ばれることがあり、この場合には事業所得または雑所得として扱われるケースもあります。
ということで多少あいまいな部分はあります。産業医に限りませんが、原則として給与所得なのか事業所得なのかは、契約書になんて書いてあるかじゃなくて「実態」で判断されるということなので、あいまいになってるんでしょうね。
ということで、私の知る範囲では、産業医紹介会社でも、報酬扱い(=事業所得)での支払いはお断りして、すべて給与で支払っている、というところがあります。
番外:「労コン持ってたら事業所得」か?
労働衛生コンサルタント(労コン)持っていたら産業医は事業報酬になる、っていう話はたまに聞きますし、それが労コンを取るモチベーションにまでなっている場合すらあるっぽいのですが、
自分の結論としては「あんまり関係ない」です。
これ、なぜまことしやかにそう言われているかというと、労コンの口述対策でも覚えることになるこの条文がもとになっているようです。
労働安全衛生法 第81条2項
労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
「あっ法律に報酬って書いてある!よっしゃ労コン持ってるから全部報酬=事業所得や!」という結構短絡的な発想なのではないか…
ここでの「報酬」をそのまま事業所得と考えるのは無理があるし、
そもそも、労働衛生コンサルタント業務を行うならまだしも、あなた労コンを持っているだけであって、産業医業務をしてますよね? となれば前提が崩壊します。
法人化すると
さて、労コン持ってようが基本的に産業医は給与所得とわかってしまいましたが、法人化して法人として企業と契約すると話は変わってきます。法人相手に給与は払えないので、とりあえず法人収入ということになります。医療法は会社による病院や診療所の開設を認めていませんが、産業医は「医者しかできないけれど医療行為ではない」というわりと反則な位置付けにあるので、会社として引き受けできます。(今のところ)
なんだ、ビビらせやがって、やっぱり法人化したらいいんじゃないか!
…?
法人は作るの簡単、管理するの大変という落とし穴
もう落とし穴って言ってしまってますけど、やっぱこの方がしっくり来ます。
会社作るときのコストは、どこまで士業に頼むかにもよりますが
合同会社で15万円くらい、株式会社で30万円くらいみておけば作るは作れます。医者だと臨床の仕事とかで忙しいので士業にいろいろ頼む人が多いかと思いますが、いずれにしてもこの時の諸手続きは「会社作るぞ!」ということでアドレナリンやらドーパミンが出て楽しくやれると思います。
つまり会社作るのはある意味簡単です。
しかし会社の経理や諸手続きはそこまで簡単ではありません。
会社はちゃんと帳簿をつけないといけないので1回どっか訪問行ったらそのつど売上を計上し、経費を計上するのに領収書の山と格闘し、自分で記帳するなら仕訳だなんだと非常に大変な思いをいつもすることになります。
忙しいという事でで人や税理士に任せることはもちろん可能ですがその場合当然費用がかかります。また、記帳は頼まないにしても、会社の決算を自前で行うことは、不可能ではないにしても極めて困難です。(やってる人もいますが、よほど時間があって好きでないとできない)個人の確定申告なら毎年やってるし余裕っしょ、とか思ってると死ぬことになります。
なので税理士に顧問なり決算なり頼むことになりますが、当然年間2ケタ万円はコストがかかります。
年間30-40万円くらい見ておきましょう。
他にも、法人の収入を自分のお金にするには法人から自分に役員報酬を払わないといけません。その時当然個人に所得税がかかってくるし、社会保険料もかかります(常勤先で入ってるから自分の法人では社会保険に入らないというのはダメ)
「法人の収入=自分のお金」じゃないですからね。会社の財布と自分の財布は完全に別です。ここを混同するとめちゃめちゃになります。
この感覚に慣れられず、「俺が稼いだ金は俺のだろ!」みたいな人は法人化によりむしろストレスが溜まると思います。
あと、オフィスを借りるなら当然そのお金がかかります。
登記できるバーチャルオフィスでも月額7000円くらいはかかります。年間10万はみましょう。
イケてるスーパー産業医の先生はweworkでも借りてください。
あ、忘れてましたけど法人の銀行口座作るのはとても面倒くさいです。かといって個人の口座でやるわけにもいきません。
会社との契約なのに、振込先が個人名義の銀行口座だったらめちゃめちゃ怪しいですよね?
法人口座がないと実質的にお金のやりとりができないので、何も始められないのです。
作る時の審査なども死ぬほど面倒なのですが、法人口座はインターネットバンキングとかに月額手数料がかかります(都市銀の場合)。あと振込手数料も個人口座の倍くらいします。銀行は個人相手と法人相手では全く別の顔を見せてきます。
例えばインターネットバンキング手数料が月額2000円だと年間24000円。
大したことないといえばそうかもしれませんが、個人ならかからないお金です。
あー、あと当たり前ですが法人にも税がかかります。給与と経費で全て法人収入を使い果たし、赤字になったとしても最低7万円弱はかかります。
他にも雑費はいろいろかかりますが、
税理士報酬 30万
バーチャル/シェアオフィス 10万〜
ネットバンキング 2万
法人税 7万〜
事務作業の手間 Priceless
(医者の時給で考えましょう)
ということでランニングコストは金銭面、手間面の両方でかなりあります。
加えて、経費引いた収入から自分の給与を出すと、自分個人にその分所得税と社会保険料負担がかかります。
…あれ?
全然お得にならないじゃんという話
そうです、普通にやってたらあんまりお得にならないんです。
いやあいつは自宅を社宅にしとる!とか、小規模企業共済がーとか、
車を経費で買っとる!とか、ただの旅行を出張扱いにしとるんじゃとか、
家族や愛人を役員にして高額な役員報酬を払ってるんじゃー、とか、
いろんな話はありますし、それはまあ節税になるとは思うのですが、
それもこれも、それを上回る法人収入がないと何にもお得になりません。
自己資金を会社に突っ込んで経費に回していたら、会社やさんごっこしてるのと同じです。
最初のほうに書いた、
会社としての収入がある程度なければ会社作っても得しようがない
ということに尽きるわけです。
法人契約にしてくれないという落とし穴
自分は嘱託先もたくさんあるから、法人のランニングコストを払ってもまだおつりがくるし、やっぱり法人化するぞ!という先生もいると思います。
そこで一つ、予想してなかった問題が出てくることがあります。
いま契約してる企業、法人契約に切り替えてくれますか?
これ、紹介会社が間に挟まってるところはあんまり問題ないんです。紹介会社と産業医の間での契約になってるので、訪問先の企業にとっては産業医が個人だろうと法人だろうと関係がない。
紹介会社は法人契約に変えてくれと言えばすんなり変えてくれます(はずです)
問題は企業と産業医個人が直接契約してるときで、与信調査に引っかかるときがあります。
大きな企業だと法人と契約するときには一定のルールがあって、与信調査をクリアしないと契約できないなどいろいろな制約がある場合があります。
個人では医者は医者というだけで絶大な社会的信用があり、
めちゃめちゃな額のローンも簡単に組めますが、
医者が作ったできたてホヤホヤの法人は全然世間的に信用がない
ということです。
よく調査の一環で、バランスシートを出してほしいとか言われることもありますが、作ったばっかりの会社で1期目だとそもそもそれがない。
これは某社から回ってきた案件のメールのスクショです。
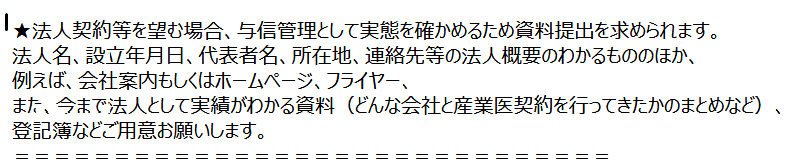
面倒でしょ?もちろんこれは新規の話なのですが、法人契約は会社にとっても比較的面倒と思われることが多く、こいついけてない産業医だなと思われていたらそもそも担当者の時点で法人契約お断りされるかもしれないし、
担当者とはうまくいっていたとしても、会社のルールとして与信調査が必要で、それにひっかかったとしたらどうにもなりません。
あと、実体験ではなく見聞きした範囲の話ですが、中小規模の産業医事務所で医者がやってるようなところが間に挟まってると、そことの契約を法人に切り替えるのを断られたりめちゃめちゃ渋られる事もあるっぽい。
嘱託先は複数あっても、法人契約に切り替えられなかった会社があって、その結果コストをペイできなくなった、とかなると非常に悲しいので、法人化を真剣に検討するなら前もって法人契約にできるかどうか探りを入れておいたほうがいいです。
それでも法人化したい
自分の周りで言うと、マイクロ法人をやっている医者は、
1、産業医たくさんとか不動産収入とか、
いっぱい本書いてるとかで、法人収入がすでに結構ある
2、法人収入はあんまりなく赤字だが、
とにかく「社長」になってみたかった
3、投資マンション屋にカモられてるバカ
のどれかです。1は法人化するのはある意味当然だし、2も目的をかなえているという意味で全然いいでしょう。3は別として、
1、2のどっちかでなかったら安易に法人化しないほうがいいんじゃないかな、というのが自分の感想です。
ただ、自分が1に当てはまるのかどうかわからないというのが最大の問題だと思うので、結局おすすめは
税理士に相談すること
です。医者は、医学に関することを他業界の人が言っていたら「素人がイキりやがって」と思いがちですが、お金に関してもそうです。
お金とか税のプロは税理士・会計士。この記事だってプロから見たら「バカじゃねえの」と思われるはずです。
とにかくプロに、法人化したほうがいいのかしないほうがいいのか、じっくり相談してそれで決めてください。
最後に
よく人の状況も知らないのに「法人化しましょうよ」と言ってくるやつは
多分悪い奴なので注意しましょう。
※気が向いたら課金してもらえるとやる気が出ます。
課金で増える行はお礼のメッセージ+㊙まめ知識の1行だけです
ここから先は
¥ 200
いつもありがとうございます。
