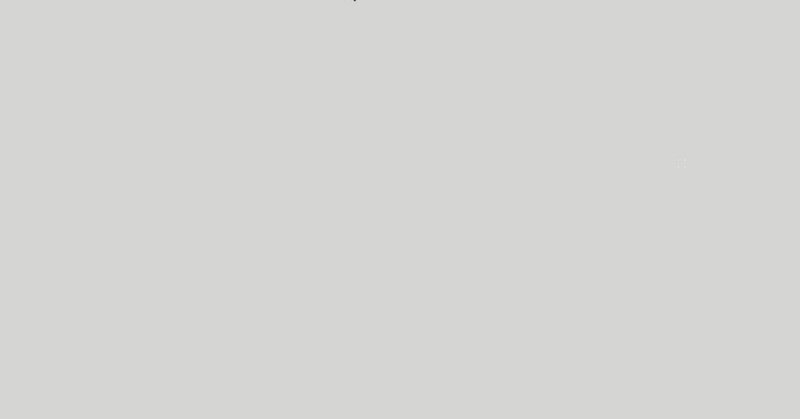
香りとテキストにまつわるフレイバーテキスト
デザイナー・リサーチャーとして活動する青山新さんに、香りとテキストの関係について寄稿いただきました。香水の商品紹介文を〈フレイバーテキスト〉として読み解き、そこから立ち昇る香りを静かに聞く。美しくも妖しいエッセイをお楽しみください。(編集部)
*
まずは香りと関係のないものからいこう。Nigel CabournのEVEREST PARKAはその公式サイトで、3,000字近い文量をもって紹介されている。
本製品は、世界最高峰であるエベレストに挑んだ、英国登山隊が着用していたヴィンテージウェアをベースにして、デザインされています。
商品については以上である。残りの2,900字は人類の極地開拓競争に捧げられている。月に星条旗が突き立てられ、アムンゼンが南極点を制す。各種の前人未到のうち、ついに英国が破したのは世界最高峰だった——すばらしい、感動的だ。
この商品紹介テキストにはブランドのスタンスが極めて明瞭にあらわれている。彼らが提供しているものとは、ブランドの、ひいてはイギリスのオーセンティシティである。グースダウンのフィルパワー? 鮮やかに発色したベンタイルコットン? コヨーテファーのラグジュアリー? よろしい、だが関係のないことだ。顧客はテキストを読み、在りし日の帝国の威信、探検家の情熱、そうしたものを追体験する。それらの物語が衣服として結晶し、目の前に立ち現れていることそのものに感嘆する。きみは極寒のエベレストを想像しながら生温い都市でジャケットを羽織り、滝のような汗を流すだろう。
このエピソードはわたしが香りについて書こうとすることの完全な寓話である。
*
ともあれ、服にせよ香りにせよ、身に纏うものであることに変わりはない。2020年以降、これらの購買体験は大きく変わった。各種のオンラインフィッティングや来店予約制が導入され、CtoCと区別のつかないような小規模ポップアップが湧き起こった。そもそも、オンラインショップや百貨店にみっしりと陳列された服や香水は「比較検討を重ねればもっともすぐれた選択肢を選び取れる」というフィクションを加速させる。しかし当然ながら、あらゆるものをあらゆる観点で検討し決断を下すためには、無限の時間と処理能力が必要になる。ゆえに真に重要なのは、いま/ここにおける不完全性をかけがえのない一回性としていかに聖別するか、という問いになる。消費者はどこかの時点で、無限の選択肢を比較検討する「全知全能のフィクション」から、信ずるに足る一回性を瞬間ごとに紡ぎ出す「愚者のフィクション」へと信仰の対象を変えざるをえない。
この観点において、香りは議論の中心となる。なぜなら香りに対する印象は、服のそれに輪をかけて繊細だからだ。昨日と今日、いや数時間前と今でさえ、香りに対する印象はまるっきり変化する。そしてやっかいなことに、わたしたちはそれが香料の化学的変化に由来するのか、自分の身体的・心理的変化に由来するのか、それとも時間や空間といった環境的変化に由来するのかを嗅ぎ分けることがほぼ、できない。こう考えると、香りの選択において瞬間瞬間の判断を寿ぎ、その一回性に揺るぎない物語を付与することはほとんど不可能にも思える。わたしたちはいかにして、商品リストをザッピングするカウチソファの神から、無二なる香りを纏った愚者に変身できるのか。この変身の最中において嗅ぎとられるものこそ、テキストの香りである。というのがこのエッセイでのわたしの主張になる。
視覚的実体を持たない香り、特に香水を取り巻く各種のメディウムは、それぞれがそれぞれの発展を遂げている。一番わかりやすいのは直接的に香りのイメージを表現する(フォト)グラフィックだろうが、他にも例えばボトルデザインでは、木や金属、レザー、綿などを使ったFilippo Sorcinelliの各種ラインや、Mendittorosaなどが高い独自性を示している。こうしたものたちの総体として醸し出される雰囲気(アトモスフェア)はまさしく、現実の香りと欲望の香りが混ざり合った境界的な存在となる。
しかしその中でも特に、香水の商品紹介のテキストは面白い。本来商品紹介とは、インターフェースとしての商品の背景をなす構造を、言語に仮託して前面化するものであるはずだ。しかし香水のそれはむしろ、テキストを通じて本来商品に内在していたかどうかさえ不明の質感を生成する(もちろんこれは、服や食事、アルコールといった、物質が主体でありながらその体験の主観的価値判断に重きが置かれる商品に共通の性質ではあるが)。わたしたちはテキストで語られた世界観やシーンから、実体とフィクションの境界線上に広がる香りを嗅ぎとる。その意味においてこれらのテキストは、極めてパフォーマティヴなものになる。テキストを経由して初めて知覚可能な香り。言語の原初的な魔術性を保った存在。すなわち、文字通りの〈フレイバーテキスト〉がここに潜んでいる。
*
さて、先に述べたように、こうした〈フレイバーテキスト〉の魔術が最大限に発揮されるのが、実際に商品を買うかどうかを判断する場面である。パラメータの羅列から一回性の物語へと飛び移るためには、香りの物語が語られるだけでは不十分なのだ。そこには、物語の香りが立ち込める必要がある。
ここからは、わたし自身が購入した香水を例に、〈フレイバーテキスト〉から立ち昇る物語を探索してみたい。
例えば、By KilianのBack to Blackでは「蜂蜜と煙草による媚薬」が主たるテーマとして語られる。蜂蜜と煙草。この組み合わせ自体はそれほど突飛でないが、あらためて考えるとこれらはクロード・レヴィ・ストロース『神話論理』の二巻『蜜から灰へ』を思い起こさせる。ここでは、料理という「火による文明化」の周辺を回るものたちとして、火を通さずに食べられる蜂蜜と、灰になることでこそ楽しめる煙草が挙げられ、自然→文化のベクトルが宙づりにされる。Back to Blackではこれが媚薬(aphrodisiac)という、正気と狂気の間をとりなすアイテムの構成要素として登場してくるわけだ。そしてなにより、香水という存在自体が、蜂蜜と煙草に連なって「料理の周縁をなすもの」として考えられる点も美しい。
*
真ん中に大きな換気孔があり、きわめて低い手すりで囲まれた、不定数の、おそらく無限数の六角形の回廊で成り立っている
ホルヘ・ルイス・ボルヘスの有名な短編「バベルの図書館」。これと同じ名——Biblioteca de Babel——を冠した香りを、アルゼンチンの香水ブランド「fueguia 1893」がリリースしている。ブランドが商品に添えたテキストを引用してみよう。
Borges’ cedar shelves are lined with books. Heavy leather bookbindings, vellum leaves and the smell of ink. Layers of words, thoughts, time and materials that make up a weathered book, brought to life.
(ボルヘスの杉材で出来た書棚には本がびっしりと並んでいる。重厚な革の装丁、羊皮紙とインクの匂い。古びた本に宿る幾重にも重なる言葉、思考、時間と物質が息を吹き返す)
バベルの図書館は、アルファベットで表現可能な全ての文字列を収めているとされる。すなわち、Biblioteca de Babelから立ち昇るインクの香りとは、あらゆるテキストの香りである。そしてバベルの図書館の性質上、上記の引用文もまた、その書棚のどこかの本に記されていることになる。あらゆるテキストから立ち昇った香りはフレーバーテキストへと変換され、それ自身の中に蔵せられる。ここには香りとテキストを巡る相補性の円環が納められている。
香りとテキストを巡る相補性。この観点において、先に引用したテキストの「息を吹き返す」の一文は興味深い。つまりこの香水の香りとは、蘇った古書たちが吹き返した息そのものだということだ。香りを意味する「flavor」の語源は「吹きすさぶ風」であり、霊感の到来を意味する「afflatus」とその系統樹を同じくする。命や閃きは世界を巡る神の息吹である。そしてそれは息吹であるがゆえに、匂いと音を同時に持つことができるのだ。
実際に、香水では音のメタファを用いて表現されることがままある。例えば香りの調和と音楽の和音はともに「accord」で表わされ、各種の香料を並べた調香台は「オルガン」と称される。もちろんここで、日本の香が「聞く」ものであることを指摘してもいい。fueguia 1893はこの音と香りの相似性にきわめて自覚的であり、通常香水の構成を表す「Top / Middle / Last note」に対して、「Tonic / Dominant / Sub Dominant note」の表現を当てている。これはそれぞれ音楽用語で主音/属音/下位属音を表し、香りの構成が音階に準えられていることがわかる。
さて、ここで出てきた「note」は、〈フレイバーテキスト〉を巡る物語をまとめるにふさわしいだろう。この単語は「物事を知らしめるしるし」をその意味の中心とするとされ、事実、テキスト・香り・音のすべての意味を兼ね備えている。創造を司る神の息吹は音となり、香りとなり、テキストとなって吹き荒れる。そう考えると、〈フレイバーテキスト〉から香りが立ち昇ることもそれほど不思議ではない気がしてくるが、どうだろう?
*
「誰もいない森で倒れた木は音を立てるか」という認知にまつわる有名な思考実験がある。わたしはこの話を想像する時、いつも香木のことを考える。東南アジアの森の奥深くで人知れず木が倒れる。いくらかの樹脂が流れ、木肌に染み込む。その部分を残して木は腐り落ち、残ったものは沈香と呼ばれる。小さく割られた沈香を香炉に入れる。熱された木肌から香りが広がる。沈香から立ち昇るその香りは、同時に音であり、テキストでもある。わたしたちは遥か昔の見知らぬ木が倒れる音を聞くことはできないが、その香りを聞くことはできる。そして、そうした想像について、このようにテキストを書くこともできる。
今このテキストからはどんな香りが生まれているだろうか?
青山 新(あおやま・しん)
1995年生まれ。デザイナー・リサーチャー。未来志向型のデザインに広く関心を持ち、執筆/表現活動を行なっている。現在フリーランスとして活動中。直近の作品に「オルガンのこと」(樋口恭介編『異常論文』所収、早川書房)、「以顔繪」(『小説すばる2022年2月号』所収、集英社〉など。 https://scrapbox.io/shinaoyama/
ほかの記事も気になる方へ
OKOPEOPLEとお香の定期便OKOLIFEを運営するOKOCROSSINGでは、最新記事やイベント情報などを定期的にニュースレターでお届けしています。ご興味がある方は、以下のフォームよりぜひご登録ください。
編集協力:OKOPEOPLE編集部
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
