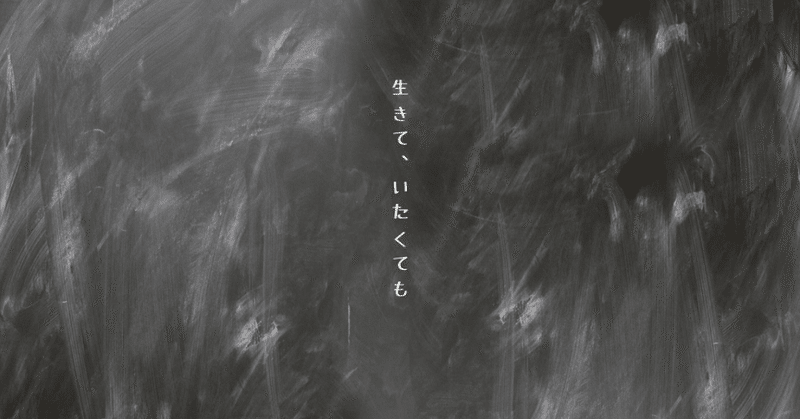
生きて、いたくても――Oct#16
「……『クエスチョン』?」
偶見が首を傾げる。まさにクエスチョンだ。
「うん。取り敢えずは、聞いて貰おうかな」ノートを開いて、彼女は話し出した。
新運動「クエスチョン」、その定義は第一に、インパクトがあって唐突、脈絡なくそれでいて面白味を持つ、エンターテインメントであるものとする。そのパフォーマンスをどう感じ、評価するか、そしてそれは果たして芸術たり得るか、と言うのは観客に委ねられ、ここが一つのクエスチョン――問い掛けの意味に当たる。但し、これでは既存のものと大差ない。
重要な第二の定義、それは無作為なパフォーマンスの中にたった一つだけ、目的を持った法則を採用し、且つその目的はパフォーマーの為だけにあるもの、客観的には認知されないものとする。秘された目的・法則に対する「?」の表意だ。主張があっても、それは内側でとどめられる。表面的にミーニングはないけれど、純粋なパフォーマンスでもない。全てを観客に提
供するのに、所在はこちら側。奇妙なバランスだ。
「目的を持った法則、って言うのは?」
「つまり、その活動の目的を、見える形で法則化する事ですね。『クエスチョン』は、率直に言ってしまえばそれを実現する為の手段に過ぎません。込める意味は何でもいいんです、例えば芸術への批判、平和の訴えから好きな人への告白まで……まあ、隠された目的なので、何をやっても伝わらないでしょうけど、この活動にとってはそれが正しいんです。秘匿性も、芸術を芸術足らしめる、一つの美点だと思ってますから」
要約すれば「クエスチョン」は、「意外性のあるパフォーマンスの意味を観客が想像し評する事は自由で、それはその個人の答えとして常に肯定される。しかしそれとは別に、パフォーマーが定めた目的やテーマが存在し、パフォーマーは観客の見識からは解放された、不可侵の内に実行出来る」活動、と言う事になる。「そして」彼女は続けた。「私たちに於いては『復讐』が、その目的になる訳です」
「え……っ?」
心臓が大きく跳ねる。それは宙に舞ったまま着地点を失ってしまって、空っぽになった胸の奥で、混乱と焦燥がシルエットの様に去来する。
「ちょっ、みかちゃ、」
「三上、今、何て……」
「……全部聞きました。あ、でも、珠ちゃんを責めないで下さいね」
三上は穏やかな相貌を崩さない。
「だって、おかしいじゃないですか。確かに私と宮下君は、長いつき合いじゃないですけど、それでも宮下君が思慮深くて慎重な人だって事くらい、分かります。こんな突拍子もない計画に乗るとは思えなかった。渋々どころか、積極的に推進してましたしね」
「それで……あの時に、か」
二人が美術室を後にして、僕が美術部員たちと話していた、あの時。
「理由があると思って、珠ちゃんに、正直に言って欲しいって。全部、納得行きましたよ。だからこそ、協力しようとも思った。暴力とかに頼らない、それ以外の何かしらに『復讐』の意味を着せて見立てる。私はそれを、素敵だと思ったんです。確かに、言いにくい事なんでしょう。少し強引に聞き出しました、ごめんなさい」
「……三上の推察も尤も、だとは、思う」
僕は動揺を静めていた。彼女の目は、意味を乗せて来なかったから。何でもないかの様に、いつも通り振る舞ってくれたから。それが却ってありがたかった。さも深刻そうな雰囲気を出されていたら、知られたと言う事実は蟠りと苦痛を伴った筈だ。
「だから、思いっ切りやらせて下さい。成し遂げられる様に」
「……それじゃあ、三上も」
「勿論、参加しますよ。目的を共有する以上、ただの『協力者』でいる心算はないですから」
三上が組んだ手を下に向けて、凝った空気を押し潰す様に伸びをした所に、三つのカップが届けられた。僕の五官は決して豊かではないけれど、それでも口に運ぶと、香りの高さや雑味のなさは感じ取れた。
「あたしも、どうせやるなら派手がいい。小規模、広範囲、派手。最高じゃん」
「でも三上、具体案はあるの?」
「そうですね、やりたい事は大体固まってます」
ノートのペイジを次々と捲って行く。昨日の時点でも、進めておきたい箇所があると言っていた。もう纏めてあるのだろう。
そこに書かれた文章や図説の中でも一際目を引く、第一回の「クエスチョン」の題名。
「浄化作用入り紙コップの死、或いは新たなレゾンデートル」。
