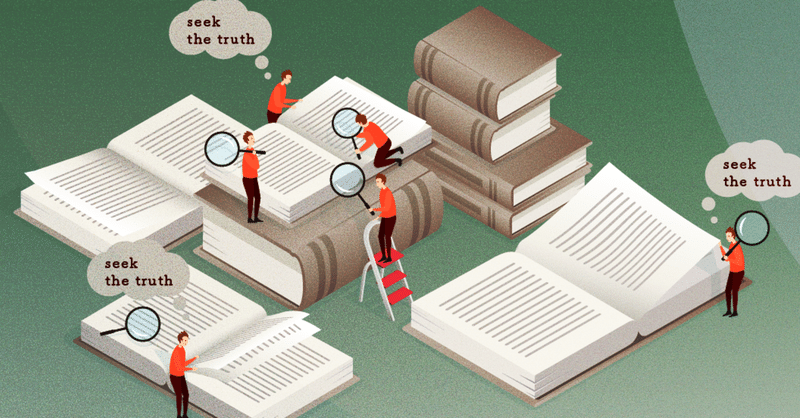
「心理職はサステナブルな仕事か」という疑問
『サステナブル(Sustainable)』。
この言葉をよく耳にするようになって久しい。日本語訳にすると、「持続可能な」という意味や「継続性のある」「ずっと続けていける」という意味になるようだ。
一般的にはSDGsをはじめとする環境問題や社会の在り方などを考えていく上で用いられる用語のようである。
私たちが生きている世界において、今目の前にあるものはいつか消え行くかもしれないし、100年たってもそこにあり続けるかもしれない。そのためには、持続可能であり続ける努力が必要になる。このことに異を唱える人は少ないのではと思う。
話が大きくなりすぎたので、社会という大きな枠組みから、もう少し身近な自分自身の職に視点を移してみよう。
私は臨床心理士という仕事を生業にしている、心理業界では平均年収程度の平凡な草の根カウンセラーである。
そんな私の仕事はサステナブルなのか。
こう聞かれると、『はい。サステナブルです!』と力いっぱいこたえられる自信は、はっきり言ってない。
このnoteを偶然読んでくださった方の中には、「いやいや。私は常勤職だし、研修も積んで特定の技法で論文も書いて、博士号も持っていて、開業もしているし、十分サステナブルだわ!」なんて方もいらっしゃるかもしれない。
が、残念ながら、私自身はそんな恵まれた状況にはない。
学会費や研修会費を見ては、「1万円の研修費高いなぁ、懐痛いなぁ」と思うし、一方で、「いやいや、自己研鑽のためなんだから仕方ない!」と思っておサイフを泣く泣く開ける。そんなごくごく普通の心理職である。
そんなごくごく普通の心理職からして、今の心理業界は、いや、心理職はサステナブルな仕事かと言われると、その労働契約の形態やキャリア形成の点から見てサステナブルとは言えないのではないだろうかと思う。
さきほど平均年収と書いたが、臨床心理士の平均年収は300万から600万程度。平均値を取れば約340万円となっている。
現在カウンセラーと名乗る人の多くが保有をしている臨床心理士という資格は、資格の取得までに大学4年+大学院2年:計6年の基礎教育を受け、その後やっと資格試験の受験資格を得る(資格取得ではない)という狭き門を潜り抜けてやっとスタートラインに立てる。仮に私立の臨床心理士養成校で6年間の学費を払った場合、資格を得るまでに約720万程度の先行投資が必要となる。
この資格をストレートで取得した場合、25歳で現場に出ることができるが、そこから60歳まで仮に働いたとしても、35年間の間に先行投資をした額を回収しようとすると、なんと年間20万以上は稼いでいないとこの金額は回収できないという計算になる。
平均年収340万-20万=320万
実質1年あたりの先行投資額を抜いた平均年収は320万。
これは先行投資をした費用に対してのvalueとして大きいと言えるかというと、言えないなぁと肩をすくめる人が大半なのではないだろうか。
と、ここまでネガティブな側面ばかりを書いたが、この仕事の最大の魅力は『やりがい』という点にある。
「人の幸せに貢献をする」。
つまり、労働の対価はClの望むべき幸福な未来である。
『仕事の価値=priceless』。
そんな風に感じている人が大勢いるからこそ、この業界はここまで発展をしてきたように思う。
現に今の日本の心理職の中で、認知度の高い心理職種の一つである「スクールカウンセラー(SC)」は1995年に文部科学省が調査研究委託事業としてその事業を開始して以来、今年で25年目を迎えている。
スクールカウンセラーの時給は1000円~5500円までと、設置主体や地方自治体によってその給与は異なるが、心理職が給与の面で比較的安定した職を確保したいとき、選択肢の一つとしてあげられるが、その多くは週1-2日、1日6-8時間程度、年間30-35週程度の契約である。金額にして年間約100万。しかし、そのスクールカウンセラーですら大半が1年契約の非常勤職であり、社会保険の対象にはならず、雇用の安定性があるとはいいがたい。一部例外的に常勤職のSCもいるが…。
と、いうわけで、こころのケアの重要性という視点が広まっている現在において、心理業界としてはサステナブルではあるかもしれないが、職としてサステナブルであるとは言いにくい現状にあると、資格取得以降ずーっと個人的にひそやかに悩み続けている。
では、職としてサステナブルであり続けるにはどうしたらよいのか。
それを考えていきたいのが、このnoteのテーマである。
心理職は倫理的な観点や、学術的な要素も強い職である面から見て、資本主義システムの在り方となじみにくい。
ただ心理職が業(なりわい)である以上、つまりその技術をもって生計を営める専門的職種である以上、その労働に対して対価が支払われるというのは当たり前のことだろう。
ではなぜその心理職が職として生計を立て続けていくのが難しくなっているのか、そこを打破していくにはどうしたらよいのか?ということを、これまでの自身のバックグラウンドであったビジネスという視点から労働環境、キャリアアップ、ビジネスモデルなどの点を今後考えていけると嬉しく思う。そして、私一人の頭の中にあったことが、誰かの目に触れることで、また違った広がりになる事を祈っている。
ちなみに企業生存率という言葉がある。ある事業体の中で100年後に生き残っている企業は1%という話だそうだ。
100年後、私たちの仕事は生き残っているだろうか。
未来が見えない今だからこそ、考えたい。100年後の未来のために。
この仕事がサステナブルであるためにできること。
改めて、もう一度問う。
『あなたにとって、心理職はサステナブルな仕事ですか?』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
