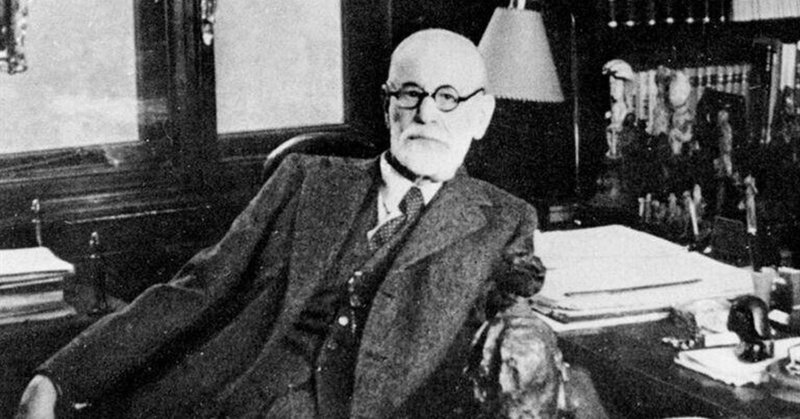
◆読書日記.《小此木啓吾『フロイト思想のキーワード』》
※本稿は某SNSに2020年3月26日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
小此木啓吾『フロイト思想のキーワード』読了。
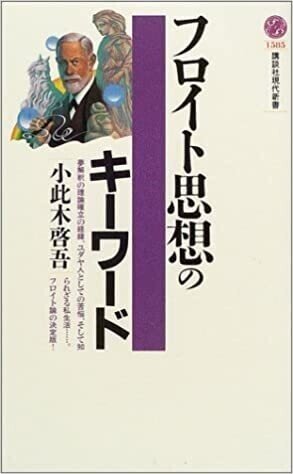
著者は元日本精神分析学会の会長を務めた事もある精神分析医。日本のフロイト研究の第一人者でもあり阿闍世コンプレックスの研究などでも有名なビッグネームでもある。
しかし、この人の著書はいずれも平明で読み易く広く一般にも受け入れられているという。
その著者がフロイト思想の重要ポイントをキーワードごとに分かり易く説明してくれている、となれば興味を持たない訳にはいくまい!という事で本書では精神分析の巨人・フロイトの思想をキーワードごとに整理して説明する事で、あの広範なフロイト思想の全体像を概観しようという試みのフロイト解説書。
◆◆◆
一読、フロイトの『精神分析入門』を読んだ時の事を思い出した。実に分かり易く精神分析について説明されている。
しかも、その精神分析的な物事の捉え方から、人間精神の根源にある問題に切り込んで行こうという「人間の謎」という巨大な難問に立ち向かっていっているような興奮を覚えるのだ。
ぼくはフロイトの著書は、現時点で『精神分析入門』『続精神分析入門』くらいしか読んでいなくて、それ以外だといくつかの解説書を読んだくらいだ。
しかし、ぼく自身がシュルレアリスムの研究(勉強?)をライフ・ワークとしている部分もあって、精神分析というジャンルは宿命的に様々なシュルレアリスム関連の話題について回っていた。
ってな事で自然とフロイト思想は意識せざるを得なくなる。
現代ではフロイト思想は心理学の方面からは「科学的ではない」と言われて批判されているという。
何故かと言えば、心理学は実証実験によって人間心理を捉える「実践的な科学」と捉えられていて、それに比して精神分析は「無意識」という、観測も実験もほぼ不可能なものを対象としているために「実験できない=科学ではない」と言われているからだ。
これはぼくも半ばそう思っていて、これまで「シュルレアリスム理論に影響を与えた思想」という意味では重要でも、科学的な知見としての理論ではないので、以前はフロイトにはあまり深入りしても仕方ないとさえ思っていたほどだった。
その認識が多少変わったのは、去年読んだ高田明典『知った気でいるあなたのための構造主義方法論入門』で、「無意識とは「説明概念」であって「ある」ものではない」という考え方を読んでからだった。
この本の著者の高田明典氏は「無意識」を取り扱う精神分析も科学的思考を持った立派な科学だと擁護しているのだ。
構造主義は科学的な方法である。構造主義は物事の背景にある構造を把握する方法論である。
何故構造を把握しなければならないのか。それは物事を「制御」するためである。
科学というのはそもそも、自然や物事の法則を見つけ出し、その法則を「制御」して利用できるようにするために発展してきた。
だから、精神分析の場合「無意識というのはあるのかないのか?」という「無意識の有無」という問題はどうでもよくて、重要なのは、それを把握する事で人間精神というものを幾らかでも「制御」する事にある。
フロイトには人間の精神の制御への道のりを作った。だから「非科学的」などではないのである。
現在、精神医療の分野では精神分析よりも、薬物療法のような物理的に効果を上げる方法や認知療法などが主流になっているために、フロイト流の精神分析は「死んだ」とさえ言われているようだ。
だが、それでも精神分析家というのは未だに存在するし、フロイトやユングを学んでいる人も大勢いる。
それは、前述したように人間の精神の中でも謎の多い「無意識」という領域について未だに解決できていない部分があるからでもある。
人間の精神は未だに謎が多いが、だからと言って何の説明も加えられないでも気にならないかと言えばそうはならないのが人間だ。人は「知らない」という事にストレスを感じるものだからだ。
本書はそんな感じで、ぼくが今まで読んできた精神分析やフロイト思想の考え方を一から復習させてくれる内容であったと思う。
自我-イド-超自我という関係性も、最近ではアニメ『イド:インヴェイデッド』なんかで出てきていた時にはあまりピンとくる内容ではなかったが、本書のおかげでそれもおさらいできた。
その他にも改めて本書の解説を読んでいて「あっ!そう言う事だったのか!」と色んな知識がビシっとつながった部分があって、そういうところは実に参考になった。
中でも特に「エロスとタナトス」については、衝撃的だった。
「エロス」というのは性愛だけの話ではなくて、男女の恋愛であり両親の愛や家族愛、隣人愛等も含まれる「生を産み、育んで"人間の生"を推進する本能」であり、その意味で「死の本能」であるタナトスと対になる考え方だ。
「性本能」とは「生本能」と一緒のヴェクトルにある、これらは共に「エロス」なのだ。
そう言う意味で「エロス」と「タナトス」は対立関係にある。
だが、その反対概念であるはずのエロスもタナトスと表裏一体の関係にあるというのはバタイユの『エロティシズム』論に出て来る話だ。
個体の死を願い暴力による破壊衝動を持つのも、子供を作り同じ種を愛そうというのも、同じく本能的な部分に属する。
つまり、それが我々が乳幼児の時期に持っていた野性に近い「快感原則」に基づいた「快感自我」だった。
我々は両親や他の大人たちによって、より人間的な「現実原則」に基づいた「理性」や「知性」をしつけられて「現実自我」を得る。
これらの野性と知性との関係によって自我-イド関係が構築されていく。
この自我-イド関係を、社会規範的なものが内面化された「超自我」が調停役を演じる。これが、フロイトが考えていた人間の精神構造だった。
この構造が理解できれば、精神分析は人間精神や心理や精神病理だけでなく教育、宗教、芸術、社会、倫理などにも言及する事ができる正に画期的な思想となる。
改めて考えてみると、これほど広範囲の分野についての分析が可能になる学問が現れたという事は、当時は相当画期的な事だったのではなかろうかと思う。
それだけに医学からも他の学問分野からも精神分析は随分と批判を受けたようだ。しかし、葬送されたと思われる精神分析も、まだ死んではいなかったと思う。
ジャック・ラカンのテーゼも「フロイトに戻れ」だったし、現在の精神医療の考え方も、フロイトの開拓した分野を足掛かりに発展してきたことには変わらないだろう。
ぼくとしても、本書を読んで改めて精神分析は未だ死んでいないという認識を得られたのは幸甚だったと思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
