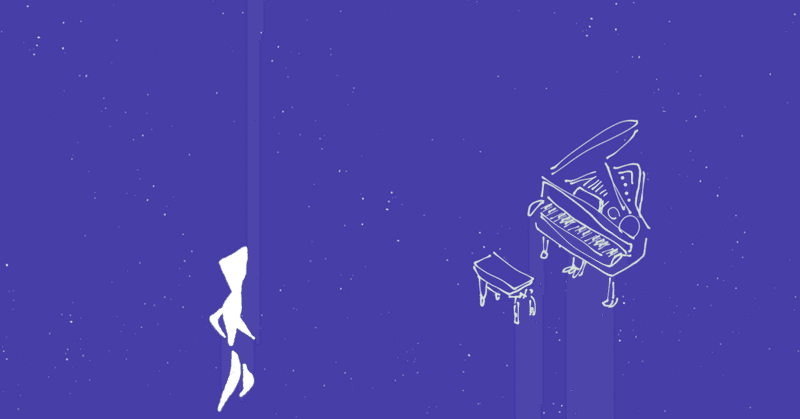
待ち人ピアノ
《あらすじ》
管理職多々倉の妻が雨でもないのに某日深夜、髪を濡らして帰ってきた。考えられる理由は一つしかない。じき妻は1通のメールを残して姿を消す。結婚を控えた親友が同棲することになり、入れ替わるように同棲相手のピアノが断捨離でやってきた。ピアノに縁のない多々倉だったが、深酒の夜、共同住宅で泥酔に任せピアノを弾いてしまう。それを機にピアノにのめり込む多々倉。そこに部下マドカが首をつっこんでくる。多々倉に密かに思いを寄せていたマドカは仕事では優秀だったが、良くも悪くも天然が仕事を左右する問題児。マドカにはプロのピアニストになるための英才教育を受けた過去があった。見えざる扉が開くたびに、2人は距離を縮めていく。
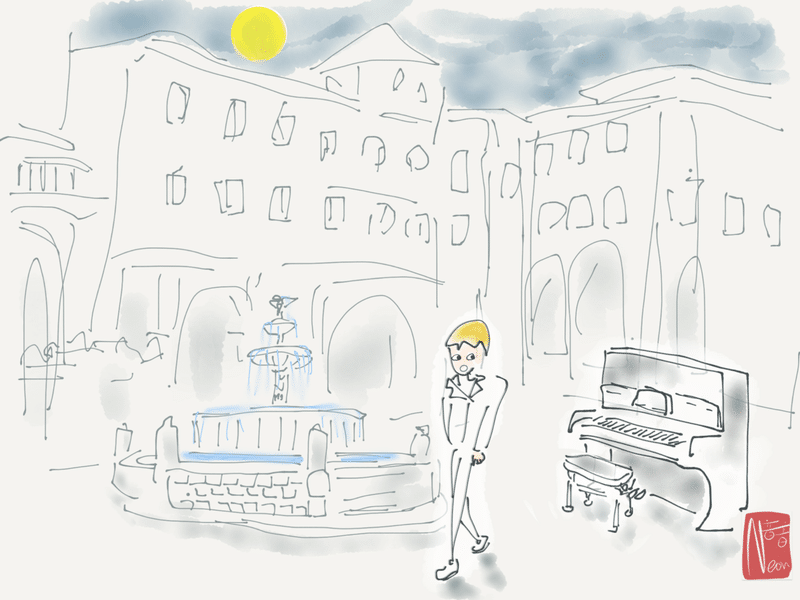
光取りの半円形の高窓から、満月から2日欠けた月が家の中に朧な光を投げかけていた。高窓に月が現れるのは半月ぶりのことだったろうか。ふたりで見る月はどんな日にも浪漫で時間を埋められたのに、ひとりになってからの光は冷たい。
5月中旬。
新型コロナの猛威が長引いたせいですっかり外飲みの習慣がなくなった。慣れてしまえば家飲みのほうが気楽でいい。酔って気持ちよくなればそのままベッドで横になれるし、今となっては口うるさく責め立てる者もいない。煩わしさから解放されたことを喜ぶべきなのだろう。こなさなければならない仕事量は変わらなかったけれども、社会は暮らしのトーンをスローダウンした。おかげで自分の時間が増えた。家で仕事をしている限り、就業時間中にも生ゴミは捨てに行けるし、宅配に再配送してもらう無駄も減った。煩わしい宗教の勧誘と新規営業の飛び込み訪問さえ除けば、平和で落ち着いた毎日を獲得できたといっていいだろう。
慣れてしまえば今の暮らし方もまんざらではないと思うようなった。寂しさにも慣れて、ひとりでいることに不自由を感じなくなったことが功を奏しているのだと思う。
深酒をしたかったわけではない。クライアントからのリクエストでなければ出席などしない。研修を終え配属された新人との顔合わせという名目で、実質、夜の営業の恩恵に与ることを目的とした「よろしく」飲み会であることが見え見えだった。
その日がテレワークでなかったことがせめてもの救いだった。会社は自宅での就業を週3日、全社員に課している。出社の希望日を前々週まで提出し、次の週にはシフトが決まる。出社日の2日のうちの1日に、よろしく飲み会があたった。
自粛が開けても週3日の自宅就労は続いている。会社は出社によるオフィス確保のための固定費削減策を予算に組み込んでいたし、働く側もいまさら週5で出社することにも煩わしさを感じるようになっていた。新型コロナの自粛は明けて、きっちり土産を残していった。
テレワークの日に営業的飲み会に出かけるのは億劫なこと極まりなかった。出社組が帰宅の路につくころ、わざわざ繁華街まで電車で出かけなければならないというのはあまりに不合理に思えたし、割に合わない。納品物を郵送したのに取りにこられたみたいで、在宅勤務の意味が大きく揺らぐ。
営業的飲み会で、深酒をしてしまった。いや、正確には営業飲み会のあとの「おごり」飲み会ではめをはずしてしまったのだ。あれがよけいだった。おとなしく帰っていればいいものを、外出を2回に分けたくはなかった合理的思考というやつが、後悔に結びついた。欲を出せばいつだってどこかで帳尻合わせの反動がくる。
久しぶりの外飲みだったこともある。うまく飲み会のリズムの勘を取り戻せなかったことも関係していただろう。それに、とっくに忘れたこととしていたから、忘れるための酒ではなかった。もしかしたらだけど、月がひときわ地球に接近していたことが関係していたかもしれない。月は、遠く離れた青い地球の水を誘惑し、潮流をその手招きによって引き上げる。その魔の手が、頭蓋骨を通り抜けて意識をつかみ、すっぽりと引き抜いていったのかもしれなかった。我を譲らぬネオンが腑の抜けた我が身に入り込み、浮き足だった繁華街に蠢く雑多な欲望の数々がまんまとぼくを担ぎあげたのだ。
(スーパー・ムーンのせいさ)と路地の奥から声がした。
「月の誘惑。狼男だって、満月に導かれて変身するんだ」
千鳥足で肩を組む同僚の松田がわけのわからないことを叫んでいる。いや、前後不覚はぼくのほうだったかもしれない。クライアントを送り出してから打ち上げだといって繰り出した新宿という底の知れない沼の底で、ぼくは水に浮いてじたばたしながら泳いでいる。嫦娥が月の背中を覗き見て、月女神が獣人を操り狼を街に徘徊させた。ムーンなんとかという紫のネオンが手招きで誘っている。「社長」と絡む巨人めいた黒人男たちの誘いがぐらぐらと肩をつかみ、得体の知れない店に誘い込もうとしていた。とられた腕を振りほどき、あまたの誘いを払いのけ、ぼくらはふらふらとあてもなく歩いた。どこに向かうともなく。
まるで獣人マリオネットに姿を変えられたような気がした。
「おれらは操り人形だ」と松田が叫んだ。スライムみたいに定まらない思考回路が松田の発した言葉の端をとらえて、ぼくは意味を咀嚼することなく「そりゃそうだ」と応えてる。深層の意識はまったく逆のことを考えているというのに。
そしてこの松田という男が、仕事のあとの深酒に陥れた張本人だ。
操り人形? 誰がぼくたちを操っているという? 天空から月光に浮かび上がる輝線を巧みにさばいているのは誰だ?
天を仰げば、嫦娥の指が手招くようにぼくらを動かしているのが見える。したり顔の彼女は天に浮かび、地に蠢く男どもを操りながら品を定め、どいつを喰らうかべろりと舌なめずりをしてみせた。
スーパー・ムーンのせいさと声をあげたのは松田だったかもしれない。
「月探索機と女神をごっちゃにしているんじゃねーよ」
月フリークの松田がクダを巻いた。だが問題はそこじゃねーよ。しこたま飲んだ思考停止の頭脳では、現状維持はおろか、すでに地べたに吐き出すことしかできなくなっていたことだ。
おぞましい湿気に襲われ飛び起きた。着たままのワイシャツは皺くちゃでぐっしょり汗を吸い込んでいた。気持ち悪い。
ここは?
自室のベッド。
鍵盤蓋が開いていた。夜中にピアノ、弾いたのか。
泥の眠りから抜けきれない重い体に鞭打って、今日も仕事、すでに支度の時間に突入していたが、起き上がれる気がしない。鉛の夜を抱え込んだままの躯体では、新しく来た朝に対応する活力が湧いてこない。あまりに気怠るすぎる。
それでも責任感に操られ ざっとシャワーを浴びて家を出る。なんで今週に限って2日連続で出社しなけりゃならないんだ。誰だ、こんな理不尽なシフトを組んだのは。
あいつだ。総務のガリメガネ。
出がけに「メタボに気持ちばかりが焦るのよねえ」が口癖の管理人が鼻息荒く湯気をたて、憤慨に顔を紅潮させて迫ってきた。彼女を見ると、決まって家政婦を思い出す。あの目撃をする家政婦だ。顔はテレビ向きではないが、体形と話し方がそっくりなせいだ。
で、なにごとですか?
「多々倉さん、朝から苦情の雨あられよ。夜中のピアノ、近所の迷惑を考えてちょうだい」
よもやとは思ったよ。朝起きた時にピアノの鍵盤蓋が開いていたんだもの。やっちまったんだな、と思った。身に覚えはなくても、状況証拠を突き付けられてはぐうの音も出ない。冷や汗が体内外問わず染み出して、内側では食道を下って胃に届き、そいつが背中を寒くした。
いやあ申し訳ありませんでした、身に覚えはなかったけれど、反省を恐縮に乗せて、頭を下げる。
「ほんっとにもう、たいへんな時期なのはわかりますけど、気をつけてくださいね」
頭を下げながら、ふざけるなの怒りが脳天を突き抜けた。家政婦のあんたになにがわかるっていうんだ。
だがこの状況での反論は分が悪い。『忍』の字を思い描いて飲みこんで「はい、反省してます」と苦い照れ笑い、奥歯ともども怒りを噛みしめ「行ってきます」で逃げるようにその場をあとにした。初夏の爽快な晴天に似つかわしくない苦みのきいた1日のはじまりだった。
4月上旬。
妻が姿を消したのが3月初めだったから、あれからもう1か月が過ぎたことになる。
「あ、今シャワー中だから」
衛星放送の版権管理の職に就いている彼女の、ふだんから遅い帰宅が深夜におよぶようになり、ある日の明け方、雨でもないのに髪を濡らして帰ってきた。その妻を、夜通し待っていたぼくが問い詰めたらバスルームに閉じこもり、さらに追及したら返ってきたひと言だった。
おかしいと思ってはいた。それまで施錠していなかったバスルームの鍵を、彼女はいつしか当たり前のようにかけるようになっていた。
その夜は、妻が帰ってくるまでとてつもなく長かった。二度と夜は明けないんじゃないかと思うほど、闇が世界や心の中に無尽蔵に広がっていた。秒針が刻む時間は、あてにはならなかった。時間がふくらみ、空間を歪めていた。
テレワークで時間の融通はきくとはいえ、さすがに夜明けまであとわずかの時間まで起きているのは辛い。眠らないことには翌日、といってもわずか数時間後に始まる業務に支障が出てしまうと、諦めて寝ようと決めた直後のことだった。
「明日も早いから」、シャワーを浴び終えると、妻はそそくさと数か月前に別にした自室に急いだ。そんな彼女の横顔がうしろめたかったことを生々しく覚えている。
何が起こっているのか、察しがつかないことはない。感情にまかせて右腕を振り上げ、腕力を武器に審尋し、改心を説くこともできなくはなかったけれども、そんなことをしても閉じた殻を開くことはできないことをぼくは経験から知っていたのでやめた。
いちど坂道を転がりはじめた丸い石は広い踊り場に出るまで止まることはない。彼女には彼女の〝生き場〟があって、ぼくはそこからはじかれたのだ。ここで藪をつつけば、般若が出てくる。間違いなく。
ぼくの身に責任の覚えはないけど、彼女はすでに引き返せない身の覚えを抱えてしまったのは間違いないだろう。第三者に介入できない秘密を妻はその腹に隠している。
ぼくの大事な一部が、乾いた瘡蓋のようにぼろりと剥がれ落ちた。つい最近までぼくは妻と偕老同穴、相思相愛だと思っていたのに、打診や合意の手順を踏むことなく、妻はぼくにとって第三者になった。妻はもう妻ではない。自分の、ではなく、単なる三人称の彼女になった。
認めたくなかった。認めてしまえば、ぼくはひとりになる。理由もわからずいきなり置いていかれるなんて寂しすぎる。
ぼくに落ち度があったのだろうか? 叱責を自己反省に置き換え自分に尋ねてみた。自分ではわからず、妻に尋ねたこともあった。だけど、うつむく妻の頭は左右に振れるだけだった。
今は仕事に没頭していたいの。お願い、そっとしておいて。
ぼくが悪いのなら改めるから、きちんと話してほしい。
あなたのせいじゃないの。仕事に振りまわされて、少し混乱してるだけ。ごめん。
嘘だった。何日かして届いたメールには「別れてください。理由は訊かないでください」とあった。
骨をつなぎ留めているボルトが瞬時に溶けてなくなったみたいだった。支えるものを失くした骨格が、ぐしゃりと地面に頽れる。それを合図にいっせいデリートをかけたみたいに頭の中が真っ白になった。
メールをくれて以来妻は家に帰らなくなった。少なくともぼくの在宅時には。そしてぼくの不在を狙って自分の荷物を引き上げはじめた。3回目で最後の大物、ベッドがなくなると、引き上げ証明書みたいに離婚届が置かれていた。それにしても、よく調べたものだと感心させられるところもあった。週に2日しか出社しないその日を調べ上げておかないと、こんな芸当はできない。なにごとにもきっちり線引きをしないと気が済まない妻らしい行動だった。
離婚届は、妻が残した唯一の気配だった。記入捺印して提出すればすべてが終わる。妻の気配がすべて消え失せる。
未練がましいのもわかるし、どれだけ懇願しても、また祈願しても、出ていった妻が帰ってこないだろうことはわかる。だけど、万が一のことであっても、妻が新しく選んだ男とうまくいかなくなって心変わりしないとも限らない。
裏切られたことで湧き出す憤怒に、いなくなったことで広がる荒涼が神妙なヴェールをかけて、揺れる心は戻ってくれることに一縷の望みをつないでいた。
こんなのじゃいけないことはわかっている。だけど、いきなりあるべきはずのタガを外された人間に、すがる以外の方法など残されているというのだろうか。
翌日もその次の日も、妻から連絡はなかった。それから1週間後。望みはとうとう息を切らし、腐敗した希望が臭気を放ちはじめた。
決着をつけるなんて格好のいいものじゃない。運命に操られるままに、出社日の朝に役所に立ち寄って離婚届を提出してきた。満開の桜を瞬時に散らすほどの風が荒れ狂った日のことで、その季節に似つかわしくないほど気温が上がった。まるで盛夏に焼かれるような陽ざしが容赦なく弱り切った心身に突き刺さってきた。
「多々倉さん、お電話。松田さんという男の人から(♪)。ふたつ上のフロアにいる方ですよね。よく電話をしてくるようだけど、仲がいいんですね」
末席の亀川がいつもの調子で私語のない静寂の職場に能天気な声を響かせる。
カタカタとキーボードでテキストを積み上げては、ツツツーとデリート、打ち直してはゴールに向けて黙々と流れていく時間に無駄口はいらない。話す時間があるなら打て、が職場の空気だ。それに、今日みたいな日には鬱陶しさに拍車がかかる。余計なことは言わんでよろしい。
--仕事中悪い。すぐ済むから少しいいか?
「かまわない」と虚脱したままのぼくが答える。
松田は、年の暮れに同棲中の彼女と晴れて戸籍上の夫婦となる。袂を分かつ者あれば結ぶ者あり。こうした状況だから祝福ムードになれそうにないが、社会人も10年やっていると平静を装っていられるようになる。
--突然で悪いんだが、頼みごとがある。
「なんだ?」
--ピアノ、もらってくれないか?
現実感がなさすぎたせいで、話がぼくをスルーして誰か違う人に向けられている、そんなふうに聞こえる。
「何を言いだすんだ、やぶからぼうに突拍子もないことを。うちにはピアノ弾きはいないぞ」と、だからぼくも真に受けることなく横に受け流す。
--籍入れるまで亜希子がうちで暮らすことになって、だいぶ断捨離したんだけどまだ荷物が収まりきらなくてな。どうしてもピアノは手放せないって言い張るんだ。だけど、知ってる人にならってやっとのことで手を打った。そこでおまえに白羽の矢だ。
「冗談でもそれはないぞ」、どうやら松田は本気らしい。突然すぎるし、虫もよすぎる。それに勝手もすぎる。
どうしてこういう日に限ってこうも厄介事が集中するんだ? 仕事以外のことは考えたくはなかった気分だったし、荷物のめんどうをみる気もなかった。
--亜希子がぜひって。置けるだろう?
「そういう問題じゃなく」
--辛い時期だってことはわかるよ、でも、
「その問題でもない!」
松田とは長いつきあいで、お互いのことはよく知る仲だ。まさか離婚届で決着つけると話したこの日をあえて狙ったわけではないだろうが、タイミングが悪すぎる。
「考えさせてくれ」とぼくが引き際を伺うと、期待しているよ、とくに亜希子が、と松田はぼくの思惑(断りを含んだはぐらかし)を瞬時に察知し、引き伸ばし策に打って出た。
「頼む」
松田の婚約者亜希子とのつきあいは大学時代にはじまる。つきあいといっても恋人だったわけではない。なんとなくウマがあったのだ。講義のおさらいをし合い、シリコンバレーのにわか知識を聴いてもらったり、ゼミをどうするだとか、ささやかな自分のコミュニティに欠かせない、小気味よく決まるギアみたいにしっくりなじむ会話を交わし合える異性の友だった。
彼女に特別な感情を抱いたことはなかったし、亜希子もぼくを異性として意識することはなく、松田に紹介したら趣味嗜好がやけに合うようで意気投合、そのうちふたりがつき合うようになった。
あれから12年。
学生時代はよく3人でつるんでいた。終わってしまった時間、そこにあるのは懐かしさばかりではない。3人で温泉にも出かけた。法師温泉で亜希子はものおじせずに混浴の浴槽に飛び込んできた。ぼくは目のやり場に困り、ルール上湯船に沈められないタオルを呪った。ぼくの困惑顔に小悪魔の顔で肩を寄せて亜希子はぼくをからかおうとした。湯の波に揺れる乳房が目から離れず、あのとき初めて亜希子を異性と意識したことを思い出した。
いや違う。亜希子はあのときも異性を意識することのない友だちで、裸の亜希子は女の魅力をデフォルメした別個体だった。幻想が作り出したもうひとりの亜希子。その女の要素でできた亜希子を思い出すと、今でも脳髄がどんよりと重みに耐えかね縦に伸び、上も下も熱くなる。
スキーにもディズニーランドにも南の島にも3人で出かけた。松田と亜希子の意気投合ぶりは今でも変わらず、いくら話しても話題が尽きないネタの湧出量に感心するくらいだ。
亜希子に隠し事があるとはとうてい思えない。裏表をもたないパートナーは、貴重な存在であることが今ならわかる。今となっては信頼できる相手こそ人生の伴侶としてふさわしかったと断言できる。
もし亜希子がぼくを選んでいたら? ふたつに分かれたふたりの亜希子は、ぼくの腕の中でひとつに戻ろうとするのだろうか?
これ以上考えるのはよそう。今や亜希子は親友のフィアンセだ。
それでも。逃した魚は大きかったかと今さらながら考えることはある。
その亜希子が今、ぼくを頼っている。
不幸中だが幸いにもピアノを置く空間はある。いなくなるなんて考えたこともなかった妻が消え、親友の彼女(彼女もまた特別に仲のいい友人のひとりなのだが)の想いが込められたモノがやって来る。
取引として、割は合うのだろうか? とうていそうは思えなかったが、そんなことを考えていたら口が、貧乏くじの連鎖だな、と放っていた。本音が出たということだろう。
--え、なに?
「いや、なんでもない」
まるで盛夏を先取りしたような陽光が、職場のすりガラスから刃物で切ったようにビルの合間を抜けて斜めに差し込んでいた。昼をまわりさらに気温が上がったのか、自動調整のエアコンが室外機にはっぱをかけた。
ゴールデンウィーク。
5月の大型連休がはじまるまで五月晴れならぬ卯月晴れの勤務日がつづいたが、連続した休みに入るととたんに雨。吸い込む空気さえ湿気を帯び、おまけに梅雨寒みたいに気温が下がったせいでベッドから出たくない。
妻が去ってから2か月が過ぎていた。台所を磨く者もいなくなり、残された1本の歯ブラシがこめかみの疼きにのせて哀愁を深めていく。フローリングの床に発生した埃の塊が、意志をもったみたいにして日に日に増殖していった。
不思議なことに、思い出はどれもが具体性の一部を欠くようになっていた。掃除をする妻は表情を欠き、となりにあった妻のベッドライトのカタチが思い出せなくなっている。身を絞る苦衷に耐えかね精神の保護回路が働いたのか、回路は思い出を不確かで曖昧なものにしていく。
だが、スイッチが入ったはずの保護回路は、いつからか機能をまっとうできなくなったようだった。かえって安寧とはベクトルを異にする感情を刺激し際立たせ、ざらつきを増幅させている。視力が落ちてモノがよく見えなくなる移行期、たとえば月の輪郭が初めてぼやけて見えたとき、抗えないものを前にした自分に驚愕し、悔しくもあり、焦燥し、怒りを抱いたあの時の苛立ち、そんな嫌悪を覚える感覚が今のぼくを蝕んでいる。
もしかしたら、ぼくはやっと悲嘆と絶望と落胆の入り口に辿り着いたのかもしれなかった。ひとりで抱え込むには大きすぎた負荷を、保護回路が一時的に散らしてくれていたと考えれば、不完全なフラッシュバックにも納得がいく。虚空のドツボに堕ちる本番はこれからなのか? それを思うとぞっとした。
松田は、段取りついたら「運ぶからさ」で話を結んだ。ぼくはしぶしぶ認め、運ぶときは手伝うよ、と答えていた。
いつくるんだろう、ピアノ。欣快はなくもなかったが、憂鬱がすべてのプラス思考を覆い尽くした。
この連休中、松田は亜希子と「プレ新婚旅行」でハワイだし、その間に、なんて話ではなかった。
だから。
ピンポン。
まさか、ね。
はい、どなたですか?
えっ、なに? マジかあ。
おいおい、運ぶっていう話だったよな。
「お代はこちらになります」
おまけに着払いかよ!
朧な姿はエアパッキンを剥くことで輪郭を明らかにする。ローランドの電子ピアノ。
奥行き50センチほどで腰ほどの高さは、予想していたよりもコンパクトだった。都会の住環境からすれば、ピアノで生計をたてない限り、重量面、容積面、音量調整機能面、メンテ面で有利な電子ピアノでことは足りる。もしピアノを弾く気があるならば。
デジタルとなることで失うものは、弦の共鳴が筐体に広がり指を伝って入り込んでくるピアノそれぞれで違う個体ごとの〝声〟だと、たしか亜希子がそんなことを言っていたようだと、また聞きでうろ覚えの解説を松田から聞かされたぼくも、言われたことを理解するには経験と知識があまりに足りない。理解できたことといえば、事前に松田から聞いていた25年選手とは思えないきれいさ。濃い木目調は目立つ傷も色褪せもなく、大切に使われてきたことがうかがい知れる。
どこに設置しますか?
ひとしきり思案して、ベッドルームにと伝えた。
2人1組の業者さん、呼吸を合わせて訝しげな顔をそろえたけれども、2LDKにはもっとふさわしい場所がほかにあるのだから不思議に思われてもしかたない。それでも他人の目線で判断された〝適所〟に惑わされる謂れはない。
「何か問題でも」と眉を吊り上げると、何事もなかった顔にすり替えプロの手際でそそくさと設置し、退散していった。
ベッドルームを選んだのは、あるべきものがなくなってバランスを大きく欠いていたし、眠りからこの世に戻ったとき、となりにいた人がいなくなったのを紛らわせることができるかもしれないと考えたからだった。それまでそこにあったモノが持ち去られたことに打ちのめされる前に、なぜそこにピアノがあるのかに神経が向けば、1日のはじまりをどん底から這い上がることではじめずにすむ。
鍵盤蓋は、中央のくぼみに指をかけ、少し引き上げてから筐体に押し入れるタイプだった。
ぎぎっと、そこはピアノもどきの老齢なる嬌声のご愛嬌、長寿の歴史を物語っていた。黒と白の鍵盤は磨かれ光輝を放ってはいたが、さすがに使い込まれた感はいなめない。それが率直な感想だった。
電源をつなぎセットで届いた椅子に腰をかけた。ペダルはふたつ。鍵盤はたくさん。88鍵と言われた気がするが、どうせ弾けないんだもの、たしかめるまでもないだろう。
スイッチを入れ鍵盤に適当に開いた指を振りおろした。
じゃかじゅわぁん。不協和音にとうてい届かない不快雑音が巨大な公害の火花となって散った。なんだこの巨大な音量は? ボリュームつまみを確かめると、マックスに振られていた。休日の昼どきだったからよかったものの、陽と音を落とした夜だったらたいへんなことになった。不幸中の幸いということか。それでも迷惑を被ったご近所さんはいただろう。この蛮行、不慮の事故なんです、もうしませんと、騒音に顔をしかめたかもしれない住人に素直に頭を下げる自分を思い浮かべて赦しを乞う。
気を取り直してボリュームを下げてピアノと対峙した。
ドがどれかは知っている。黒鍵がふたつ並ぶ左下。真ん中あたりにあるドレミフェソラシドが基本、そんなことをテレビのクイズ番組で聞きかじっていた。となれば、これが基本のド。そこから白鍵をひとつずつ右に追っていけば基本のドレミファソラシドだ。
学生時代に我流ギターはかじったが、鍵盤楽器にふれるのは小学校以来のことだった。はるか昔の記憶に残るのはピアノではなく、ピアノを思い切り幼く縮めたピアニカ。笛と鍵盤楽器のあいのこで、鍵盤数も数えられるほどしかなかった。
音階は? 問題ない。たぶん。人差し指で順番に、こうして、ほらドレミファソラシドだ。逆に辿ってドシラソファミレドにリズムをつければ『もろびとこぞりて』になる。
あとは? 弾ける曲は?
ない。
無だ。
音階しか弾けない。ピアノにまつわる知識はこれしきのことで底を突く。
ピアノがやってきた初日。それ以上進めなくなって鍵盤蓋を閉じた。
考えてみればピアノを弾けないぼくにこんなものをと、宝の持ち腐れぶりに誰にともなく呆れてみせるが、考えるまでもなくしばらくすれば要らぬお荷物に変わることがわかりきっていた。捨てる神あれば拾う神ありで、ピアノがハンガーラックとその座を競いはじめたのはその夜からだった。
5月中旬。
連休が明けると、いつもの週3日のテレワークと週2日の出社の毎日に戻っていた。出社日は遅く出て、帰宅も遅い。この夜に寄せたシフトは、自粛前と変わらない。
休みのあいだ何をしたわけでもない。テレビを観て消して、コンビニで食いもん買って食って容器を溜めて大きなゴミ袋をふたつ作り、10回眠って起きたらいつものペースに戻っていた。
納期から逆算して組むスケジュール、予備日程であるバッファを確保するのはバグほか不慮の事態に備えてのこと。管轄部署にはスタッフが5人いて、彼らを束ねている。進捗管理業、仕上がったプログラムを確認する。
ほかに営業やら企画部やらイベント事業部、マーチャンダイジングを扱う部署もある大所帯の中の1プログラミング部門、3つの島があり、うちはその3番目にあたる第3制作部。中小企業からの依頼ならジャンルを問わず引き受ける何でも屋的なプログラミング集団だ。1番目の第1制作部は大企業の販売管理専門で、2番目の第2製作部はエンタテイメント系を引き受けている。エンタテイメントと言えば取り扱いの幅は広そうに思えるが、最近ではもっぱらスマホでマーケティングに使うアプリ開発に終始している。かつて手掛けていた自社開発ゲームは、採算が取れないということで6年も前に事業から撤退していた。
出社日は少し気が晴れる。仕事以外のことを考えなくてもすむことが、気を楽にする。
逆にテレワークでは気が沈む。スタッフの顔は見えないくせに、ことあるごとに妻の影が部屋のあちこちを行き来する。
そういやまとめたゴミ袋、いつ出せばいいんだっけ? もう覚えてもいいものなのに、妻の領域だった仕事はちっとも頭に入ってこない。
キッチンは必要最低限の調理で汚した鍋とフライパン、食器数個が連休中の怠惰を引きずっていた。
その直後のことであった。ハワイから帰ってきた松田が連絡をよこしたのは。
「どうだ、ピアノ、少しは弾けるようになったか?」
「ふざけるな!」、兎にも角にも文句のひとつやふたつやみっつやよっつ! 100こ並べても足りないくらいだ。
「悪かったな。俺が運ぶと言ったのに亜希子が勝手に業者を頼んでたみたいでさ」
このやろう。むかつくことをいけしゃあしゃあと。
「そう怒るなよ。今夜おごるからさ。おまえの都合がよければの話だけど」
「おまけに着払いとはどういう了見だ!」
買えば数十万の電子ピアノだということはわかる。だがこいつは中古だ。相場は知らないが、送料だけで済むなら安いもんだって理屈は通らないだろう? どうなんだ? それに勝手に送り付けてきたのはそっちだ。ぼくの知ったことじゃない。弾く気があれば容赦の余地もあるだろうが、衣類置きと化した今、費用負担がこっちではわりが合わなすぎる。
「ん?」と松田は聞き流したふうを装いながら苦い笑みを浮かべているのがわかる。「お・ご・る・か・ら・さ」と繰り返したあの言い方、そこには含みがある。都合が悪くなると〝間〟と〝勢い〟で流れを変えるやつの常套手段だった。その手際と手並みは天賦のもので、仕事でも遺憾なく発揮されている。その高次元の技をもって松田は手を打てと言っている。しかもクライアントを接待したそのあと、ついでみたいなおごりだと? 調子がいいにもほどがある!
そしてその果ての深酒。そして翌日の家政婦管理人に指摘された失態。悪いことのみごとなまでの連鎖。インディアナ・ジョーンズなら観客を喜ばせられる展開も、我が身に起これば天中殺以外のなにものでもない。
いい加減にしろ!
ピアノを弾いた記憶などなかった。
だがぼくは無意識にピアノを弾いた。
酒の場で松田は「どうだ、ピアノ、少しは弾けるようになったか?」と再び訊いてきた。
でもぼくはピアノを弾いたことになっている。
でも、弾けないぼくがどうやって?
で、何を弾いたというんだ?
曲? それとも……。
「どうした?」
ひとり目まぐるしく表情を変えるぼくに、異変に気づいた松田が訊いてきた。
幻想世界にノウムという妖精がいる。あれも多生の縁、ひょんなことから知りあったノウムはgnomeというスペルの小人で、地中深くに眠る宝の番をしている。
何を守っているのとぼくが尋ねると、教えないと答えが返ってきたような気がした。言い方は実に素っ気なかった。ファンタジーの世界ならなんでもありなんだがな、とぼくはノウムに聞こえよがしに心で声を響かせる。そう、ファンタジーの世界でなら、ぼくにもピアノが弾ける。
ぼくがピアノを弾く--甘い夢だということはわかっている。甘い夢は甘いうちが花で、現実が入り込むと苦く辛く酸っぱく苦しいものに変わっていく。それでも、誰にも話さないのなら、甘い夢にひたっていたっていいじゃないか。鍵盤上を流麗に踊る指。演奏曲はショパンかベートーヴェンか。『月光』ならスローだし、弾けないことはないんじゃないか、うかつな夢は無限に広がる。
出社日、仕事帰りに営業している家電量販店はない。それに楽譜も仕入れておきたかった。いや、勘違いしないでくれ。本気でピアノを弾こうなんておこがましいことは微塵も考えちゃいないし、弾く気もさらさらないと、ぼくは誰にともなく言い訳をする。言い訳しながら、夜10時までやっているとなりの駅の名曲堂楽器に帰り際に寄ろうと考えていた。
「どうしたんですか? 今日は楽しそう」
亀川が新しい案件の仕様書を持ってきて、耳打ちするように囁いた。
「キミは、なんでいつもぼくの出社日と同じ日にいるんだ?」
「さあてね。たまたまなんじゃないですか」
亀川の投げかけに応えずに、ぼくが訊く。
「きっと、多々倉さんの鼻歌を聴くためじゃないですかあ?」
「なっ」
ぼくが鼻歌を歌っていたっていうのか? まさか。
「歌っていましたよね。ふんふんって」
「ふんふんだって? そんなことはない。微塵も」
亀川の指摘に虚を衝かれ目を丸くすると、「動きが鼻歌まじり」と亀川がからまるように言う。
「そんなはずはない」、真に受けたぼくが間抜けだった。
「そんな感じがしただけですぅ」
仮に鼻歌を歌っていたとしてだ。それを亀川が揶揄したのだろうが、ぼくよりむしろ後ろ手でリズミカルに自席に戻る亀川のほうがよっぽど楽しそうに見える。
なんだい、亀川のやつ。
きりのよいところで仕事を切り上げ、9時に「お先に」。
会社から名曲堂楽器までは、電車を使わずに歩いても15分。電車を使っても歩く時間は入れれば所要時間は変わらないから歩くことにした。閉店まで時間はないが、買うものは決まっているから問題はない。
名曲堂楽器はもともとレコード店が時代の潮流に乗って楽器店に移行した店で、かつてはオーディオ類が充実していた。今は時流とスペースの関係で大型オーディオは姿を消したが(今後売れることはないと踏んでメーカーに返送したのか?)、ヘッドフォンなどの小物は健在だった。
ヘッドフォンと言えば一過言ある。父はゼンハイザーに心酔し、ぼくはボーズに憧れた。ところが店には知らないメーカーのヘッドフォンが並んでいる。現代は「ビーツがフリークに人気」と店員から聞いてショックを受けた。かつての名機が並んでいないことに気落ちしたのではない。時代に取り残された感が手痛い仕打ちみたいに心を打ちつけたのだ。ぼくはここでも取り残されている。
対応してくれたのは、70歳前後、白髪をうしろで束ねた痩せた老人だった。ビーツにフリーズしていると、「これなんかはいかがです?」と勧めてくれたのがオーディオテクニカのヘッドフォンだった。「値段も手ごろで、今も現役で人気です」。
「ピアノの楽譜もほしいんですが」、落ちた肩から声を絞り出すと、ジャンルとレベルを尋ねられた。
レベルってぼくのピアノのレベル? そんなもの無い。考えたことさえない。無知のうちは自分を無知とは思わない。恥辱を受けて初めて知らなかったことに恐れ入る。そしてそのことに気づかされた今、訊いた自分が愚かだと恥じ入った。これではレストランで漠然と「料理をください」と注文するようなものだ。困惑顔を浮かべた様子から実力を推し測られたのだろう「これからはじめられるなら弾きたい曲を選ぶといいですよ」。見透かされた。
造詣の深そうな導き方、物事を的確に捉える鋭さ、人の気持ちを踏みにじらない紳士的ふるまい、やわらかな物腰。オーナーなんだろうなと漠然と考えているぼくを、心の奥から冷ややかに嘲笑しているぼくがいた。そんなこともわからないのか、と心の中のぼくが無知のぼくを罵る。そんなだから、と心の中のぼくがつづけた。
「うるさい」とこちら側のぼくが押し黙らせた。そんなだからどうだというんだ! 「去った妻の真実など、ぼくが知るわけないじゃないか」。
弾きたい曲など思いつくはずもなかった。それでも、少し前に夢見た演奏曲がある。「月光、ですかねえ」と砂漠に砂を撒くように意味なさげに言うと、迷うことなくピアノピースを1冊棚から取り出した。
『ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 作品27-2【幻想曲風ソナタ】』
「弾きたいのは第1楽章ですね?」と訊かれたが、それさえ知らないぼくは「はあ」とピントが合わない。楽譜を開くと、聴いて知っているはずの曲は無音で紙に張りついている記号でしかなかった。わかってはいたのだけれども、途切れなくつづく音符は、成し遂げるのに大儀な苦行のようにぼくにのしかかってくる。
本当にこれを弾けるようになるのか。ページをめくってもまだつづきがある。再びページをめくると、道のりの長さに血の気が引いていくのがわかった。
「あの、これからピアノはじめるんですけど」とぼくは正直に打ち明けた。
背伸びをしてもピアノは弾けない。知ったかぶりをして混乱の深みで息絶えてしまう前に、生き延びる手を打たなければならなかった。だから「もっとこう、がらんとしているというか、音符の少ない曲がいいんですけど」と謙虚に出たら、オーナーらしき老人、一瞬かたまり、直後に大笑いをされてしまった。
「いや、失礼。無謀だとは思いませんが順を追って弾かれるのもいいですよ。海外には探り引きでみごとな演奏をこなすピアニストもたくさんいますし。千里の道の克服も夢ではありません。それでもやっぱり一歩からはじめることです」
結局『月光』はあきらめ、ジョン・レノン超初級版、ジブリの楽譜をオーバーイヤーのオーディオテクニカに添えて会計してもらった。少なくともこれで近所に迷惑をかけることはなくなった。問題は演奏の第一歩を踏み出せるかどうか。いや、踏み出す必要もなかった。夜中の気まぐれで隣家に迷惑をかけないこと。これこそが買い物におけるいちばんの目的であった。
ところが名曲堂楽器でぼくは、あの老人に背中を押されてしまった。オーナーらしき人の『イマジン』から弾かれるといいと思います、というアドバイス。ギターをやっておられたなら、コードは理解しているでしょう? なら、ギターを思い出しながら弾くと、すんなり入っていけますよ。
ほんとかなと疑問を抱いたけれども、彼が言うなら実現できそうな気がした。人を納得させることがとてもじょうずな人だった。
疑問は払拭しえなかったが、心は動いた。弾いてみよう。
開いた『イマジン』には五線譜の上にコードが書かれている。曲の出だしはCで、次はF。Cはドミソ。Fはドファラ。ギターで知った知識だ。それをピアノにあてはめてみる。右手親指でド、同じく人差し指でミ、薬指でソ。指は、それぞれの鍵盤の上にある。あとは3本の指を同時に振り下ろすだけだ。
ジャン。たしかにCの和音。
次に覚えなければならないコードはドファラのF、ジャン。うん、これこれ、この音。だがこれはまだ曲じゃない。でもそれは、千里の道の第一歩のように思えてきた。この一歩はピアノ弾きにしてみれば小さい踏み出しだが、ぼくにとってはとてつも大きな一歩だった。
楽譜の音符と和音を見比べてみる。ドミソ、ドファラ。合ってる。
『イマジン』の弾きはじめは、最初は四分音符(♩)が1拍ずつつづく。
C、C、C、CM7(C+シ)、それからF(ドファラ)で4拍伸ばす。それをもういちどくり返す。
左手は、と。オクターブ低いドとソを8分音符(♪)で。半拍ずつ繰り返し4拍分を繰り返せばいい。次がFで、さらに低いラとファの組み合わせを8分音符で4拍分弾く、か。
右手に添えると。あれ? これって曲になってる。弾けてるじゃん。たどたどしさは当然でも、曲にはなっている。たったこれだけのことなのに体裁が整うとはなんたる驚き。ピアノは秀外恵中で門外漢だとばかり思って疑わなかった、その愚かな先入観がぱっかりと割れて砕け散った。光明が輪を作り、広がり、スポットライトとなってピアニストとなったぼくを照らし出す。快哉で、散り散りになった気力が充溢してくる。
ノウムはたしかに存在していて、きっとぼくの才能に気づいている。せっかくもって生まれた才能を外部に流出させないために、その番人として現れたのだ。たぶん。
だが、もう遅い。ぼくは自分の才能に覚醒した、と気をよくして、最初の4小節を繰り 返し繰り返し弾いてみた。いい感じ。
ああ、ピアノが弾けるってこんなに楽しいものかと、このとき初めて思った。ピアノ弾きからすれば弾いたことにもならない稚拙な演奏なのに、いい大人がこれほど嬉々としている。
これなら、すぐに全体を弾けるようになる、そう信じて疑わなかった。だけど苦難の局面はわずか5小節目にやってきた。あれ、右手に3連符がでてくる。しかも一拍休んでからだ。それに右手と左手のリズムが違うじゃないか。こうか? 鍵盤を追っても、指が思うように曲を奏でない。ちくしょう、これか?
だめだ、違う。
希望ににわかに影がかかり、表情から覇気がぷしゅうと抜けていく。代わりに諦観がひゅうと入り込んできて、気持ち、沈没。喜びも三日天下。時計の針は午前2時を指していた。
明日も仕事がある。テレワークとはいえ、そろそろ休まなければならなかった。それ以上練習する気力も時間も残されてはいなかったので、残念だが今日はここまで。だいじょうぶ。明日仕事が終わればつづきが弾ける。ローマは1日にしてならず。ぼくはピアノでローマ帝国を築こうとしていた。
夏掛けを引っ張り上げながらぼくはベッドで進捗を振り返ってみた。両手の指を使って音を奏でることはことのほか大きな喜びをもたらしてくれた。それ以上に驚いたのは、ピアノに向かっていた2時間の時間推移である。あっと言う間だった。没我は烏兎怱怱。脇目もふらずに打ち込んでいた。目を閉じると、心地のよいフェードアウトが待ち受けていた。
意識は、駅ピアノの鍵盤に向かっている。プログラムを打ち込む早さで指が鍵盤上を行き来する、両腕が交差する。この駅はどこだ? ヨーロッパ? 小さな中世の建造物みたいだった。観るともなしに流していたテレビのピアノ番組、その記憶にも見当たらない駅の風景。入鋏は列車ごとに車掌が行うから駅構内に改札は無い。乗客と見送り客を隔てる障害物がないだけで、小さな空間が実にのびやかに感じられた。人はまばらで、がらんとした駅構内の臍にグランドピアノが置かれている。そのピアノの鍵盤を音符を追う指が舞う、ステップを踏む、踊り、跳ねる。
人は透けた影、厚みを増しながら幾重にもふくらんでいくのがわかる。人がにわかに増え始めている。その人垣を透かして列車が入ってきた。降車する旅人を迎える曲は『A列車で行こう』。来る人を、行く曲で迎える、その矛盾が眩暈を呼んで、時空のレイヤーが離れつながりでたらめに再構築しはじめた。止まらない観客の足はさらに増え、人ごみの密度のせいで軽い酸欠状態に陥ると、ひとりの女が逃げるように観衆から飛び出していった。
ずきん。胸が痛む。
弾きながら、走り去る足音を追う。
女は妻だった。顔も手も足も胴体もすべてが黒尽くめの影となった男が発車間際の列車から手を伸ばして妻の手をつかもうとしている。
行くんじゃない、とぼくは演奏の手を止め、妻に叫んでいる。
妻はぼくの声を耳に入れてはくれなかった。
男が列車から妻の手をつかもうとさらに手を伸ばすが、すんでのところで届かない。男は届けと心で叫ぶ。ぼくが届くなと声をあげる。
妻の顔が悲壮に包まれ何かを叫んでいるが、声を向けた相手はぼくにじゃない。影の男にだ。
何を語りかけている?
ずきん。
雑踏にかき消され何を口にしているのか聞き取れない。男の名か? 男が身を乗り出すと、妻のすがるように伸ばした指先をつかんだ。直後、速度を上げた列車にはためくように妻が連れ去られる。Take the A Train。ピアノの演奏を止めたはずのぼくは、去る妻を皮肉にも快活な曲を弾いて送っていた。行先はA Trainが向かうハーレムなのか。
りりりりりりり。
発車音ではなかった。ルーティンな目覚ましのベル。いやな夢が終わり、重い1日のはじまりを予感させた。
5月下旬。
「これじゃ全然わからない。矛盾だらけだしぃ」
出社日。またしても亀川がいる。それに悪い予感は的中し、出社したときにはすでに起爆スイッチが押されていた。クライアントを前に、亀川が啖呵を切っていた。しかも相手は、40代後半の管理職。中小の中でお偉いさんにあたる役職だ。その役職者に対してため口である。
「ふざけないでくれたまえ」
憤怒の爆煙から顔を突き出した管理職は、頬を紅潮させていた。
クライアントはお金も出すが口も出す。多くのクライアントがそうだ。お金は出すが口は出さない神対応のクライアントは今では噂さえ聞くことはなくなった。時代はすでに古き良き時代のカラーを塗り替えてしまったのだ。
知っていて口を出すならまだいい。軋轢は、聞きかじり程度の知識で仕様書作成の現場に口を挟まれたときに起きる。するとかきまわされるだけで仕事が遅々として進まなくなる。
とくに年配者には取扱注意者が多い。業績を認められリーダーに抜擢されても、ご褒美役職では現場の知識に追いつかず問題が起こりやすい。担当責任者の管理職にはメンツもあって、これが往々として事態をこじらせる。
いいものに仕上げたいならよぶんな口を出さないでほしい現場が反駁すると、もう火に油。リーダー(ぼく)がクッションになるところを、立ち寄りの打ち合わせでオフィスを空けていた際に起こったアクシデント。
「すみません。まだひよっこなので許してやってください。あとできつく叱っておきますから」
納得にはほど遠い顔をしながら、それでも説得が仕事のひとつだし、ことを荒立ててこじらせるとお互いに困るから、管理職、しぶしぶの顔に変え、わかりましたと首を縦に振ってくれた。
自分のしでかした騒動に反省の色でも浮かべてくれれば可愛げもあるものの、当の亀川はあっけらかんとしたものだ。プログラミングの専門学校を卒業して入社してきた亀川は物覚えもよく、JavaもC言語も、おまけにケータイ・アプリにも対応するRubyも書けることからこれまで幾度となく助けられてきた。その年の卒業生でイチオシと学校から太鼓判を押された実力は認めざるを得ないものだったし、重宝もしていた。
でも。
「亀川、ちょっと」
クライアントを丁重に送り出したあと、亀川を会議室に呼び出した。部下の教育。これもまたぼくの仕事のひとつである。
「おまえなあ、自分の主張はわかるが、仕事にはお金の流れと人の流れがあって、継続という流れもつくらなきゃならんのだ、わかっているのか?」
「はい、充分に」、にこやかな能天気はこちらの言いたいことが伝わっていない証。臆面の欠如は相変わらずだ。
「あのなあ」
わからない者にはわかるように。呆れ顔を真顔につくり直し、
「時代はアンタンカクを求めるようになっている」と言うと、
「はあ? 何ですかそれ?」と暖簾に腕押しのレスポンス。
話の芯はそこじゃない。これからだ。
「プログラマが重宝されていたのは、プログラマが足りなかったころの話。今は時代が変わって競合が増えすぎた。もうちやほやされる時代じゃない。競争に勝たなきゃならない時代なんだ。わかるか? 競争に勝つには見積もりで〝安く〟受けて、〝短期間で納品〟できて、〝確実〟な仕事をこなす、そんなプログラマ集団だ。これらを当たり前にこなせたうえで、次につなげる知恵を絞る。人とつながっていく工夫、仕事を潤沢にまわす算段、そういったものが必要なわけだ。でないとお金も流れてこない。お金が入ってこないと支払える給料が減りこそすれ上がることはない。給料が上がらないのはたまらんだろう?」
「はい、たまりません!」
そう言うと亀川は人差し指を唇にあてて口を尖らせた。
「それにしてもうまいこと言いますね」
ん? なにがだ?
「アンタンカクですね、覚えておきます!」
逡巡した結果の最良の教えと思ったが、込めた願いは空まわり。言いたいことはそこじゃない。厚顔にはじかれた思いがした。暖簾に腕押しは撤回、あんぽんたんなこいつは蛙の面に水だ。
それでも亀川の天然は、ときにオフィスの張り詰めた空気の腰をいい意味で折ってくれることがあって、助けられることがある。締め切りに追われる日々がつづくとスタッフみんなに苛立ちが蔓延し、吊り上がる目が一触即発に邁進する。体力も消耗戦で残りのエナジーもごくわずか、限界が近づき、焦りも加わる。
「ぼくが締め切りを調整するからいい仕事をしてほしい。確実に仕上げることがいちばん」と安短確の〝確〟を強調しても、納品日に間に合わないと仕事の継続に翳りが出ることを知っているベテラン連中は、「はい」と理解を装うが、仕事の手をゆるめることはない。
焦燥はいけない。ミスを呼び、結果遅れることはあまたの事例が物語っている。そんなとき。亀川が「私が体を張ってでも納期を調整しまぁす」と胸をたたいたことがあった。テレワークが定着する少し前のことだ。
亀川がいかに優秀でも熟練たちには敵わない。ひとりで頑張ったところで、間に合わないものは間に合わない。仕上げるのに不足する時間は、メンバーそれぞれの労働時間で調整するしかない。残業が自慢だった時代から諸悪の根源になった現代社会の労働環境、残業してくれとはマネジメントの立場からは言えない。強要できないこともわかっている。それに、安短確を求める世のクライアントたちは、自社の労働環境改善には躍起になるが、こと労働時間に関する調整ではたいがいの場合ひずみが生じ、そのしわ寄せを業務の下部組織にあたるわれわれ下請けが調整していくことになる。
つまり解決しようのない構造的問題をわれわれは抱えこんでいるということだ。諸事情を鑑みて納期にバッファを設ければ〝短〟で競合相手にやられてしまうし、〝確〟を担保できなければクライアントからいとも簡単に切り捨てられる。ルーティンで仕事がまわっているうちは安泰でいられるが、特殊な歯車で動く仕事も中にはあって、そのときには気も神経も遣えば、心臓に悪い綱渡りをしなければならないことがある。
絶対にしてはいけないこと、それは、自主的残業の強要だ。違法性の側面もあるが、もっとも危惧すべきは個人の尊厳無視と労働意欲を考慮しない封建的指示組織に、スタッフの働きつづけたいという意欲は宿らない、そう考えているからだった。強要は、モチベーションを間違くなく刮ぎ取っていく。すると循環にも歪が出てくる。下手をすれば納期が遅れるだけで済まなくなる。スタッフの結びつきが空中分解してしまっては、もともこもないのだ。
「わーん、終わらないよう」
亀川が夜分に入って悔し涙を流し出した。熟練たちは憤懣こもるキーボードの入力作業を止め、いっせいに亀川に目を集める。
「終わらせたいよう」
終電までやってから帰る、誰もがそう思って緊張の糸を神経が攣るほどに張っていた。
だが、終電で帰っては時間的により窮地に陥ることもわかっていた。
「しょうがねえなあ」
ぼくより5才年上の年長プログラマが、自分の緊張の糸を切った。顔は苦いが言い方はやさしかった。
「オレはやってく。亀川にいいとこ持っていかれたくないからなあ」
他の3人が年長につづくと、鬼気迫る緊張感からほとばしる汗のようなカタカタ音が音色を変え気力に満ち、縁の下から持ち上げられるような安定した響きに変わった。おかげで仮眠をとる夜明け前には、遅れた分をずいぶん取り戻せた。窓のすりガラスに月の青い光が斜めに走っていた。出社時に浮かんでいたのはたしか十日夜の月だ。満月まであと5日。満月に日と納品日がたまたま重なっていた。
満月の納品日。ぼくらスタッフは、満面の笑みを浮かべた。亀川がいると、苦しいだけの追い込みに充実感が流れこむ、そんな奇跡がときどき起こる。
6月上旬。
クライアントへの仕様書提出は、こちら側で仕上げたものに赤字を入れてもらうことで決着した。急ぎの案件もないし、2日のうちのこの日の出社日も9時前には会社を出られそうだった。
残業が伸びない日は、家でピアノ。未だつまずいている『イマジン』5小節目が目下、飛び越えるべきハードルになっている。
いっぽう、つまずきの要因も見えてきた。楽譜に書かれた音符が多く、リズムが複雑化すると、音符の音への変換機能がフリーズしてしまうのだ。
和音を奏でる楽器にふれた経験はあっても、ギターはタブ譜、いわば型を覚えてしまえばなんとかなる。ところがピアノはそうはいかない。1音1音が独立していて、演奏を単純化するための公式がない。
ピアノの特性が、とてつもなく巨大な壁となって立ちはだかっている。
どうすれば膠着状態を打ち破れる?
退社時間が近づくと、翌日の仕事の段取りもそこそこに、新しく現れた課題に真剣に取り組む自分がいた。
障壁の原因は? 左右の音のタイミングが違うところでつまずくとなれば、右手と左手の動きを独立させて動かせるようにしなければならないということだ。楽譜で弾けないわけだから、何かしらの橋渡しが必要になる。アドバイスをくれる先生はいない。もともとのピアノの持ち主、亜希子なら問題を解決してくれるだろうが、彼女も多忙だと聞いているし、なにより気恥ずかしかったのでやめた。あれだけ引き受けるのに抵抗したのだもの。どんな顔して「教えてください」なんて恥ずかしいことが言えるというのか? 自力でどうにかしたいという意地もある。
どうすればいい?
鞄にケータイとノートパソコンを詰め込んだとき、そっか、と閃いた。タブ譜を作ればいいんだ。時系列に並べた図面化した鍵盤で弾く音を追って理解する。可視化すれば音をつかまえられるはずだ。
自宅。
イラストレーターで鍵盤図をつくり音の長さを考慮して打ち出した。おさえる鍵盤に目印をつけてあるから……。音をヴィジュアル化するとピアノ演奏が向こうから近づいてくれたような気がした。足踏みしていた5小節目。どう弾けばいいのかがわかる。
弾いてみる。
これだ、この音。合ってる!
やたっ!
歩みは相変わらず牛歩だったけれども、そうこうしているうちに数日でイマジンの折り返し地点(1コーラスの半分だったが)を超えていた。
「田所さん、なにかいいことあった?」
数日後、デスクワークをしているぼくに亀川が耳元に口を寄せ訊いてきた。
「いや、とくに。なぜだ?」、くっつきすぎた顔から上半身を逸らせて離れると、
「ここのところ、追われている顔してないから」と奇異なことを言う。
「顔が追われていないって?」
「そう」、亀川が背筋を伸ばしてぼくとの距離をとった。
「なんだそれ?」
「楽しそうなんだもの。キーボードたたく指がリズム刻んでるし」
ため口は相変わらずで、いつも以上に馴れ馴れしい。それに、気になることもある。亀川に、ピアノを弾いていることを見抜かれている? まさか。
「不思議か?」、亀川の投げかけに惚けてみせた。返答は元気な「はい!」。
亀川があまりに嬉々とした顔を見せたものだから、裏に潜む思惑を勘ぐり底意地悪く、「不思議や秘密のひとつやふたつは誰にだってあるものさ」とはぐらかしたら、泣き出しそうになったのでバツを悪くしてしまった。
目の端が、亀川の唇の動きを捉えたような気がした。動きに韻を当てはめたら「いじわる」と綴ることができた。いや、本当にそう言ったのかどうかの確証はもてない。唇が動いたかどうかも疑わしい。ただ、そんな気がしただけだ。
昨今の若い連中は、飲みに誘っても体よく断ってくる。5才年上の年長を除けば、あとの4人はみな20代が2人と30代がひとりである。彼らは自分を大切にする。仕事が忙しくても、終われば自分の時間に戻っていく。彼らは組織に粘度の高いつき合いを求めない。粘度の高いつきあいは良くも悪くも集団力を上げるが、それをしない。高度成長期にはそれが業績や経済にレバレッジをかけた。
だが今は違う。
集団力は悪しき一面を浮き彫りにした。つき合い残業がその象徴だろう。もちろん、今の会社にも残業はある。だがここの残業は圧力をかけた集団力によるものではない。結束によるものだ。与えられたものではなく自発的意志でつながる結束だ。目標を見すえ、分担した業務の責任をそれぞれが担う。集団力の他人の顔色で結びつくのとは違う。今の部署に結束はあるが集団力はない。そしてその結束は身勝手なエゴイズムの集まりではない。結束は業務によって形成され、たとえば誰かの仕事が滞っていれば見逃すことなく手が差し伸べられる。
年長者も含めて5人の部下は業務による結束を心得ているしある意味完成しているから、ぼくは誰も誘わない。亀川も誘わない。それぞれがいい距離感で均衡が保たれている。
ぼくはその中で、自分の役割をまっとうしている。スタッフをまとめ、求められる仕事の精度をあえて少し高めて納品する。「いい仕事」と評される仕事は、社内での、そして社外とのつながりを好循環させる潤滑油だ。
そしてぼくもまた潤滑油。社内の風通しに気を遣うソフトウェア。ソフトウェアは、与えられた仕事を完璧にこなすためにある。ぼくは今、部署に意志を与え、結果をまとめ、会社を循環させている。
社内での役目が終わればぼくもまた自分の時間に戻っていく。新たにつかんだ戻るべき自分の時間へ。
夕方、家族構成変更届の確認をしてほしいと総務部に呼び出された。傷口はなかなか治癒してはくれなかったが、支えができたおかげで痛みがいくぶん和らいできたようにも思う。もう、ゴミ袋が大きくふくらむこともなくなった。キッチンもきれいに片づけられている。歯ブラシは、まだ1本のままだけれども。それでも、何という魔のタイミング。塞がりかけた傷口を上から強烈にこすられた思いで出向くと、担当の年配女性に「たいへんね」と同情めいたことばをいただく。彼女もまたこの会社の社風に染まった社員である。それぞれが自律している集合体のひとり。
だから「3組にひと組が離婚する時代ですから、あんまり深く考えないことね」というひと言に、噂話に臍で茶を沸かす粘着性の下心は感じられなかった。彼女もまた仕事が終われば自分の時間に戻っていく。高校生の娘と暮らす彼女もまた、3組のうちのひと組、同類である。
子どもができると世に幼児があふれていることに気づくと言うが、ピアノの気づきも似たようなものだ。たまにランチで出かける手作りカレーの喫茶店は年に数度プチコンサートを開催することも気づいたし(手作り雑貨を並べる棚と化していたアップライトピアノが実は今でも現役で稼働していることを知った)、打ち合わせで使うホテルのカフェのピアノが日本ではマイナーだが高級機とされるメイソン&ハムリンであることもネットで調べた。
新宿駅までの道のり途中の牛丼屋となりが、中古輸入ピアノの販売店という直球ド真ん中であったことにも今さらながら意識が向いた。
気にかけていないと、何も目に入らない。もしかしたら、ぼくは妻の、気にかけなければならなかった大事な何かを見過ごしていたのかもしれない、そう考えたら、また胸がずきんと疼いた。確信のない安心感、きっとそのようなものにあぐらをかいていたのだと思う。
ぼくは楽しさの共有こそが仲を結ぶつなぎになると信じていた。だけど楽しさの共有だけでは、きっと頼り合うことなどできなかったのだ。思い返すと、外食をしているとき、ぼんやりと窓の外を眺める妻がいた。休日の列車旅でスマホに見入る妻が驚いて口に手をあてたり、ため息をついたりしていることもあった。友人や同僚とのやりとりに、そんな喜怒哀楽はあってあたりまえだ。だから気にとめることはなかったし、尋ねたこともなかった。隣にいるのに、そばに寄り添っているという実感を、ぼくは与えてこなかったのかもしれない。送られてくるシグナルに、ぼくは気づかなかった!? 少なくとも、ぼくは今のピアノほど、昔の妻を見つけようとしていなかった。
ネットをサーフすると、フジコ・ハミングも辻井信行も、名だたるピアニストの演奏が聴ける。テレビの駅ピアノ、空港ピアノ以外にも、ストリートピアノもあれば、ピアノを設置した音楽室を提供する自治体が存在することも知った。
情報網の波で見つけたいちばんの収穫は、YouTubeにはピアノの先生があふれていると知ったことだった。主にアメリカのサイトではネットレッスンがポピュラーなのか、クラシックからジャズのまるごと1曲を、あるいは演奏テクニックを映像で、サイトによっては時系列で構成されるデジタル鍵盤図を交えて指導してくれる。さすがに英語はハードルが高いが、ことばに壁はあっても見ているだけで弾き方がわかる。
世界共通語の音楽は国境を越えて好奇心の容器に遠慮なくなだれこんでくる。レッスンサイトを見つけてはiPadを譜面立てに横起きし、1、2小節を再現しては停止して巻き戻し繰り返し視聴。演奏する鍵盤をたしかめながら曲を細切れに再現、そして先に進み、3、4小節にとりかかる。このように曲を区切りながら積み上げていく。
『イマジン』の目標、1コーラスを楽譜で仕上げながら、YouTubeでビリー・ジョエルの『ピアノマン』を追った。
音は相変わらず棒立ちで流麗にはほど遠かったけれど、演奏する自分に酔うことはできる。ジブリの楽譜も開いてはみたが、楽譜を追うよりいい方法を見つけたことで、しばらく書棚で休んでもらうことになった。
YouTubeに教わるようになってから、『ピアノマン』をフル・コーラスで音を追えるようになっていた。ピアノ演奏とは摩訶不思議。弾けるようになれば楽譜に書かれている音符から弾くべき鍵盤が透けてくるようになる。ほどなくしてジブリの初心者用楽譜を開くと、弾くべき鍵盤を読み解けるようになっていた。
曲は『人生のメリーゴーランド』。1日2時間弱。10日あまりで音をたどれるようになった。
そろそろ『月光』にいってみるか。明日も出勤日。残業は2時間ほどですむはずだ。帰りに名曲堂楽器に寄ってこよう。時計を見ると深夜2時に届くところだった。
衣類は元の鞘に収まるようになっていたし、鍵盤蓋を邪魔する者はもう誰もいなくなっていた。
6月中旬。
翌日。珍しく8時に帰り支度をはじめることができた。
「区切りがいいので上がらせてもらうよ」
オフィスの窓が拾う光にネオンが混じるようになって2時間は経つ。
夜の光は不思議だった。どんなに煌々と光輝いても、陽光とは違って闇を照らし切ることはできない。闇は闇として間違いなくオフィスの壁の向こうで存在感を増していたし、人工的な光は、太刀打ちできないながらも精いっぱい抵抗し虚勢を張っているように見える。
月の光はどうだろう。闇を中途半端に残したまま、照らす世界を蒼く包むあの妖艶な光は。
蛍光灯の光に照らし出された職場は、区切りのつかないスタッフたちの仕事モードを煽りつづけている。急かされる光に彼らはひっきりなしにテキストと記号を書き込みながら、DeleteとBack spaceで2歩も3歩も下がっては、新たに文字と記号を並べていく。
このころになると夜間でも気温は下がることなく、湿気もいちだん渋みを増して、始終エアコンの室外機が唸りをあげる。会社に残っているのはうちの数人ととなりの第2制作部の連中だけだった。同じフロアの総務、経理、営業部の電気はコンプライアンスを証明するみたいに今日も5時半きっかりに消されていた。
「おつかれさまでしたあ」
2人残っていた第3制作部のひとりが仕事に区切りをつけ、席を立った。
気の抜けたスタッフの対応はいつものこと。集中は切らさないがそれは内に向くものであり、吐き出されるのはなんとも間の抜けた惰性の挨拶。いちいち体育会のりではちきれんばかりの挨拶をされても、かえって疲れてしまう。
「さぁでしたあ」
ひとり残された画面を睨む亀川が、よほど仕事に集中していたのか、あるいは時間に追われていて集中せざるをえないのか、モニタに向ける鋭い目線からはほど遠い腑抜けた声で、ひとり言のように挨拶を返した。
新宿の繁華街を抜けるといったん裏路地の住宅街に入る。寂れた街灯に、施錠の行き届いた門のない家々がつづく。玄関に備え付けの電灯は申し合わせたようにスイッチが切られている。闇を照らし魔を抑制するはずの明かりが、闇と同化し助長している。かつてこの路地で夜の女が脚線美を見せつけ男を誘っていた。その裏路地を、月の光がひたひたと濡らしている。
「来ると思ってました」
蛍光灯で照らされた名曲堂楽器の奥、楽譜コーナーに、亀川がいた。1駅歩くぼくを、1駅乗った彼女が追い越していた。
「なんでおまえがここにいるんだ?」
「なんとなく」、亀川は後ろ手で体を前後に揺らしてご機嫌でいる。
すると奥から「マドカちゃん、お待たせ」と、かの白髪ヒッピーふうの人物が1冊の分厚い本を持って出てきた。
「ありがと」、亀川がそれを受けとる。
「なんでまた今さらながら楽典なんかを?」
「就職したときに捨てちゃったから。たまには左脳を刺激しないとね。ばかになっちゃう」と茶目っ気でウインクしてみせた。
円日ちゃん? ガクテン? なんだそれ? 予想もしない断片が次々に顕在化してくる。
亀川が老人に「こちら会社の上司の多々倉さん」と友だちみたいに紹介された。
「はあ、どうも」
どう理解していいものか、わからなかった。だから、「どういうこと?」と訊くことにした。
亀川に説明を求めて顔を向けると、うふ、と焦点をずらしてくる。
瞬時に場の空気を読み取った白髪の老人が「マドカちゃんは、この子がちび助のころからのお得意さまでね。お母さんが音楽教育に熱心で、てっきりピアニストになるのかと思っていたら同じキーボードでも音楽じゃなくパソコンのほうに就職したってんで、あのときは驚かされましたよ」と助け船を出してきた。
ピアニスト? 音楽教育? 混乱が混沌に呑み込まれていく。
「えっ、どういうことですか?」
尋ねるも老いた男、「あなた、この間ベートーヴェンの楽譜をお求めになられようとした方ですよね?」
ぼくの質問に答えるより彼はぼくを覚えていたほうを優先させた。そんなことより、ぼくは今のこの状況をどう把握すればいいのだ?
「ですから言っているじゃないですか」
横やりが、楽譜の物色という当初の目論見をみごとにはがしてしまった。
そして今ぼくは、亀川と深夜の喫茶店に向かい合って座っている。ぼくはアイスコーヒーを、彼女は冷たい抹茶ラテで間を保っている。
窓の外をカップルやら同僚との飲み会のグループやらが不定期に通り過ぎていった。閑散としてしてしまった町は、またその舞台を変えた。元に戻ったのかもしれない。だけどそこにいる人たちは、もう自粛前の人たちではない。自粛後の人たちだ。何かが変わって、時代を前に進めている。
窓の外を行く彼らは、自粛後に口にすべき話題を口にしている。だけど、何を話しているのかはガラスの厚みが邪魔をしてわからない。高架の上を電車が発車しては入線してきた。電車は連続しているのに、亀川の話は途切れ途切れで的を射ない。
「概念は人類を成長させるんです」
焦点のずれた会話には慣れっこだったが、楽器店での疑問は解消しておきたかった。
「歴史が物語っているし、これからもつづきます。でも」
「でも」とぼくは慎重にコマを進めようと亀川のことばをなぞって先をうながす。話の主導権を握らないことには解決への道筋が拓けない。だがその思いも肩透かし。
「私には時間がなかったんです。言うなれば身を立てるために」
「身を立てるために? つまりピアニストではだめだったってことを言いたい?」
少しずつ誘導していくよりないか、と腹をくくるぼくがいる。
時間がかかりそうだな、と煩わしさにうんざりしたが、終電まで時間はある。家に帰ったって、すぐに眠るわけではないのだ。外で夜更かししても、体制に影響はない。
いや、違う。ピアノを弾く時間が減るという実害が出る!
「そうです。ピアニストの具現化には、100年の歳月が必要だってことがわかったんです。もし私がピアニストになるのなら」
いやはや、誘導の道筋を間違えてしまったか、よけいわからなくなってきた。
「人の想像力は国をまとめることができるようになったんですよ。でもそれには何百年、何千年もかかった。農業を集団で行おうとイメージしたのも人間でした。実現するのに何百年もかかっています。何年かかってもいいというなら話は別です。でも私には悠長に時間をかけることができませんでした」
亀川の真剣な顔を見ていたら、これ以上何を言っても無駄に思えてきた。
「そっか」
区切りをつけて、さっさと帰ろう、そう思った刹那。
「なんてね」と亀川が両肩を上げた。
「つなぎとめておきたかったんです、本当は」ととたんに寂しい顔をした。
あの老人はお楽器店のオーナーで、お店にはよく通っていたこと、楽典は音楽を学術としてとらえるための参考書みたいなもので、大学時代の愛蔵書の1冊だったけれども音楽に区切りをつけるためにいったん決心して捨てたものの、ちょっとしたきっかけで--それはぼくに因るものらしい--読み返したくなって注文したこと、親が彼女をプロの演奏家にしたがっていたこと、自分の技術進捗曲線を分析してもらったところ、世界一流とされるピアニスト・レベルに到達するまでの時間が算出されたこと--それが100年の根拠らしい。
ちなみにぼくには、その100年は彼女のやる気にはっぱをかけるための方便であって、物理的に必要とされる時間ではないことがわかる。バネを縮めて伸ばすのと同じだ。本当に才能がないのなら、継続を暗示する指針は示さない。
でも亀川は真に受けた。
人は100年も修行できるものではない。
亀川が言う、時間をかけて築き上げてきた想像力と発展の推移、これはユヴァル・ノア・ハラリを読んだからだろう。あの難しい本を亀川は。理解している。頭の出来はもともとがいいのだろう。だけど、世間を知らなすぎる。いいとこのお嬢ちゃんだったことが、この時見えてきた。
だが亀川はぼくより1枚うわてだった。亀川はその口から、修行の100年は親が娘の反骨精神を引き出すための方便だったと語ったのだから。
話は理路整然としており、短時間で語り切るにはかなりの力量を要する話をみごとに凝縮していた。
こいつ、天然じゃなかった。
それに、ほかにも感心させられたことがある。
「えっ、大学中退してプログラミングの学校に入ったんじゃなかったのか?」
「はい。いえ、いいえ。ええっと、大学は卒業しました。親に心配かけたくなかったから。3年になって、夜間のプログラミング専門学校に通いはじめたんです。二足の草鞋ってやつですね。これからの音楽にはパソコンが絶対に必要になるからって言ったら、母はあっさり納得してくれたました」
「でも本心では音楽に役立てるつもりはなく、プログラミングでやっていこうと?」
「そうです。さっきも言ったように、私には100年単位で技術を習得する寿命がないことがわかったから」
「いい加減にしろ」
もうネタは割れているんだよ、とことばを乗せて、ぼくは顔をほころばせた。
「ちょっと前、ランチで財布を出したとき、レシートが落ちたこと覚えてません? カレーのおいしい喫茶店に連れていってもらったときのこと」
いつだったか『イマジン』のゴールをどうにか切ってきぶんのよかったあの日のことを亀川は言っている。タイミングが合ったことで、一緒にメシでも食いに行くか、と雑貨販売棚としてピアノを使っている喫茶店に誘ったのだった。
「あのときですよ。落ちたレシートに名曲堂楽器とあって、楽譜を買ったことがわかったんです。そのときは何の楽譜だろうって想像しただけだったけど、多々倉さん、会社で指を動かすじゃないですか、ときどきこう」と言って、亀川はピアノの鍵盤上を躍らせるように、しかも相当な手練れであることがわかる滑らかさで右手を動かしてみせた。「わかりやすかった。とっても。そのとき浮かべていた顔がとてもうれしそうに見えて」とそこまで話したところで、舞台が暗転したみたいな顔に切り替えた。
「私、小さいころからピアノを習わされていました。監視するように母がいつでも横で目を光らせていて。うまく弾けないとぴしゃりと手を叩かれるんです。指をケガする運動は禁止、だから体育の時間は見学ばかりでした。ひとり、みんなが楽しそうにするのを見ているだけ。見ているだけなんてつまらないから、いろんなことを空想して遊んでいました。体育の授業中、退屈しないように、前もって書店のいちばん目立つところにある本を買って、ん? 買ってもらって、読んで、その内容を思い出していたんです。
すごいんですよ。読んでから思い出すと、内容が記憶のひだからはなれなくなるの。わかります? その感覚」
「ぼくは、それだけ高い記憶能力は持ち合わせていないよ」
「うそばっかり。いろんなことを知っているじゃないですか、安短確とか、それから、安くて短くて確かで、とか、仕事のこといろいろ」
もはやからかわれているとしか思えなかった。それだけの知能をこいつは持ち合わせている。
「それでね、帰ったらまたピアノ。指の動きを滑らかにするトレーニングから入って練習して。その繰り返し。そんな毎日がいやでいやで機会があれば逃げ出したかった」
天然は、多少なりとも入っていることは確実だな、と思った。
「そして、機会を作って逃げたんです」
亀川はぼくの目を直視してきた。上司として気の利いたことを言わなければならないと思った。思ったものの、湧き出た感情がことばに変換できなかった。音符が音に変換できなかったあのときのぼくみたいに。
亀川がつづけた。
「私、ピアノが嫌いでした。だから音楽から離れたかったのかもしれません。そして晴れて離れることができました。これでもう、ピアノと縁を切れるって。自分で稼ぐことができるようになって、家を出てひとりで住むようになって、ピアノのことなどすっかり忘れてしまおうと思っていました。2年も経てば、好きだった彼氏のこともすっかり忘れちゃうみたいに」
うっかり、好きだった彼がいたの? と訊きそうになってしまった。尋ねてもどうにもなるものではないのに。それに、どうにかしたいわけでもない。
「そんなとき、多々倉さんがうれしそうに指を動かしているのを見て、ピアノが好きなんだなって思ったの。私が嫌いだったピアノ、どうして好きなのかなって。私にはなかったピアノへの想いが多々倉さんにはきっとあるんだろうなって。そう思ったら、訊いてみたくなっちゃって」
「ピアノを?」、場違いだった。
「いえ、訊きたいのはどうしてピアノが好きなのかってこと。だって雰囲気でわかるもん」
どうやらぼくにも天然の気はあるらしい。
「なにが?」
「ピアノ、じょうずじゃないってこと」
「おいおい、そりゃあないだろう」
そう答えてから、しまったと第六感が感じ取った。これじゃまるで。
恋人同士の会話じゃないか。
いつの間にか亀川のペースに呑まれていた。だが、まあいい。部下を知ることもぼくの仕事のひとつだ。
「ぼくは持ち上げられているのかい? それとも落とされているのかな?」
苦笑いを返した。
ふたりのレイヤーは上司と部下という関係で成立しているのだけれども、亀川はそれを飛び越えようとしていた。ぼくがピアノを弾く弾かない、ピアノを楽しむ楽しまないというレイヤーは、亀川とは関係のないことだ。だが彼女はぼくを悪戯猫の首根っこをつかまえたみたいに、悪事を白状させようとしている。後ろ指をさされることなどひとつもしていないというのに、彼女はぼくを叱りつけようとしている。
なぜぼくがピアノに嬉々とするかだって?
どうして答えられないの?
そういえば、言われてみるまで考えたことなどなかった。亀川に問われながらぼくは亀川にとらわれていた。そしてぼくは彼女の問いに答えるだけの理由を自分の中に見つけだすことができなかった。亀川に指摘されるまで、ピアノを楽しんでいることさえ意識していなかった。川が下流に流れる自然の摂理と共に、ぼくのピアノ時間が向かうべきところに流れていたというだけのことだ。ピアノの設置場所には恣意的意識が働いたけれども、それは寝起きの仕掛けであって、ピアノを弾く理由ではない。楽しむための仕掛けでもない。
何を咎められているのかわからない猫は、これでも立場上、にゃあと誤魔化してしまうわけにはいかないので、思案する。
「そろそろ閉店のお時間です」
ぼくの逡巡を遮るように、店員が伝票をテーブルに置いて去っていった。あと5分で10時になるところだった。ぼくは喫茶店のタイムリミットに救われたのかもしれない。代わりに、意に添えるかどうかは知らないが、亀川は理解の瞬間を、僕から聞く答えの楽しみを、あとにとっておくことになった。つまり、「今度ね、多々倉さん」、次がある。
駅に向かいがてら「もてたのかと思ったよ」と照れを押しておどけてみせた。待ち伏せされたとすれば期待もあるという思いが掠めた気の迷いが、うっかり本音の背中を押した。
「まさかあ、多々倉さんとは」と亀川に渋い顔をされた。
冗談のつもりで言ったはずなのに、亀川の冷酷な返答に胸がずきんと痛んだ。冗談だったんだよ、そう自分に言い訳をする。あれは、心にできた逢魔が時の幻影。
しばらくは誰ともつきあうつもりはなかった。誰かと交われば閉じかけた傷がぱっくりと口を開きそうだった。ひとつ笑えば、笑った分だけ傷口がみりみりと裂けるような気がした。新しい傷は、きっと過去を意地汚くほじくり返してくるに決まっている。
深く考えることもよした。深く考えれば〝たられば〟に囚われ、できなかったこと、しなかったこと、足りなかったものが無尽蔵に吹き出し矢のように降り注ぎ、ぼくの全身と全霊を切り刻んでいく。
「でも、好き」
温度を削ぎ落とした冷たい言い方だった。背筋を冷たくしたのは、装飾を排し核心を突く鋭さにやられたせいだった。だがそれは、彼女がぼくに向けた愛からではなく、ピアノを好きでいるぼくに好奇の目を向けているからだ。
気持ちが揺れたことは認めよう。だが本心ではこれ以上、傷を広げたくはない。
亀川に対して、これまでの思い描いていた亀川像を改めざるを得ないと思った。彼女の内側には、それを支える骨太のバックボーンがある。ただの世間知らずではなかったのだ。
名曲堂楽器店で亀川は輝いていた。表舞台に立つ道は選ばなかったけれど、彼女を照らすスポットライトが消えたわけではない、そんな気がした。
頭上から降り注ぐ月光が音色を変え、耳にさらさらという音が届く。場所が変われば月の音が変わる。あるいは共にいる人が音の質を変えるのか。亀川と受ける光の指は鍵盤を追い、奏でられた音が光に化身して宙に舞い、降り注いでくるようだった。『ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調作品27-2【幻想曲風ソナタ】』。月の光は『月光』の音階そのものだった。
月明かりに耳を傾けていたふたりが駅に着く。改札口で亀川が、じゃあ私はここで、と口を開いて手を振った。彼女の家は駅から歩いて5分ほどだと言う。送るよと言うと、それにはおよびません、私が多々倉さんを駅まで送ったんだからと制されてしまう。
月の光だけが誰にも制されることなく地上に降り注いでいた。
「じゃあ。明日も頼むよ」と手を振った。
改札に向かい歩きはじめると、「今度」と亀川に呼び止められた。「会社、早く終わった日に王子に行きません?」と振り返ったぼくに言う。
「王子? なんでまた」
「ゲストハウスができたんです。ラブホテルだったところ。そこにアップライトピアノが置いてあって、自由に弾けるんです」
電子ではなくアコースティックピアノ、知らぬ者同士がことばを交わすゲストハウス、そして元ラブホテル。最後の一語が意味深で、不埒がひときわ波を高くしてから引いていった。
電車に乗った。揺られていると田舎町のローカル線と音が違うことに初めて気づく。ピアノが鍛えた聴覚がそのように小さな差異を聞き取ったのだろうか。
旅先の列車はレールの継ぎ目にフェルマータがかかる。なのに都会の電車はひっきりなしで忙しい。スタッカートでリズムを刻む。都会の電車は新世界にも停まらないし、鳥捕りに出会うこともない。カムパネルラも現れないし、さよならを告げられることもない。
さようなら。
妻が選んだ最後のことばは「さようなら」ではなかった。「別れてください」だった。
さようならには思慕があり未来の邂逅に一条の光がさしている。だけど「別れてください」は一方的で冷酷で決定的なうえに次がない。断ち切られる思慕。行き場を失くした感情が首を失くした蛇のように未来永劫、地面をのたうちまわるだけだ。
耳が、遠くの鐘をとらえた。鐘は忙しく響き渡っている。音は車窓を通して聴こえてくるのか、頭の内部で鳴らされているのか、妻とのことで思考がかき乱されたせいでよくわからなくなっていた。あるヴィジュアルが浮かんで消えた。わずかに見えた映像から、鐘は指で奏でられていたことがわかった。
『カンパネッラ』
思い出したようにgnomeに気が向かうことがある。才能を守る小人は、果たしてぼくの才能を解放してくれるのか。それとも、そもそも才能には実るべきものなどなく、実のところ見切りをつけられようとしているのか。それも、同じスペルのGNOMEでグノームと表現するゼミでの研究課題と、透かし絵同士を合わせたみたいに重なるせいだ。
グノームは2010年過ぎからフォークにより、デスクトップ環境を他の技術に受け渡しつつある。もともとGNOMEのソースコードから枝分かれしたわけだから基本には消えてはいないのだが、主流の座は潮流の最先端に引き渡してしまった。
今ではCinnamonやMATEのほうが通りがよく、GNOMEは血肉の一部と化して表舞台から姿を消した。今から振り返れば10年以上前のことだ。周到な根回しを要するM&A部門の松田に言わせればたかが10年と笑い飛ばされてしまう年月だが、デジタル世界の10年は人類が歩んできた100年に匹敵する。いや、現実にはそれ以上だろう。
かつてグノームがその価値を未来へつなげるだろうと期待されていたとき、心血を注ぎながらもいつどこで他者者に取って代わられるかわからない不安に怯え、払拭しきれずにいた技術者たちの猜疑心。ノウムもまた、ぼくの才能を疑心暗鬼で探っているきっと。
これから先、いつまで? 100年という年月が、今のぼくに執拗にまとわりついてくる。
妻の手を取った影の男が月光に照らされ、白日の元ならぬ白月のもとにさらされた。スーツ姿で髪は短くビジネス・シューズの靴底を、できる男ふうに響かせてはいたけれども、丸く小さな顔、細いウエスト、なだらかな曲線を奏でる脚線、そこから踏み出される脚のすっと伸びるシルエット。決定打が端正な男装化粧、胸のふくらみ。僕から妻を奪ったパートナーは男ではなかったのか!?
またしても嫌な夢だった。
8月中旬。
上弦が欠けはじめ半月が過ぎたころ、名曲堂楽器近くで会社帰りに亀川とベトナム料理を食べた。初めて休日を一緒に過ごした週末。仕事の話はいっさいしなかった。
亀川はハノイの交通事情と東京のベトナム料理店事情にやけに詳しかった。ベトナムに行ったことがあるのか? 尋ねると、これから多々倉さんと一緒に、とお約束の答えが返ってきた。人の話をはぐらかす才能は相変わらず一級品だ。
直後に「ダン・タイソンって聞いたことありますか?」と訊かれたが、ぼくにはそれが人名なのか地名なのかあるいはそれ以外の名称なのかさえ区別ができなかった。
食後に王子のゲストハウスに向かった。ピアノは中国語を話すグループの若い男に占領され、陶酔顔でクラシックが途切れない。人に聴かせるレベルの腕前で、モーツァルトかな、とこぼすと亀川が、当たり、と我が事のように喜ぶ。曲名を教えてくれたが通称じゃなかった。ピアノ・ソナタ第4番変ホなんとかという作品番号だ。資料の整理番号と同じようだが、資料と違って長ったらしく、風情や曲のイメージを廃した悠久の囚人番号のような名称では、いちど耳にしただけじゃ覚えきらない。
「ピアノ・ソナタ第4番変ホ長調 ケッヘル282」、亀川が見透かし、ぼくの脳みその皺に刻みつけるように口に含んでゆっくりと、たしかに曲名を繰り返した。言い終わるか終わらないうちに演奏曲が次に移っていった。
「なかなか弾けないね」、宿泊者ならずとも飲食ができるゲストハウス併設のカフェバーで、ぼくは珍しくコロナをラッパ飲みしながら、彼女はジンジャエールのストローを吸いながら、順番待ちをしている。
「何を弾いてくれるの?」、訊くと亀川、あからさまに驚愕で目を丸くし感嘆符を口から吐き出す。何を言ってるの、とその仰天した顔が語りかけてきた。
「多々倉さんが弾くのに決まってるじゃない」
「まさか」
苦笑いがこぼれる。このタイミングで、驚かすんじゃないよ。
「あんなに上手な人のあとに弾けるわけないじゃないか」、焦りが冷静さを欠いていたのだと思う。
「ふうん」、亀川、なにやら意味ありげである。「弾けることは認めるわけね」。
そうきたか。トラップだったわけね。亀川といると、調子を狂わされっぱなしだ。考えてみれば、うまい具合に張り詰めた空気を緩められているようにも思う。初めてそれを、悪くないなと思ってしまう自分がいる。
その日、結局は弾かずじまいで次回につなぐ約束をした。訊こうと思っていたダン・タイソンを訊きそびれてしまった。まあ、いい。自分で調べればすむことだ。
「ひとつ訊きたいんだけど」
8月下旬。
王子で会った翌週、大久保のまた違ったベトナム料理店でぼくは亀川に切り出した。
「なんですか、あらたまって」
「この前、人の名前だか名称だか、ドン・ジョンソンみたいなこと言ったよな」
亀川は投じられた石が湖上で波紋を広げるように、知識の探知機でぼくの問いかけの解答を探している。少女が困ったように唇を突き出した仕草で、答えをたどっている。それを無垢と受け取るかあざといと受け止めるか、亀川の解答次第だった。亀川は、ぼくを焦らしている。
「ああっ」、場に即した答えに辿り着いたのか、声をあげた亀川が、手のひらを打って合点したという顔をした。それから「近いけど違いましたあ」と言った。
想定外の答えだった。話をはぐらかされたと思った。いつもの躱し身の術。人生を舐めているのか、世俗にあくせくするせわしなさを達観からあしらっているのか、なんとも捉えどころのない雲のような身のこなし。
「ダン・タイソン」とたしなめるように言ってから「どちらもおじさまに変わりないけど。それにふたりとも素敵です。多々倉さんも!」
「いや、そうじゃなく」
訊きたかったのは、人命が合っているかどうかではなく、そのタイソンさんと亀川とのつながりだった。ただ知っている、という程度の仲ではないだろうという予感がしていた。ダン・タイソンがどのような人物なのかは、ネットで調べていた。アジア人で初めてショパン・コンクールで優勝したベトナム・ハノイ出身のピアニスト。
「彼のコンサートに行ったことがあるんです」
「それだけ?」
「それだけです」
「もしかした、ハノイで?」
「はい。母に連れていかれただけだから、自分で行ったわけではありません」
「そのときピアノを弾いたよね」、ぼくはカマをかけた。
亀川が口元を固く結び、うんざりした顔を横に向けた。ふれられたくない話題だったのだろうか?
彼女は横を向いたまま俯いて首を左右に振っただけで、答えは亀川の胸の内にしまわれてしまった。彼女には彼女の、人に話したくない事情がある。ぼくにだってあるのだ。
彼女の内情は知らない。だけど似たような感情が共鳴し合った、そんな気がした。
ぼくが何も聞くまいと決め口を噤むと、彼女は「私の恥ずかしくて悔しい思い出のひとつです」と、まるで覚悟を決めたように目を逸らしたまま教えてくれた。それから意を決し、ぼくの目を見すえる。瞳が朧月のように揺れていた。その瞳があまりにも艶麗で、ぼくはその中に吸い込まれてしまう。そういえば、かつて松田と深酒をした夜、あの日も月に惑わされたことを思いだした。
彼女の吐息がぼくの頬をかすめ、直後に亀川の唇から体温が伝わってきた。共鳴を共有してもいいじゃないか、そう思ったのはぼくだけではなかった。唇を合わせた。彼女の意思が唇を通して流れ込んできた。彼女の唇もまた、痛みで濡れたぼくの心みたいに潤んでいた。
躊躇いを繕いながら、彼女から身を躱すふりをして、唇をずらす。もしかしたらぼくは蓋をしてしまったはずの心の奥底で、彼女を求めていたのかもしれなかった。つかみどころのない不思議な娘に、呆れ顔を突きつけながら、本心では自分では太刀打ちできないポテンシャルを持ち合わせた彼女に畏敬し、暗渠に流れる本心が惹き寄せられていたのだ。
ふれた唇が離れていることを意識したとき、切なさがぼくを襲った。
その夜、亀川を「マドカ」と呼んだ。彼女の恥じらいを慈しみ、広がる吐息に溺れ、豊満な肉体にいきり勃ち、大胆不敵さに昂まり畏怖し心を捕われ、絞り取られるように射精した。ホテルの窓に月明かりがあたって部屋の中にひと筋の光を落としていた。月明かりは窓をすり抜けて円日の肩から胸を照らしている。ぼくの下で円日が息を整えようと呼吸を早くしている。
唇を離したときのように吸いつきあった体を離すと、円日の影になっていた体を月明かりが照らし出した。光は波打ち、彼女の肌を縦横に泳いでいく。円日の肌に這う月光はその後彼女の肌から内部に染み入っていく。次第に光り出した肉体が眩しくて目が眩む。と同時に愛おしさと切なさが込み上げてきて、ぼくは彼女を抱きしめたい衝動に駆られ、背中に腕をもぐりこませた。
ぼくは円日を包み、光に溶けた円日に包まれている。彼女は紛れもなくぼくを捉え、微笑み、含もうとした。甘く居心地のいい瞬間。それは繭を連想させ、挿入に掻き立て、ふれるかふれぬかの間際で焦らされ、握られ、離され、疼きが思考を飛び越えて。そしてもうひとつのぼくがもっと強く立ち上がり、求め求められ、狂い、それから一気に昇りつめると頂点を境に無音無色の世界に突入した。
ぼくは、やっと果てることができたと思った。安堵に包まれた先にあるそれは、失って以来、ずっとぼくが求めていたものだった。
こんなに近くにいたのに、気づかなかった。ごめんと口に出すと、とろけ、しなだれ、彼女の乳房に伏せた顔から落ちた涙が彼女の白い肌に広がっていった。
泣いているの?
泣いてなんかいるもんか。
そうね。田所さんは泣かない。泣いても泣いたとは言わない。弾けるのに弾けないという人だもの。
ばかなことを言うもんじゃない、言ったぼくは彼女を強く抱きしめていた。
11月下旬
夏が終わり、秋も暮れに向かって急ぎ足になっていた。
年の瀬を迎える間際、公私ともにクソ忙しいのに松田は挙式を終えた足でハネムーンに旅立っていった。その松田が、頻繁にFacebook に写真とコメントを海外からアップしている。動画もあって、そのひとつを再生してみた。
松田が亜希子の後姿を追いかけている。コメントが喘ぎ気味なのは、急ぎ足の彼女に追いかけながらも追いつかないからだろう。
待てってば、アキコ。
ん? それって尻に敷かれているみたいでちと情けなくないか、松田。
プラハ・マサリク駅。日本ではまげを結った武士が闊歩していた江戸時代の1845年開業と解説が入る。くすんだ黄色の石造りの建造物はこぢんまりしており、通路も低く狭いが、風情があって現代的なプラハ本駅と対をなす、とつづくコメント。
「アキコー、どこに行っちゃったんだ?」
あ、その間抜け面、成田離婚を引き起こす原因ナンバー1の失態そのものじゃないか。
とそのとき『エナジー・フロー』が遠くから流れてきた。その演奏は、長年鍛えあげてきた腕のたまもので、流麗で繊細である。すると松田「あ、いましたねえ」とにやり。その意図的な笑み。もしかして演出だったか。
プラハ本駅からレイルジェットでウィーンに発つまでの束の間を利用して、アキコが絶対に寄りたいと言い張った駅。コメントは、日本のテレビ番組で観て、中欧に行くなら立ち寄ろうとふたりで決めていた場所だと目を潤ませている。
こんちくしょう、のろけやがって。
映像はホームからパンニングして黒のアップライトピアノで止まり、そこからゆっくりとズーミングしていく。弾いているのはたしかに亜希子だった。何度も一緒にメシを食い、飲み、旅行をも共にした仲なのに、そういえば亜希子がピアノを弾く姿を見たのはこれが初めてだった。
ぼくの知る彼女はぼくの前でピアノを演奏したことはないけれど、彼女が弾いていたピアノが今、ぼくのところにやってきた。ぼくの部屋に、ぼくの知らない亜希子の一部が居座っているような気がした。それは、亜希子にとって捨てなければならない記憶であったろうか。手に入った次のもののために押し出された過去の記憶。ぼくの部屋のピアノは押し出された遺物であり、引き受けたぼくもまた〝生き場〟からはじかれた遺物であることと結びつく。
亜希子は捨てることで幸せをつかんだ。ピアノは幸せの犠牲だったのだろうか。
人は、手放して、手に入れていく。それは、自粛後の人たちが何かを変えて時代を前に進めているのと似ていた。
幸せとは何?
妻はぼくといて幸せではなかったのか。妻は新しい男と、あるいは女かもしれないけれども、今現在幸せでいるのだろうか。歳を追うごとに純度が下がり混沌が制御をかけてくる感情に、手放しで「幸せ」とはなにかを純粋にとらえにくくなっていることはわかる。それでも彼女の幸せが不幸を上まっていることをぼくは祈る。今なら、そう言える。
目の前で幸せを炸裂させた円日と結びついたことで、心根からそれをことばにすることができる。ぼくもまた、妻がいなくなったことで手に入れたものがある。確実に手に入れておくために、押し出してしまわなければならないものがある。そうさせるものをぼくは今、手にしている。
円日の幸せを今いちど考えてみた。満面の笑顔と心の底に抱えた複雑な思い。ぼくは彼女に幸せを感じさせることはできるのだろうか?
彼女の本心を探る作業は月の裏側を覗くのと似ている、とふと思う。月探索機が映像を地球に送ってくるまで、想像しかできなかった向こう側の世界、それは誰かが秘密の扉をこじ開けるまで、決して真実がさらされない世界。そして人のもつ宇宙は、どこかに必ず知られたくない裏側がある。
スマホの画面は演奏を流しつづけていた。亜希子の右手が高音に向かって流れるようにステップを踏んでいく。曲も終わりに近い。そして最後の単音で指を止め韻を引く。音が駅のドームの隅々に染み入っていく。
ほどなく余韻を断ち切る拍手で駅が埋まった。
「では、これからウィーンに行ってきます。またお会いしましょう」
厚みを増した拍手を祝福にすり替えた締めのコメント。ふざけるな! ぼくは、仕事場でプログラムのチェック中だってことをすっかり忘れて、スマホに怒鳴りつけていた。
円日はいちどもピアノを披露してくれたことがない。少なくともぼくの前では。
「ピアノはまだとってあるのか?」と訊いたことがある。
「処分してしまったわ。きっと今ごろ、中国か中東の中産階級の人の手に渡っているんだわ」と円日は素っ気ない。言い方は「せいせいしたわ」だったが顔に曇りが混ざっていた。気持ちをざらつかせたのは諦観からか寂しさからか。円日の裏側もまた、覗きこむことができないでいる。
毎日が、いつもと同じように過ぎていく。仕様書に従ってスタッフがプログラムを積み上げていく。エアコンの温風にパソコンが放つ熱気が絡んでいくのがわかる。意志で結束するぼくたちは、ときに仲間の作業を手伝いながら、自分の時間に戻っていく。つきあい残業はしない。チームでこなすべき仕事に歪が出たら、我が事として手を差し伸べ整合性をとり合いながら、区切りをつけて自分の時間に戻っていく。
自分の時間に、円日と過ごす時間が増えた。ぼくの家のシングルベッドで一緒に眠ることもある。そんな日には「弾いてみせて」と円日が駄々をこねる。たいがいが、遅いからと近所を気遣うぼくが断る。
「マドカにこそ弾いてほしい」とぼくがお願いする。
「遅いからだめって言ったばかりじゃない」
円日にたしなめられる。
「ぼくはヘッドフォンで聴くから」
そう言うと「ずるい」とふくれて、可愛い女を演出してみせる。
なんとか音を追える程度の『イマジン』を披露した。ぼくが弾いて円日がレコーディングをたしかめるようにヘッドフォンに神経を集めた。弾き終わると決まって円日は「素敵」で締めくくる。
「弾いてみてよ」
お願いしても頑なに円日は弾かない。鍵盤にふれようともしない。円日の決意は月の石ほど固い。この話題になると判で押したように浮かべる苦渋の表情を隠そうともしない。しかたなくぼくがつづけて弾く。『人生のメリーゴーランド』を、『ピアノマン』を。もてる(本当に限定された)レパートリーのすべてを。
弾く鍵盤を記憶から呼び戻す速度が指の動きについていかなくなると演奏が止まり、思い出してつづきを弾こうとすると曲を見失い最初から、そんなこと、しょっちゅうだ。
そして、初めて楽譜で追った『月光』を弾く。YouTubeでプロの演奏を手本に、演奏に磨きをかけつつある途上の入り口にさしかかったばかりの『月光』をたどたどしく奏でる。音を切るところではダンパーを離し、強弱のつけかたも自分なりに調整できつつある。
誰に聴いてほしいとも思ったことがないピアノ。聴衆がひとりでもいると緊張が邪魔をしてつかえてピアノがますます弾けなくなっていく。
ぼくは聴いてもらうためのピアノを弾いていたわけではないことに、気づく。弾いている自分を意識すること、自分の時間の中にピアノ演奏が組み込まれていることにこそ満足があった。聴衆が円日ひとりでも、聴かれると演奏に集まっていた神経が乱れることがなによりの証だった。
つかえながらでも弾いているさいちゅうに、「令月って、万葉集にあるのよ」と円日が口をはさんだことがある。『月光』を演奏しているときだった。珍しいことだ。いつもなら、ぼくが鍵盤から指を離すまで話しかけてこないのに。
「なにそれ?」とぼくが止まっていた指を鍵盤から離し、訊く。
「時代が変わって、しなければならないことに意味がついてくることがある」と彼女はつづけた。
「どういうこと?」
そういえば、ぼくは彼女に何度となく、彼女が放つことばの意味を尋ねてきた。だけど、彼女はほとんど正面から答えてくれない。ぼくが気づくまで待っているわ、と暗示しているみたいにその都度思う。
気づかないぼくが鈍いのか?
「ごめんなさい、邪魔しちゃって。つづけて」
円日はぼくの演奏を中断したのではなかった。音階が一段上がるエンディング間近でぼくは追うべき鍵盤を見失い、鍵盤上で指が迷っていたのだった。
ふたりでいるのに、円日の存在を忘れて自分の世界に入りこんでいた。聴かれることにはかき乱されるのに、弾いて浸り切れば没頭できる。没頭の中で迷ったぼくに円日が手を差しのべ現実に引き戻してくれた。
元妻はぼくたちの関係を祝福してくれるだろうか。円日は元妻と夜を過ごしたぼくの部屋で、心を平穏に保つことはできているのだろうか。ぼくはこのまま『月光』を弾きつづけていいのだろうか。いろいろな思いがあぶくのように湧いては消え、演奏が終わると思い浮かんだ描画のすべてがいっせいになりをひそめた。
静寂だけが残されていた。ぼくは沈んでしまった無音の中で弾いたばかりの鍵盤をイメージの中でなぞり直していた。
どんなに指を動かしても、ぼくに音は届かない。聴こえているのはヘッドフォンを耳にかけ、目を閉じて曲に揺れてる円日にだけ。おぼつかない指先でやっと楽譜を追いかけられるようになった腕前に、なぜそこまで陶酔した顔をしてくれるのか、ぼくには不思議でならなかった。
「素敵」
それでも円日は1曲弾き終えるごとに笑みを炸裂させてぼくの腕にしがみつく。
翌2月上旬。
こんなところにも駅ピアノがある!
札幌雪祭りへの旅道中、新幹線からの乗り換えで新函館北斗駅で降りたった際、構内のグランドピアノが目に止まった。
「弾いたことある?」と円日が訊いてくる。彼女はグランドピアノのことをを言っている。
「ないよ」、アップライトにさえふれたことはないのに、グランドピアノなんて恐れ多くて、そんな異次元には踏み入れない。
「弾いた弦が、子宮の奥に響いてくるのよ」
「子宮の奥? ぼくにはないからわからない」、松田を経由して亜希子も同じことを言っていた。
「私があなたを受け入れるように、あなたの中に私を受け入れる空間があるのよ。わたしがおさまっていないと心もとなくなるところ。そこに響かないかしら」
奥さんがいてもかわないと思っていたのよ、ベッドでこぼした円日が最近大胆になった。そそるのもうまいし、つい乗せられそうになって、結局は乗ってしまう。
「言っていることがわからない」とぼくは惚けてみせる。
「弾けばわかるはずよ」と、理解の領域を知らないぼくの手を取った。
「あなたが怖じ気づいているなら、わたし、弾いてみようかしら」と円日が突然、冗談っぽく口にした。目を輝かせ、ぼくを挑発していることがわかる。
「じゃあ。怖じ気づいているから、弾かない」と、弾く気もないのに意地悪を口にする。それに円日は弾くことはない。これまであれだけ頑なだったのだから。絶対に。
「じゃあ? じゃあってなあに? そのつもりなら、わたしも。じゃあ、わたし、ほんとに弾く」
珍しく円日が意地になった。だけど腹に力をこめた声が震えていた。本当は弾きたくないのだ。なら弾かなくたってかまわない。
だが真顔に変わった円日は、口にしたことを翻そうとはしなかった。その迫力に気おされた。これにはぼくも仰天させたれた。あれほど演奏を拒んでいた円日がなぜ?
理解を演算しようとしたけれど、可能性はひとつも見当たらない。
「本気?」、真剣に訊いてみた。
「4年ぶりだけど、今なら弾けそうな気がする」と彼女は本気を認めた。
ピアノを前にし、椅子に腰を落として高さをたしかめる。気持ちははやるのに体が一瞬拒絶したのがわかった。嫌なら弾くことはない、ぼくが繰り返し念じると、意を決した円日が鋭い眼光でぼくの思いをはね返した。
緊張が空気の比重を重くし、厳寒の冬、駅構内とはいえその寒さはヒーターの発する熱をおさえこんでいるのに、高まる緊張が汗を誘い、円日の額を伝っていく。行く手を阻む泥水をかき分けるように、手探りで昔の勘を取り戻そうとしているのがわかる。至難を極める作業をしているというのに、それでいて福音の喜びが円日の口元から漏れた。円日は、純度を欠き混沌が制御をかけてくる感情にこびりついた錆を落とそうとしている。
笑みは勝算を見込んでのことか。それとも自暴自棄からくる諦めからか。
円日が鍵盤に指を降ろした。最初の和音がダンパーで尾を引きはじめる。スローに流れはじめた和音はわずか数歩で立ち止まった。
無理か?
だけど円日は首を左右に振って迷いを断ち切り、いちど終わってしまうかのように思われた曲をつなぎはじめた。
スプリンターの実力はいやというほど伝わってくるのに怪我から復帰したばかりで実力の半分も出せない、そんな陸上選手を思い起こさせる空気が流れた。
音は、まだつながっていない。
こんなんじゃない、こんなはずじゃない。円日の悔しくて辛くてうまくいかないことへの苛立ちと焦りがぼくに伝わってきた。技術的にすごいことは音の出し方で理解できるけれども、千鳥足の演奏では中途半端感から抜け出せない。
悔しい、悔しくて情けなくて苦しくて、できないって叫んでしまいたい、逃げ出してしまいたい、あのとき逃げ出したように、円日がそう叫んでいる、硬く結んだ唇が、言いたいことを伝えてくる。
音は、よろめきながらも歩みを止めなかった。歩みは次第につながるようになり、散らばっていた音符が近づいては離れ、円日との距離を縮めていく。ばらばらだった音がつながっていく。指で弾かれて初めて音になっていた曲が、やがては場に出現してくるみたいに演奏者と一体になっていく。音が渦を巻き流れが地球をめぐり、世界各国に向かっていった。音はどこまで届くだろう? 思いを馳せた刹那、音が曲を形成しはじめる。触手ははるか遠く、ドイツのケルンに届いた。指はキース・ジャレットか、オペラハウスで演奏された楽曲をたぐり寄せている。音は伸び、ふくらみ、厚みを持って絞られ、流れていく。
こんな広がりのある音を、どうやれば出せるんだ? 経歴の厚みが違うぼくが、敬意を払いながらも驚きに呑まれていく。
円日はかつて「たいがいの曲は、いちど聴けば再現できる」と言ったことがある。
「探り弾きなしで?」
「そう」
まさか、冗談、ぼくは言って笑った。それができたらすごいことだから。円日も、そりゃそうよねと言って笑った。だけど冗談は、できないと答えたほうにこそあった。
最近、ノウムのことを考えなくなった。それはこの日の伏線だったのかもしれない。才能があふれだしてしまったこの状態では、もはや出番はない。
彼は、地中深くの自分の棲家に、きっと引き上げていったに違いない。
でも。才能はぼくにではなく円日のほうにこそあった。
ザ・ケルン・コンサートの『PartⅠ 』はエンディングを迎えることなくボレノ・ジャズ・アレンジに風に移行していった。ヨーロピアン・ジャズ・トリオの1曲だ。それもまた終わることなく違う曲に出会い混ざり溶けていく。『エリーゼのために』のサビを弾いたかと思うと、今ではフランツ・リストの『ラ・カンパネッラ』になっている。ピアノの弦が鐘を鳴らす。強く弱く左右の腕が残像を残しながら交差し、鐘の音を出現させていく。行き交う旅行者が足を止め、聴衆となって音に呑まれ息を飲む。驚きが体に入り込み陶酔に変わっていくのがわかる。
誰、あのひと? 著名なピアニスト?
胸をときめかせた聴衆のひとりがつぶやいた。
円日の演奏はまだつづいているというのに、演奏後に彼女と交わすシーンが未来から蘇ってくる。楽曲は時を超え魅惑の引力で人を結ぶ。ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンやフランツ・リストが、キース・ジャレットが、その時代ごとに演奏した舞台の日が今日と時空を超えて結びついていく。円日の演奏と演奏後に交わしたことばとが絡みあってくる。
「あなたにスポットライトが当たっていたのが見えたわ」
「あれだけ演奏に集中していたのにぼくを見ていたっていうのかい?」
「見えていたんじゃない。見ていたのよ」
「まさか」
「本当よ」と信じないぼくにぷんと冗談ぽく怒って見せ、それから「たぶん見ていたんだと思うわ」と言って寂しい顔をした。
曲はもういちど『ラ・カンパネッラ』に戻ってきて円日は演奏を終えた。20分間ぶっつづけで演奏した。手の甲で額を拭うと、汗を含んだファンデーションが手の甲に移った。
はち切れんばかりの拍手、アンコールの声さえあがっている、それを円日が両手のひらをひらひらさせてなだめた。手馴れたものだった。円日は、親の期待値以上の実力を秘めた真正のピアニストなのではなかったか。
聴衆からの讃美を落ち着かせると、円日がこほんと可愛らしい咳をする。それから口だけを動かし、静まり返った会場に「ありがとう」と言ってみせた。間を置いて、聴衆の気持ちの揺れが鎮まるまで待っていることが伝わってくる。塊となった観衆を前にこうしたゆとりの呼吸を置けるのは天性の資質かもしれなかったが、場数の豊富さが働いていることも関係しているはずだった。
彼女の経歴はぼくに測り知ることはできない。そしてどれだけの賞賛を浴びてきたかも。彼女が自らの意志で話してくれるまでは。
「たくさんの拍手をいただけて、とっても幸せです。こんなに幸せって本当に久しぶりです」と言って深々と頭を下げた。それから「もう少しピアノをお借りしていいですか?」と尋ねている。いいも悪いも聴衆はそれを望んでいるのだ。そんな訊き方があるかと、頼もしさを含んだ呆れ顔を向けたのも束の間。「つづいてわたしのだあいすきな人が『月光』を演奏します」と聴衆に笑顔を投げた。
え。お、おい、ちょっと待てよ。それって、その大好きな人って、ぼく、かあ? 肝が氷点下まで下がり、冗談にしてはふざけすぎだと呆気を吹き飛ばして憤りが湧いてきた。
やめてくれ!
観衆の波が割れ、ぼくに花道ができる。円日に向けられた拍手に負けず劣らずの熱く厚い拍手がぼくを包み込む。
「ああ、あなたといるとピアノは楽しい。私、ずっと損をしてた。ピアノが嫌いだったことを言っているんじゃない。あなたと早く巡り会えなかったことが。あなたと会えて、嫌いだったピアノが嫌いじゃなくなったんだもの。わたしはあなたが弾くピアノが好き。嬉しそうに弾いて、つまずいては悔しい顔になって、じょうずに弾けたときに弾ける顔が無垢で素敵で。
初めはピアノのどこがそんなに楽しいのか、不思議でならなかった。でもね。プロになって聴かせるのを強いられると辛くなるけど、弾くのが楽しいピアノを聴くのって楽しいものなのよ。あなたに教えてもらったことよ。そうこうしているうちにもうひとつ気づいたことがあるの。ピアノを楽しんでいるあなたが、もうひとつ違った喜び方をすることがある。なんだかわかる?」
ぼくはわからないと答えた。
「わたしがあなたの演奏を聴いているとき、あなたはやさしくわたしを包み込んでくれていた。わたしを包んでくれるときも、あなたは楽しそうにしているの」
なぜこのタイミングでそんなことを言う?
「子宮に響く共鳴を感じてきて。みんなに聴かせるんじゃなくてよ。わたしだけに聴かせてほしいの。あなたの中のわたしの居場所、その子宮で感じてきてほしい。わたしはあなたに聴いてもらうことで楽しませてもらったわ。もう、最高なきぶん。だからあなたにもわかってほしいの。もっと共鳴するために」
グランドピアノだったからそう思えたのだろうか?
かもね。
時空の前後がでたらめにつながってぼくの頭の中で反響していた。
ぼくは聴衆の拍手を一身に浴びてピアノに向かい、椅子を引いて腰を降ろし、円日だけに意識を集めた。それから最初に鳴らすべき音をたしかめて指を静かに鍵盤に降ろした。
<完>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
