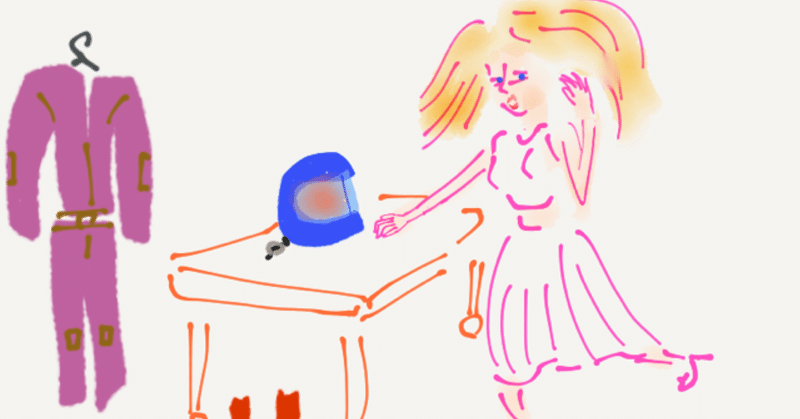
【二輪の景色-3】 CT110 男と女。
モノに魂が閉じこもっていることがある。髪の毛が伸びる類のホラー指向の話をしているのではない。生き別れた妹と分け合った河原の石ころの片割れだとか、優勝を逃し交換した泥の落ち切らないシャツだとかに。そうしたモノからは、たゆまぬンスタルジックのオーラが放たれ続ける。
思いを引き寄せる力は、恋のときめきに似ていなくもないが、熱しやすく冷めにくいものではないから、生息分布は恋とは別領域ととらえておいたほうがいい。それに、もし恋と混同したら、彼女が嫉妬してしまう。恋とノスタルジックは似て非なるもの、「キミを愛してる」の信憑性を損なわないためにも分けておくに限る。
数十年も前に作られたバイクが我が家にやってくる日のことを想う。オートバイの黎明期に荒れた野も山もものともしない強靭な躯体を与えられたそのバイクは、傲岸にして磊落なたくましさで自在に大地を駆けた。
今の世は近代化されたとはいえ、荒れ狂わんとする地に、水に、火に脅かされている。科学が見上げるベクトルは車をも空に羽ばたかせたが、確かに空に向かえばおおかたの災難は避けられるかもしれないが、万人は救世のノアの方舟に乗れない。多くは地に足をつけ、災難の数々と真っ向から四つに組み、対峙しなければならない。
そんな場面であの荒地をこなすバイクがあったなら。近い未来に現実のものとなるかもしれない災難に立ち向かえる事前の備えの被災を乗り越える杖としてーーそうした想いがあのバイクに期待を込めた。
期待が膨らみ、崇め奉った。それは未来に救いの手を差し伸べる救世主。魂が宿ったのはその時だった。
手元に置いておきたくなった。彼女はそれをただの物欲だと揶揄したけれども、そうじゃない。そいつは僕たちを、僕たちの愛を救ってくれるのだ。
しかもだよ。そいつは実らぬ恋と違って、チャンスがあれば、限られた金にものを言わせて(言わせるだけの金額で折り合えば)手に入れられる。
そんな古いバイクが今の時代の荒波を乗り超えられるのかと問われれば、口ごもらずをえない。古い水夫でなければ古い船は動かせないだろうと指摘されれば、それが真実なのかもしれないと虚勢がしぼむ。でももしそれらの助言を真にうけ、好機を逃してしまったら、古いバイクは博物館の金庫にしまわれ、未来永劫この世界に出て来られなくなってしまう。
新しいバイク乗りなら大人しく新しいバイクに乗っていなさいと人はいなす。だけど、長いものには巻かれない。同調圧力にいいようにしてやられているままじゃ、碌なことにはなっていなかったからね。
だからこう言ってやる。「そうですか。余計なお世話をありがとう」
やってみるまでわからないじゃないか。なのに人は自分限定の経験をさも最大公約数的最善策で、役に立つこと請け合いと平気で嘘をつく。いちど宿った魂の炎は、ちょっとやそっとじゃ揺るがない。「つべこべ言わずに引っ込んでいろい」と言ってやる。
それから数日が経ち、ついに。
「早く走りに行こうよ」と彼女が突如せっついた。まだ、エンジンをかけるところまでいっていないんだ、と僕が返す。「つまんないの」と彼女が口を尖らせた。
「整備し終えたら私にちょうだい」と彼女が仁王のように立ち、鼻息荒く迫ってきた。「可愛いバイクだから、私のほうが似合うって」としつこい。免許も持っていないくせに何を血迷ってる、口には出さないが、本音が疳の虫を刺激する。でもきっと彼女、僕を困らせたいだけなんだ。そう思った矢先、彼女が教習手帳をひけらかした。「へへ、どうだ、小型二輪、教習中なのさ。このバイク、私にも乗れるんだから。だから、くれ」。やばい。彼女、本気らしい。「ちょうだい💕」猫撫で声で甘えてきた。しかもひたと細身の身を寄せて、それでも出るべきところは出過ぎるくらいに膨らんだその身をくっつけ、人差し指で僕の胸元なでにかかった。お色気作戦で、一気に攻め落とすつもりなのか? だが、ここで相手の術にハマっては男が廃る。据え膳食わぬ以上の恥なんざかきたくないから、渾身の力をふり絞り、伝家の宝刀を振り下ろす。だぁめ。
それでも執拗な攻撃は止まない。
「だったら、動くようになったら、後ろに乗せて」と彼女が言う。「ぎゅっとしがみついてあげるから。ボヨヨン付き」と彼女がおどける。ボヨヨン? 妄想が妄想に波状の刺激を与えて、ボヨヨンがこだまする。うっかり鼻の下を伸ばしてしまった僕は、咄嗟に吹き出そうとする鼻血を止めにかかった。
理性で弾き返せても、本能はまだ彼女の色香の術の中。そんな僕を尻目に「私は荷物じゃないわ」とリアのキャリアを撫でながら彼女が言いだした。なるほど。確かにキャリアに座れば、なんだかお届け物みたい。でも、シングルシートのままじゃ2人乗りは難しいけど、リアキャリアにタンデム用のシートを装備すればいいいだけのこと。
とはいえ2人乗り仕様にするべきかどうか、僕は迷った。こんな小さなバイクに2人で乗っても、馬力的に遠乗りはきつい。それに2人乗ってしまうと、荷物を積む場所がなくなってしまう。必然的に遠くには行けない。お泊まりは難しい、悩ましい。
ああだこうだ考えている僕が煮え切らないように見えたのだろう。痺れを切らしたように彼女が「しょうがないわねえ」と切り出した。
なに、それ? しょうがないって、どういうこと? 僕には彼女が何を言わんとしているのか、皆目見当がつかなかった。
戸惑う僕を前に彼女、今度は「じゃあ、出来上がったら一緒に走ろう」と言う。決定打をものにした打者のように、なんだか勝ち誇っているように見える。
「どういうこと?」、事情を飲み込めない僕がもう一度彼女に尋ねた。
すると彼女「私、CT125を買っちゃったから」と。
ということは、つまり、最新のハンターカブを買っちゃったってこと? 免許を取得する前に?
事情を順序よく整理して初めて僕は彼女の仕掛けたとんでもない悪戯に驚愕した。
ええーっ。
およそ半世紀前に前9万8000円で販売された初代CT。排気量は110ccであった。CT110と呼ばれ、発売当時、そいつはまだハンターカブとは呼ばれていない。兄弟車の排気量的弟分に与えられた「ハンター」の冠は、時の流れがCTという型番とハンターという愛称の間に引かれていた境界線を消し去り、いつのころからか「ハンターカブ」と言われるようになった。
そのCT110が最新の技術を纏って現代に甦った。セルボタンで始動もできるCT125。新型には最初からハンターカブという名称が正式に与えられた。
彼女は110ccの旧型と125ccの新型の新旧2台で走るのだと主張する。当然、新型は買った彼女が操縦することになる。バイクは、乗って慣れて、少しずつ小さな痛い目に遭いながら牛歩の如く進化して、畳の目を数えるほどに緩くゆっくり腕を上げていけばいい。
経験を積んで運転技術を磨いてほしいという気持ちはある。だけど、乗ると危ないのも確かだ。だから、免許を取ろうとも、バイクを購入しようとも、眺めて磨くにとどめてほしいという気持ちもある。心境は、使い込んで使い物にならなくなったスプロケットのように複雑だった。
「わかった」と僕は流血をとどめた鼻から荒い鼻息を噴射させ、腹を決めた。
できるだけ安全なルートを選び、小さな体験を少しずつ積んでいってもらおうか。腕が上がるまで、僕が君を守る。ボヨヨンの夢は消えたけど、いつかどこかでいい思いは巡ってくる。
「ところで」と僕は言う。「CT125が来て僕のCT110と一緒にツーリングに行ったなら、たまに車両を取り替えっこして走ろうよ」
すると彼女、ひとしきり考えてから「やだ」、楔を打つみたいにきっぱり断ってきた。「貸して傷つけられでもしたら悲しいから」
おい、それはこっちのセリフだろう。
郷愁の風は、置いていかれた者へ同情を寄せるみたいにして、いつでも突然に吹き寄せる。突如、降って湧いたようにできたふたりの隔たりは、もしかしたら近い未来の暗示なのか?
まさか。
僕らの関係をノスタルジックにさせないために、ツーリングでいいカッコをし続けるために、守るのがいつでも僕の役目であるために、CT110、ちゃんと整備をしておこう。

「私の小型二輪免許取得のほうが先かもね」
「え、教習所に通っていたの?」】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
