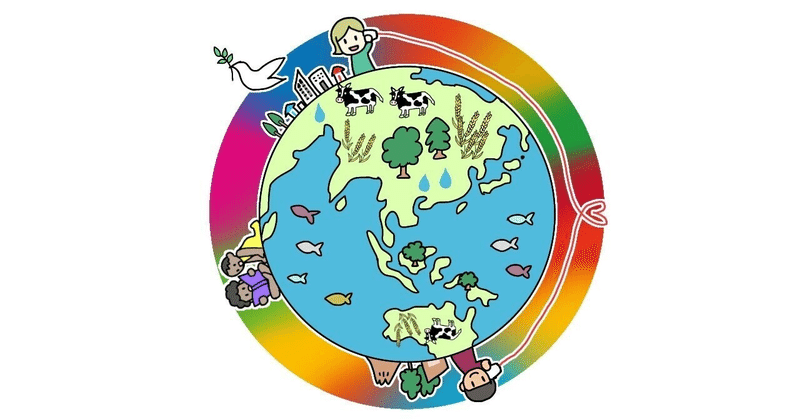
noteを通して環境や国際関係について考えを深め合える場を作りたい
1.noteを用いてしたい事 → 双方向的な意見の交流
私は国際関係や環境問題について多くの人と考えを深めたいと考えています。なぜならそれらには答えがないと考えているからです。
学ぶ環境や関わる人によって人は考えを形成されていきますが、そのために考え方が人によって異なるのでしょう。
それは、例えば国家の在り方として何千年も前から戦争があり、模索されてきたはずなのに首長国や共和国などさまざまなものが存在していることからも言えるでしょう。
そのような人間の性質から、たくさんの背景を持つ様々な人(専門家の方々、全く別の学者さん、主婦の皆様やサラリーマン、学生の方々などなど)と意見を交流していきたいと考えています。
その意見交流の対象を国際関係についてや環境問題などにしていこうと考えています。
2.と、ここでひとまず著者について → どんな人間の意見なのか
環境や国際関係とは真逆の分野を学ぶ大学生
「環境問題や国際関係について考えを深めていきたい!」と前置きをしておきながら、実は全く違う分野を学んでいる大学2年生なんです。😆
その分野は…
スポーツ政策学なんです!
まぁ、無関係かといえばそうでもないのですが、上記を専攻する大学生ではないんですね。(笑)
都心にキャンパスを構える某体育大学で日々勉学とスポーツに励んでおります!
専門のスポーツは → バレーボール!
専門は上記のように、バレーボールを行ってきました。ですが、幼少期からたくさんのスポーツに取り組んできています。
物心ついた頃の3歳から12歳まで空手をしてきて、
その間に9歳から11歳までは水泳(競泳)。
そして11歳からバレーボールを専門に今まで取り組んできました!
今はご縁がありまして、学連として大学バレーの推進をさせていただいてます。
転向のきっかけは、単純に自分の限界を感じたから…
と、まぁスポーツについてはそんなところです!
プレイヤーを辞めて…
ずっとバレーボールのことばかり考えた中高生時代だっただけに、プレイヤーを辞めると、脳みそにスペースができた気分で(笑)
そんな時に “あの東京オリンピック“ が開催を迎えようとしていたのです!
ここである種の自身の転換点があったのかな、と感じています。
大学柄、オリンピックにボランティアとして携わらせていただく機会がありました。
田舎で育った自分には想像もし得ないほどの外国の選手達を目の前にすることと…
そこで感じたことは、世界って未知の塊なんだなってことでした。うまく言葉にできませんが、ある種の劣等感のような、はたまたある種の希望のような。
新しい挑戦の時のワクワクとドキドキと、もっと早く知っておきたかったという残念さと。
その後もパラリンピックまでボランティアをさせていただくことができ、そこで「スポーツを通じて世界を繋げたい」という感情に駆られました。
それは、自分自身がボランティアで感じた(上記で述べた)ものを整理した末に繋がった答えだったといえます。そしてすぐに目標となり、国際スポーツ団体や中央競技団体などに就職したいというものに繋がったのです。
新たな夢「国家公務員」
国際スポーツ団体や中央競技団体といった目標は、別の夢へと変化していきました。
それが、「文部科学省」「外務省」です。
動機についてはまたの機会として、簡潔に。
・全ての子どもがたくさんの世界を知って羽ばたいて欲しい
しかし、調べてみると…
一次試験が全科目範囲から出る学力試験 + 専門科目(国際政治や法律など)
ましてや論述試験まで。
面食らった。今までバレーボールしか脳みそになく勉強もしたことがなかった自分自身。(高校はスポーツ科で偏差値40、私の最高偏差値は42)
最高で大好きな友人たち、そして…
そういえば!寮(某県人会)の友人に相談してみよう!と相談することに。
その友人の通う大学は “University of Tokyo” こと東京大学✨
私 :「(過去問を見せて)ここ受けようと思うんやけど、勉強教えて欲しい!」
友人:「んー、とりあえず1週間で48時間勉強してみて。できたら教えれる範囲では協力するよ!」
私 :「(48÷7は…約7時間!?そんなことある!?どんな鬼やねん!)
とりあえず明日から頑張ってみるかと一人決意を固めた水曜日の夜…
その翌日から、空きコマや休み時間、移動時間も駆使。(土日に貯金じゃー、と10時間頑張ってみたりして…)
迎えた1週間後の水曜日。
なんと1週間の総学習時間52時間!
友人:「いやー本当にやれると思わんかったわ。」
こんなことを言いながらもスポーツマンスピリットを理解しすぎだよ、と。(笑)
勉強を始めたことで変化が!
スパルタな友人のおかげで1日勉強するのすら苦でもなくなった頃、日常生活で変化が起こり出しました…。
それは、寮の友人たちの会話が理解できるようになったのです!(笑)
(この寮、アホなほど学力が高く、東大、早慶、最低でもMARCHと異常な場所なんです!会話が意味わからないくらい質の高いこと。)(→ある種の異国)
と、まぁ以上が私自身についてのこと、そして勉強との無縁生活から勉強を始めるに至った経緯です。
3.なぜ “環境問題“ や “国際関係“ を勉強するに至ったのか。
大学でのメジャーはスポーツ政策
上記でも述べたように、大学ではスポーツ政策学を専攻しています。
国際関係論や環境問題との共通点といえば、
「より良い環境や社会のために」「問題点(改善点も然り)を見つけ」「より最善なアプローチを考察していく」
といったことになるのではないでしょうか。
正直いうと、全く違う学問に感じます…。
だがしかーし!いろんな学問を学ぶ(専門領域ではなく、あくまで一般常識程度に)ことで、問題の捉え方が増えていくことに気が付いちゃったんです。
なぜ国際関係なのか
国際問題を学び始めるきっかけは単純に、「国際関係論が入省試験で出るから」。
国際関係論を学び始めると、「リアリズムがどうだ、リベラリズムがどうだ、トゥキディデスの罠がどうだ」…。
あぁぁぁぁぁぁ、わからん!知らん!
冷戦とか聞いたことあるけど知らんし、ウェストファリア体制については聞いたことすらない!
ここでまたも友人の登場✨(本当に出会に感謝すぎます)
「まずは世界史を学んでみたら?」
そうか、世界史で全て網羅されてるんだ。
すると、こういった国家体制があったのか、民族闘争があったのか、信仰政策があったのかと、新しい知見の宝庫であることに気がついて…。
世界史&国際関係論の泥沼化スタート!
なぜ環境問題なのか
そんな勉強にハマった頃、Netflixでとある映画に出会いました。
それが “残された楽園〜オカバンゴ・デルタを生きる〜“
これは、南アフリカ共和国の上に位置するボツワナという国にあるデルタ、オカバンゴ・デルタが舞台となっているのです。
ぜひみなさんの目で見ていただきたいのですが、番宣を少し…。
カラハリ砂漠の中心にある一定の時期に誕生するデルタ。
唯一のオアシスで生命維持を行う多種多様な生命がそれぞれの生存をかけ自然の素晴らしさと恐ろしさを与えてくれる。しかし、そんなオアシスも束の間、すぐに砂漠へと一変しそこでも生命を削っていく…。
そんな自然のいろんな姿を見せてくれる素晴らしい映画です!
そこで自然の素晴らしさを感じたのとともに、人間の身勝手さにも気が付いた気がしました。自然の素晴らしさとは一言で言っても、それは自然の過酷さ、美しさ、儚さ、一族の絆などを総括したそんな意味を込めています。
自分自身の望んだ人間世界とは相反した自然に感銘を覚えたとともに、人間はなぜこれほどまでに自分の好きなことばかりできているのか、とも感じました。
そして、他の作品をたくさんみていく中で、プラスチックが海の生態系の脅威となっていること、また漁業が海の生態系を崩していること、森林伐採が行われることで生息地をなくしている動物がいること…たくさんの現実を知りました。
そこで、プラスチックの使用を必要時を除いて避けよう!とよく利用するスターバックスコーヒーでは店内用のカップやグラスを使うように。
極力テイクアウトではなく、イートインをする!
などなど自分なりのアクションは起こしてみるようになりました。
そんなこんなで、環境問題を考えるようになったのですね。
4.今後の方針宣言〜未来のために一緒に考えを深め、行動しましょう!〜
投稿頻度は週1を目指す!
投稿頻度は週1を目安に考えています。自身、先述の通りで、国家公務員を目指しています。そのために勉学に励んでいるのですが、他のこと(このnote活動も然り)も頑張っています!
なので、週1を目安に頑張ろうと思います!
と、いうのも、プラスで論述式問題の解答をするように書いていこうと考えているので、ちょっと見にくさが出てしまうかもしれませんがどうかお願いいたします!
テーマは主に5つほど
・国際関係について
・環境問題について
・国際協力について
・スポーツ環境対策について
・スポーツの国際関係等について
主には論文や長文記述のような感じで書いていこうと考えていますが、こういった感じの自身の考えを綴ったりもしようかと!
最後に
よりよい未来のために、未来の子どもたちのために、そして、地球に住む全ての生命のために、一緒に考えを深め、よりよい人間行動を考えていきましょう!
微力ながら、尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
