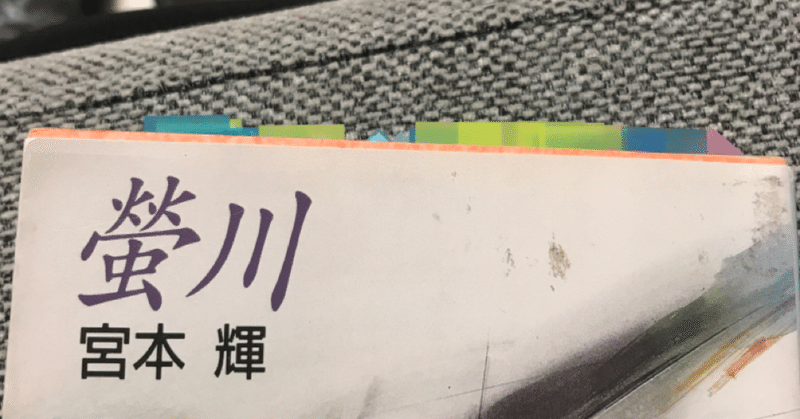
【読書】『蛍川』宮本輝(感想と考察)
風がやみ、再び静寂の戻った窪地の底に、蛍の綾なす妖光が、人間の形で立っていた。
生と死は、言葉や時間、倫理などでは到底表し切れない。また理解しきれない何かがあることを、まざまざと突きつけられるような作品でした。『泥の河』で8歳だった主人公(別人物)が『蛍川』では14歳になる。それぞれの年代の子どもたちが何を思い、感じているのか。6年の時の経過によって、少年に見える世界がガラリと変わっていく様は、かつて少年だった誰もが共感できる部分を含んでいるのだと思います。少年の生と、少年に関わる人々の生。それらがどのように交わってゆくのかについて、感想と考察を書きたいと思います。
あらすじ
昭和37年3月の末、富山の街に住む龍夫は父、重龍と母、千代の3人で暮らしていた。父の事業は失敗し、多額の借金を残したまま脳溢血で帰らぬ人になる。お金を工面するため、一人父の古い友人に会いに行く龍夫。同じ女の子を好きになり、一生の友達を誓い合った友人の死。父の前妻との出会いが龍夫の人生に1つ1つ重なってゆく。
龍夫と千代は、千代の兄を頼って大阪に移り住む瀬戸際に立たされる。いたち川音の上流に数十年に一度訪れる蛍の大群を見ることで、大阪行きの決心を固めようとする千代。亡き友と龍夫自身が恋焦がれる英子と蛍の大群を見に行くと約束した龍夫と英子に、銀蔵爺さんの4人は蛍を見るため河の上流へと向かう。
蛍は、華やかなものではなかった。交尾を終え、死んでゆく蛍の大群が4人の目の前にあるだけだった。
父と子
痙攣を起こして崩折れてゆく瞬間の父の顔が、胸の奥に刻まれていた。もうわしをあてにするなという父の言葉が聞こえて、彼は寝返りをうった。ー老いて憔悴した父が嫌いだったのである。
龍夫は重龍(以下「父」)と52歳差という年の離れた親子だった。母の千代は重龍と22歳の年が離れている。どこにでもいる家族・珍しくはない家族という言い方は、形だけを見たうえの言葉であって、家族にとっての現実は唯一無二だと感じたのが、上記の一文。
これからの生を持つ龍夫と、死に向かってゆく重龍の間には、どうしようもない程開けた距離があることを、二人の会話が物語っている。父の喪失を、14歳の少年がどのように感じるか。僕には分からないけれど、そこには言いようのない不安があるのだと感じる。生活の問題は否応なしに、龍夫のなしかかってくる上、本来なら心の支えともなる父に頼れない現実を龍夫がどう感じたのかは、想像の域を出ませんでした。
遺伝子
運というものを考えると、ぞっとするっちゃ。あんたにはまだよう判るまいが、この運というもんこそが、人間を馬鹿にも賢こうにもするがちゃ。
父が死に、父の昔の友人に龍夫が大金を借りいれる場面です。他人から初めて聞く父の過去・子の知らない父の姿。14年も一緒に生活をしておきながら、全く知ることのなかった父の姿。読んでいて不思議な実感がありました。
物理的な距離と、内面的な距離はイコールで結べないこと。父がまだ生きているぼくにとって、自分は本当の父を知っているのだろうか、と疑問を関しました。それでも龍夫の目に見えていた父は龍夫にとっての現実であり、龍夫の知らない父の52年間。それが遺伝子として龍夫の中に眠っていることを、考えると何とも言えない感覚に陥りました。
「運」について、僕にははっきりとした答えは出ませんでした。龍夫と同い年で死んでしまった、親友の関根を見ていると、運というものは気づかないだけで、日常のありとありとあらゆる所に存在しているのかなと、考えさせられるのです。
矛盾
子供を捨ててまでも夫と別れてきた女が、妻を捨てでも子供の親になりたいという男のもとに嫁いだのである。
母の千代が重龍との過去を回想する場面です。重龍と千代という二人の人間が抱える矛盾。そういった矛盾はあまねく人の中にあるものだと感じざるを得ません。自分の幸せと他人の幸せに折り合いがつかないのに、その人でなければならない。心の底が交わることは決してないのに、それでも関係を続けたいという人間の心理。
『泥の河』でも感じた、心の距離をここでも感じました。「心」をどこまでも解剖していった先になにがあるのか。自分に当てはめて考えるとなお一層答えのでない問を投げかけられたような気持ちになりました。
死としあわせ
死ということ、しあわせということ、その二つの事柄への漠然とした不安が、突然波のように体の中でせりあがってきて、龍夫はわっと大声をあげてのけぞりそうになる自分を押さえていた。
「死は生よりも尊い」上の文章を読んだとき、胸に浮かんだのは、夏目漱石の言葉でした。「死ぬこと」が決まってるいのちえを生きるなかで、常に付きまとってくる「死」を、作者がどのように捉えているのか。それが気になって仕方ありません。
「息子が大きいなって、それからしあわせになってからしぬがや」でも、龍夫が大きくなる前に父は死んでしまう。誰かのしあわせに、自分の生が絡んでいる。喜ばしいことでもあって、恐ろしいことでもある。「しあわせ」とは、おそろしものなのではないかなと思います。
愛について
おばちゃんのできることは何でもしてあげるちゃ。商売がなんね、お金がなんね。そんなもんがなんね。みんなあなたにあげてもええちゃ・・
父の前妻「春枝」が龍夫に残していった言葉です。僕は、息子と妻を残して死んでしまった、父の愛が形を変え、姿を変えて、龍夫に戻ってきたのかなと感じました。
愛はひとの間を流れて、自分の愛したものへと帰ってゆく。だとしたら、人のためと思ってしたこともいずれは自分に帰ってくる。そうであればいいなぁと心から思うのです。
まとめ
『蛍川』という作品に出会えことに、何かしらの運命すら感じる。それが読み終えた後の率直な感想です。今の自分が、色々なことに目を背けながら生きているとも感じました。生きることと死ぬこと。しあわせとふしあわせ。自分と他人。家族と友人。運命。
答えのでない問に向き合い続けること。それが人間の宿命というか、すべきことのように思います。向き合った先になにがあるのか、『泥の河』にも『蛍川』にも、明確な答えはない。というのが今感じることです。
龍夫の心情描写について、感想をまとめることができませんでした。感情移入してしまい、なかなか龍夫を、一人の人物としてとらえきることが出来ませんでした。再読を重ね、じっくり考えて行きたいです。
きっと、何度も読み返すであろう『蛍川』。その度に感じることを大切にしていきたいと思います。
貴重な時間をいただきありがとうございます。コメントが何よりの励みになります。いただいた時間に恥じぬよう、文章を綴っていきたいと思います。
