
vol.1|創業者、木下美智子の化粧品
iLabという化粧品を語る上で、創業者である木下美智子(以下、彼女)のことを語る必要がある。彼女がどんな人であり、どんな人に向けてこの化粧品を創ったのか。それを知ってもらう必要がある。彼女がこの化粧品に込めた想いや、その商品に対する情熱を、残された者は伝えなければならない。
簡単に化粧品をつくることができる今だからこそ、これだけのコンセプトを込めたスキンケアを語らなくてはいけない。だって、このスキンケアを創ったのは、今から約20年も前。今よりもずっと前の話だから。

彼女(創業者)との思い出は沢山ある。一緒にいた正味の時間を思い返すと短いが本当に沢山ある。約15年近く関係が途絶えていたが、今でも彼女との暮らしや話した内容、記憶が鮮明に残っている。それぐらい、彼女はいつでも誰の記憶にも残る人だったに違いない人だ。
去年、彼女は亡くなった。亡くなる前の1年半、約15年振りに再会をした。再会した彼女は無口になって自宅のベットに横になりながらテレビでドラマを観ていた。久しぶりにあった彼女は無口だったけれど、彼女と手をつなぐだけでわかることも多かった。そばにいてもあまり会話はなかった。あれだけおしゃべりだった彼女は、脳梗塞を2回経験したからなのか、それともこれまでの人生で人よりも多く話しすぎたせいなのか、彼女はまるで別人のように言葉を失っていた。自宅に住んでいるお手伝いさんには色々言うようだが、私には何も言わなかった。とにかく感覚、感性の人だった。手に、目にする感覚、肌への感触や口にするものを誰よりも、何よりも大切にしていた人だから、すべてを感性に委ねていたのかもしれない。

彼女と出会ったのは私が19歳の時だから、もう21年前になる。神田生まれの江戸っ子女性。「てやんでい!」ということばがすぐ出てきそうなぐらい、強気でせっかち。まぁまぁの早口でお喋り好き。プライベートは几帳面、何をするにも潔癖な女性だった。私は当時大学生で、彼女の夫が住む別荘の近所に、たまたま父親が小さな山小屋を建てたので、大学生の夏をリゾートバイトしながら一人で暮らそうとしていた。当時は定住する人などいなく、夏の避暑地として皆が暑い時期だけを凌ぐためだけに過ごしていた八ヶ岳の麓、清里だ。

彼女の夫は彼女と年齢も離れていたので、八ヶ岳に定住していた。たまたま夏の避暑地に近所の山小屋の娘(私)が、大学生の長い夏休みを避暑も兼ねてバイトをしに来た。そんな私を、父が近所の定住者だからといって、彼女の夫と繋げてくれた。人生は不思議だ。それがきっかけで、彼女の夫と一緒に過ごすようになった。
夜は真っ暗になる別荘地。静かで街頭ひとつない夜の森は、本当に人気がない。当時大学生だった私は、幽霊だろうがなんだろうが、動物でも真っ暗の中に出くわしたら腰を抜かしてしまっただろう。それぐらい夜の別荘地は静かで真っ暗、びくびく過ごしていた。私は山小屋で一人過ごすことがとても怖く、彼女の夫とお互い1人暮らしということで夕食を共にし始めた。しばらくは彼女の夫に送ってもらい、彼と彼女の山小屋と父の山小屋とを行き来して暮らしていた。それも数週間で面倒になり、彼と彼女の山小屋で暮らすようになった。当時、彼は83歳。何かあると「もういつ死んでもいいよ。」というのが口癖だった。本当に死ぬのかは別として、週末しかいない彼女からすれば、誰かが彼の側にいて、彼が元気でいるのかわかることは嬉しそうだった。

彼女は週末になると東京での仕事を終えて、最終の特急あずさに乗ってやってくる。彼女の夫は免許を取るなと彼女に言われて素直に従い、免許を持たなかった。車がないと生活に不便な山に住んでいるにも関わらず、移動はすべてタクシーだった。運転ができる私は彼と一緒に暮らすようになってから、彼女を迎えにいくのも、遠くへの買い物も、どこに行くにも運転手のような役割が必然とできていた。自分の家は近くにあるけど、夜の怖さや、彼との夜の晩酌タイムがすっかり気に入っていた。彼女がいる賑やかな週末は楽しく、彼女と彼、その二人のやりとりを見ているのも楽しく、本当に一緒に過ごした不思議な3人、山小屋生活である。

当時彼女は76歳(だったと思う)。東京で社長をしている(らしいということはわかった)→そもそも彼女が化粧品会社や他の会社を経営していることも知らないし、正直大学生だった私にはあんまり興味もなく関係がなかった。彼女はいつも真っ直ぐな人だった。化粧が嫌いで、肌を何かで覆うことが嫌いな人だった。物事へのこだわりが誰よりも強く、それはパートナーである彼にも強くそのこだわりを押し付けるという被害は及んでいたけど、彼は彼女に従っていた。それは彼女が誠実で素直な人だから、彼はそんな彼女を愛し尊敬し信頼していた。それは妻というカテゴリーよりは人生のパートナーといった、とても中性的でニュートラルな印象で、大正生まれの夫が、昭和初期生まれの職業婦人である妻との理想的な関係だった。

彼女がある日キッチンでずっと取り寄せている、サラダに使うトルコ産のオリーブオイルの話をし始めた。オリーブオイルを絞るときに熱が加わるものが多く、その熱がオイルに加わるとその時からオイルの劣化がはじまるから、そんなオイルは良くない、だからこの絞るときに熱が加わらない製法をとっている、このオイルを選んでいるという話がひとつの例で、なぜこれは良いのか?その理屈がはっきり自分で納得したものしかは選ばないぐらい徹底して自身の生活をも管理していた。
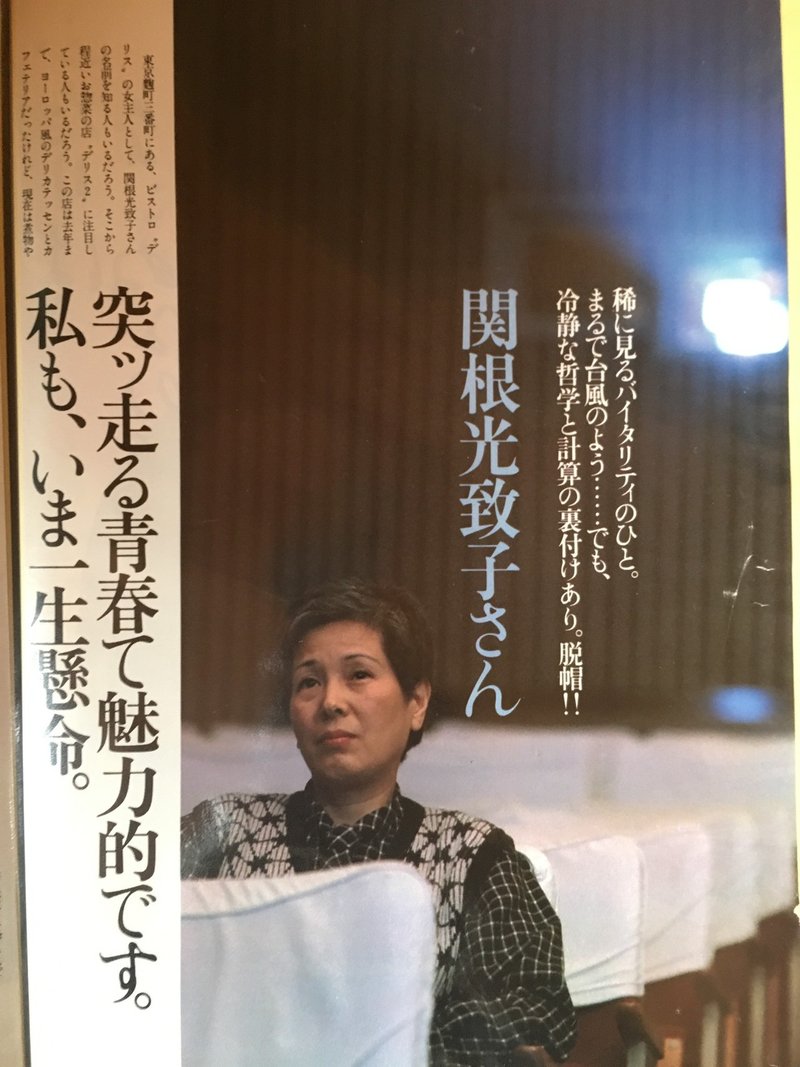
その強いこだわりで、彼女の暮らしは構築されていた。最先端でありクラッシック(伝統的)。相反するそのキーワードが浮かぶ化粧品、それがiLabだ。彼女のこだわりがこのiLabという化粧品にギュッと込められている。彼女が自分の肌に使っても良いと認められた唯一のスキンケアでもある。

スキンケアの開発を進めたのは、彼女が当時手掛けていた輸入品のへアケアのHelsinkiformulaというブランドから付随している。当然、ヘアケアに対するこだわりも強く、当時はスカルプケアなんて言葉がまだ新しい時代に、当時アメリカで大ヒットしていたヘアケア製品を輸入し販売し始めた。彼女が納得したヘアケア製品だったから。その時代のスキンケアはみんな顔の毛穴にフォーカスした商品が多く展開されていた。彼女はいち早く顔の毛穴ではなく、頭皮の毛穴に注目していた。彼女は「頭皮と顔の皮膚は1枚の皮なんだから、頭皮の特に毛穴も顔の毛穴以上に大切にしないとだめ!肌があれる、ニキビ、敏感肌も、諸悪の根源はすべて毛穴にある!」と断言していた。

今だったら美容感度の高い人にはすんなり受け入れられる、有機、オーガニック、ゲルマニウム、アユールベーダ、ヨガ、瞑想、こんなキーワードは約20年前の当時の彼女の暮らしでは常識であり日常。その早すぎる感性やアイディアが斬新だった。
私は色んなことがあって疎遠になって、18年ぶりに彼女に会った時、本当に驚いたのは彼女の変わらない透明感のある、きめ細やかな肌だった。過度に肌に手を加えることを嫌い、なるべくナチュラルでオーガニック、哲学があるモノや暮らしを大切にしていた彼女。シミひとつない美しい素肌を目の当たりにすると、彼女が積み上げた経験と知識が込められたiLabという化粧品はなんてすごい商品なのだと改めて感じた。それが今変わらず販売されていて、18年ぶりに再会した彼女の肌にきちんと証明されているのである。「哲学=フィロソフィーのないものは使ってはいけません。」と聞こえるような、その独特の使用感と時代に流されない強いこだわりがいっぱい詰まっている。

自分の信念を曲げることなく生き抜いた彼女が、手塩にかけてつくった化粧品を、その彼女の感性に触れることができた私は生き証人として彼女のこだわりと哲学を伝えるとともに、このiLabというブランドや商品に込められた話を伝えていくこと。それが再会した意味、自分の与えられた役割と感じている。
iLabのスキンケアはこの春で21年目を迎えました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
