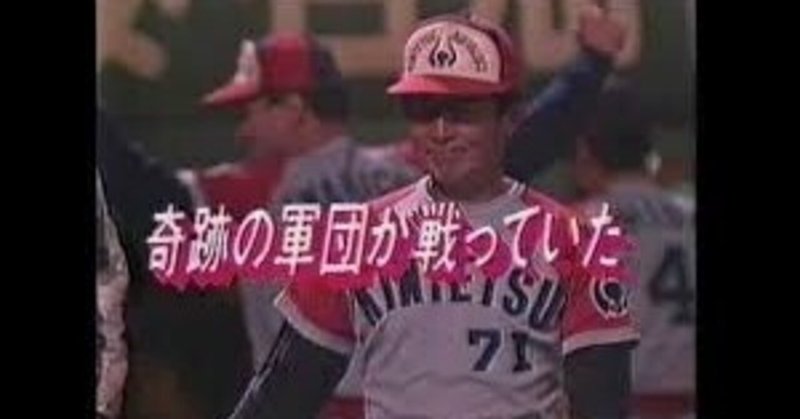
10.3度目の受験
浪人生活2年目も、特に成長なく過ごしてしまったが、時の流れは残酷で、またしても受験の季節がやってきてしまった。
ところで、受験の前年の10月19日、事件が起こる。私が3度目の受験をする1989年と、その前年の1988年というのは、まあ、昭和最後の激動の年である。前年の10月19日にはニューヨークのウォール街の株の大暴落(ブラックマンデー)があり、それから丸1年の記念日であり、昭和天皇の容態がもうダメらしいというところまできており、東京地検はリクルートへ強制捜査に入るという、報道番組ではニュースの特異日だったらしかったが、そうしたビッグニュースを全てぶっ飛ばす事件である。
昭和最後の時代を知っている人は思い出すであろうが、この日、川崎球場でロッテ対近鉄のダブルヘッダーの試合が行われ、これに2連勝すると近鉄の逆転優勝でパ・リーグを制することになったのだが、これだけだと単なるパ・リーグ(当時はセ・リーグに対して全くマイナーな存在だった)の優勝争いに過ぎないのだが、この試合は日本中を騒然とさせることになる。この年の6月に助っ人外国人のデービスが大麻不法所持により逮捕、退団するという楽しい話題を提供してくれた近鉄の優勝を願っていた私は、予備校で授業なんか受けているどころの心境ではなく、試合開始の15時には帰宅して、観戦体制バッチリだった。ちなみに、当時の野球中継は巨人以外は放送されない状況だったのだが、大阪の朝日放送(ABC)は試合開始から終了まで異例の完全生中継を実施することになっていた。そして、騒ぎは試合開始前から始まっていた。
現場となった川崎球場は、万年閑古鳥が鳴く球場として有名だったが、この日は朝から無料招待券を持った客や各地から動員された近鉄ファンが大挙して押し寄せ、球場の定員を大幅に上回る人々が集まった。指定席は定数分の入場券があらかじめ用意されておらず、更に自動発券機がなかったため、不足した分は窓口の係員が座席表を確認しながらゴム印で席番を打つという手作業で発券した。さらには「大人用」の台紙を使い切ってしまったため、「小人用」の台紙の「小人」の表記をペンで消去して使いまわし、さらに指定席完売前に席番無しの立ち見券を発行するという異例の対応をするなど、係員は終始発券の対応に追われた。それでも発券が追い付かず、球場周辺には長蛇の列ができた。第1試合開始の15時前にはチケットは売り切れになり、無料招待券で入れる自由席に入場制限がかけられた。入場できなくなった人は球場に隣接する雑居ビル、マンション、アパート等の上の階に観戦場所を求めて集まり、右翼側場外にあるマンション「ハウスプラザ角倉」は階段や踊り場、さらには屋上までが人で一杯になったほどだった。第1試合に近鉄が勝利したことでさらに観客が球場周辺に押し寄せた。当時、駒沢大学に進学していた高校の同級生のシコ中も駆けつけたらしかったが、とても球場に近づける状態ではなかったらしい。
放送の方は、朝日放送(ABC)の他、福岡県の九州朝日放送(KBC)と、宮城県の東日本放送(KHB)では、朝日放送制作の中継を第1試合から同時ネットで放送したが、肝心のキー局であるテレビ朝日は眼中になく、試合経過だけニュース速報で知らせるだけであったが、試合の経過を知った視聴者から中継を求める電話が数百件にもわたりテレビ朝日に殺到。さらに、「局内のどこへいっても、誰もがABCからの裏送りで局内向けに流れているテレビ中継を見ている」という有様でもあったため、編成局では20時以降の第2試合中継の放送をめぐって協議に入った。協議では、『ビートたけしのスポーツ大将』と『さすらい刑事旅情編』(当時21:00 - 21:54に放送されていた全国ネットの連続ドラマ)の全面差し替えも検討されたという。結局、21:00から10分間だけ中継を放送したうえで、『さすらい刑事』以降の番組の放送開始時間を10分ずつ遅らせる方針に落ち着いた。本来は22:00から放送する『ニュースステーション』のスタッフは後述する事情から「10分遅れで番組スタート」という方針に異議を唱えたものの、テレビ朝日の編成部では、スポンサーや系列局との折衝を開始。いずれも了承を得られたため、第2試合途中の21:00(7回裏・ロッテの攻撃中)から全国放送に踏み切った(その際、テレビ朝日はABC側に近鉄寄りの実況から中立な実況をするように指示、安部も「ロッテもプロです」、「ロッテもザ・プロフェッショナルとしての意地とガッツをぶつけての良い戦い」などとロッテを意識したり配慮したりする実況をしていた)。実際には、10分で切り上げる予定だった中継の時間延長を繰り返したあげく、21:30を迎える直前で『さすらい刑事』の休止と22:00までの中継延長を決定。結果として、21時台はCMなしの中継が続いたため、事実上「サスプロ」(スポンサーの付かない自主編成番組)として放送された。以上の対応を直々に指示した当時のテレビ朝日編成部長の斎田祐造は、中継を見ながら、「(CMを出稿しているスポンサーからの収入で成り立つ民間放送としての)身を切るようなエライ(大変な)ことをしている」という思いに何度も苛まれたという。この措置によって、『ニュースステーション』は22:00(9回表・近鉄の攻撃中)から放送を開始したものの、メインキャスターの久米宏はオープニングで事情を説明。「今日はお伝えしなければならないニュースが山ほどあるのですが、このまま野球の中継をやめるわけにもいきません」「どんな番組になるか今夜は分からないんですが、伝えるニュースもいっぱいあるし助けて下さい」という表現で、視聴者に理解を求める事態にまで発展したのである。もう受験準備どころの騒ぎではない。
さて、受験であるが、浪人生活も2年になると、だんだんと志望校に対するこだわりがなくなってきた。一応、第一志望は東京藝術大学美術学部建築科だったものの、それにこだわってこれ以上浪人はしたくない。YouTubeなどを見ていると、東京藝術大学美術学部のグラフィックデザインを目指して7浪した挙句、結局、多摩美術大学のグラフィックデザインに入学した人の動画があったり、9浪して医学部に入った人の話も聞くが、そう言う人は、超人的な意志の持ち主に違いない。私には到底不可能だ。そういうこともあり、3度目の受験では、これまでの受験姿勢を180度変換して、手当たり次第に建築系の大学を受けることにした。
まず、最初に受験したのは、神戸芸術工科大学環境デザイン学科。いまの大学案内を見ると、建築コース、ランドスケープコース、まちづくりコースに分かれているようだが、私が受験した時には、こうした分け方がされていたかどうか定かではない。私が大学を卒業したあと、いろんな大学で学部や学科の再編がされており、また、新設の芸術系大学も増えた。私が最終的に入学した多摩美術大学も、それまで独立していた建築とインテリアが統合し、そこにランドスケープが加わって環境デザイン学科になっている。コースも、確定的ではなく、それぞれ横断的なカリキュラムも可能である。
さて、神戸芸術工科大学環境デザイン学科の入学試験は、学部入試制度もいろいろなタイプの入試ができて、一般選抜入学試験Ⅰ期の試験科目を見ると、3時間の鉛筆デッサン又は小論文+持参作品・資料+学科試験になっている。私の時は鉛筆デッサンだけだったので、どの選抜試験を受けたのか、今となってはわからないし、不合格だったので調べようがない。
次に受けたのが、大阪芸術大学建築学科の推薦入試である。試験科目は小論文と面接だけだったと思うが、小論文は特に問題なかったと思うのだが、面接でやってしまった。志望動機を聞かれた際、マンフレッド・タフーリの「建築のテオリアーあるいは史的空間の回復」を持ち出して、「建築の思想性に感銘を受けて」みたいなことを喋ってしまい、墓穴を掘ってしまった。いまなら、多少突っ込まれても、「階級的批評はあっても、階級的建築はない」という、いかにもマルクス主義者らしい主張、つまり、マルクス主義的な視点からの建築批評は可能であっても、マルクス主義の思想を表現した建築というようなものは存在しないと答えることはできるものの、当時はそこまで読み込んでおらず、土台となるマルクス主義さえちゃんと理解していなかったので、面接を担当した試験官に、「なんて、薄っぺらいヤツ」と思われたに違いない。大阪芸術大学という大学は、当時は、関西では名前と受験番号さえ書けば受かる大学と、いわゆるFラン大学の象徴的な大学と揶揄されていたので、私の代わりに合格発表を見に行った姉は、私の番号がなかったことに相当のショックを受けたようだ。
こうして関西の2つの大学がダメだった私は、残る関東方面の大学にかけるほかなくなった。どの順番で受けたのか忘れてしまったが、筑波大学、武蔵野美術大学、多摩美術大学、東京藝術大学の4大学を受けることになった。
筑波大学は芸術専門学群の中に建築デザインのコースがあるのだが、年間に5~6人しか受からない狭き門で、その意味では年間14~15人合格する東京藝術大学の方がマシかもしれない。また、東京藝術大学と同じく国立の大学なので、どういう日程で、どの選抜方法で受験したのか忘れてしまったが、もしかしたら推薦入試だったかもしれない。
筑波大学を受けるにあたっては、ちょっとした旅行気分を味わった。通常なら新幹線で東京まで行って、そこから筑波まではバスというのが一般的な行き方であるが、私はまず、名古屋まで近鉄特急で行き、大垣発東京行きの夜行快速列車(かつては定期列車であったが、2009年以降は臨時列車「ムーンライトながら」として運行されているようである)で東京まで行って、上野から朝一の常磐線に乗って土浦まで行って、土浦駅から筑波大学まで歩いたのである。距離にしたらどれくらいだろうか?まあ、無謀というか、若かったとしか言い様がない。さすがに帰りは東京駅まで高速バスに乗って、新幹線で帰った。合格発表の時も同じ方法である。
ところで、筑波大学の入試であるが、鉛筆デッサンと小論文と面接だったと思う。鉛筆デッサンはまあまあ。小論文は、「自分の住んでいる街の問題点と解決策」みたいなテーマだった。私の実家のある街は、高度成長期に近鉄が大規模に開発した大阪の郊外住宅地で、その時代、同じような郊外住宅地がいくつもできて、その副作用として大都市中心部のドーナツ化を招いたことを問題視し、郊外の開発を極力抑制し、大都市中心部の再開発(最近の傾向で言えば、都心にタワーマンションをどんどん建設)による人口の都心回帰を図るべきだという論調で書いた。その小論文に問題があったとは思いたくないが、問題があったとすれば、やはり面接である。どうも私は面接で余計なことを言ってしまうきらいがある。筑波大学の面接でも、建築単体のデザインよりも、建築の集合体=都市のあり方に興味があるというと、面接官に、「それなら、そういう方面に進んだらどうですか?」と言われてしまい、その言葉が心に突き刺さった。結果は思ったとおり不合格である。
武蔵野美術大学、多摩美術大学、東京藝術大学の受験に際しては、センター試験こそ奈良女子大学で受けたが、入試から合格発表まで、東急新玉川線(現:東急田園都市線)の三軒茶屋と駒沢大学の中間にあったシコ中のアパートに泊めてもらって受験した。
まず、武蔵野美術大学造形学部建築学科の入試であるが、学科は英語と国語、実技は鉛筆デッサンだった。ただ、それは昔の話で、いまの試験科目を見てみると、建築学科に関しては数学の試験がある。昔だったから良かったものの、いま、武蔵野美術大学造形学部建築学科を受験するならば、数学がネックになって、合格はほとんど無理だろう。しかし、一方で、建築学科では、共通テスト3教科方式という学力試験のみで受験できる方法があって、大学入学共通テストの指定科目のみで受験でき、武蔵野美術大学独自の試験は実施しないということで、実技試験もないということか?しかも、共通テストで理系科目を外し、英語・国語・地理歴史を選択すれば、極めて有利に戦える。かつて、芸術大学や美術大学の受験では、実技試験が必須であり、だからこそ美術予備校の存在意義もあったのだが、時代は変わるものである。
ところで、私が受けた武蔵野美術大学造形学部建築学科の学科試験の国語と英語はそんなに難しくもなく、鉛筆デッサンも自分としては割とよくできたと思うので、期待して合格発表に望んだのだが、悲しいことに私の受験番号はなかった。はっきり言って、美術大学の学科試験は、高校レベルの学力さえあれば楽勝である。ということは、鉛筆デッサンがダメだったのか?何が原因で落ちてしまったのか、未だにわからない。
次に、多摩美術大学美術学部建築科である。学科試験は武蔵野美術大学同様、英語と国語で、実技試験に平面構成と建築写生があった。多摩美術大学美術学部も、学科編成で環境デザイン学科に統合された建築科の入試では、いまでは実技試験のない共通テスト単独方式があって、学科だけで勝負したければ、そういう方法もあるが、この場合、数学と理科も受けなければならず、理系科目が苦手だった私は痛し痒しというとことか。まあ、一般方式の実技試験は5時間の鉛筆デッサンだけでいいみたいなので、鉛筆デッサンには自信があった私にはこちらが向いているかもしれない。入学試験は、学部のある八王子キャンパスではなく、大学院と二部のある上野毛キャンパスで行われた。シコ中の部屋からは、東急新玉川線(現:東急田園都市線)で二子玉川まで行って、大井町線に乗り換えて一駅だったので、非常に近かった。
実際に、多摩美術大学美術学部建築科を受験してみた感想は、学科に関しては楽勝で、問題は実技試験にあった。これは実際に、入学してから教授陣との初の面接の時に明らかになるのだが、実技試験の平面構成も、建築写生も、点数は散々だった。補欠とは言え、良く合格したものである。あの美術予備校での実技トレーニングの日々は一体なんだったのかと今にして思う。平面構成のテーマは、「四季を表現しなさい」というもので、制限時間は7時間。このテーマは、河合塾美術研究所名古屋校建築コースで一度やったことがあり、内心「ラッキー!!!」と喜んだのだが、私の作品は、モンドリアンの「赤・青・黄のコンポジション」の出来損ないみたいな代物で、単純な矩形だけで四季を表現するのはかなり無理が有り、色彩だけで勝負するのではなく、形状に関して、もっと工夫が必要だったと思う。建築写生も、今になって思い返すと、構図を選んだ時点で失格だったと思う。建築の立体感がまるで表現されておらず、のっぺりとした水彩画になって、見返してみて、まるでダメだったのが自分でもわかる。写生の場所や構図選びは、キャンパス内の屋外であれば自由に選べたにもかかわらず、出来上がりがどんな作品になるか、あまり考えずに描き始めてしまったのが間違いだった。合格発表ではもちろん私の受験番号はなかった。ただし、幸運の女神が微笑んだのか、敗者復活で生き残った。
さて、残すは、毎年の受験シーズンのメインイベントである東京藝術大学美術学部建築科だけである。ここまで全ての大学に落ち続けている私は、「もう、背水の陣だ」と言い残して、上野の受験会場へ向かった。そんな私を見送るシコ中の目はヤケに心配そうだった。
試験会場の教室への入室待ちの受験生の面々は、何度も見た顔があるし、共に河合塾美術研究所名古屋校建築コースを受講していた同志の顔も多かった。顔見知りのあいだでお互い健闘をたたえ合う。そばで話していたある受験生に至っては、「今年合格したらマンションを買ってやる」と親に言われているヤツもいて、ほかの受験会場とは違う、異様な雰囲気に包まれていた。
いよいよ教室に入場して、机の上の材料を見ると、数枚のスチレンボードやボンド、定規、カッターはいつも通りだが、今回はそれに加えて5mm角の角材が数本含まれていた。試験官の合図がないと、テーマの書かれた問題用紙を見ることができないので、あれこれ想像するのだが、立体構成で角材など使ったことがないので、かなりの不安がよぎる。時間になったので、問題用紙を見ると、そこに書かれていたテーマは、「角材が宙に浮いているように立体構成しなさい」だった。去年の球体に続いて、またしても空中シリーズだ。なかなかの難問である。何枚もスケッチをしながら考えたのだが、悲しいことに何も思いつかない。ただただ時間だけが経過していく。周りを見渡してみると、立体の作成に取り掛かっている受験生もいて、なるほどな~~~と思うものの、真似するわけにはいかない。苦肉の策で思いついたのは、スチレンボードで立方体のフレームを作り、そのフレームに角材を引っ掛けて中に浮かすというものだったが、心配なのは、そのフレームをどうやって固定するかで、結局、その心配が最終的に悲劇を生むことになる。
お昼の休憩を挟んで午前・午後と合計7時間。一心不乱に立体作りに励むのだが、フレームが細すぎると強度不足で壊れてしまう。かと言って太くても不格好で、なかなか綺麗なプロポーションで作ることができない。そして、最大の課題であったフレームの固定方法であるが、立方体の平面をそのまま置いたのではあまりにも芸がなさすぎる。あれこれ試行錯誤してなんとか形にはなったものの、かなり不安定なのは間違いない。そしてタイムアップとなり、後片付けをして教室を出ようとしたとき、人生最大の悲劇を目撃することになる。なんとなく後ろ髪を引かれる思いで私の机を振り返ったとき、7時間かけて必死に作った私の立体が崩れ落ちたのである。
もはや合格発表など見に行く気力もない。それでも現実を直視しなければと見に行ったのだが、当然、私の受験番号が張り出されることはなく、実家の自室で、3年目の浪人生活を迎えるべきか、大学は諦めて就職の道を選ぶかで、悶々とした数日を過ごしていた。第3の道として、文系科目の学科試験だけで入れる適当な大学に進む道もあったのだが、それはそれで大学生活の4年間の時間が無駄に思えて気が進まなかった。そんな時、捨てる神あれば拾う神ありで、多摩美術大学から一本の電話がかかってきた。
「補欠合格されていますが、どうされますか?」
もはや選んでいる場合ではない。
「ハイ!!!お願いします」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
