
自宅が“映えない”整理収納アドバイザーのこれからの仕事術
整理収納アドバイザーとして仕事をいただいているのに、自宅の収納の中は決して美しくない。この一見相反する事実を、私はおおっぴらにしている。
私が仕事をする上で大切にしているのは「自分をさらけ出す」ことだ。それって結構勇気がいる、でもラク。そんな相反する私の中の感情に気づいたのは、そんなに前のことではない。
整理収納アドバイザーの自宅っていつもキレイなんでしょ!?
私は「片付け相談所かげいろ」という屋号の元、個人宅の整理収納サポートに伺ったり、新築時の収納計画のお手伝いをしている。
整理収納アドバイザーには珍しいタイプだと思うのだが、私は元々片付け上手でもきれい好きでもないし、かといって汚部屋出身でもない。(私の周りのアドバイザーは、得意を仕事にした人か、苦手を克服してその術を伝えたくなった人か、どちらかが大半だ)。
私は「まぁまぁ」で生きてきた。特別きれいでもないけれど、散らかってどうしようもないというほどでもない。フツーの部屋、フツーの家で育ち、暮らしてきた。
そんな私がどうして整理収納を生業にしているかというと、「現状を見て、お客様の希望を伺って、解決の方法を一緒に考え、かたちにしていく」というプロセスが好きだからなんだと思う。そのような仕事を探し求めて、整理収納について学び始めた。
整理収納アドバイザーと並行して受けているライターの仕事も、取材したものをどう文章としてかたちにしていくか…と考える過程が好きなのだ。そして両方に通じるのが「人の話を聞く」のがとても楽しいということだ。
そんな私だから、周りのアドバイザーたちの美意識の高さや、メディアで見かける家中どこもかしこも整っていて美しい!というビジュアルに、劣等感を感じている時期があった。いや…完全に過去の話でもない。未だに、アドバイザー仲間と自宅の写真を持ち寄って講座をするときなど、「私は“映えない”担当だから」なんてちょっと自虐的になったりもする。
アドバイザーになりたての頃は、それこそ無印のお揃いのケースを何個も買ったりして「いわゆる整理収納アドバイザー的な家」にしようと試みたこともあった。それはそれですっきりしていい気分になるのだけれど…私ちょっと無理してる?ほんとに収納の中をここまで「美しく」する必要ある?分かりやすく使いやすければそれでいいんじゃないの?そんな風に感じている自分もいた。
そうじゃない自分を認めよう
そこで、私は、ありのままの私を必要としてくれる人に向けて、サービスを提供していこう、と決め、自宅セミナーを開催した。その名も
「“映えない”わが家の収納セミナー」
インスタで「映える」ことが盛んにもてはやされている時代に、あえてそうじゃない整理収納もあるんじゃない?と言ってみたくなったのだ。
パントリーは白いケースをずらっと並べて…が正解、のような認識が広がる中、直置き満載、おしゃれでも何でもないケースが置かれ、子どもたちに任せきりのぱんぱんの「おやつ箱」がある舞台裏的パントリーを公開。

決して美しくはないけれど、どうして困らないか、を参加者さんたちに伝えた。
正直、かなり勇気が必要だった。こんなので整理収納アドバイザーって言えるの?そんなこと言われるかも、という恐怖もあった。
でも、開催してみたら…
たくさんの方が参加したい!と言ってくれたこと。パントリーを開けたときに聞こえる安堵にも似た声。「映えない収納万歳!」と記された事後アンケート…やってよかった、と思えた。
これからの時代
整理収納の業界でも、世間の流れと同様、リモートでのレクチャーやアドバイス、講座が増えてきた。私はまだ積極的には取り入れてはいないけれど、インターネット越しだと、より自分をさらけ出さないでも、仕事はやっていけるんじゃないかな、と感じたりする。わざわざ「映えない」収納を公開する必要も別にない。
自分のキャラクターだって同様だ。整理収納アドバイザーは一種のコーチ業だから、凛とした自分にしておいた方が、きっとそれらしい。わざわざ黒子のような「ぺたこさん」をキャラクターとして多用して、自分の陰キャラを前面に出す必要もないのだろう。
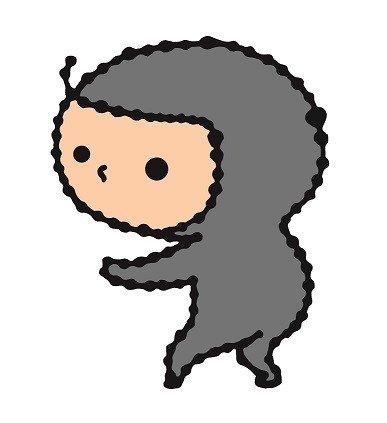
でも、残念ながら私は凛としていないし、自宅も「美的収納」ではない。そのことに引け目を感じながら違う自分を演じるのではなく、地味だけど、寄り添い力には自信があります!という、こんな私がいいと言ってもらえるお客様に見つけてもらった方が、お互いにハッピーだ。
これからはきっと、「物質的な」距離を近くとることはあまり求められない時代になっていくのだろう。だからこそ、「精神的な」距離は、お客様と近くありたい。そのためには、自分をあえてさらけ出すことで、精神的に近寄ってくれそうなお客様と出会える可能性は高くなると、私は信じたい。
そのためには、発信だ。その方法は…まだまだ模索中だけれども(笑)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
