
第2部 アニメ論:「アニメ・まんが的リアリズム」からサルトル的実存へ(1)
第2部における「問い」
いわゆる本格SFを愛するものとしてはSFとファンタジーとの間には一線を引いておきたいが、第1部で論じてきたように、そこにパタフィジック、シュルレアリスムという概念を導入すると、本格SFであってもそれはファンタジーとつながってくる。もちろん従来SFとファンタジーは相性の良いものであり、例えば、『デューン 砂の惑星』シリーズなどは神話をベースとしているという点でファンタジーであると言ってもいいであろう。映画で言えば『スターウォーズ』に代表されるいわゆるスペースオペラと称される一連の作品もそうである。そして、SFが魅力的であると同様に、ファンタジーもまた魅力的、魅惑的である。なぜならそこに広がるのはまさに「超トンデモ」な別世界であるからである。
そして、人はその別世界の話であるファンタジー作品を見て、読んで感動する。感動するだけでなく、納得いかない場合もあるし、文句(批判)を言いたくなる場合もあるであろう。しかし、改めて考えてみればこれは不思議なことである。本論におけるファンタジー作品の定義については次節で改めて述べるが、SF作品は、基本的には何らかの形で現実世界とつながりを持っているのに対し、ファンタジーの世界は一般的に現実とは違う、現実とはむしろかけ離れた世界、現実とはあくまで一線が引かれた向こう側の世界であるからである。SFに登場するエイリアンは、それと遭遇する可能性があるかどうかは別として、この広い宇宙のどこかには存在するかもしれない生命体である。つまりあくまで現実側の世界とつながっている。一方、ファンタジーに登場する妖精やゴブリンは少なくとも今の時代では、科学的には、つまりは現実的、物理的、フィジックとしては、存在しない存在である。しかし、それでも我々はそこに、妖精やゴブリンが存在する世界に、共感や郷愁、あるいは怒りや悲しみといった感情を感じることができる。また、そこに登場する者(物)に、たとえそれが人ではない何かであっても、生き方や生き様といったものを見て取ることができる。もちろん同じこと、現実ではないことに対して感動してしまうことの不思議、はフィクション全般についてもいえることではある。しかし、先にSFを例に述べたことの繰り返しになるが、いわゆるファンタジー以外の通常のフィクションは、その舞台が現実社会であるという点で、つまりは「リアル(現実)」に基づいた「リアリズム」として描かれていることで現実とつながっている。しかし、ファンタジーはその当初から「リアリズム」を原則、あるいは前提としていない。むしろ「リアル」でないこと、「リアル(現実)」に基づいているという意味での「リアリズム」には基づいていないことのほうをその原則、前提としているのである。
第2部は、その謎、その不思議から出発するものである。ここでの問いは「人はファンタジーなのになぜ感動するのか、人はなぜ明らかにリアルではないものに対しても感動してしまうのか」、とまとめられよう。しかし、この問いに対しては「もはや我々は「リアル(現実)」に基づくものではない「リアリズム」の世界を生きている。「リアリズム」とは「現実感」のことで、それは「リアル(現実)」を前提とする必要がない。という見解が既に存在する。大塚(1989,2000,2003)、東(2001,2007)などによる「アニメ・まんが的リアリズム」の考え方がその代表である。よって以下、まずは先に予告していたように本論における「ファンタジー」の定義とそのアニメとの関係の説明から入り、次に大塚、東らの議論を整理するところから始める。
ここから先は
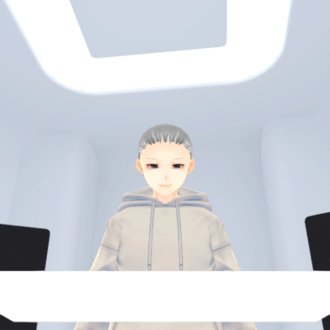
主に2022年から2023年3月頃までに書いたSF、アニメ、アバター(Vチューバー)、VR、メタバースについての論考をまとめました。古くな…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
