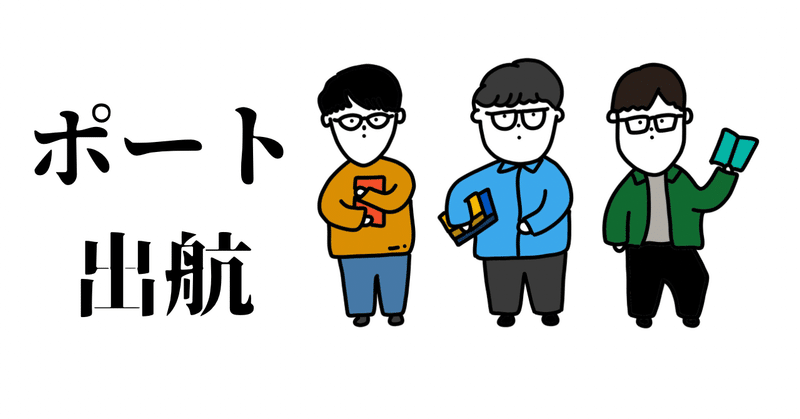
出航 -しかし、情熱はあり、-
この物語は、ある男のサークルからの出航と、そしてある男たちのサークルからの出航の物語である。
多くの読者にとってこの物語は役に立たないかもしれない。五年間の物語の中で、偉業を成し遂げる訳でもないし、友情物語でもない。かといって感動エピソードがある訳でもない。
しかし、そこには情熱があり、追い求めたものがあった。
1:加入と独り立ち -しかし、妬みと渇望があり、-
高校から続けていた小説活動は、ある種の空想の具現化であった。
幼い頃から考えることが好きだった彼は、空想の中でヒーロー作品のその後のストーリーを空想し、独自の解釈でごっこ遊びに耽っていた。
中学校になれば、美術部に入り絵を描くことで自分の作品を作ろうとした。下手なりに自分の作るものを形にする楽しさを覚えた彼は、高校でも美術部に入ろうと思っていた。
だが、断念した。理由は明快だ。女子しかいなかった。なんの信念もない理由で、彼は美術の道を絶った。
そして、またしても何の信念もない理由で、彼は文芸部に入った。何となく面白そうで、週2でゆるく活動できるからだ。
そこで出会ったのが、小説の執筆だった。当時本なんて碌に読まなかった彼だが、初めて作ったルーズリーフ数枚の小説は、謎解きのエンタメ作品だった。
面白かった。そしてサークルの人に褒められた。なんとも陳腐な理由で、彼は小説執筆にハマった。
それからも読書量は増えた訳ではないが、ドラマ化の作品の推理小説を読みながら、またしても小説は出し続けた。いつしか誰かに読んでもらいたいと思いは積もり、クラスメイトに渡すようになったころには、すっかり書くことが好きになっていたのだ。
そして高校卒業後、彼は大学の文学研究会に足を運んでいた。
小説を書きたい。その思いで扉を叩くと、新入生の一人が部室に溶け込むように座っていた。今まで会ったことないような、どこかたどたどしい口調。初対面一番、仲良くなれないな、そんな上から目線の結論を出していた。
しかし彼が、後に文字通り「切っても切れない」サークル仲間となった伊奈であることを、彼はまだ知らない。
※
サークルに入り、同期は6人ほどであった。言うまでもないが、文学研究会である。
サークルの活動の主な部分は、小説の書評会と部誌での小説執筆である。書評会はノルマがあり部員全員が行う必要があったが、部誌はその限りではなかった。だからか、小説を書く部員はサークルの総数からグッと絞られる。彼の入った代も例に漏れずであり、主に部誌に掲載するメンバーは二人に絞られた。
彼はもちろん出し続けていた。そしてもう一人が、伊奈であった。
だが、彼らは違っていた。
彼は、ペンネームをつけなかった。ペンネームをつけるなんて作家ごっこしてるみたいで恥ずかしい、そんな捻くれた理由だった。
伊奈は、ペンネームをつけていた。新入生のペンネームは目立ち部員にはバレることもあったが、つけていた。
そして、後にもう一つ違っていたことがあることを知った。
彼の作品は面白くなかった。
そして、伊奈の作品は、面白かった。
※
部活にはやけに小説に熱心な先輩Aがいた。毎回部誌に作品を寄稿し、書評会でも目立つ発言をしていた。文学を愛するまさに文学研究会部員らしいその先輩は、彼の作品にも目を通していた。
「部誌、出してたよね?書くんだね」
電車でそう聞かれた。当然、本名で出していた彼の作品は出していたことはバレバレである。その日はぼんやりと他愛もない話をしたような気がする。
そしてその後、先輩Aから突然声をかけられたのだ。
「俺のサークルからの脱出に付き合ってくれないか?」
先輩Aの提案は、同人誌を作って文学フリマというイベントに参加するということだった。その理由は実に先輩らしく、「井の中の蛙大海を知らず」から抜け出したい。つまり外の世界で自分の力を試してみたいとのことだった。
小説を書くことは好きだった。自分の力を試したいという想いもあった。だから彼もまた、その計画に乗った。
脱出艇となるサークルの小説ノルマは、三万字だった。その時彼はせいぜい八千字程度しか書いたことがなかった。
四倍もの文量に及ぶ作品への挑戦は、死に物狂いだった。プロットは浮かんだが、どう書けばそんな文量が書けるのかなど知る由もなかった。とにかくプロットと睨めっこしながら書く日々が続くも終わりの見えない地獄が続いた。大学も二年生になったころ、第一稿の締切が迫っていた。春の陽気に一つ下の新入生が目を輝かせている中で、彼は徹夜の目を擦りながら学校への坂道を上っていた。
小説のために徹夜などしたことがなかった。迫る危機にもかかわらず、原稿のスピードは時計の秒針に追いつかない。とうとう原稿は未完のまま、8割がたの状態でPCを閉じた。そしてそれだけではない、彼は自信がなかった。その物語が面白いのか、わからなかったし、どのように完結させるべきかも、わからなかった。
その日、部室で赤入れがなされた。そして結末についても、考えていたものへの反応は微妙なものだった。
頑張った作品が評価されない悔しさ、そしてアドバイスへの的確さに、目を起こされた彼がいた。目まぐるしい二日間の中で、全力と玉砕を経験した。
そしてその壁を乗り越えて、彼は先輩Aと共に文学フリマに参加するための本が完成した。先輩の渾身の作品と、一緒に参加したもう一人の作品、そして人に揉まれ指摘を受け入れ作り出した、彼の作品を載せた同人誌である。
「ペンネームどうする?」
先輩Aは、彼に問いかけた。無論同人誌である、本名で出すことなどもちろん先輩は想定していない。そして彼もそうだろうと思っていた。
自分を冠する名など、彼に思いつきもしなかった。小っ恥ずかしさとアイデアのなさはペンネームに露呈した。
七氏野。
名無しの権兵衛、それ以上でも以下でもない。それは捻くれた彼の思考の露呈でもあり、おそらく、有名になんてなれない、という諦めでもあったのだと思う。
文学フリマの初参加は、想像以上の売れ行きで終わった。達成感と感動を噛み締めて、先輩Aと七氏野は会場を出た。
「最高だな」
「はい…!!」
確かな興奮、そして知らない人に手に取り読んでもらえるという感動。それが、七氏野の初めての文学フリマだった。
※
文学フリマでの出来事は、七氏野に強い自信を与えていた。自分の初めての経験、今まで書いたことのない文量と外での経験。井の中の蛙大海を知らずというべきか、とにかく大きな経験と達成感が、七氏野自身の大きな自信となっていたのだ。
ここまでできたのなら、自分でも面白い小説を作れるかもしれないと。人を感動させたり、何かを変えてくれるような話を作れるかもしれないと。
そしてその自信を一瞬でへし折られた出来事が、数か月とも経たないサークルでの夏合宿だった。
夏休みの湖の近くに位置する合宿所で行われたその二泊三日の場が言葉通りの「戦場」となることを、行きのバスから降りた七氏野は知る由もなかった。
「なんだろう、人が書けてないんだよね。ただのパーツっていうか。棒人間みたいな。感動させようっていう思いが見え透いてる感じもあるし」
テーブルを挟んで、先輩AとB、そして伊奈。普段部誌に作品を出している面々で開かれたその批評会は、前述の通り七氏野にとっての「戦場」となった。
音楽家などは「苦悩の末生んだわが子だ」なんて作品のことを例えることがあるが、七氏野にとってもその自負は少なくともある、いやあった。彼なりに自信を持ち、悩み書いてきたものは、それ以上に読み、書き、考えてきた面々に脆く崩されたのだ。
そして彼の自信をさらに打ち砕いたのが、同期である伊奈の評価であった。伊奈の作品は彼の作品と比べて面白いと評価をされていたのだ。同じ土俵で戦っている彼の作品が評価され、自分の物が評価されないことに、七氏野は悔しさと反発心を抱いていた。
悔しさを胸に、彼はいつの間にか泣いていた。批評会という名にふさわしく散々な批評をされた惨めさか。いや違う。ただただ悔しかったのだ。ここにいる奴らと同じ土俵に立てていない自分のことが。
だって、彼らの作品は面白かったから。心を打つ何かが、共感させる何かが、キャラクターの輝きが。自分にはなんで出来ないんだ。なんで、面白いものが出来ないんだ。
それが、とにかく七氏野は悔しかったのだ。
悔しさばかりで終わると思っていた合宿だが、確かに得るものがあった。
一つは、先輩Bとの会話、いやアドバイスだった。
先輩Bのことを、七氏野は好きだった。小説を読んでくれ、人間性が面白く、好き勝手いじれる面白い先輩、くらいに思っていたが、同時に一番語り合えるようにも感じていた。好きな作品や、創作の悩みを。
先輩Bは、飲み会で悔しさを吐露する七氏野に言った。
「小説ってさ、物語だから。読者を面白がらせる何かが必要なんだよ」
「俺はさ、小説を面白くさせることって3つあると思ってて。主人公の尖り、設定の尖り、主人公の成長・変化。このバランス感なんじゃないかなって」
確かに、面白いと思った作品は、三つとも当てはまっていた気がする。iPhoneに殴り書きしたそのメモの活字をにらみながら、七氏野は実感していた。
そしてもう一つ、読書会での「星進一」との出会いだった。
読書会は、後輩主催の初めてのレクリエーションで、ショートストーリーの小説一本をその場で読んで、その感想を話し合うというものだった。
そしてそこで読まれたのが、星新一の「おーい、でてこーい」だった。
電撃が走る、なんて漫画みたいな表現ありえないから。そんな風に思っていた七氏野だったか、この時ばかりはその言葉が一番しっくり来た。それくらい、「なんだよこれ」という作品だった。
前述の先輩Bからのアドバイス、小説を面白くさせる三要素。ぱっと見当てはまらさそうなこの短いストーリーに、見事にその法則は当てはまっていたことも、より驚いていた。
主人公の尖り。これは完全に主人公が記号化されていることで解決していた。七氏野が今まで書いていたものは、中途半端に主人公のバックボーンをいれているものの、人間性が欠けているような、身のない動きであった。しかし星新一の小説では、ストーリーの起承転結が終始重要視されており、そのために登場人物(特に主人公)に関しては、徹底して「ストーリーを動かす記号」という形を徹底していたのだ。
設定の尖りは、言うまでもなかった。「おーい、でてこーい」では、街に底の見えない・わからない大きな穴が出来ている。ゴミ箱代わりに使われてしまうその穴だが、ストーリーが最初からぐっと引き込まれたのは、その異質で不気味な穴であったことは、言うまでもなかった。
そして、主人公の成長・変化。これも星新一は飛びぬけていた。ここで言えば、主人公というよりもストーリーの結末だろうか。とにかくストーリーの始めと終わりで起こる大きな「変化」。それがとにかくずば抜けて印象的だった。
「これか」
七氏野は確信めいた結論を得た気がした。棒人間しか書けないのなら、いっそ棒人間として突き抜けてしまおう。感動じゃない、面白さ。驚きで突き抜けるのだと。
そうして、七氏野にとっての地獄の夏合宿は、「悔しさ」「一縷の望み」を同時に手に入れたような三日間として幕を閉じた。
※
そして、二回目の文フリの参加が決定した。他のメンバーも募って、2冊目の合同誌を作ることが決まった。
そしてそれが合図かのように、七氏野の戦いが始まった。今までただ面白いと思った作品をオマージュするように要素をなぞって書いていたような形から、完全にアイデア勝負の戦いになった。
とにかく、七氏野は小説を書いた。思いついたアイデアをそのまま、Word三ページほどの小説として落とし込む。まさに星新一のような小説の作り方をした。そして先輩に、サークルメンバーにとにかく読んでもらった。
そして、文フリの小説については、とにかくアイデアを考えることを徹底した。設定の尖り…、とにかくそこを打破する何かを考えていた。
「なんだよ、面白いオチってよ…」
オチなんてそう簡単に思いつくかよ。そんなんだったら夢オチなんて言葉出来ないだろ。そんな悪態を心でぼやいているとき、ふと思いついた。
夢オチを面白くしたら、どうなるんだろう…。
七氏野の新作のタイトルは、「夢堕ち」だった。夢でオトスのではなく、夢で堕ちる、堕落していく…。そんなワンアイデアから設定を尖らせて尖らせて、そう考えていくうちに出来たのが、カプセルホテルで正夢を見れるというその小説の設定だった。
そしてそうして出来上がったその作品は、今までにないくらいの達成感と「面白いものが出来た」という実感があった。
「やっと、自分の道を見つけたね」
文フリの小説の第一稿の読み合わせの会で、先輩Aから開口一番で言われた言葉は、七氏野にとってとにかく嬉しかった。自分が掴んだ手ごたえが、先輩とも共有できたこと。何よりもあの日ズタボロに酷評された彼らと同じように面白い作品が作れる土俵に立てたことが、何よりも嬉しかったのだ。
そうして出来上がった作品は、先輩Aだけでなく他の先輩や同期からも良く褒められた。自分の作り上げた作品を面白がって読んでくれていることが、何より七氏野に自信をつけさせ、そして興奮させていた。
そのまま二回目の文フリも良い形で幕を閉じ、また三回目の文フリも決まっていった。
そしてその順調に築き上げられた「自信」と「誇り」だが、次第に「大きな壁」と「傲慢」に上塗られていくのは、そのすぐ後であった。
※
三回目の文フリでも、同じようにアイデア勝負の作品を作っていった。恨みを持つ相手への「報復」を支援する団体と共に、恨みを晴らす話。だがしかし、夢堕ちの時のような自信ある作品にはならなかった。
それもそのはずだ、復讐という題材に対して、恨みを持つというバックボーンを持つ人間で作品を作っていった。棒人間になりきれないその人物を動かすには、七氏野はまだまだ力をつけていなかった。その大きな誤差に気づけなかったまま、その三冊目の文フリの作品は出来上がっていった。
それと同時に七氏野は、ある意味過去に得た「面白い作品を書けた」という栄光を忘れられないというなんとも惨めで陰湿な人間になっていた。
面白い作品、書けていないのか?俺は?
なんて本気で思っていた。それは本心半分、悔しさ半分だ。心のどこかで、三回目の作品には夢堕ちのような強い手ごたえを感じていなかったし、微妙かも、という自覚もあった。けれど一度納得できるものが出来たのに、そんなことはないというなんとも情けない自堕落な考え方で、言葉通りに堕ちていた。
作品性の違いなのかもしれないな。
なんて成り損ないのバンドマンみたいな結論を出すほど、彼は落ちぶれていた。確かに先輩Aとは明らかに作風が違っており、彼の作品も、彼が褒める作品に対しても七氏野自身は「難しいな」なんて思ってもいた。
そんなこともあり、七氏野自身で引いた一線はその溝を埋めれないままに、四回目の文フリに向かっていく。
そこで七氏野の落ちぶれは最高潮を迎えた。
きっかけはいくつかあった。大学のゼミナールが忙しくなってそもそも書く時間が取れなくなっていったこと。そしてスランプ状態が長引いておりその自覚も芽生え始めていたこと。先輩A自身の同人誌のクオリティへの追及。作品を認められていく他メンバーと、スランプを抜けられない自分。どんどん自分が必要でないんじゃないかなんて気持ちに堕ちていく。
そうして卑屈で最低な思いを胸にしたままの七氏野は、サークルの場で負け惜しみの一言を口にする。
「やる気なかったし」
そんな訳ないのは、七氏野自身が一番わかっていた。にもかかわらず、出来ない自分の情けなさ、次々完成させていく他メンバーへの妬み、混ざり合った絵具は真っ黒になって反吐よりも醜い一発となった。
そして四回目の文フリをきっかけに、七氏野は先輩Aと喧嘩になった。いやそんな綺麗な関係性ではなく、ただ単に落ちぶれた七氏野への的確な怒りをぶつけられたにすぎない。
何より七氏野はわかっていた。どれほど先輩が文フリのために準備し、気を回し、活動をし、手配をし、動き回っていたのか。それなのに妬み嫉みで言ってはならない一言を口にしてしまったのは、どうしようもない自分へのもどかしさだったのだ。
自分でやらなきゃならないんだ。
七氏野は混沌とした心を抱えながら、ただまっすぐにそう思った。自分で作ったサークルで、文フリという戦場に向かう。それが妬み渇望していた先輩Aのようになる、最善の道なのだと。
微妙な関係性のまま時間が過ぎていた中、七氏野は先輩Aに長文のLINEを送る。非礼を詫び、醜い心をさらけ出すような文面を送った。その文面によってしばらく続いた綻びを解消したと同時に、七氏野は切り出した。
「自分で、新しくサークルを作ろうと思います」
2:ポート結成 -しかし、結成には波があり、-
サークルを作ることを決めてから、七氏野はどうしようか考えていた。
サークルには二つのやり方がある。自分自身が入っていたように複数人での団体運営、そして一人で全て行う個人運営だ。
切り出してみたはいいものの、プランも何もない彼にとって、それすらも考えられていなかったのだ。しかし、七氏野自身の小説のルーツを考えていけば、その結論は容易に片が付いた。彼自身、小説は何かを作り追い求めるものであると同時に、人とシェアし分かち合うものであった。身近なサークルメンバーと一緒に作った小説について語り、その時間を楽しむことが、彼にとっては楽しかったのだ。ともなれば、サークル運営は団体運営と自然と結論が付いた。
そうなると問題になるのが、サークルメンバーだった。一番身近な例でいえば先輩Aであったが、彼は不定メンバーを募り合同誌を作るといった、いうなれば部誌に近い作り方をしていた。しかし七氏野にとってはそんなおおっぴろげに収集するガッツも、それを統率する自信もなかった。だから自然ともう一人固定メンバーを集めるという方向性になっていった。
「誰とやればいいんですかね」
部室にいた先輩AとBに、七氏野は相談していた。悩んでいた七氏野にとって、先輩たちへの相談というのは、ある種藁にも縋る想いであった。何が正解で、どんな選択をすれば良いのかなどわかるはずもない。自分で探し、自分で見つけ出し、自分で作り上げなければいけない。そんな不安が、彼らへの相談へという形で表れていた。
だが、彼らの結論は思った以上にあっけなく出た。
「伊奈でいいじゃん」
伊奈か。七氏野にとってその結論は意外であった。
そもそも、伊奈については先輩Aのサークルにもメンバーの候補に挙がっていた。けれど先輩Aの「なんかタイプが違うからな、合わないわ」の一声で、あっけなくその案は却下されていた(先輩Aのサークルであるから当然のことであるが)。また七氏野自身でも意外だと思った理由として「仲の良さ」があった。そう、そこまで仲が良いという訳ではなかったからだ。思い出してみれば、部室では先輩と一緒に何度も話していた記憶はあるが、サークル以外の時間で伊奈と飯を食べた記憶がなかった。こういうのって仲が良いもの同士でやるものではないのか?とも思っていた。
「伊奈って、そんな仲良くないですけどね」
「仲良いって、俺と七氏野もそんなもんじゃないか?」
「まあ、そうですかね…」
確かに、飯に行かなかったとか交流がなかったという訳ではないが、先輩Aと七氏野の関係性も、そこまで仲の良いという形ではない。どちらかと言えば、先輩Bの方が仲は良かった。仲が良いというよりも、ムキになったり対抗心を燃やしたりするけれども、心のどこかで尊敬の気持ちがある、父親や恩師に近いような存在であった。
「仲が良いとかじゃなくてさ、七氏野が一緒にやりたいかと思うかだろ。一緒にサークル活動をしたいのかとか、もっと言えば、伊奈の小説への姿勢をどう思えるかとかさ」
先輩Aの言葉を聞き、もう一度伊奈のことをじっくりと考える。伊奈は変わっていた。七氏野にも先輩Aにも、その言動を度々いじられ部室で何時間も彼の性格について談義を酌み交わされるほどに。伊奈は変わっていた。どこか距離を取っているのに、誰よりも距離を深めたいなんて思っているような図々しさがあった。伊奈は変わっていた。七氏野と同じように、ずっと部誌に小説を寄稿し続ける少数派に徹し続けるような奴だった。伊奈は変わっていた。七氏野が自信を持てた「夢堕ち」の没設定で小説を書いてくれと言ったら、二つ返事で了承して書き上げてくれるような、変人作家だった。伊奈は変わっていた。冬の合宿で夜中ずっと創作談義をしてくれるような、強い姿勢のあるやつだった。
「俺、誘ってみます」
七氏野はそういって、目の前の先輩たちに頭を下げた。
※
「俺さ、文フリのサークル作ってみようと思う。だからさ、一緒にサークルやってくれないか?」
七氏野は大学近くのつけ麵屋をすする手を止めて、しっかりとした声で言った。あの部室での会話の後で、七氏野は伊奈をLINEでラーメン屋に誘った。「ちょっと話したいことがある。嫌な話じゃないよ、多分」そんな回りくどい言い方で呼び出して、金曜の学校終わりのラーメン屋でサークル参加を切り出したのだ。部室で待っている間、先輩Bもいて、何故か彼も一緒につけ麺屋へと向かっていた。なんで着いてくるんだよ、断られたら気まずいだろ…。心の中で七氏野はぼやきながらも、どこかで正直、伊奈ならやると言ってくれるだろうと思っていた。そもそも、先輩Aとのサークル活動をしている中でも、伊奈はどこか羨ましがっていたからだ。そんな彼の思いが分かっていたから、二つ返事でOKと言ってくれるだろうと、どこか思っていた。
「サークルかー、うーん」
だが、伊奈の返事は煮え切らないものであった。どこか遠慮していそうで、どこか自信がなさそうな声だった。その様子に嘆きと驚きと少しのいらだちを湧きあがらせていた。隣でつけ麺をすする先輩Bは、驚きながらまた箸を動かしはじめる。
「なんで?文フリ参加したいって言ってたじゃん」
「うーん、まあそうなんだけどさ…」
伊奈はときより七氏野に文フリに出たいと嘆いていた。先輩Aの反応を知っていた七氏野は話半分で聞いていたものの、一緒にやれたらそれはそれで面白いかもと思っていたのだ。自分の思っていた反応とかけ離れた応答に、七氏野は若干、嫌かなり混乱していた。
「なんか、俺にサークル活動なんてできるのかなって」
「いや、できるって。俺も一緒に頑張るしさ」
「うーん、でもさ。俺ってその、ずっとひとりで書き続けてきたからさ、なんか合同誌とか、人と一緒にやるとか、出来るかなって」
「それは、うーん…」
彼の不安について、七氏野は百パーセントの確信をもって大丈夫とは言えなかった。誰よりも先輩Aの背中を見てサークル活動をしてきた七氏野にとって、合同誌の制作、ひいてはサークル活動の辛さは十分理解できているつもりだった。大学のサークル活動のように自分の小説をもくもくと書いて、寄稿して、部員に読んでもらう。そんな活動とはやはりサークル活動は違っていた。時にはサークルのメンバーの小説の添削もするし、その結果書き直しも起こったりする。先輩Aは一人でやっていたが、七氏野自身の力では、どうしても合同誌制作や販促、ブース設営などすべてにおいて一緒にやることは確かだった。手を取り合って、一緒にやることになる。
先輩Bがつけ麺を食べ終わることには、すっかり七氏野と伊奈は沈黙を貫いており、残ったあとわずかの麺がつけ汁につからないまま残っていた。先輩からのフォローも入り、再びサークル加入の会話はヒートアップしていくが、結局冷えたつけ麺を食べ終わる頃にも結論はつかずに、店を出ることになった。
その日は結局、サークルの結成は出来ず仕舞いで終わった。
※
「伊奈どうだった?やってくれるって?」
「あ、それが…」
先輩Aが部室に入って早々聞いてきたので、七氏野はことのあらましを一通り話した。先輩Aはじっくりと話を聞きながらも、なんでだよ!、突っ込んでいた。
「すんなりOKって言ってくれると思ってたんですけどね」
「まあ、プライドとかもあると思うしな」
「プライド?」
「今まで僕らが文フリ文フリってやってきて、参加できてこなかったわけだしさ」
確かに僕は結局伊奈を文フリに引っ張ることができなかったから、そう思っているとしたら、僕との結成に多少なりとも抵抗感があるのはわかるかもしれない。
「でも、やるなら伊奈しかいないと思ってるんで」
取り付く島がない。そんな言葉がしっくりくるぐらいにあの日は歯が立たなかった。けれども七氏野にとっては、彼と一緒にやることしか頭になかった。
「ふーん。じゃあ、僕もサポートするよ」
え? と七氏野がこぼすと、胸を叩いて任せろというような表情をする先輩Aがいた。
※
年末の時期になると、文学研究会では忘年会をやるのが恒例だった。その日は大学近くの古風な飲食店を貸し切って、バイキング形式での食事だった。ばらばらと席が配置されている中で、七氏野と伊奈と先輩Aが同席に座り、乾杯も早々にサークル結成の話に進んでいた。
やろうぜ!
いやでも。
そこを何とか!
うーん、でも。
起伏のない会話が続く中で、先輩Aは切り出した。
「じゃあ伊奈はさ、やりたいか、やりたくないか。それで行ったらどっちなんだよ。文フリ参加したいって言ってたけど、そこのところどうなんだよ」
いや、メンバーに入れずに進めてた俺らがそれ言っちゃうんだ。と思いながらも、七氏野は伊奈の回答が気になっていた。
「それは…やりたいですけど」
初めて伊奈の本音を聞けた気がした。自信のなさげな声にまくしたてるように、先輩Aは続けた。
「じゃあ、やればいいじゃん」
「いや、でも。やれるか自信がないですし」
「やりたいんだろ、やればいいじゃん」
「そうですけど…」
何かきっかけがあれば、そんな状況だった。七氏野はじっと聞いていたところから、伊奈に向けての言葉を探した。
「この一年間さ、色々創作のこと話して、部室でも合宿でも話して、一緒に部誌も出し続けて。このサークルで一緒に文フリのサークル作るなら、伊奈しかいないと思う。一緒にやろうよ。やりたいんだろ。一緒に文フリ出ようぜ」
ただまっすぐにその想いを伝えた。その後数分また話し続けて、伊奈の心はようやく前を向いてくれた。
その日の夜、伊奈は七氏野にLINEで、「よろしくお願いします」と送ってきた。「よろしく」と七氏野は返し、新しい文フリのサークルは結成した。
※
新しい文フリのサークル名は、「文芸サークルポート」となった。純粋に楽しく小説を書き続ける場にしていきたい。という思いから、港みたいに創作の場としてのサークルにしたいという思いから、港という意味の「ポート」にした。
そこからは、怒涛の制作期間に映っていった。目下の問題は、次の文フリで出す合同誌だった。残り五か月というタイムリミットの中で、二人でファミレスで話し合った。合同誌なら、何かしらのテーマを設けた方がいいかとなり、いくつか出し合って「海」がテーマになった。文字数制限はとにかく時間がなかったので、五千字以上という最低ラインだけ設けて行うことにした。
「でも、間に合うかな…」
「うーん、確かに…」
テーマ紙になるということは、イチから作品を書き上げなければならなかった。全力で書き上げるつもりであったものの、もし刷れなかったら…。そんなことが頭をよぎるのは、初出展である彼らにとって当然であった。
「じゃあ、個人誌作ろう」
「個人誌?」
「うん。自信のある作品一作で、それぞれ個人誌作ればサークルとして本が出せなくなることはないし、なにより自分たちの読んでほしい自信のあるもの出せるし」
「確かに、いいかも」
そうして、それぞれ一冊ずつ個人誌の校正を進めながら、新作を書くという結論で終わった。
だが、そこでも七氏野にとっての苦戦は続いた。そもそも彼は自分自身で校正をしたことがなかった。本のテンプレートを決めて、行数と文字数を確定してレイアウトも決めていく。どれもこれも先輩がやっていた以前のサークルとは違い、今回は自分一人でやらなくてはならなかった。一方で伊奈は、文学研究会の製本を担当していたこともあり、校正については慣れていた。サクサクと進む彼にとにかくやり方を聞き、やりとりを続けて何とか中身の校正は完成した。
そして次に来たのは、表紙の制作だ。表紙なんて校正以上に経験値がない。さらに七氏野自身の個人誌だけでなく、合同誌の表紙も作っていかなければいけない。とにかくいろんな小説の表紙を見ながら、持っていたコンデジで撮影した合宿での海の写真をベースに、合同誌の表紙を作ることにした。大学のパソコンルームで、ソフトなんて持っていない七氏野はパワーポイントで格闘して、中々納得できない表紙と向き合っていた。
そして個人誌についても、表紙をどうするか悩んでいた。大学での片思いの話。そのテーマならと、大学の構内でイメージカットになりそうな場所をいくつか撮り、やはり合同誌の表紙と同じように、写真ベースでの制作にした。
表紙を作ってみると、初めての挑戦すぎることもあり、デザインの難しさに驚いた。一日かけて精一杯作った表紙が、翌日見てみるとどうしようもない駄作に見えてしまった。必死に作った表紙のレイアウトが、どこかのサークルの表紙とレイアウトが被ってしまい、なおかつそのクオリティの高低差に落胆して没にしていった。トライアンドエラーを繰り返しながら、ようやく表紙が完成したころには、最初に作った表紙とは見違えっている完成度にそこはかとない達成感を覚えていた。
そうして、個人誌の準備は整い、あとは合同誌の小説を完成させるのみとなった。
※
「なあ、進捗は?」
「うーん、まだ半分…」
「まじかよ…」
文フリまで残り二ヶ月を切ったころ、七氏野も伊奈も第一稿すらも完成できていない状態であった。いろいろな要因はあった。個人誌の制作もあったこと、そもそも書き始める時期が遅すぎたこと、そして二人とも驚くほど執筆スピードが遅いこと…。だが言い訳しても、時間は待ってくれず、締切は伸びてくれなかった。
「とにかく、なんとしても出さなきゃ」
「うん、最悪個人誌は出せるけど…、でもね」
この時点で、二人とも校正も表紙の制作も終わっていて、既に製本所への発注が済んでいた。そういう意味で言えば、彼らが正真正銘一作も持って行けずに赤っ恥を売りに文フリに参戦する、という最悪の事態は免れられてはいた。
「でも、合同誌を出さないと。サークルなんだから」
「そうだね」
そう、七氏野も伊奈も、個人ではなくサークルとしての参加なのだ。であれば、彼らにとってサークルでの合同誌の制作は必須であった。
※
「完成したね」
「うん…でもね…」
完成はしたが、失敗もしているという状態であった。既に製本が出来る期限、要するに納品日は過ぎており、そういった意味では彼ら二人は合同誌制作の戦いに完全敗北していたのだ。
「こうなったら、個人誌だけで?」
「うーん、いや」
「じゃあ、どうやって?」
「自分たちで製本すればいい」
七氏野の提案は、コピー本での配布だった。文フリでも何度か見たことがあった、コピー用紙に印刷したものをホチキス止めした本。それであれば自分たちで時間を見つけて印刷をすれば、文フリ当日には間に合う。
「でも、それでお金とる?」
「それはなー…」
確かに、通例で言えば、コピー本は販売する本のおまけ程度の立ち位置で、それを売るというサークルも中々いなかった。さらに新しいサークルである自分たちがやるのであればなおさら、そんなやり方はどうなの? という思いがあった。
「フリーの…コピー本として売ろう」
開始早々幸先不安。そんな漢字だらけの結論が頭をよぎる中で、どうしようもない彼らは、コピー本での初合同誌という、なんとも言えないスタートを切る決心をした。
※
コピー本制作の日、七氏野と伊奈は大学の最寄り駅でもお互いの中間地点でもない微妙な場所のサイゼリアに行った。中々中間地点でのコピー機のある場所(しかも安い)がなく、仕方なく近場でコピー機のありそうなその場所を選んだ。しかし、検索してヒットしたお店は運悪く閉まっており、結局コンビニの印刷機ですることになった。合同誌の仕上がり同様に、幸先の悪いスタートである。
コピー本とはいえ、表紙ばかりはこだわりたいなとなり、カラーでの印刷をした。一冊で総額二百円。それなりの額を払った紙の束を携えて、七氏野と伊奈はサイゼリアへと降り立ったのである。
「あと何部?」
「うーん、二十?」
もくもくと紙を折り、ホチキス止めをする二人。スパゲッティはとうに食べ終えていたため、ドリンクバーと共にガソリンが入った彼らは、もくもくと作業にいそしんでいた。
「まさか、合同誌がフリーペーパーになるとはな」
「たしかに。でも、取ってもらえるかな」
「大丈夫だよ、きっと」
準備が大成功したわけではない、躓きも多い中での、文フリ初サークルでの初出展となってしまった。開始早々大きな波に見舞われたと言わざるを得ない。
しかし、情熱なく惰性でやっていたなんてことは微塵もなかった。惨めで、後悔して、辛い中でも、彼らの出せうる力と情熱と魂を込めていた。本気じゃないわけがなかった。今までおんぶにだっこだったサークルを抜け出して新しくサークルを作った七氏野。不安ながらもサークルの加入を受け入れて、初めての文フリ参加に挑んだ伊奈。そして何より、自分の作品をまだ見ぬ読者に届けたい、誰かのための小説を作りたい。その想いは、その情熱は、一つ一つの製本に、押し込まれたホチキスの芯に、確かにこもっていた。
「絶対、成功させよう」
「…うん」
※
文フリ当日になった。初めてではない参加ながらも、自分たちの力で作っていったサークルでの参加に、七氏野は今まで以上の緊張を感じていた。そしてそれは伊奈も同じであり、会場に着いた二人は緊張しながら顔を見合わせていた。
「レイアウトどうしようか」
「うーん。ランチョンマット買ったから、それに置こう」
本を立てた方が見られやすくなる、なんてテクニックを知らない彼らは、最低限の備品だけを携えての参加だった。平済みで置いた個人誌二冊とコピー本を見て、七氏野はとうとうこの日が来たと実感した。個人誌の値段はそれぞれ百円と二百円。ほぼほぼ印刷費回収くらいの値付けだったのは、安い方が売れるだろうという安直な値段設定と、まだ確かな自信を持てない自分たちへの現れであった。
「それでは、文学フリマ、スタートです!」
運営からのアナウンスが入り、文学フリマがスタートした。会場には次々と一般参加者が入ってきて、そろそろと歩きながらブースの本を眺めていく。自分たちの本も見てくれ、と熱のこもった視線を向けていても、中々ブースに目を止める人は少なかった。
一人、一人と人は去っていき、その姿を目で追うしかできない二人は、ただじっとまだ見ぬ読者を待つしかなかった。
「あのー…」
え、来た?? と思ってその声の主を見ると、先輩Bだった。
「なんだよ、その顔」
「いや、何でも」
「悪かったな、お客さんじゃなくて。まあ、お客さんだけどな」
そう言って先輩Bはコピー本を手に取り、個人誌二冊を購入した。
「ありがとうございます」
「じゃあ、頑張ってな」
初の購入者は身内、なんともリアルなその経験は、ただじっと一人目を待っていた二人にとっては、すごくありがたいことであった。自分たちの知らない人に買ってほしい、それは確かであるが、やはり身内でも手に取って、興味を持って、購入してくれるのはとにかく嬉しかった。
それからも、来ては離れていく人々の姿を見つめる時間が続いた。そうして開始から二時間が過ぎようとした時、もう今日は無理かと諦めた時だった。
「あの、これってフリーペーパーですか?」
「あ、はい!フリーペーパーになってしまったんですけど、一応合同誌です!」
手に取ってくれたのは、女性のお客さんだった。じっくりとフリーペーパーを読み進めながら、持っているトートバックにそれを入れて、そして平済みのそれぞれの合同誌に目をやった。
「これ、少し読んでもいいですか?」
「もちろんです!」
お客さんは冒頭からじっくりと読み進めた。話しかけるのもどうかと思った二人は、そのまま黙って下を向いたまま、とにかく試し読みの邪魔にならないことを徹底した。
「ありがとうございます。これ二冊ともください」
「ありがとうございます!二冊で三百円です」
「すみません、千円からで」
「あ、はい」
初めて自分たちの作った本が売れた。目の前で起こった小規模の奇跡がただただ嬉しくて、笑みがこぼれながらも、お釣りを用意する手は若干震えていた。
「こちら、お釣り七百円です。ありがとうございます!」
お客さんが去った後、七氏野と伊奈は目を見合わせて、頷いた。一つ本が売れた。まだ見ぬ読者が、購入者に変わった。その事実を噛みしめていると、フリーペーパーを気になったお客さんがまた、ブースに訪れた。
コピー本カラーなんですね。
百円、安いですね。
へー、テーマが海…。
色んな感想を呟きながら、いろんな人が本を手に取ってくれた。フリーペーパーだけもらってくれたり、どちらかの個人誌だけ買ってくれたり、全部持って行ってくれたり。どれも二人にとっては新鮮ですごい驚きであり、想像していた何倍も嬉しい出来事であった。
Twitterを見てきました、と言ってくれた人もいて、自分の小さな呟きが見知らぬ誰かの興味を惹いていたことが、驚くべき出来事のように感じられた。
喜び、驚き、笑い、落ち込み、そしてまた嬉しがる。喜怒哀楽の表情のほとんどを使った初出展は、あっという間に終わった。
フリーペーパーは完売。個人誌も数冊を残してほぼ買ってもらえた。想像以上の出来事に、震えあがった二人は、目を見合わせた。
「最高だな!」
「…うん!」
いつかの文フリの日を思い出す。興奮した胸の高鳴りと、激しく押し寄せる達成感。そして喜び。初心に帰った七氏野の、ポートとしての初参加はこうして終わった。
ポートの航海は、ここから始まっていくのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
