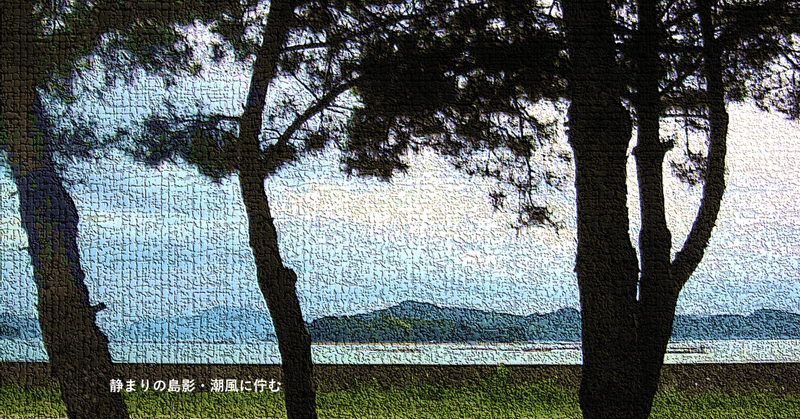
ワタクシ流☆絵解き館その242「白馬賞」青木繁・幻の受賞作品へのアプローチ⑧⇒追補「唯須羅婆拘楼須那」
■ 「白馬賞」青木繁・幻の受賞作品の手がかりのなさ
青木繁は、1903(明治36)年、属する絵画会の白馬会に出品した絵画群で、《白馬賞》を受け画壇デビューを飾った。
「ワタクシ流☆絵解き館その194《白馬賞》青木繁・幻の受賞作品へのアプローチ④⇒『唯須羅婆拘楼須那』」と題した過去の記事で、青木繁が「白馬賞」を受賞した作品群の一枚で、発表後行方も知れず全く手がかりのない幻の絵「唯須羅婆拘楼須那」について、その読みと図柄を推測してみた。詳しくは、その記事を読んでいただきたい。
■ 須羅婆拘楼須那は、「スーラセーナ・クルシュナ」
その読みは「ユー・スーラセーナ・クルシュナ」と解釈し、インド神話の神ヴィシュヌの8番目の化身であるクリシュナを描いたと推測した。そして、クルシュナ=一般的に通用しているのはクリシュナ ( 以下クリシュナで通す ) のイメージは、「わだつみのいろこの宮」の山幸彦を連想させると気づいたことを述べた。
インド神話を白馬会出品作の題材に選ぶほど、当時インド神話にのめりこんでいたことが、そののちに描く「わだつみのいろこの宮」の発想、造形の、深い処での水脈となっているかもしれないと考えたわけだ。
なお、スーラセーナは、インドの16大国のひとつスーラセーナ国を意味し、この国はヤーダヴァ族の国であり、その族長がクリシュナであることで、「スーラセーナクルシュナ」となっていると解釈した。
今回は、青木がインド神話の中から、クリシュナを題材に作品を制作した背景を探ってみた。
■ クリシュナ神話が紹介され始めていた
青木繁の《白馬賞》受賞は1903(明治36)年、同年の早稲田大学出版部の出版物に、高桑駒吉『印度史』がある。この書では、インド神話の英雄クリシュナの事跡が詳しく語られている。
クリシュナについては、世界三大叙事詩と称される『マハーバーラタ』に多く語られていて、明治30年代には、この叙事詩が、知られつつあったと思われる。青木がどういう書物を読んでインド神話の知識を得ていたかはわからないが、まだ広く一般に読みやすい解説書は出ていなかったから、『マハーバーラタ』に触れた学術書であったと思われる。
『印度史』は学術書であったが、それから11年後の1914(大正3)年に、総合文芸雑誌『處女』 ( 出版は女子文壇社 ) の6月号に、ポーランドの小説家、ノーベル文学賞受賞者ヘンリク・アダム・アレクサンデル・ピウス・シェンキェーヴィチの「讃頌(さんしょう)」という短編が載っている。これは、万能の神クリシュナの、奇蹟の一場面を切り取った読み物である。
『處女』には執筆者に吉井勇、小川未明、佐藤春夫、川路柳虹ら著名な書き手たちの名が見える。

■ クリシュナを描いた日本人画家の絵が文展にも出ていた
1911(明治44)年9月開催の第5回文展に、朝井観波が、「クリシナ」という題で日本画を出品している。下の挿図。
クリシナは当時の表記で、クリシュナのことである。こういう絵が、公募展に出品されるということは、クリシナというタイトルだけで、ああ、インドの英雄の話か、という程度の理解は持たれるほどになっていたことを示すだろう。


朝井観波の「クリシナ」は、下に再掲した以前の記事に記述したような伝承に沿った場面であろう。これがインドの絵画では、一例として下の挿図のように描かれる。
「web版「インド思想史略説 」に、簡潔にこう説明されている。(野沢正信ー 執筆時沼津工業高等専門学校 助教授)「第2節 ヒンドゥー教の神々」の章
バガヴァットに対する信仰を説いた10世紀頃に成立したと推定される『バーガヴァタ・プラーナ』によれば、クリシュナはマトゥラー周辺にヴァスデーヴァの子として生まれ、幼い時から怪童としてヤムナー川に住む毒竜カーリヤを退治するなど、さまざまな奇蹟を行い、ついにはマトゥラーの悪王カンサを殺して人民を救った英雄として描かれる。また美貌の牧童として描かれ、笛の名手で夕べにヴリンダーヴァナで笛を吹くと、牧女たちは恋情をかき立てられ、惹きつけられて、彼のもとに集まり、歌い踊り、奔放な愛に戯れる」



18世紀初め バハーリー作 インドの絵画
■ インドの宗教・文化を絵画化する気運が底流にあった
1911(明治44)年第5回文展には、荒井寛方《竹林の聴法》が、1916(大正5)年の第3回院展には、筆谷等顔の「貧者の一灯」という絵が出ている。
これらは仏陀を描いた宗教画と言える絵であるが、インド主題の作品のひとつであり、インドの宗教、神話を絵画化する気運が、明治後半から大正前半の芸術家の中にあったと見ることができる作例である。


■ 青木の絵は、「わだつみのいろこの宮」の構図のエスキース (草案画稿 ) だったか?
さて、では青木の描いた絵の図柄はどうであったという、肝心のテーマである。以前の記事、「ワタクシ流☆絵解き館その217 ヒンドゥー教の神クリシュナと、青木繁《わだつみのいろこの宮》」でこう述べた。再掲する。
■ 《わだつみのいろこの宮》の山幸彦と共通する要素
⭐ 樹下・秀麗な容貌・霊力
ヒンドゥー教の神々の中でも最も著名と言っていいクリシュナは、全知全能の祖神ヴィシュヌの10の化身の内、8番目の化身である。クリシュナがどのような様子で描かれるか、その特徴は、次のとうり。
① 横笛を携えた、まるで美少女にも見える秀麗な容貌の美青年
② 樹の中に現れ樹の下に立つ
③ そこにいる人をたちまち魅了、陶酔させる霊力を持つ
■ 《わだつみのいろこの宮》の山幸彦と共通する要素2
⭐最愛の、宿命の人の存在
クリシュナの伝説には、一人の主要な女性が登場する。ラーダーである。彼女は、祖神ヴィシュヌの妃ラクシュミーの化身とされる。クリシュナには最愛の、至高の存在だ。しかしラーダーはクリシュナ妃ではない。つまり二人の仲は、永遠の、宿命のロマンスとして位置づけられる。
クリシュナは、マトゥラー国の暴君カンサ王の悪政に苦しむ民衆の声を聞いたヴィシュヌ神が、カンサ王を倒すため化身した神である。その役目を果たし、カンサ王を倒すのだが、そのとき以降、ラーダーはクリシュナのそばから消え去ったとされる。
これは、海幸彦が地上に戻って兄海幸彦との戦いに勝つ出来事や、地上に来て一子ウガヤフキアエズノミコトを生んでだけで、豊玉姫が山幸彦の処から帰って再び会うことがなかった展開、また山幸彦は身まかるまで、豊玉姫を深く思い続けた結末までの構成に、類似しているように思えてくる。
上の連想をふくらませれば、次の点が青木の「唯須羅婆拘楼須那」には要素としてあったと推測する。
📌 1. 樹下の姿を描いていること
📌 2. 美しい風貌に描いていること
📌 3.宿命の人ラーダーをともに描いていること
この3点を必須と想定すれば、それは、明確に意識するまでには至っていないだろうが、山幸彦豊玉姫の姿が浮かんできて、後年描く「わだつみのいろこの宮」の構図のエスキース (草案画稿 ) と言っていいものだったのではないだろうか。
「大穴牟知命」にしても「わだつみのいろこの宮」にしても、青木の大作絵画の構成の大枠は、優れた男神と、その男神に魅せられて、男神を助け、やがて去ってゆく女が出会う場面というシチュエーションである。
画家として世に出るときから、青木の脳中には、そのシチュエーションが画題として棲みついていたという気がする。
『古事記』や『リグヴェーダ』や『聖書』に魅せられ耽読した青木だが、その中から、上に述べたように、共通して見いだせる場面として、男が自分の運命に、決定的な出来事をもたらす女に出会った場面に目を止め、そのときの男の、忘我であったり、放心であったりする状態を想像していたのではないかと思う。
令和5年9月 瀬戸風凪
setokaze nagi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
