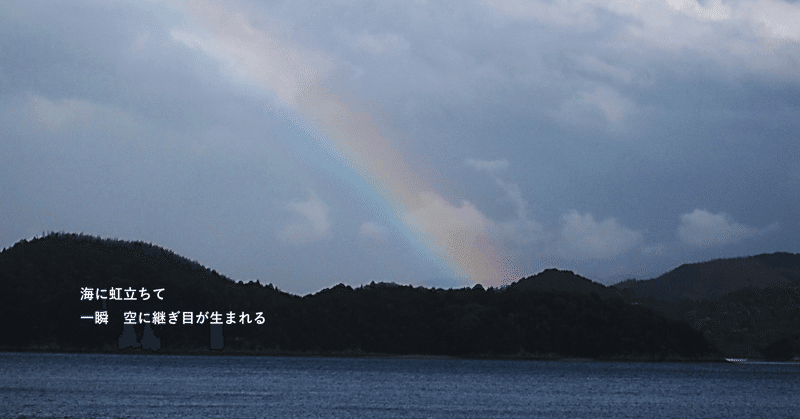
俳句のいさらゐ ▩▩▩ 松尾芭蕉『奥の細道』その三。「象潟や雨に西施がねぶの花」
◩◩
『奥の細道』には、童女や若い女性をイメージさせている句が以下のようにある。
草の戸も住替る代ぞひなの家 芭蕉
雛飾りの色彩を思わせて、そこにいる童女を浮かび上がらせている。
次の句。
まゆはきを俤にして紅粉 (べに) の花 芭蕉
尾花沢から立石寺への途中の吟。
まゆはきは、眉掃きで小さな刷毛。妙齢の女性の面影が立ち上がって来る。
次の句。
早苗とる手元や昔しのぶ摺 芭蕉
上の句は、信夫郡の文字摺石を見物したときの句である。同行者曽良の『曽良書留』には初案として
五月女(さおとめ)に仕方望まん信夫摺 芭蕉
として載っている。こちらの方が、より若い女性の姿を前面に出している。
次の句
しほらしき名や小松吹く萩すすき 芭蕉
これは、現在の金沢近郊の小松市での吟。土地褒めの句であるが、小松の名に、「しほらし」と形容を与えるのは、童女の面影を重ねているように見える。

◩◩◩
『奥の細道』を貫いているのは、目で確かに見た事象を句にするという態度だが、引いた句は、その基本的な創作の構えに立った上で、一巻の演出としてやわらかな空気感を出すために、童女や娘の雰囲気を持ち込んだ意図が感じられる。
芭蕉は旅をしながら、『奥の細道』を心中で書き続けていた。密命を受けた探索の旅などという、文芸を真に愛好する心からは、決して出てこないような奇妙な詮索が幅を効かしているが、はっきりと、創作のための旅であったと言い切れる。そこに行って、見て、そのときに去来した思いを句にする。それが旅の全てであった。
ときには、感嘆を表に出し、ときには、雅語とは反対の生活用語を使い、ときには、絵画的装飾を意図して、句を選んでいる。『曽良書留』にはあって、『奥の細道』では捨てた句もある。硬軟と雅俗を深慮して句を選び配している。

◩◩◩◩
「象潟や雨に西施がねぶの花」もまた、その意図に含まれる句だと言える。しかし、前掲の句と異なるのは、西施というすでに伝説の厚い衣をまとった美人を、あえて出して来たところだ。
この用い方は、『奥の細道』のゆるやかな統一感、まとまりを崩しているように私には思える。
和歌俳諧の詩文を嗜む者なら知らぬ者のない、有名な歴史上の美人を比喩に出すと、目に映るものを、臨場感を大事にした巧みな動詞の使い方で描き止めて来た『奥の細道』の手法から考えれば、西施の名に付随している陶酔の美のイメージに、寄りかかり過ぎることになるからだ。悪く言えば、既成の形容に堕して、陳腐な比喩になりかねない。

◩◩◩◩◩
そういう、紀行全体の完成度にかかわる句の危うさを、芭蕉は充分にわかっていたはずだ。それでもなお、雨にねぶの花けぶる象潟の第一印象は、西施の故事で揺るぎなかったのだ。
象潟を訪ねることが、いつからか心に棲みついた芭蕉の宿願であり、それだけに、この場所は幾度も幻想を愉しんできて、すでに芭蕉の心中には、この世ならぬ美しい情景が出来ていたというべきだろう。
その幻想を裏切らない絶景を、芭蕉は象潟で見た。それを表現するのに、「西施」は、選ぶのに抵抗のない言辞であり比喩だったと思う。
「西施」の形容を、この情景こそに与えるべきだという明快な信念が、この句を陳腐にも、凡庸にもさせなかった。
そして、二度と西施の形容を私たちが使うことは出来ない「止めの作品」になった。以後、美しさの形容に「西施」を持ち出せば、全て、凡句と言って間違いない。
◩◩◩◩◩◩
すでに大きく変貌し失われてしまった歌枕の風景、名所の風景はいくつもある。しかし、芭蕉のこの句があるゆえに、今日では、田野と化している象潟の往年の優美な景を偲ぶ心には、同じく今は往年の姿を失ったどの地を思うよりも、深い惜念がある。
現実に今日も存在する場所でありながら、象潟、とつぶやくだけで、今日の象潟は忘れて、芭蕉の作り出した文学的幻想空間に引き込まれるのだ。
令和5年4月 瀬戸風 凪
setokaze nagi
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
