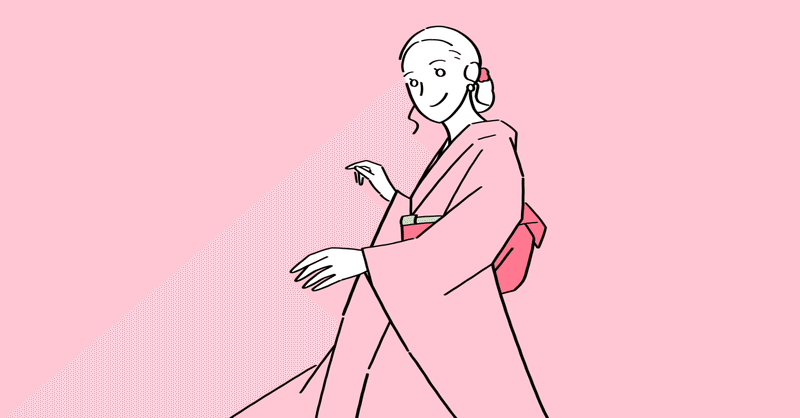
僕とかぐや姫
みなさん、こんにちは。
大学3年の音谷といいます。音谷は「おとや」と読みます。
みんなからは「よしむね」と名前で呼ばれています。
あ、そんなことはどうでもいいですよね。すみません。
今日みなさんに聞いてほしいのは、僕の2度目の失恋の話です。
あ、行かないでください。聞いてください。暗い話じゃありません。暗くはないです。
しいていえば何味か分からないアイスクリームを食べたような。そんな感じです。
2分で終わる。いや、終わらせるので、ぜひ聞いてくれませんか。
僕が彼女と出会ったのは、今からちょうど1年半前のことです。
出会ってすぐに僕らは恋に落ちました。
寒空の中、かじかむ手を2人であたためあい、満開の桜の下でお弁当をつつき、バイクを走らせながら打ちあがる花火を見たりして、いくつかの季節を共に過ごしました。
同棲を始めたのはちょうど半年前のことで、昨日が同棲半年記念日。
記念日といっても、何か祝ったわけじゃないんですけど。
この節目をむかえて振り返ってみると、彼女は半年前とかなり変わってしまいました。
半年前の彼女と、今の彼女の印象は、まるで違います。
そうですね。誰かに「彼女らは双子で、半年前に姉と妹が入れ替わったんだ」といわれたら「な~るほど!」と手を打ってしまいそうなくらい。
それくらい変わってしまったんです。
どんなところが変わってしまったかというと、まるで100年の封印から解き放たれたモンスターのように、この世を謳歌し始めたといいますか。
のんびり過ごしていた2人の時間が嘘だったかのように躍動的に、社交的に、彼女は毎日を楽しむようになりました。
「毎日やりたいことが多すぎる。体が2つあったらいいのに」
最近の彼女の口癖です。
2人暮らしがキッカケだったのか、別のことがキッカケだったのか、
どうして変わってしまったのか、直接理由を聞いてみたことはないんですけどね。
そんなある日、ことは起こりました。
それは僕がTVでゴルフの試合を見ながら、そうめんを湯がいていたときのことです。
ガチャリと玄関で音がして、彼女が帰ってきました。
僕は「おかえり」とキッチンで少し大きな声を出します。
あ、そうだ。彼女の紹介を先にするのを、忘れていました。
実は彼女、おとぎ話に出てくる「かぐや姫」なんです。
そうです。そうそう、あの竹の中にいて、おじいさんに発見された……
あのかぐや姫です。
有名な話ですよね?
実は僕。最近まで、かぐや姫のちゃんとしたストーリーを知らなくて。当の本人に教えてもらいました。
本人に教えてもらうって、すごくないですか?
腰までとどく黒髪を、途中でひとつに束ねた彼女はいつも薄桃色の着物を身にまとっています。
そう、本物感ありますよね。
彼女は「かぐや姫」として現代に生きているんです。
外は気温34℃の炎天下だというのに、彼女は一粒の汗も流していません。
女優は顔に汗をかかないというけれど、彼女もまたそうした女性の一人なのでしょうか。
「そうめん食べるけど、いる?」
そう尋ねた僕に彼女は「大丈夫」と答え、ストンとソファに身を沈めて
「そうだ、よしくんにあとで一緒に考えてほしいことがあるんだ」といいました。
僕は煮え切ったそうめんをザルにあげ、水道の水で冷やしながら
「なんかまた変なこといってるよ……」とげんなりしました。
「あのね、プロポーズされてるの。5人の人に」
彼女はそうめんを食べている僕に向かって、そういいました。
僕はびっくりして
「プロポーズって…… あのプロポーズ?」
と聞いてしまいました。
だってかぐやんは僕と同い年で、まだ大学生です。
あ、すみません。彼女のことを「かぐやん」と呼んでいるのでつい。
次から「かぐやん」で通させてもらっても、問題なさそうでしょうか?
「もちろん断ったよ。でもみんな、理由を教えてほしいってしつこくて。それでいっちゃったの。『ある条件を満たしてくれたら結婚する』って。だからその『ある条件』を、今からよしくんと考えたいんだよね」
みなさん、どうですか?
怖いですよね?
僕も怖いです。
かぐやんのことは置いといて、まず先にプロポーズしてきた男性について考えてみますね。
5人……?
偶然だとして、同時期に5人は多くないですか?
そして、断ったら普通、諦めませんか?
プロポーズするって、相当の覚悟だと思うんです。
そんな一世一代のプロポーズを断られたら、普通、落ち込みますよね。
「ショボーン」とかなって、かぐやんの顔なんか見たくないはずですよね。
それなのに「理由を教えてほしい」って、なんたるメンタルの持ち主なんでしょうか。
傷に塩を塗りつける行為ですよね。そんな猛者が5人そろってるって、どんな状況ですか。
かぐやんは続けます。
「ある条件はさ、5人全員『できそうでできない』ことにするの。そうすれば誰も条件を満たせない。誰にもできないと分かれば、全員納得して諦められると思うの」
……うん。
確かに男という生き物は、何かに挑戦するのが好きな生き物だ。そして並々ならぬ努力の果てに、どうやっても手に入らなかったそのときには「これだけやったんだ」という変な充足感につつまれながら、泣く泣く諦めるという構図が成立する。
うん。
いや、なんだそれ。
危うく、かぐやんのアイデアに飲み込まれそうになってしまった。
……こんなんでいいのか、俺。一応彼氏だよな、俺。
ここらで「誰だよ、俺の彼女にプロポーズなんかしたやつ。出てこいや!」とか、かましておいたほうがいいんじゃないか。
僕は急に、彼氏風をふかせたくなりました。
みなさんもそんなとき、ありませんか?
「どんなのがいいと思う?」
上目遣いのかぐやんは「その顔をはずるいよ」と思うくらいかわいくて。
だけど僕は「半年前のかぐやんのほうが好きなんだよ、いつ戻ってくれるんだよ」と心の中で語りかけます。
「そうだね……」
かくして「できそうで、できない難題を考える」という訳の分からない時間がスタートしました。
「まずは石作さんね。この人は歯が全部銀歯なの」
「……え、全部?」
「だからこの銀歯を全部、金歯にしてくるとかはどうかな?」
「……金?」
「そう、金」
「え、それはさ。万が一、石作さんが銀歯を全部金歯にしてきたら、かぐやんは金歯まみれの石作さんと結婚することになるけど、いいの?」
「いいよ、もちろんだよ、約束なんだから」
石作さんの銀歯は正確にいうと、上下合わせて16カ所あるという。それらがすべて金になったら目を見張らずにいられる自信はない。
「じゃあ、石作さんは金歯ね。次、庫持さん。庫持さんには育てるのが超難しいっていわれてる梨を育ててもらおうか」
「……梨?」
「うん、前にTVで見たんだけど。ある農家さんで、希少価値の高い梨を3年かけて育て上げたんだって。それがね、真っ白な梨なの」
「白い梨」
「そう。なんでも土に『あるもの』を混ぜないとできないみたい。企業秘密らしいんだけど。農家のおじさん、めちゃくちゃ怖い人だったから、たぶん庫持さんが聞きにいっても教えてくれないし、素人が育てられるものじゃないと思う」
「なんかさ、庫持さんの難易度、石作さんに比べて高くない?金歯はお金と勇気があれば、歯医者さんでやってもらえるけど、梨を育てるって時間もかかるし」
「何いってんの。気合いと忍耐さえあればできるよ。愛の力があればね」
「……」
「次は誰?」
「次は阿部さん。阿部さんは実家がお金持ちなの。ほら初白町の丘の上の大豪邸。あれ、阿部さんの実家」
「え、あそこ……!?」
「よしくん、どう思う?どんなことなら、できそうだけど、でも自分には無理だって思う?」
「うーん……」
「分かった。わらしべ長者はどう?最初は麻のひも1本からスタートするの。その麻ひもと何かを交換してもらって、また交換してもらったものを交換して。どんどん価値の高いものに変えていってもらおう」
「それは、どうなったらゴール?」
「そうね……、自分の実家と同じくらいの大豪邸にしようか」
「ぇえ!」
「何」
「麻ひも1本から、あんな大豪邸にするなんて無理でしょ」
「大丈夫。阿部さんメンタル強いから。俺ならできる!とかいうから」
「……。でもホントに豪邸までいったらどうするの?」
「いいじゃない、そこが新居になるわけだよね」
「あ、そう……。え、そういうこと?」
「あと2人だね。大伴さんと石上さん」
「まだいるのね……」
「大伴さんは妻子持ちだから、あんまり大げさなことはちょっとね」
「いやちょっと待って。なんで既婚者がいるの、おかしいでしょ」
「え、おかしい?」
「いや、もうおかしいよ。最初から外しなよ」
「……ふーん。でも一応考えておこうよ」
「や、一応って何……」
「今さ、玉野動物園でパンダのお披露目をしてるよね」
「ああ、先月からやってるね」
「そうそう。あのパンダさ、首に橙色のコードを下げてるの、知ってる?」
「え、そうなの?」
「そうそう。飼育管理用の細いコードで、細すぎてTVにも映らないくらいなんだけど。そのコードね、実は絶対に切れない素材でできてるの」
「うんうん」
「そのコードを取ってきてもらおう」
「え、なにその『今夜いただきにあがります』みたいなの。もうキャッツアイじゃん」
「わはははは」
「わははははじゃないのよ」
「さあ、最後の石上さんは、よしくんが考えてね。私、4人分も考えたんだから」
「そういわれると、何もいえないよね……。分かった、考える。課題は、その人自身に関連していることのほうが良さそうだよね。何か特徴ある?石上さん」
「石上さんは鳥好きな人だね。確か、インコを飼ってたと思う。すごくなつかれてて、カゴから出すと自分の指にとまってくれるって嬉しそうに話してた」
「鳥好きかぁ……」
「あ、あれは?SNSで見たんだけど。ある養鶏場のニワトリがね、卵じゃなくて、石を産んだらしいの」
「石?」
「そう、緑がかった青い石らしいよ。重さは卵と同じくらいなんだけど、その石を産んだニワトリは『不思議な力を持つ鶏』ってことで、養鶏場が一気に観光名所になってるみたい」
「じゃあ、取ってくるのはその石?」
「ううん、その石を産むニワトリ」
「鶏泥棒だよね……。犯罪になるんですけど」
「えへへ、そうだよね……。じゃあ、こういうのはどう?その石を産んだニワトリがいる養鶏場の卵は、高確率で1つの卵に黄みが2つ入っているらしいの。だからその養鶏場の卵を、私たちの目の前で石上さんに1つ割ってもらって、黄みが2つ入ってたら、めでたくゴールインっていうのは?」
「おお!……って、おおじゃないよ。もはや神頼みだよ」
「ほとんど運だよね。石上さん、運悪そうだから、これがいいかも」
「失礼なやつだな」
「よしくん全然考えてくれないじゃん、もう!」
「うん、ごめん」
みなさんお察しのとおり、かぐやんにプロポーズした5人は誰も課せられた難題をクリアすることはできませんでした(唯一、阿部さんは麻ひも1本からベンツまでたどり着き、タダモノじゃない感がありました)。
そしてかぐやんはこのプロポーズ騒動のあと、急に「月に帰る」と言い出しました。
僕らはまだ出会って2年とたっていません。
僕は悲しいのかどうかも分からず、複雑な気持ちでそのときをむかえていました。
「よしくん」
満月の夜、僕らの住むマンションの4階のベランダのそばに、使いの人と思われる女性たちが迎えにきています。みなさん厚い雲にのり、ふわふわと空中に浮かんでいます。
最後のとき。
かぐやんは僕を抱き寄せました。
「よしくん、私ね。半年前に決めたの。どうせここにいられなくなるなら、最後はところん楽しもうって。地球って月で噂してるほど悪いところじゃなかったよ。街は明るくて綺麗だし、食べ物はおいしいし、人は親切だしね。……急に変わっちゃったよね、私。よしくんが呆れて見てたの、知ってたよ」
あ、知ってたんだ。そう思ったら急に力が抜けました。
「よしくんが私から距離を置こうとしてくれたおかげで、半年間やりたいことは全部やれた。もう心残りもないくらい」
え、そうなの?
「私はけっこう好きだったよ、よしくんのこと。月にはいないタイプだったし、こんなに何にもできなくて、頼りがいのない人は初めてだったから」
や、褒めてないよね。
「でも、私のこと大事にしてくれてるのは分かってた」
うん。
「心配してくれてるのも知ってた」
うん。
「よしくんは、人を大切に思える人だよ」
……そうなのかな。
「月にこんなに早く帰らなきゃいけないこと、黙ったままにしてごめん」
そういってかぐやんは、その身体をゆっくりと僕から離しました。
かぐや姫は月に帰る。
物語のとおりに、本当になるものなんですね。
僕らが過ごした1年半も、かぐやんにとっては長期休みに訪れたハワイくらいの感覚しかなかったのでしょうか。
そんなふうには思いたくありません。
「今までありがとね」
「ありがと」の言葉がかわいくて、視界がにぶってきたから、グイッと歯を食いしばって耐えました。
「かぐやん、ありがとう」
普通にいうつもりが、思いのほかカッコ悪い鼻声になったので、急いで「ズッ」と鼻水を吸い込みます。
かぐやんはベランダから雲の上へ、フワッとジャンプして飛び乗り
僕を見てフフッと笑い「じゃあね」といいました。
その姿はどんどん遠くなっていきます。
僕は彼女の表情が分からなくなっても、豆粒くらいの大きさになっても、ずっと真っ黒な空を見つめていました。
彼女が帰る月には、ここと同じような世界があるのでしょうか。
それなら、いつか月に行ってみるのもいいかもしれません。
僕が月に行っても、彼女と同じように楽しめないことは、とっくに分かっているけれど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
