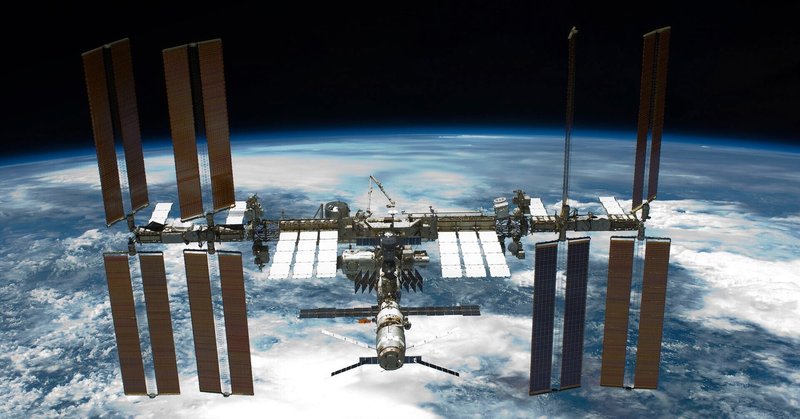
丸山圭三郎『言葉と無意識』を読む
この書物は第Ⅲ章からが面白い。ソシュールの思想を超えていきます。
著者は、人間だけが世界を二重に分節して生きているのではあるまいか、と問うています。〈身分け〉る網と〈言分け〉る網の二重分節です。〈身分け〉という言葉の出所がpp.166-167にあります。
長い間西欧形而上学の根となっていた心身二元論を超えるべく、精神の対立項としての客体的身体という概念を斥け、大和言葉の〈身〉というキー・タームを用いたのは市川浩氏であった。この動的・関係的統一性としてとらえられた身のダイナミックスは、さらに〈身分け〉という概念を生み出す。
「〈身分け〉は、身によって世界が分節化されると同時に、世界によって身自身が分節化されるという両義的・共起的な事態を意味する」(市川浩、『〈身〉の構造』)。
……〈身分け構造〉とは、身の出現とともに外界が地と図の意味分化を呈するユクスキュル的な〈環境世界〉にほかならない。生物の環境世界は常に〈生への関与性〉にもとづいた意味として出現し、それにかかわる身の方も環境世界を介して分節される。
そして、著者の『ソシュールを読む』では、次のようにあります。
コトバをもつ以前には〈身分け構造〉が過不足なく掬ってくれていた自然が、文化の網では掬い切れないカオスとして存在し始め、これが日常の生活にまで氾濫する。文化の秩序はこれを抑圧し、〈言分け構造〉の分節を押しつけようとするが、人は内より湧き上る欲動と文化のタブーの間で分裂し、ついには文化・社会への適応不能と自然への防衛不能という二重の不能症に陥り、ボーダーライン・パーソナリティ的障害に苦しめられる場合も少なくない。――p.282
鵜呑みにしてきた日本語で、苦しんでいないだろうか。
言語そのものが、悩みの温床となっていないだろうか。
以上、言語学的制約から自由になるために。
