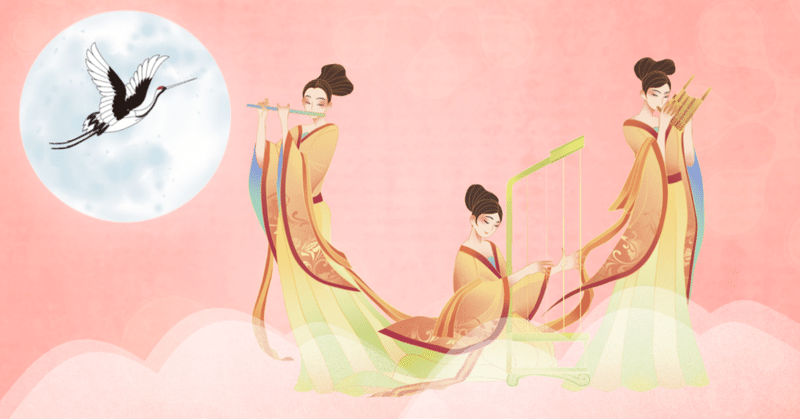
三保の松原を表現する軽羹
5月、ゴールデンウィークが始まったかと思えば、もう6月に差し掛かろうとしています。
5月が終わる前にしたいことがひとつあります。
それは「毎月1回は « 読むお菓子 »をご紹介しよう」と決めているので、5月最後の悪あがき、今日はお菓子のことを書きたいと思います。
今回ご紹介するのは、春霞という名の軽羹(かるかん)のお菓子です。
(写真を撮るのを忘れました。頑張って文章で表現します!)
この軽羹は地元の和菓子屋さんの特注品で、桃色、緑、白が鮮やかなお菓子です。
軽羹とは蒸し菓子で、少し蒸しケーキに似ています。
これは前回の記事でご紹介した、謡曲のイベントに合わせて出展したお茶席でお出ししたお菓子です。
謡曲の催しにはお題がありまして、それが「羽衣」でした。
羽衣といえば。
三保の松原に降りてきた天女の話は、日本の歴史に親しい方なら、きっとご存知がしれませんね。
しかし私といえば、ハゴロモといえばわたしが思い浮かぶのは、恥ずかしながら「ハゴロモフーズ」程度です。
私のお茶の先生は謡曲を習っています。その関係で、このイベントではお茶席を担当するよう主催側から打診され、引き受けたそうです。謡曲のテーマが「羽衣」で、それに沿ったお茶席を、と。
この話を受けてから、先生はずっと、茶道具は何にしよう、お菓子はどんなものにしようとずいぶん考え続け、、そしていろんな人に相談していたのを側から見ていました。
今回のお菓子の銘は「春霞」。
下から白、緑、桃色と、3色が重なっています。
この3色と配置は、それぞれに意味があります。
駿河湾の白い砂浜の先には、緑色の松原が茂っています。そこに天女が忘れてきた淡い桃色をした羽衣がかかっている……
そんな情景がお菓子となっているのです。
そう、このお菓子は、謡曲でもお馴染みの羽衣伝説が表現されているのです。
お茶会では、私は皆さんの前でお茶を立てました。そのそばに先生がいて、先生がお客様にお茶席の説明をします。
謡曲の鑑賞にいらっしゃる方や舞台に立たれる方がお茶を飲みにいらしたのですが、茶席では、私以外は皆さん日本の歴史や文化に造詣が深くて、とても知的な会話が展開されていました。
羽衣伝説を見立てた軽羹は大評判、また先生選りすぐりの茶道具も羽衣伝説の世界観をなしていて、皆さんとても感心して帰られました。
先生、謡曲のお偉い先生から絶賛されていて、株が上がりましたな。
ひとつのお菓子が日本の昔話を、そして人々の知性を引き出すことができるなんて、すごいなぁと側から見て思ったのでした。
茶道はもちろん、茶菓子も奥が深いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
