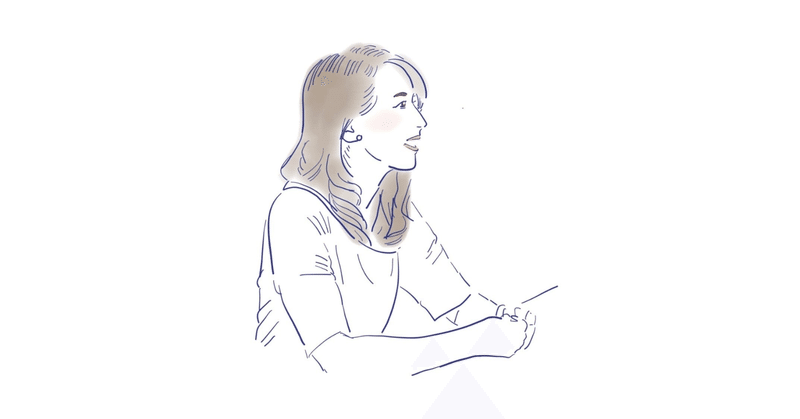
#175 立場が変わると言動が変わる 24/5/19
みなさん、こんにちは。
今日は、役職など役割の変化と言動が変容を考えます。
考えるきっかけは、この4月に新年度が始まり、新たな役割を得た従業員の言動を見ていて感じたことです。どの組織も新しい課長、部長、部門責任者など、管理職を中心に役割や立場が変わった人が多くいます。
その人たちの発言、振る舞いなど言動が、コロッと変わった場面をいくつか散見して考えてみたくなったことが背景です。ポジティブにいいね、と思えることと、若干ネガティブに感じる部分の両方があります。
まず、ポジティブな側面から考えてみます。これは、とてもシンプルなことです。
その役職、立場に見合った視座での発言が増えたことです。
たとえば、ラインの部門長から間接部門の部門長に異動された方がいます。これまでは当然ながら、現場視点から社内的な取り組みに苦言を呈されることも多かったです。
しかし、今度は会社の視座から、その取り組みや企画を進めるのが適当だ、と割に自分の言葉になって発言されている場面が見られました。つまり、個別最適から全体最適に判断様式が更新されたと捉えられるかもしれません。
また別の方を見てみます。同じラインで課長から部長に昇進された方がいます。これまでは、The課長で、自分の管掌範囲に発言が留まり、他の課長の管掌範囲にまったくと言っていいほど意見や疑問を投げかけるシーンはありませんでした。また、評価や人材マネージメントの判断は従業員側におもねっていると言えるほど偏っていました。
それが部長になってから変わりました。
たとえば人事評価場面において、他の課長が昇格推薦した理由に対して「それは説明になっていないですね。専門性や、その専門性を持って、どんな成果が出せるように今の格付けと変わったのか」と建設的な疑問を提起していました。
この2つの例のように、分かりやすく役職・役割が一段変わると、その立場、視座からの発言に変わりやすく作用します。そして、それに続く行動も前向きに変容していきます。これが役職任用のポジティブな効果の1つと考えます。
次に、少し斜めに見たときの考えです。ポジティブな面の裏側とも言えます。
それは、役職や役割がセットされたら、そう振る舞うマインドセットに対する不足感です。リーダーシップを誤解しているとも言えます。逆を言えば、ポジションパワーを使った、権力格差を用いたリーダーシップの発揮です。
それが人の弱さや情けなさでもあります。肩書きや役職がついたら、それに応じて振る舞う、言動をするリーダーシップのあり方です。この思考様式、OSは、時間をかけてでも入れ替えていきたい重要課題の1つと人事部門の1人として問題意識を持ちます。
これに個人としては対応するには、どんな役割や立場にいようとも、自分はどうありたいか、どうしたいか、を確立し、常にアップデートをかけることが1つです。beingとwillingを持つことと考えます。そのためには、日々の行動ベースで、自分の考えや意見を主張すること、が小さくも大きな一手だと考えます。
さて、みなさんの、役割や立場が変わり自分の言動が変わったポジティブな体験はどんなものでしょうか、
それでは、また
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
