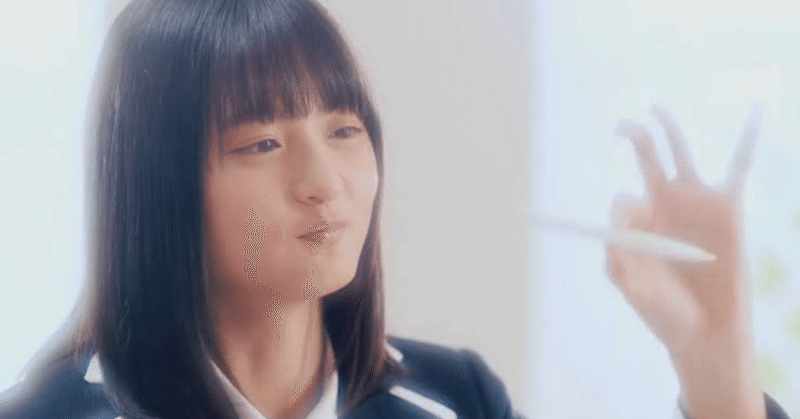
第1話
その出会いを私は偶然とは呼びたくない。人は必要な時に必要な人と出会う、そう思っているから。
「君は私の事、殺さないといけなくなると思うなぁ」
君に言われた衝撃的な言葉。今でも脳裏に焼き付いている。
「なんでそう思うのさ」
「だって私、預言者だから」
君との出会いは偶然、いやそんなこと言ったら怒られるかな。
春と夏の狭間、不快な暑さの漂う雨の日だった。
「何してるの?」
病院近くの公園で傘もささずにベンチに座る君。
「別に、あなたには関係ないよ」
僕の心配を不快に思ったのか、突き放す様な口ぶりに少しイラッとした。
「お節介は嫌われるよ」
ずぶ濡れの君の減らず口は止まらない。もう後には引けなかった。
「見て見ぬふりをして風邪でも引かれたら後味が悪いだろ。ほら」
持っていた傘を強引に君に握らせる。
「あなたはどうするの?」
思いつきの行動だった。これじゃあ立場が変わっただけだ。
「僕は…家が近いから大丈夫。それじゃあ」
恥ずかしくなった僕は君の顔も見ずに走り出した。
少し走ると駅に着いた。全身びしょ濡れの僕は、不思議と世界と切り離された様な気になる。
傘をさしている人には自分は見えていない。消えたわけでも、透明人間になったわけでもない。
ただ景色に溶け込む。雨の街に溶け込んだ感覚は、悪いものではなかった。
君もそんなことを思っていたのかな。いや、今はそれどころじゃない。
いくら初夏とはいえ、雨は冷たい。これでは自分が風邪を引いてしまう。
コンビニで傘を買う選択肢もあった。
でも、僕は景色に溶け込む事を選んだ。
「ふぁああ…」
昨日、雨に濡れたのがよくなかった。風邪を引いたきもするし、とりあえず眠い。
昼休み、机に伏して小眠りにつく。背中で受けた陽は昨日と変わらず、不快だった。
「んー…あれ?」
昼休みを終えるチャイムが聞こえると、僕は体を起こす。ガタンと何かが机の横から落ちる音がした。
「これって…昨日の傘?」
昨日の彼女に貸した傘がそこにはあった。ということは…
「同じ高校なのかよ」
どうしてかは分からない。その日から僕は彼女を探した。
あれから数日、僕の休み時間は彼女を探すことに当てていた。しかし…
「どうしてどの教室にも居ないんだよ」
どの学年の教室を探しても、彼女の姿は見当たらなかった。
「お前、最近忙しそうだな」
昼飯を食べている時、友達にもそう言われてしまった。
「人を探してるんだ」
「ほへー。どんな人?」
どんな人?と聞かれても、僕は彼女のことを全く知らなかった。
「んー…生意気で…幸の薄い顔の女の子」
「そんな奴に会ったって良いことないだろ」
まぁ、彼の言う通りだ。なんで僕は彼女を探しているんだろう。
「まぁ、もう少し探したら諦めるわ」
「おう、好きなだけやれ」
昼飯を食べ終えるとそいつは自分の席に戻っていった。
僕は暇を潰すために机に伏した。友達も多くないので、これは通常運転だった。
その日の放課後、僕は図書室に寄ってから帰ることにした。
本が好きなわけではない。もしかしたら彼女がいるかもしれない、そう思ったからだ。
図書室はひんやりと寒い、静かな空間だった。僕は重い扉を静かに閉めると、図書室の奥に足を進めた。
高校の図書室とは思えないくらい本が充実していた。
奥には読書スペースも充実していて、初夏の陽射しの中、数人が本を楽しんでいた。
立ち並んだ本の壁を抜けると、一番奥に一人用の机があった。
「あっ…」
そこには僕の探し求めていた彼女が本を片手に僕を見ていた。
「あ〜ぁ、見つかっちゃった」
残念そうに口を尖らせる彼女。その姿はこの前より元気そうに見えた。
「なんだよ、それ」
「楽しかったでしょ?学校を使ったかくれんぼ」
「残念ながら。同じ高校とは驚いたけどね」
椅子を移動し、そこに座る。この席なら多少の話し声は迷惑にならないはずだ。
「私は最初から知ってたよ。お節介好きな君のことを」
「なら一言かけてくれても。無言で傘が置いてあったら怖いだろ?」
「でもあの日、夕方に雨が降ったでしょ?君も私の傘に助けられたくせに」
確かにあの日は天気予報でも言っていなかった雨が降った。無論、傘は持ってきていなかった。
「その節は助かったよ」
「素直でよろしい」
よくよく考えたら、あれは僕の傘だ。まぁ、目の前のドヤ顔に免じてそこは言葉を飲み込んだ。
「それで、君はなんで私を探してたの?」
「それは…」
その質問の答えを僕は用意できていない。
「聞きに来たんじゃないの?」
「なんであの日、私が雨に打たれてたか」
心臓をギュッと掴まれるような感覚がする。
僕の心を見透かしたような、そんな自信が彼女の表情に表れていた。
「まぁそんなところ。ちょうど今、気になった所だよ」
「聞く覚悟はある?」
「もちろん」
この時のお気楽な返事を僕は一生後悔する。世の中には知らなくても良いことがある、そう学んだ。
「私、病気なんだ」
彼女の言葉に頭を殴られた様な衝撃が走る。
彼女は笑っていた。その笑顔に暗い影は一切無い。
窓からの柔らかい風が机の上の本をめくった。
……To be continued
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
