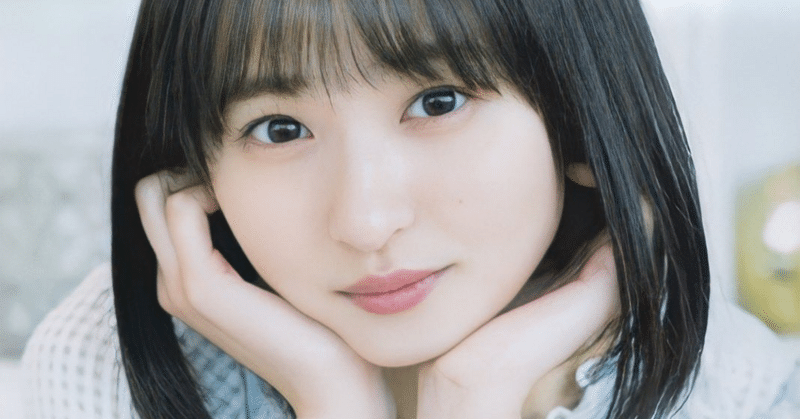
最終話
無機質な部屋に響く機械の音。何度も寝たこのベッド。
目をつぶる度に最後のような気がしてしまう。
君と夏祭りに行きたかったなぁ…
朝から降りしきる雨。夏の終わりを告げる雨は僕の気持ちを代弁している。
雨はやっぱり好きじゃない。意識していなくても、あの日のことを思い出してしまう。
球児たちの夏も終わった。彼らも夢の時間から現実に戻っているだろう。
それは僕も同じだった。
あれからさくらと連絡は取れていない。
僕の輝いていた夏休みは、もう面影もない。
ただ、もやもやとした気持ちを抱えながら、それを確かめる勇気もないまま、僕は夏休みの終わりを待っていた。
「はぁ…」
トタンに当たる雨音が頭に響く。
本棚から『サクラ咲く』を手に取る。さくらとの約束を少しでも進めておこう、ふとそう思った。
慣れない読書をどれくらい続けただろう。僕を呼ぶ母の声で我に返った。
「〇〇〜、玄関にお友達が来てるわよ」
友達と聞いて思いつくのは3人だ。でも、今、家まで来るとなると…多分あいつだ。
「今行くよ」
栞を挟んで本を閉じる。一縷の望みを抱きながら、僕は玄関へ向かった。
「どうしたの遥香?」
玄関には遥香が俯きながら立っている。傘を握った手は細やかに震えていた。
「〇〇…」
遥香は僕を見るなり、大粒の涙を流した。いや、その涙腺は既に決壊していたのかもしれない。
「ど…どうしたんだよ」
いきなり抱きつかれて泣かれる。何が何だかさっぱりだった。
「私じゃダメだった…
私じゃ、さくを助けられなかった…」
さくらの名前を聞いた時、嫌な予感がした。
「お願い〇〇…
さくを…
さくを助けてほしい…」
自分に何ができるのかは分からなかった。でも、今は何か行動せずにはいられなかった。
「さくらはどこ?」
「乃木病院…」
事情を聞くと、僕の嫌な予感はほぼ当たっていた。
「分かった。ありがとう」
母に大泣きの遥香の事を任せると、僕は神立の中に飛び出した。
雨は容赦なく僕を襲う。傘を差す余裕なんてない。
道すがら何回も人に当たった。今の僕は、景色に溶け込むには想いが強すぎるみたいだ。
ずぶ濡れの中、病院に飛び込んだ。その空間にそぐわない僕は完全に浮いていた。
「すみません、遠藤さくらって子なんですけど!」
息も整わぬまま、僕は受付のお姉さんに尋ねる。戸惑いながらも、まずはタオルを貸してくれた。
「5階の506号室です」
「ありがとうございます!」
病院内を走る訳にはいかない。エレベーターの待ち時間がひどく長く感じた。
息は整ったはずなのに、まだ鼓動が心臓から漏れて聞こえた。
体が震える。雨に濡れたからでは無い。
「さくら…」
呟きに呼応したのはエレベーターの到着音だった。
506号室。そこは個室だった。ナースセンターの目の前だったから探す手間が省けた。
震える手で僕は扉を開けた。
「さくら…」
目の前に横たわるさくらには禍々しい機械が繋がれていた。
チラッと僕を見るとすぐに顔を背ける。
「君なんて知らない。帰って」
突き放すような冷たい言葉だった。
でも、僕にはそれが強がりだと分かった。
「その服着てて言われても…
こんな時まで強がらないでよ」
福岡で買ったあのTシャツをさくらは着ていた。
「本当に君はお節介なんだね。お節介は嫌われるよ?」
さくらが僕を見ながら減らず口をきく。
さくらは“いつも”を装っていた。
「今日は君がずぶ濡れだね」
「時間がなかったんだ」
さくらの声は細く弱かった。頬は更に痩けた気がする。
「どうして?この前まであんなに元k…」
そう言おうとして僕は気づいた。僕は大きな、愚かな勘違いをしていたんだ。
あの日、さくらはコーヒーを飲めるようになったわけじゃなかった。
ラーメンを1人前食べられるようになったわけじゃなかった。
お腹の調子が悪いから頻繁にトイレに篭っていたわけじゃなかった。
ダイエットで痩せたわけじゃなかった。
観覧車に乗りたかった本当の理由も分かった。
「私、もうダメなんだ」
僕はその言葉を受け入れる事が出来なかった。
「嘘…だよね…」
本当は分かっていた。ここに来る間も覚悟を決めていたはずなのに。
「嘘じゃないよ。
ねぇ、こっち来て」
さくらは僕を手招く。僕は椅子をベッドの横にに移動させて、それに座った。
「私、余命半年だったんだ」
さくらの唐突な言葉に、僕は衝撃を受ける。
ここから僕らの答え合わせが始まった。
「いつからなの」
「んー、公園で君と会った日に告げられたんだ。
本当は私、あの日で死んじゃうつもりだったんだよ」
笑いながら言われても、僕は全然笑えなかった。
「色々頑張って…それで余命半年。
もう嫌になっちゃってさぁ〜」
リアルな言葉は重みが違った。僕が口を挟む隙も、返す言葉もない。
「でも、君が私を見つけてくれた。
傘を貸してくれた。
これは運命だって思ったの」
雨は勢いを増す。でも、さくらの声は僕の耳に真っ直ぐに届いた。
「運命って…僕らはあの日、初めて会ったじゃないか」
さくらは首を振った。
「君は初めてでも、私は君のこと知ってたよ」
「えっ…」
僕の不思議そうな顔を見て、さくらは薄白い満面の笑みを浮かべた。
「じゃあ…少し昔話に付き合ってよ」
話は僕がさくらを知る前まで遡った。
「中学校までは病気とは上手く付き合えてたんだ。
でもね、高校に入ってから少しずつ、私が勝てなくなってきちゃったんだ」
勝てなくなる…その意味はあまりにも重く、僕には分かりっこなかった。
「体は痛いし、治療は辛いし。希望も失いかけてた。
そんな時、学校で君を見つけたの。
初めて見たのは君が教室で寝てる姿。
お昼はいつも決まった子と食べてたよね。
体育の時は端っこで参加してたし、放課後はすぐに家に帰ってた。
今思うと、私ってストーカーみたいだね。
ごめんね、引かないで」
「大丈夫だよ」
僕は驚いた。無味乾燥な僕の生活が、誰かの興味を引いていたなんて。
「何回か見ているうちに、私にはピンと来たの。
“君ってまるで私みたいだ”ってね」
僕がさくら?いや、そんなことはない。
「僕はさくらみたいに我儘じゃないし、
テストの点数だって悪くない。
減らず口だってきかないし、
それに…僕はそんなに強い人間じゃない…」
僕は精一杯の強がりを言った。さくらは優しく、弱く微笑んだ。
「君は私の過ごしたかった“普通”を持っていたの。
だから私は君に自分を当てはめた。
もし元気だったらこういう高校生活だったんだな、って。
そりゃあ、テストの点数は低いけどね」
悪戯なさくらの言葉に安堵している自分がいる。
いつものように振る舞うさくら。
外の雨足は一層強くなる。やっぱり、雨は好きじゃない。
「だから、私は君のことを知ってたの。鋭い君なら、もう全部分かったんじゃないかな」
今までの唐突な行動にも全部理由があったんだ。
「僕の休日に着いてきたのも、急に遥香とデートさせたのも、そういうことだったのか」
全て合点がいった。そして、その意味合いが大きく変わった。
「ご名答。預言者には向いてなくても、やっぱり名探偵には向いてるね」
僕らはいつもの調子を取り戻したようだった。
「うっ…痛っ…」
そんな僕の思いを嘲笑うかのように、さくらはお腹を抑えて顔を顰めた。
「だ…大丈夫?!」
さくらのこんな姿を初めて見た。僕はただ動揺するしか方法がなかった。
「だ…大丈夫…。こんなの慣れっこだよ…はぁ…っ…」
肩で呼吸をしつつも、さくらの顔は緩み始めた。
「本当にさくらは強いよ。そんな素振り、1回も見せたことないじゃないか」
「君に心配させたくないからだよ。
それに、私は強くなんかない。ずるいんだよ」
さくらの顔にギュッと力が入る。
「私には終わりがあった。
君ともかっきーとも、すぐにお別れしなきゃいけないことも分かってた。
なのに…」
さくらは言葉を詰まらせる。さくらは泣いていた。
「なのに君と仲良くなった。
2人と遊んだ。
いずれ悲しませるのを分かっていたのに、2人と思い出をいっぱい、いーーっぱい作った」
声のボリュームが大きくなった。さくらの命の灯火が揺れている、そう実感させられる。
「本当はひっそり死んじゃうつもりだった。
でも、君と触れ合う中でそれが嫌になった…
寂しくなった…
怖くなった。
どうして私だけって何回も思った。何回も何回も泣いた。
でも、私は病気に勝てなかったの」
初めて見るさくらの涙、初めて聞くさくらの本音だった。
「あの本を君に上げたのもそう。
忘れられちゃうのが怖かった。
ダメだって思ってた。
枷にしちゃいけないって分かってた。
でも、私の中での決意が弱かったの」
死を直面した人の気持ちは察するに余りある。
「そんなことないよ」
そんな言葉を掛けるのがやっとだった。
「僕はさくらとの時間を忘れることなんて出来ない。
一緒に飲んだコーヒーも、
一緒に食べたラーメンも、
一緒のベッドで寝たことも、
一緒に見た映画も、
一緒に乗った観覧車も大切な思い出だ」
目の前が霞んだ。
「ありがとう。君はやっぱり優しいね。
…でも、それじゃダメなの」
「えっ…」
「今はもう決心が着いたの。
まだ叶ってない預言、覚えてる?」
僕は頷く。忘れるはずがない。いつだって頭の片隅にはその言葉があった。
「手、貸して」
僕はさくらに手を預けた。触れた手は、以前より冷たく感じる。
「私の存在が君のこれからの邪魔になりたくないの。だから…」
さくらは僕の手を自分の首に巻いた。
「私のこと殺してよ。
君の心の中の私を殺して、君はこれからの人生を歩んでほしい」
涙が布団に零れる。さくらは笑っていた。
「我儘なのは分かってる。でも、最後まで私を預言者でいさせて…」
さくらの確かな息遣いが聞こえる。さくらはゆっくりと目をつぶった。
首に巻かれた手を、僕はさくらの背中に回した。薄く羸弱した体を、優しく抱きしめた。
「ねぇ…どうしてよ…。これ以上、揺るがさないでよ…」
「忘れられるわけないだろ。
それに、君の我儘に付き合うのはもうやめたんだ」
さくらの決心に負けないくらいの決心を今、僕はした。
「僕は絶対に忘れない。初恋をそう簡単に忘れる人がいるかい?」
「バカ…辛い思いをするだけだよ…」
「それに、ようやく見つけたんだ。さくらと僕が出会った意味を」
肩を掴み、さくらと対面する。さくらの顔は涙でぐしゃぐしゃだった。
「その意味って…なに…?」
「僕は、さくらを救う為にさくらと出会った。
まだ希望が1%でもあるなら、勝手に死なせるものか」
さくらは戸惑いながらも、何かを理解した顔をしていた。
僕の胸に顔を埋める。そして、さくらは何時間もそこから離れようとはしなかった。
「暑っ…」
大学生になっても夏の暑さは変わらない。人でごった返す駅前の風景も全く変わっていない。
僕は無事に大学生になった。大学ではなんと友達もたくさん出来た。
こんなに社交性が身についた、いや、身につけさせられたのはやっぱり“あいつ”のおかげだろう。
「〇〇、おはよう」
次に到着したのは遥香だった。
「おはよう。あれ持ってきた?」
遥香は頷く。忘れたら今日行く理由の1つが消えてしまう。
「当たり前でしょ。何のために福岡に行くと思ってるの」
僕らは今日、あのお守りを返しに行く。
「傷は大丈夫なの?」
遥香は僕に会うと必ずこの確認をする。
「もう大丈夫だよ。2年も前だし」
自然と右腹を摩ってしまう。手術の痕はまだはっきり残っている。
時間を確認すると待ち合わせ時間になる寸前だった。最後の1人も、そろそろ到着するだろう。
「やあやあ、お待たせ!」
時間ぴったりにさくらはやってきた。
「さく、そんなにはしゃいで大丈夫?」
遥香はさくらの右腹を摩った。さくらは擽ったそうに笑っている。
「かっきー、もう大丈夫だって。手術したのは2年も前だし」
僕とさくらには腹に同じ傷があった。
「2人とも、そろそろ行こっか」
「うん。じゃあこれよろしく!」
2人揃って僕にキャリーケースを預ける。この光景、いつかも見た気が…。
2人は構内に消えていく。僕は残ったキャリーケースと共にその後を追った。
「こっちは麒麟だよね」
「よく覚えてるじゃん。じゃあこっちは?」
さくらは顔を顰めた。
「ペンギン…?」
2年前と同じ答えだ。
「違うよ。確か鶯だよね?」
さすが遥香。2年前に僕がそう言ったのを覚えていたんだ。でも…。
「こいつ、実は鷽(うそ)なんだって」
2年前の僕は勘違いをしていたみたいだ。
「うわ、〇〇が嘘ついた〜」
さくらに煽られる。ムカついたから軽くデコピンであしらった。
「何を見せられてるのやら…。ほら、カップル、行くよ」
僕らは本殿に歩みを進めた。荘厳な本殿はまたも僕らを飲み込んだ。
「さく、参拝の方法覚えてる?」
「えっと…礼して…お願いする!」
「二礼二拍手お願い一礼ね」
作法を確認し、お賽銭を入れると僕らは暫し沈黙した。
神様には感謝してもしきれない。僕らは2つの奇跡を起こしてもらったんだ。
1つは3人とも大学に受かったこと。あのお守りの力は絶大だったみたいだ。
もう1つは…僕がさくらのドナーに適合したこと。
僕がさくらと出会った意味は確かにあった。
さくらが1人で背負っていた運命を、僕が半分支える。ペアグッズやタトゥーには負ける気がしない。
お守りを返すと参道から夕日が見えた。
「この後はどうする?」
「とりあえず市内に戻ろっか。さくもそれでいい?」
さくらは返事をしない。夕日を背に、ゆっくりと僕らに近づいて来る。
そして、さくらは僕と遥香の手を掴んだ。
「ねぇ、1つ預言していい?」
いつになく真剣なさくら。僕らは頷くしかない。
「これからもずっと、ずぅぅぅっと3人で一緒だよ」
ギュッと手を握る。
「そんなこと…ねぇ〇〇」
「うん。言われなくても当たり前だろ」
さくらは顔を上げた。パッと明るい花が咲く。
これからも好きなだけ預言をしてくれ。
それを僕が全部叶えてあげる。
だから、君は死ぬまで預言者のままだ。
「これからもよろしくね、インチキ預言者さん」

fin.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
